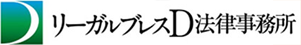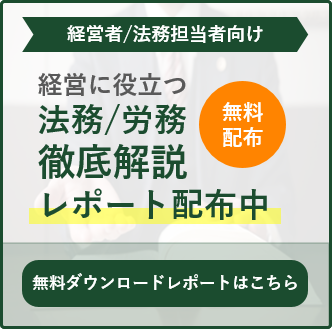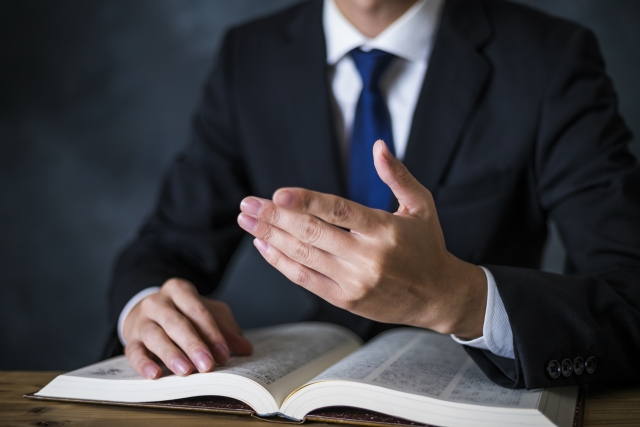Contents
【ご相談内容】
2022年4月より、中小企業を含めた全事業者パワーハラスメント対策を講じる必要があること承知していたのですが、カスタマーハラスメント対策も合わせて行う必要があると聞き及びました。
もっとも、パワーハラスメントは社内問題であることから、当社が直接問題のある者に対して指導監督ができるのに対し、カスタマーハラスメントの場合、社外の者であるため直接的な対応ができず、またお客様という立場でもあるのでどうしても遠慮が出てきます。
とはいえ、何らかの対策を講じる必要がある以上、社内体制の整備を図ろうと考えています。どういった点を考慮すればよいのか、ポイントを教えてください。
【回答】
近年、顧客による横柄な態度等に辟易する従業員が増加していること、一部従業員は顧客対応を原因として体調不良に陥っていること等が明らかとなり、従来のような「お客様は神様です」扱いを見直す動きが急速に広まっています。
そのような状況下で、2022年4月より中小企業を含めた全事業者がハラスメント対策を社内で講じることが義務化されました。そして、厚生労働省も「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を公表しているところ、基本的には厚生労働省が公表しているマニュアルを見ながら、対策を講じればよいと考えられるところです。
ただ、執筆者が知る中小企業の現場実務からすると、マニュアルに記載されている内容は、中小企業では実施することが難しい等の問題点も感じるところです。
そこで、以下では、マニュアルをベースとしつつも、必要に応じて執筆者個人の考える対処法も適宜記述しながら、解説を行います。
(参考)
【解説】
1.なぜ対策が必要なのか
(1)事業者の責務
カスタマーハラスメント対策を講じなければならない法令上の根拠としては、厚生労働省が公表している通称「ハラスメント指針」と呼ばれるものがあります。このハラスメント指針は、パワーハラスメント防止措置が義務化された際によく引用される指針なのですが、実はカスタマーハラスメントについても記述があります。
次のような内容です(一部引用)。
事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)
7 事業主は、取引先等の他の事業主が雇用する労働者又は他の事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為(暴行、脅迫、ひどい暴言、著しく不当な要求等)により、その雇用する労働者が就業環境を害されることのないよう、雇用管理上の配慮として、例えば、⑴及び⑵の取組を行うことが望ましい。また、⑶のような取組を行うことも、その雇用する労働者が被害を受けることを防止する上で有効と考えられる。
⑴ 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
事業主は、他の事業主が雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為に関する労働者からの相談に対し、その内容や状況に応じ適切かつ柔軟に対応するために必要な体制の整備として、4(2)イ及びロの例も参考にしつつ、次の取組を行うことが望ましい。
また、併せて、労働者が当該相談をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発することが望ましい。
イ 相談先(上司、職場内の担当者等)をあらかじめ定め、これを労働者に周知すること。
ロ イの相談を受けた者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。
⑵ 被害者への配慮のための取組
事業主は、相談者から事実関係を確認し、他の事業主が雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為が認められた場合には、速やかに被害者に対する配慮のための取組を行うことが望ましい。
(被害者への配慮のための取組例)
事案の内容や状況に応じ、被害者のメンタルヘルス不調への相談対応、著しい迷惑行為を行った者に対する対応が必要な場合に一人で対応させない等の取組を行うこと。
⑶ 他の事業主が雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為による被害を防止するための取組
⑴及び⑵の取組のほか、他の事業主が雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為からその雇用する労働者が被害を受けることを防止する上では、事業主が、こうした行為への対応に関するマニュアルの作成や研修の実施等の取組を行うことも有効と考えられる。
また、業種・業態等によりその被害の実態や必要な対応も異なると考えられることから、業種・業態等における被害の実態や業務の特性等を踏まえて、それぞれの状況に応じた必要な取組を進めることも、被害の防止に当たっては効果的と考えられる。
ところで、上記指針では、パワーハラスメント対策に付随する形でカスタマーハラスメントに関する記述がなされていますが、パワーハラスメント対応とカスタマーハラスメント対応は異質のものと認識したほうがよいと考えられます。
なぜなら、パワーハラスメントの場合、加害者・被害者とも社内の人間であるため、直接的な指導やフォローを行うことができるのに対し、カスタマーハラスメントの場合、一方当事者が社外の人間となるため直接的な措置を講じることができないからです。特にパワーハラスメントであれば、社内研修等を通じた事前予防対策を行うことができますが、カスタマーハラスメントの場合は事前予防対策を行うことが困難です。
カスタマーハラスメントは、パワハラ・セクハラ等の社内ハラスメント問題とは独立した問題として対策を講じるべきです。
(2)悪影響の防止
カスタマーハラスメント対策を講じなければならないもう1つの理由として、経営環境の悪化を防止することがあげられます。
この点、厚生労働省が公表しているマニュアルでは、経営環境への悪化の具体例として、①従業員への影響(精神的負荷による業務効率の低下、体調不良など)、②企業への影響(労力・時間の負担過重など)、③他の顧客等への影響(雰囲気の悪化、ブランドイメージの低下など)があげられています。
カスタマーハラスメントを放置した場合、従業員はいなくなる、お客様もいなくなる、結果的に会社経営が成り立たなくなるという重大な事態になる恐れがあることを理解しておく必要があります。
2.カスタマーハラスメント対策を行う上で現場の悩み
法令上も経営上もカスタマーハラスメント対策を講じる必要性があることは、前述1.記載の通りですが、いざカスタマーハラスメント対策を実行しようとしても、色々な障害が立ちはだかります。
典型的には、次の4点があげられます。
(1)定義・判断基準が分からない
巷では不当要求に対しては毅然とした態度で臨む必要がある…と言われますが、何をもって不当要求=カスタマーハラスメントに該当するのか、区別ができないという現場の声は非常に大きいといえます。この点、ガイドラインでは、カスタマーハラスメントについて次のように定義しています。
顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境ががいされるもの
ここでのポイントは、①要求内容の妥当性を欠く場合はカスタマーハラスメントに該当すること、②要求内容が妥当であっても、手段・態様が不相当な場合もカスタマーハラスメントに該当すること、の2パターンがあることを明示したことにあると考えられます。ちなみに、ガイドランでは具体例として次のようなものを記載しています。
「顧客等の要求の内容が妥当性を欠く場合」の例
・企業の提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない場合
・要求の内容が、企業の提供する商品・サービスの内容とは関係がない場合
「要求を実現するための手段・態様が社会通念 上不相当な言動」の例
(要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が高いもの)
・身体的な攻撃(暴行、傷害)
・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
・威圧的な言動
・土下座の要求
・継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動
・拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
・差別的な言動
・性的な言動
・従業員個人への攻撃、要求
(要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があるもの)
・商品交換の要求
・金銭補償の要求
・謝罪の要求(土下座を除く)
現場実務で悩むとすれば、どういった言動が「精神的な攻撃」、「威圧的な言動」、「差別的な言動」等に該当するのか、どのラインを超えたら「商品交換の要求」、「金銭補償の要求」、「謝罪の要求(土下座を除く)」がハラスメントに該当するのか、になるかと思われます。
結局のところはケースバイケースの判断にならざるを得ないのですが、まずは、悩ましいカスタマーハラスメントについて現場で即断即決を行う必要性はないという点を指摘しておきたいと思います。なぜなら、カスタマーハラスメントに該当するか否かは事後的に評価し、カスタマーハラスメントに該当すると判断した場合、以後は一切の対応は行わないと会社組織として(場合によっては代理人弁護士名義にて)対応することも十分可能だからです。
カスタマーハラスメントに該当するか否か悩ましい問題が生じた場合、現場としてはまずは如何にして話を終えるのかを重視して対処したほうがよいように思われます(もちろん、相手の話を十分に聞かないうちに話を切り上げようとする対応は望ましいものではありません)。初動対応に関する解説となりますが、以下の記事もご参照ください。
(2)世間の目
事業者としては、顧客の要求内容・言動等からしてカスタマーハラスメントであると判断し、毅然として態度で接したところ、このやり取りの一部がインターネット上にアップされ、何も知らない閲覧者が一方的に事業者を非難する(いわゆる炎上)という事象を頻繁に見かけます。
もちろん、事業者の顧客対応に問題がある場合は、世間からの非難は免れません。
しかし、炎上騒動を極度に恐れて萎縮し、事業者として言いたいことを言えずに不当要求に応じてしまうという事例も相当数存在するものと思われます。
事業者が検討している顧客対応について、世間基準とのズレが生じているか否かについては、事前に弁護士と相談すればクリアーすることは可能ですし、万一ネットに晒されたとしても多くの場合は炎上騒動に発展することはありません。自社のみで判断しようとするから誤りが生じうることを認識した上で、積極的に弁護士等の外部専門家に意見を求めるべきです。
(3)従業員ケア
大事なお客様である以上は多少の無茶ぶりであっても対応を検討する必要がある、一方でお客様の無茶ぶりに翻弄され負荷のかかる従業員のことも守ってあげなければならない、というのが、今般事業者に求められる責務となります。
この従業員ケアについては、最終的にはカスタマーハラスメントを受けている従業員を一人にさせないことにつきます。すなわち、当該従業員を顧客から切り離す(交渉窓口として対応させない)及び組織として対応する(上長が代わりに交渉窓口となる)といった外部対策と共に、被害を受けた従業員からの相談対応を行う、場合によってはカウンセラー等の専門家に診てもらうといった内部対策を含むことになります。
中小企業の場合、外部対策を社内で構築することが難しい場合がありますので、直ちに弁護士に交渉窓口を移管するといったことも検討するべきです。
(4)顧客への遠慮
「お客様は神様です」信仰がいまだに根強いためか、お客様からのクレームにはとにかく耐え忍ぶという方針を採用している事業者も一定数存在するものと思われます。
しかし、カスタマーハラスメント対策が事業者の責務となった今日では、上記考え方は通用しないことを認識する必要があります。
例えば社内の意識改革として、「不当要求を行ってくる者はそもそもお客様では無い」、「できないことは遠慮なくNOと言う」、「クレーマーに代わる新規顧客を発掘する方が安上がりである」等の代表者・社長からの強いメッセージを発することも検討してもよいかもしれません。
3.社内体制の整備
マニュアルに記載されている内容は、ある程度組織化された事業者を念頭に置いている節がありますので、中小企業を想定した場合、次のようなステップを踏んだほうが良いかと思いますので、以下マニュアルの順番とは少し入替を行いつつ解説を行います。
(1)事前準備
基本方針の周知・啓発
上記2.(4)でも解説しましたが、一従業員の立場からすれば「お客様を蔑ろにするわけにはいかない」と考えるのがむしろ通常であり、職務熱心な従業員であればあるほどカスタマーハラスメントに苦しむ、心身ともに崩してしまうという傾向があります。
従業員への安全配慮義務を持ち出すまでもなく、お客様だからと言って程度の如何を問わず何でも受け入れる必要はないことを社内に発信することが重要です。
基本方針の例についてはガイドラインに掲載されていますので、これを参照しつつ、自社の実情に即して加除修正して作成すればよいかと思います。
対応方法の策定
初動対応の詳細については、上記2.(1)で引用した「クレームを受けた場合の初期対応のポイントを弁護士が解説!」をご参照いただきたいのですが、マニュアルでは3つのポイントをあげています。
対象となる事実、事象を明確かつ限定的に謝罪する
状況を正確に把握する
現場監督者(一次相談対応者)または相談窓口に共有する
また、カスタマーハラスメントが疑われる場合の対応例として、マニュアルでは
現場での対応(例:時間・人・場所を変えて対応する、感情的な対応はしない等)
電話での対応(例:原則録音する、即時回答できない場合は追って返事する等)
顧客訪問による対応(例:夜間や早朝は避ける、開かれた場所で対応する等)
に分けて解説が記されています。
さらに、ハラスメント行為に応じた顧客等への対応例として次のような記述もなされています。なお、いずれの対応例も弁護士の協力体制があることを前提にした内容になっていることに注意が必要です(身近に相談できる弁護士を確保しておく重要性の一事例といってよいかもしれません)。
◆時間拘束型
・長時間にわたり、顧客等が従業員を拘束する。居座りをする、長時間、電話を続ける。
(対応例)対応できない理由を説明し、応じられないことを明確に告げる等の対応を行った後、膠着状態に至ってから一定時間を超える場合、お引き取りを願う、または電話を切る。
複数回電話がかかってくる場合には、あらかじめ対応できる時間を伝えて、それ以上に長い対応はしない。現場対応においては、顧客等が帰らない場合には、毅然とした態度で退去を求める。状況に応じて、弁護士への相談や警察への通報等を検討する。◆リピート型
・理不尽な要望について、繰り返し電話で問い合わせをする、または面会を求めてくる。
(対応例)連絡先を取得し、繰り返し不合理な問い合わせがくれば注意し、次回は対応できない旨を伝える。それでも繰り返し連絡が来る場合、リスト化して通話内容を記録し、窓口を一本化して、今後同様の問い合わせを止めることを伝えて毅然と対応する。状況に応じて、弁護士や警察への相談等を検討する。◆暴言型
・大きな怒鳴り声をあげる、「馬鹿」といった侮辱的発言、人格の否定や名誉を棄損する発言をする。
(対応例)大声を張り上げる行為は、周囲の迷惑となるため、やめるように求める。侮辱的発言や名誉棄損、人格を否定する発言に関しては、後で事実確認ができるよう録音し、程度がひどい場合には退去を求める。◆暴力型
・殴る、蹴る、たたく、物を投げつける、わざとぶつかってくる等の行為を行う。
(対応例)行為者から危害が加えられないよう一定の距離を保つ等、対応者の安全確保を優先する。
また、警備員等と連携を取りながら、複数名で対応し、直ちに警察に通報する。◆威嚇・脅迫型
・「殺されたいのか」といった脅迫的な発言をする、反社会的勢力との繋がりをほのめかす、異常に接近する等といった、従業員を怖がらせるような行為をとる。または、「対応しなければ株主総会で糾弾する」、「SNS にあげる、口コミで悪く評価する」等とブランドイメージを下げるような脅しをかける。
(対応例)複数名で対応し、警備員等と連携を取りながら対応者の安全確保を優先する。また、状況に応じて、弁護士への相談や警察への通報等を検討する。ブランドイメージを下げるような脅しをかける発言を受けた場合にも毅然と対応し、退去を求める。◆権威型
・正当な理由なく、権威を振りかざし要求を通そうとする、お断りをしても執拗に特別扱いを要求する。または、文書等での謝罪や土下座を強要する。
(対応例)不用意な発言はせず、対応を上位者と交代する。要求には応じない。◆店舗外拘束型
・クレームの詳細が分からない状態で、職場外である顧客等の自宅や特定の喫茶店などに呼びつける。
(対応例)基本的には単独での対応は行わず、クレームの詳細を確認した上で、対応を検討する。対応の検討のために、事前に返金等に対する一定の金額基準、時間、距離、購入からの期間などの制限などについて基準を設けておく。店外で対応する場合は、公共性の高い場所を指定する。納得されず従業員を返さないという事態になった場合には、弁護士への相談や警察への通報等を検討する。◆SNS/インターネット上での誹謗中傷型
・インターネット上に名誉を毀損する、またはプライバシーを侵害する情報を掲載する。
(対応例)掲示板や SNS での被害については、掲載先のホームページ等の運営者(管理人)に削除を求める。投稿者に対して損害賠償等を請求したい場合は、必要に応じて弁護士に相談しつつ、発信者情報の開示を請求する。名誉毀損等について、投稿者の処罰を望む場合には弁護士や警察への相談等を検討する。解決策や削除の求め方が分からない場合には、法務局や違法・有害情報相談センター、「誹謗中傷ホットライン」(セーファーインターネット協会)に相談する。◆セクシュアルハラスメント型
・従業員の身体に触る、待ち伏せする、つきまとう等の性的な行動、食事やデートに執拗に誘う、性的な冗談といった性的な内容の発言を行う。
(対応例)性的な言動に対しては、録音・録画による証拠を残し、被害者及び加害者に事実確認を行い、加害者には警告を行う。執拗なつきまとい、待ち伏せに対しては、施設への出入り禁止を伝え、それでも繰り返す場合には、弁護士への相談や警察への通報等を検討する。
なお、カスタマーハラスメント=不当要求があった場合の全般的な対処法については、次の記事もご参照ください。
(2)社内向けアナウンス
教育・研修
中小企業の場合、外部講師を呼んで社内勉強会を開催する、マニュアルを作成して従業員に配布する、実践式のトレーニングを行う等の教育・研修を実施することが難しいのが実情です。しかし、だからといって何も対策しないというのも問題があります。
カスタマーハラスメント対策で何より重要となるのは、初動対応であり、何よりも被害にあわない(被害を最小限度に食い止める)ことが重要です。その観点からすれば、例えば次のよう形式基準だけ従業員に周知し、カスタマーハラスメントへの該否、対処方針の決定等については追って行うとするだけでも、当面は対処できるかもしれません。
なお、究極的にはガイドラインで記載されているような、悪質なクレーム・カスタマーハラスメントの定義(該当行為例、正当なクレームとの相違)、カスタマーハラスメントの判断例(判断基準やその事例)、パターン別の対応方法、苦情対応の基本的な流れ、顧客等への接し方のポイント(謝罪、話の聞き方、事実確認の注意点等)、記録の作成方法、各事例における顧客対応での注意点、ケーススタディ等について教育・研修を実施することは言うまでもありません。
(例)
- ・30分を超えても話を続けようとする場合は、交渉を打ち切ってよい
- ・身体的接触を伴う行動に出てきた場合は、交渉を打ち切ってよい
- ・暴力団等の反社会的勢力に属することを言ってきた場合は、交渉を打ち切ってよい
- ・第三者の権威を持ち出してきた場合は、交渉を打ち切ってよい
- ・権限のない部外者が表立って行動するようになった場合は、交渉を打ち切ってよい
相談対応体制の整備
ここでいう相談対応体制の整備は2つの意味があります。
1つは、カスタマーハラスメントと疑われる事象について社内で情報共有し、組織として対策を講じることを目的とした業務報告体制の整備です。もう1つは、カスタマーハラスメントによる被害を受けた従業員に対するフォロー体制の整備です。
要は「担当する従業員を1人にしない」ことを心掛けることがポイントです。
(3)有事対応
事実関係の確認
3.(1)でも記載しましたが、初動対応で意識しておきたい事項は次の3点となります。
- 対象となる事実、事象を明確かつ限定的に謝罪する
- 状況を正確に把握する
- 現場監督者(一次相談対応者)または相談窓口に共有する
その上で、「状況を正確に把握する」方法として、ガイドラインでは次のような手順を記載しています。
①時系列で、起こった状況、事実関係を正確に把握し、理解する。
②顧客等の求めている内容を把握する。
③顧客等の要求内容が妥当か検討する。
④顧客等の要求の手段・態様が社会通念上相当か検討する。
ただ、おそらくは①~④を一担当者が判断することはできないと思われますし、ましては初動時にこれらを的確に判断することは困難と言わざるを得ません。少なくとも初動時は①を確実に押さえつつ、可能な限り②についても押さえるといった認識で対処したほうが良いと考えられます(③④については後でじっくり判断すればよいという意味です)。
(4)アフターフォロー
従業員への配慮措置
上記(2)でも触れましたが、顧客等からの身体的暴力や顧客等の言動による精神的負荷に対して、安全配慮義務の観点から事業者として適切な事後措置を講じる必要があります。
再発防止策
現実に発生したカスタマーハラスメント事案を踏まえて、一連の顧客対応に問題がなかったか、見直すべき点がなかったか、他のやり方がなかったのか等々を振り返り、対応した従業員のみならず、今後経験するかもしれない他の従業員への注意喚起することが、理想的な対応となります。
ただ、再発防止策を検証する時間が取れないということも実情ではないかと思われます。とりあえずは、顧客等の言動に対しどういった対応を行ったのか、時系列で整理する作業だけでも進めることが有用と思われます。カスタマーハラスメントに対して、生々しい事例を後で見ることができるだけでも十分に参考になるからです。
記録管理
上記の再発防止策で記載した通り、カスタマーハラスメント事案に関する対応記録を残して管理することは、今後の参考資料となることは言うまでもありません。
また、記録管理による活用法として、いわゆる要注意顧客リストを作成し、当該顧客との取引の場合は対応方針を変更する、場合によっては取引自体を行わないといった対策を取ることも可能となります。なお、取引自体を行わないとなると、かえってトラブルを招来するのではないかという懸念があるかもしれませんが、通常の商取引の場合、誰と取引するかは事業者の自由であって法的に問題ありません。したがって、「当社は取引するつもりはありませんので、お帰り下さい」と説明し、後は一切取り合わないという方法もあり得るところです。
4.取引先とのカスタマーハラスメント
カスタマーハラスメントは主としてBtoC取引、すなわち消費者からの不当要求を指すものとして用いられることが多いのですが、BtoB取引、すなわち取引先事業者からの不当要求も想定する必要があります。また、BtoB取引において、当方が不当要求を行っているとして取引先事業者より指摘を受ける場面もあり得ます。
ここでは、BtoB取引におけるカスタマーハラスメント対策について、そのポイントを簡単に解説します。
(1)当社が被害者の場合
従業員より取引先から嫌がらせを受けていると相談を受けた場合、当該従業員からヒアリングし事実関係を把握することからスタートすることになります。その後は、ガイドラインでは取引先に協力依頼を行う、取引先と共同でハラスメントの疑いのある取引先従業員から事実確認を行う、という記述がありますが、正直なところ、取引先に対して物申すこと自体が憚られるのが実情ではないかと思われます。特に、取引先に依存しているような事業者である場合、取引先の気分を害するような申入れを事実上できなことも有り得るところです。
当然のことながら、相談を行ってきた従業員に我慢するよう説得するのも問題があります。
非常に悩ましい事態になりがちなのですが、どういったルートを使って申入れを行うのか、どういった物の言い方にするのか等は色々と戦略的に考える必要がありますので、是非弁護士に相談してほしいところです。
(2)当社が加害者の場合
取引先が当社従業員より嫌がらせを受けている旨申告してきた場合、具体的な嫌がらせ内容を取引先より聞いたうえで、当社従業員に対して調査を実施し、必要に応じて社内処分(配置転換等の人事処遇、懲戒処分等の制裁)を行うのが筋論です。
間違っても揉み消すような対応に終始した場合、今の時代はネット等で告発されてしまう恐れがあります。こうなると、当社と取引当事者間だけの限定された範囲の問題では留まらず、風評被害を含めかえって問題が拡大し、事態が悪化する恐れがあります。
必要に応じて弁護士にも相談しながら、適切な対応を心掛けたいところです。
<2022年4月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
|
|





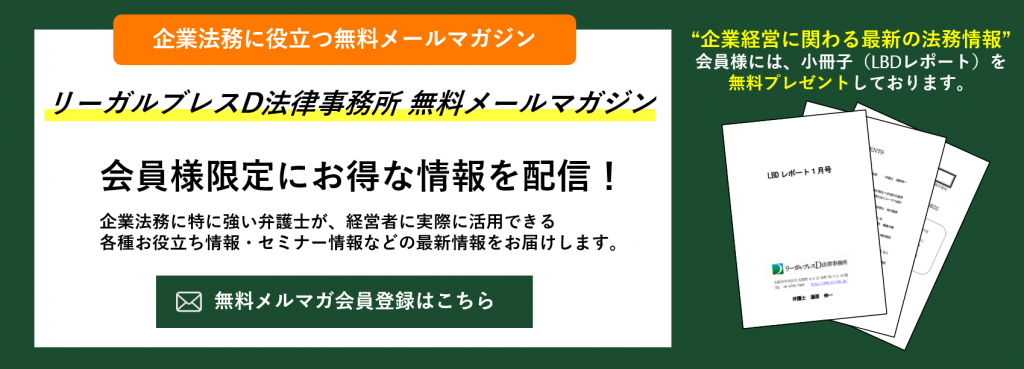
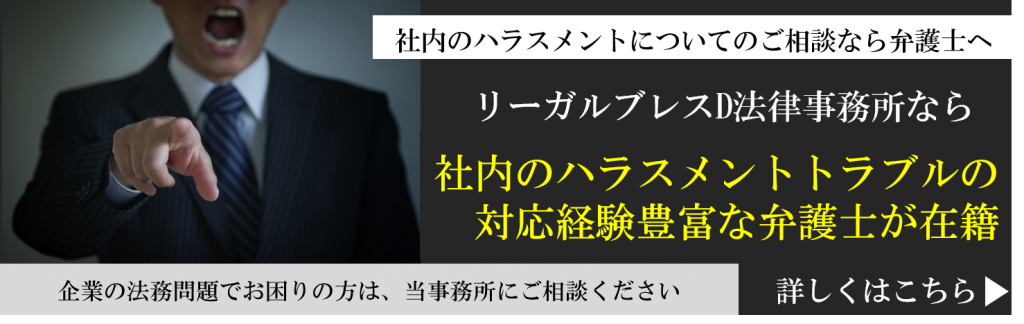
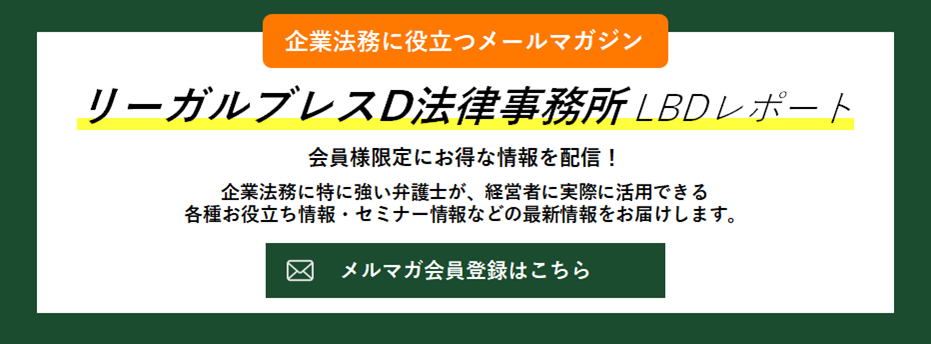
 弁護士 湯原伸一
弁護士 湯原伸一