Contents
【ご相談内容】
財務体質の強化の一環として、キャッシュフローの改善を進めています。経費削減はもちろんのこと、商品・サービスのマーケティング戦略の変更、取引先の見直しなど横断的検討を行う方針です。法務的な観点からは何に気を付ければよいでしょうか。
【回答】
キャッシュフロー改善のためにどういった施策を実施するのかにもよるのですが、キャッシュフローを改善するためには、①売上をアップすること、②経費を削減すること、③お金を残すことの3点が基本になると考えられます。
以下では、①に関連してマーケティング(値付け)戦略で留意したい法務視点、②に関連して流通取引及び固定経費を削減するうえで留意したい法務的視点、③に関連して支払いのタイミングを変更させるうえで留意したい法務的視点、に分類して解説を行います。
【解説】
1.マーケティング(値付け変更)戦略によるキャッシュフロー改善
(1)値上げ
価格変更(値上げ)の条件
まず、今すぐに価格改定(値上げ等)ができるのかという問いについては、顧客・取引先との契約内容を検討しないことには一概に判断できません。というのも、例えば、ガソリンスタンド事業者がガソリンを昨日は90円、今日は100円で値上げして売っている事例であれば、昨日は昨日で売買契約を、今日は今日で売買契約を、と別々の契約(=購入の申込とそれに対する承諾)が取り交わされていることになります。このような別々の契約と言える場合は、その都度売価を設定すればよいので、顧客・取引先の承諾を得ることなく、価格改定を行なうことは法律上可能です。
一方、ガソリンスタンド事業者が運送事業者と継続的な取引を行っており、今月はガソリンを90円で売ることで合意していたにもかかわらず、当月内に一方的に値上げして100円で売り始めたという事例であれば、これは約束違反となります。この場合は、顧客・取引先の承諾を得ないことには価格改定を行なうことはできません。
このように1回1回の個別取引と言えるのであれば、その都度価格設定ができるので、顧客・取引先の承諾は不要です。しかし、継続的な取引が交わされており、その期間中に一定額で販売するといった約束が成立している場合には、顧客・取引先の承諾が必要となります。
継続的な取引と価格変更の可否
では、継続的な取引の場合、一切変更ができないのでしょうか。
例外的なものとなりますが、BtoB取引の場合、売主が価格改定の提示を買主に行い、買主が一定期間内に返答を行わなかった場合、一定の条件がありますが価格改定に承諾したものとみなすという規定が存在します(商法509条。なお、当然のことながら、買主が承諾しない旨の回答を行なえば、価格改定は不可です)。
あるいは、BtoB取引に限りませんが、インターネット上の取引の場合、価格改定に関する案内を行った後、引き続き、当該WEBサービスを利用した場合には価格改定に承諾したものとして取り扱う旨の利用規約(約款)が定められていることがありますが、これは契約内容を工夫した価格改定の方法と言えます(但し、2020年4月1日より施行された改正民法に従った対応が必要となります)。
このように、事前に価格改定に関する案内を出し、一定期間内に異議申し立てが無い場合は、積極的な承諾を得られないものの価格改定ができる可能性もあることは一応県としてよいと思われます。
相手の承認なく価格改定ができる場合とは?
さて、継続的な取引を行っているが、何らかの事情によりどうしても価格改定(値上げ等)を行う必要がある、ところが顧客・取引先が承諾してくれない場合、どうすればよいのでしょうか。この場合、基本的には従前の価格にて販売・サービス提供をせざるを得ません。
ただ、例えば、2008年頃に発生した原油高騰による経費上昇といった外部環境の著しい変化によって、運送業の運賃価格改定を実施せざるを得ない(下手をすれば原価割れによる運送サービス提供を強いられる)といった場合には、従前の価格にて取引が強制されることは無いと考えられています。
結局のところ、売主側の予測を超えた事象が発生し、かつ売主側の責任ではないことを理由とした価格改定であれば、合理性が認められる可能性が高いと考えられます。そして、こういった場合であるにもかかわらず、顧客・取引先がどうしても承諾しない場合は、従前の価格にて販売・サービス提供ができないことを理由として契約打ち切りを行なうことが可能と考えられます。
なお、価格改定に際しては何らかの理由の説明が求められることになりますが、当然のことながら、この説明内容について虚偽・偽りがあった場合は問題が生じることになります。例えば、BtoC取引の場合であれば、よく原材料を高級化(プレミアム化)したとか、内容量を増加したという言い回しが用いられるのですが、実際には原材料や内容量に変更が無い(ほとんど変わりがない)というのであれば、景品表示法違反(優良誤認、二重価格など)という問題が生じます。また、BtoB取引の場合であっても、独占禁止法違反(欺瞞的顧客誘引)に該当するおそれがあります。そして、BtoC、BtoBに関わらず、詐欺取引であることを理由とした損害賠償等の問題や、いわゆる炎上騒ぎによる企業価値・評判の毀損といった問題も生じるかもしれません。
もちろん、ある程度の駆け引き的な説明が必要になるとは考えられるのですが、説明を受けた側がどのように感じるかという視点は持ち合わせたほうが良いと考えられます。
同調値上げ
最後に、競業他社が値上げしたことを契機として、自社も値上げするといった場合もあるかもしれません。
たしかに、競業他社が値上げしたので、自社も値上げしたから当然に違法という訳ではありません。ただ、同じ商品・サービスについて、特段の経済的変動が無いにも関わらず、競業他社が順次値上げを開始するとなると、傍から見ていて明らかに不自然と感じてしまいます。そして、こういった事象を常日頃から監視している公正取引委員会は、カルテルの疑いありとして内偵捜査を開始します。
あらぬ疑いをかけられるリスクがありますし、この手の問題は往々にしてマスコミリークによる風評被害が生じやすい類型ですので、単純に競業他社が値上げしたからという消極的理由ではなく、なぜ当社も値上げしたのか積極的な理由を準備しておかなければ、後で手痛いしっぺ返しを受けることを想定したほうが良いと考えられます。
(2)戦略的値下げ
価格変更(値下げ)の条件
競業他者を排除し、一気に市場を奪いたいと考えた場合の戦略として、値下げを行うことがあります。
まず、そもそも論として、値上げする場合は顧客・取引先からクレームを受けることがあっても、値下げする場合は顧客・取引先からクレームを受けるということは通常考えられません。そして、いくらで売るかは売主の自由である以上、競業他社の動向に応じて対抗値下げを行なうこと自体も自由であり、何ら違法性が無いのが大原則です。ただ、原価割れを起こしてまで安売り合戦を行なうことは異常であり、不健全な経済活動と言わざるを得ません。また、体力(財力)がある企業がわざと安売り合戦を仕掛けて、競業他社を潰していき、競業他社をすべて駆逐してから自社で自由に値付けができる状態に持って行く可能性もあります。これは長期的に見れば、顧客・取引先にとって不利益を及ぼすものとなります。
このような問題があることを踏まえ、独占禁止法では不当廉売を禁止しています。不当廉売については一定の要件がありますが、度を過ぎた安売り合戦にならないよう注意が必要です。
フリーミアム戦略
ちなみに、戦略的値下げの一形態として、フリーミアム戦略と呼ばれるものを実施する場合があります。これについては、無料・タダで商品やサービスを提供することになりますので、究極の不当廉売と言えるかもしれません。しかし、世間で行われているフリーミアムは、無料・タダで顧客を誘引しつつ、その顧客に対し、何らかのアプローチをかけて有料サービスを導入してもらうという経営戦術です(古くはYahooBBがモデムを無料で配布し、有料のネット回線を導入してもらうビジネスがありました。最近ではスマートフォン等の端末上でゲームを無料提供しつつ、有料課金サービスを導入してもらうというビジネスモデルが有名です)。
このようなフリーミアムの場合、ビジネスモデル全体を捉えて不当廉売か否かの判断を行なうことになります。なお、上記のようなビジネスモデルではなく、広告宣伝目的で無料で商品・サービスを配布する場合があります。この場合は、景品表示法に基づく「景品」規制が及ぶことになりますので、注意が必要です。
要は、自社の身を削る分には問題が無い、裏を返せば顧客・取引先に損が無いから問題が無いと即断するのは、少しリスクを伴うということに留意する必要があります。
顧客ごとで異なる取引価格を設定すること
取引先・顧客によって販売価格に差異を設けることも価格戦略の1つとなります。この点については、誰に対して、いくらで売るのかは、売主の自由である以上、差異を設けることそれ自体が当然に違法という訳ではありません。
しかし、例えば、競業先を追い込んでしまう目的で、競業先と取引を行っている事業者のみ異常な割引率を設定し、取引を奪い去ってしまうという場合、行き過ぎた経済活動と言わざるを得ません。上記のような行き過ぎた場合には、独占禁止法上の問題(差別対価)が生じますので、注意が必要です。
弁護士へのご相談・お問い合わせ
当サイトの記事をお読みいただいても問題が解決しない場合は
弁護士にご相談いただいた方がよい可能性がございます。
下の電話番号もしくはメールにてリーガルブレスD法律事務所までお問い合わせください。
06-4708-7988メールでのご相談
2.流通取引の見直しによるキャッシュフロー改善
(1)取引先(供給元)への要請
ディスカウント(価格交渉)要請の可否
まず検討できる事項としては、買主が売主に対し、ディスカウント要請を行なうことではないかと思います。この点、値段交渉を行なうこと自体は何ら法律上の規制はありません(但し、例えば電気の買取り金額など法令上値段が設定されているものは別です)。したがって、値段交渉を相手方が応じてくれた場合、法律上はその当事者間の価格合意を優先することになります。
ただ、取引の力関係上、買主の力が圧倒的に強くて、売主としては嫌でも応じなければならない状態になっている場合(例えば、売主の取引先の大部分を占める買主より、値段交渉に応じなければ取引打切りを示唆された場合など)、当事者間の合意のみを優先させるわけにはいきません。このような取引上の優劣がはっきりしている場合には、独占禁止法上の優越的地位の濫用に該当するとして、当事者間の合意が否定されることもあります。ただ、独占禁止法によって当事者間の合意が否定されるケースは予見することが難しく、中小企業同士での取引であればレアケースと言っても良いかもしれません。
ボリュームディスカウント
買主が売主に対し、一定数量を購入することを条件にボリュームディスカウントを要請するといった対応も検討できます。この点についても、一定数量を購入することを条件としたボリュームディスカウントを禁止する法律は現時点では存在しません。もちろん、取引上の優劣による独占禁止法上の優越的地位の濫用の問題が生じる可能性は否定できませんが、一定数量を購入することを条件とした場合、客観的に損得勘定ができますので独占禁止法上の問題は生じづらいのではないかと考えられます。なお、売主は、どの買主に対し、どういった条件で商品を販売するのかは原則自由です。例外として、市場での取引価格が硬直化し、自由経済が失われるといった場合は独占禁止法上の問題が生じますが、よほどの独占商品でない限り、普通は想定する必要はないと考えられます。
ところで、大量発注によるボリュームディスカウントを目的として、事業者団体(個々の買主が所属会員となる連合体と言えばよいでしょうか)を設立するといった手法も考えられます。このような手法自体は昔から行われていますし、最近ではインターネットで購入者を募集し、大量発注によるボリュームディスカウントを行うという手法が行われていたりします。
こういった大量発注によるボリュームディスカウントについては、原則的に問題はありません。ただ、事業者団体を通じた取引の市場占有率によって市場価格が硬直化するといった影響がある場合は、購買カルテルとよばれる違法行為と判断される可能性があります。また、通常は事業者団体の方が売主より相対的に力関係に勝る状況になりやすいので、優越的地位の濫用の問題が生じやすいといった特徴もあります。独占禁止法違反はそう簡単に成立するものではありませんが、中小企業だからといって公正取引委員会が大目に見るということは有りませんので、頭の片隅には入れておいた方が良いかと思います。
他者の仕入価格情報を利用した交渉
取引先(売主)に対する減額要求を裏付けるべく、例えば同じ売主より購入している買主より仕入れ価格情報を提供してもらい、こういった情報を元に交渉を行うということも想定されるところです。
この点、売主が買主に対して、どういった取引条件で商品を売るのかは自由であり、買主ごとでその条件が異なっても法律上は問題ありません。一方で、同じ売主より商品を購入している買主間で取引条件について情報交換することも自由であり、法律上の規制はありません。ただ、最近の傾向として、取引条件については第三者に開示・漏えいしないこと、もっと極端な場合は売主と買主が取引を行っていること事実自体を第三者に開示・漏えいしないことを明記する秘密保持契約が増えてきています。秘密保持契約において、仕入れ値が秘密情報であるとされている場合、情報交換することは秘密保持義務違反となりますので、注意が必要です。
(2)取引先(供給元)の見直し
取引先の集約に伴う取引の打ち切り
仕入れコストの削減や取引の効率化を念頭に、同一商品につき複数の売主との取引があった場合において、買主側都合で売主を1つに集約するということも考えられます。この点、誰とどのような取引を行うかは、買主の自由です。したがって、同じ商品・サービスについて売主が複数いた場合、そのうちの1つに選択集中することも法律上は禁止されません。
また、独占禁止法は、不当・不公正な取引条件を押し付けてきた場合や自由経済市場を乱す行為に対して規制をかける法律ですので、買主が単に取引先をまとめたいという意向で取引を打ち切る場合には、独占禁止法の適用はありません。
なお、選択した売主が倒産した場合に、商品・サービスの安定的供給が図れなくなるといった事業リスクは別途考慮する必要がありますが、これは法務リスクとは別観点からの考慮となります。
さて、売主を1つに集約した場合、選考から漏れた売主というものがどうしても出てきます。この場合、当該売主との契約を打ち切ることになるのですが、契約解消の仕方について何か法律上の制限があるのでしょうか。
先に確認しておきますが、これは独占禁止法の問題ではなく、単なる契約の解消の仕方の問題となります。そして、大原則論で申し上げれば、取引を行うか否かは当事者の自由である以上、いつでも取引を解消することができるというのが結論となります。ただ、契約書で取引期間を設けている場合には、中途解約が可能か契約書を読み込む必要があります。
もっとも、中途解約に関する条項が無くても、例えば基本契約と個別契約を別々に締結している場合、個別契約を締結しない=発注を行わないという選択を取れば、事実上契約を解消したのと同じ効果を持ちますので、あえて契約解除の通知を行う必要はないという手法を取ることもできます。また、契約書を締結していても、具体的な買取り義務が定められてないのであれば、やはり新たな発注をしなければ対処可能という場合もあります。
取引を行わない以上、契約解除の通知が必要とイメージしがちなのですが、上記の通り、契約関係を残していても、買主においては何ら不利益を被ることは無い場合もありますので、契約書はよくよく読み返して検討したほうが良いかと思います。なお、売主が買主に依存しており、その依存状態が長期にわたる(製造業でいう下請け業者のようなイメージです)といった継続的契約が成立していたと法的に評価される場合、上記以外に別途考慮する問題がありますが、こればケースバイケースで判断するほかないと考えられます。
リベート
売主を1つに集約する選定過程において、売主よりリベートの支払いを提案されるということもあります。「リベート」という言葉は、何となくイメージの悪い言葉のように思われるかもしれませんが、法律上は何ら禁止されていません。むしろ、一種の販売奨励金の支給であり、取引条件に関する事柄であることから、リベートをどういった場合に支給するかは当事者間の合意で自由に定めることができるというのが、法律の立場となります。
ただ、経済的な側面からいうと、リベートは売主の利益を減少させる行為であることは間違いありませんし、買主との取引上の力関係を考慮して、リベートの支払いが強制されている可能性も否定できません。一定数量の購入を条件としたボリュームディスカウントのところでも触れましたが、優越的地位の濫用に対する懸念を払しょくするのであれば、リベートの支給について客観的な取引条件を設定しておくことが肝要となります。
コンペ方式
売主を集約するに際し、売主ごとで個別に交渉するのではなく、コンペ方式にて行うということも考えられます。特に最近では、インターネット上でコンペを開催した上で取引先を選定するという方法が増加してきているようです。
この点、コンペ方式を行なうことについては、何ら法律上の規制はありません。ただ、昔からそうですが、コンペに参加する者同士が繋がってしまい、取引の機会や条件を内々で決めてしまうことが生じてしまいます。民間のコンペであっても談合は法律上禁止されていますので、当然こういった内々で決めてしまうことは違法なのですが、ときどきコンペ主催者側の担当者も談合に絡んでいるということがあります。この場合、コンペ主催者側は被害者という側面はある者の、談合に関与していた加害者という立場にもなり、独占禁止法等の制裁を受けるリスクが生じますので、社内体制を含めた管理が必要となります。
入札・オークション方式
入札・オークション方式にて売主の集約とディスカウントを図るということもありうる話です。この入札・オークションについては、コンペ方式と同じく、その実施について特段の法律上の規制はありませんが、談合リスクがあることはコンペ方式と同じとなります。
ところで、コンペ方式と異なる注意事項としては、入札・オークションで落札した場合、当然に契約が成立したと言えるのかという問題です。落札した側からすれば契約が成立したという意識を持ち合わせているのが通常です。一方、ディスカウントを目的とした買主側からすれば、思ったほど価格が下がらなかった場合、新たな取引を開始する必要はないと経営判断を行う可能性も否定できません。したがって、ディスカウントを図る買主が主催者となる場合、落札時に契約成立となるのか、入札・オークションの条件を明確に定めることで、無用なトラブルを回避できるよう注意を払うべきと考えます。
(3)中間経費の削減
中間流通業者を飛ばした直接取引の是非
中間経費の削減と書きましたが、要は、買主と売主との間に入っている中間業者(問屋など)を飛ばして、直接取引を行なうことで流通コスト分の削減を図るという手法のことをここではイメージしてください。
この点、誰とどのような取引を行うのかは当事者の自由です。したがって、中間業者が不要であるとして、直接の取引を開始すること自体は法律上禁止されないというのが一応の結論となります。
直接取引禁止条項の有効性
もっとも、中間業者も直接取引を行われてしまっては色々と不都合ですので、通常は直接取引を禁止する旨の条項を定めた契約書の締結を求めてきます。この直接取引を禁止する旨の条項が存在する契約書を締結している場合、原則的にはこのような条項は有効である以上、直接取引を行なうことはNGとなります。
なお、例えば、中間業者が商品等をほぼ独占的に取り扱っており、商品の値段設定に中間業者の意向が強く反映される状況であるため、市場における価格が硬直化し、自由市場経済が阻害されるといった市場全体に悪影響を及ぼすような取引の場合、直接取引を禁止する条項は法的に無効と判断される可能性があります。
しかし、単に一当事者にとって不都合が生じるという程度であれば、独占禁止法の問題は生じないのが実情です。したがって、直接取引を禁止する条項それ自体は原則有効であり、これに違反した場合、損害賠償請求への対応等でかえってコストがかかるリスクを想定する必要があります。
3.経費削減
(1)給料・賃金の削減
給料・賃金削減を検討する前に
賃金削減の検討を行う場面といえば、一般的には経営環境が厳しい状況のときと考えられます。この場合、経営環境の改善=経費削減の一環として人件費の削減を検討するわけですが、人件費の削減手続きに関して法律上は特段の規定はありません。したがって、雇用を守りながら全体で痛み分けを行う賃金カットによる人件費削減、会社規模縮小を伴うリストラ(希望退職、退職勧奨、整理解雇など)による人件費削減のどちらを先に実行しても、法律上は問題がないことになります。
もっとも、これまでの裁判例の蓄積を踏まえると、労働者に痛みを求めるのであれば、まずは使用者・雇用主が先に痛みを甘受するべきであるという考え方が主流です。したがって、賃金削減を行う前に、人件費以外の費目について経費削減を実行していることが前提条件として求められます。
労働者から賃金削減の了解を得るに際しての注意点
最初に指摘しておきますが、一度決めた賃金を削減することは非常に難しいです。なぜならば、会社と労働者との関係は労働(雇用)契約となります。契約=当事者の合意である以上、一方的に契約内容を変更することができないという当然の理論が該当するからです。
一方で、労働者の同意があれば賃金削減は可能です。そして、賃金削減について労働者が同意するということは、法律上は労働条件変更の契約を締結するということを意味します。契約を締結するに際しては、一部を除き口頭でもよいというのが法律上の原則論です。したがって、賃金削減を実施するに際して、絶対に同意書が必要となるわけではありません。
しかし、書面が無いことには、本当に賃金削減に労働者が同意していたのか証拠が無いことになります。特に、労使関係はどうしても使用者・雇用主の力が優位になりがちですので、同意書が無いこと理由に後で「強要された」、「無理やり迫られた」と言われてしまうと、なかなか戦いにくいのが実情です。したがって、法律上は要件とされていなくても、リスクヘッジの観点からは賃金削減に関する同意書はできる限り入手するべきです。
また、同意書の入手方法についても、労使間における使用者・雇用主優位という背景を考慮した場合、賃金削減実施の説明を行った直後に同意書にサインしてもらうのではなく、1週間程度の熟慮期間を設けて同意書を提出してもらった方が望ましいと言えます(その場でサインするよう迫られたと言われてしまうと、これはこれで反論しづらいところがあるためです)。
なお、賃金削減の実施以降、特に異議を挟んでいなかったにもかかわらず、後で突然「本当は同意していなかった」と言ってくる場合があります。使用者・雇用主としては、今さら言ってくるのはおかしい!と言いたいところなのですが、残念ながら裁判所は、明確な同意が無い場合、労働者が真意に同意していたとはなかなか認めてくれません(つまり、カット分の差額を支払うことを命じる判決を出してきます)。したがって、異議を挟まなかったから安心と考えることは禁物です。
賃金削減の対象となる労働者を個別に設定することの可否
賃金削減を実行するに当たり、例えば営業職はOKだが事務職はダメ、管理職はOKだが、平社員はダメといった法律上の決まりごとはありません。したがって、法律上は特定の労働者を対象として賃金削減を行なうことも可能です。よくある事例でいえば、管理職のみ賃金カットを行うといった具合でしょうか。
ただ、例えば、同じ業務に従事している労働者に対し、社長の好き嫌いで一方は賃金削減を実行し他方に行わないとなると、合理性を担保できませんし違法なハラスメントであると法律上は評価されてしまいます。
賃金削減の対象者と絞り込むことについては、会社側で任意に決めることについて原則問題はないものの、対象者の絞り込み基準について合理的な説明ができるようにするべきです。
賃金のどの部分を削減するべきか
一般的な日給月給制の場合、基本給と各種手当といった所定内賃金と、残業等が生じた場合に生じる所定外賃金の合計額が支給されます。また、月給以外にも賞与や一時金、退職金といったものが支給される場合もあります。
一口に賃金といっても色々なものが含まれているのですが、どれから削減すればよいのか、という点については法律上の定めはありません。したがって、賃金削減を実行するに当たっては、先に基本給を切り下げても良いですし、賞与をカットすることも法律上は自由と一応は考えられます。
しかし、月額賃金のうち特に基本給をいきなり切り下げると、労働者はたちまち日々の生活に困ってしまいますので、現実論として基本給の切り下げは最終手段として取り扱うというのが一種の慣行となっています。この慣行に従うのであれば、基本給よりも手当給のカットから賃金削減を実施することが穏当と考えられます。
労働者の同意が得られない場合と賃金削減の実施
上述の通り、労働者保護という法律の性格上、労働者の同意の有無についてはかなり慎重な判断が行われているのが実情です(裁判の場合、労働者の同意が簡単には認められない傾向があります)。
一方、労働法の特殊性として、たとえ労働者の同意が得られなかったとしても、合法的に賃金削減を実施することが可能な場合があります。これは、多数の労働者に対する労働条件の画一的処理を可能にするという観点から、就業規則(賃金規程)を変更することによって一方的に労働条件の変更ができると法律上は定められているからです。就業規則によって労働条件の変更が可能という点に限っていえば、むしろ使用者・雇用主側に有利な内容といってよいかと思います。ただ、就業規則・賃金規程によって賃金削減を図ろうとする場合、これまでに蓄積された裁判例によって一定のハードル・要件が存在します。決して無条件に賃金削減ができるわけではないことに注意が必要です。
まず、就業規則・賃金規程の変更手続きの形式面として、過半数代表者を選任し、意見を聴いたうえで労働基準監督署に提出するという手順が必要となります。この手順ですが、賃金削減の場面に限って特別要件が加重されているという法律上の決まりごともありません(例えば、事業所に所属する労働者の過半数の同意が必要といった要件はありません)。したがって、通常の就業規則の変更手続きと同じ手順で進めてよいということになります。なお、念のため付言しておきますが、労働者代表が仮に反対の意見表明を行ったとしても、その事情のみで就業規則・賃金規程の変更が無効となるわけではないことも同様です。
次に、内容面での検証が必要となります。反対者の意思に反してでも強制できるだけの合理的理由、特に賃金という日常生活に直結するものを変更する以上は、高度の合理性が求められます。この合理性については過去の裁判例を踏まえ、労働契約法10条で次のようにまとめられています(※カッコ内の事情は当方で加筆した例示です。法文上には記載がありません)。
・労働者にとっての不利益の程度(例えば、賃金カットが一定期間に限定される、勤続年数によってカット率が異なる、賃金カットの代償措置として職務軽減や休日を増やす等の事情を考慮する)
・労働条件変更の必要性(例えば、金融機関より人件費削減の助言を受けている、人件費以外の経費削減を実行している等の事情を考慮する)
・変更後の内容の相当性(例えば、変更後の内容が同業他社と比較しても高めの水準である等の事情を考慮する)
・労働組合等との交渉状況(例えば、多数回にわたり労働組合等に説明を行っている、決算書など具体的な資料を開示しながら交渉を行っている等の事情を考慮する)
全労働者の同意が得られ場合と就業規則の変更の是非
賃金削減について全労働者の同意が得られた場合であっても、就業規則・賃金規程の変更は行うべきです。なぜならば、法律上、就業規則に定める労働条件を下回る個別の合意は無効、つまり、就業規則に定める労働条件に自動的に引き上げられるという定めがあるからです(労働契約法第12条)。せっかく苦労して労働者の同意を得たにもかかわらず、就業規則・賃金規程の変更を忘れて後で足元をすくわれてしまっては元も子もありません。忘れずに就業規則・賃金規程の変更手続きも実施するべきです。
また、時々せっかく就業規則・賃金規程を作成しているにもかかわらず、金庫の中にしまい込むなどして労働者に見せない使用者・雇用主もいます。が、就業規則・賃金規程の有効性を担保するための重要な一要件として「労働者への周知性」、つまり労働者がいつでも就業規則・賃金規程の内容を確認することができる状態にあることがあげられます。この点も忘れずに実施したいところです。
(2)家賃・不動産賃料の削減
契約書に根拠のない賃料減額申出の可否
契約書に賃料減額請求ができる旨明記されていない場合、賃料減額請求ができないと諦めている賃借人もいるようですが、それは間違いです。なぜならば、契約書に明記されていなくても、借地借家法の適用がある賃貸借契約の場合、借地借家法に基づいて賃料減額請求を行なうことが可能となっているからです。万一、賃貸借契約書において賃料減額請求ができないと契約書に規定されていたとしても、当該規定は無効ですので、賃料減額請求することは全く問題ありません。
もっとも、借地借家法に根拠があるとはいえ、重大な例外があります。それは、定期賃貸借契約の場合です。定期賃貸借契約の場合、賃料減額請求ができないと規定されているのであれば、その規定は有効であり、結果として賃料減額請求権を行使することは不可能となります。最近、定期賃貸借契約が増加しつつありますが、こういった賃借人にとって思わぬ落とし穴となる条項が定められていることが多いので、注意が必要です。
賃料減額の申出と協議期間中の対応
借地借家法上の賃料減額請求権について色々と誤解を招きやすいところがあるのですが、実務上の対応としては、次のようなものとなります。
・賃貸人が減額に応じた場合、合意内容に従って減額となった賃料を支払えばよい。
・賃貸人が減額に応じない場合、とりあえずは従前通りの賃料を支払いつつ、賃料減額を認めてもらうための裁判を起こすしかない。
ところで、よく賃料減額請求権は、権利を行使したときから効果が生じると専門書等に書かれていますが、理屈上はその通りです。ただ、実際に賃料減額請求を行ったものの、減額に正当性が無い場合は、賃借人が一方的に賃料を減額しただけに過ぎませんので、賃料未払いとなります。この結果、下手をすれば賃貸人より賃料不払いによる契約解除を言い渡されることにもなりかねません。賃貸人が賃料減額に応じない場合、あくまでも最終的には裁判所が賃料減額の正当性を決めることになります。そして、仮に正当性ありと言う判断が出たのであれば、その時に払い過ぎた分を返還してもらい清算を図るというのが法律上の手続きとなりますので、ご注意ください。
賃料減額交渉の不調と賃貸借契約の中途解約
賃料減額請求権の行使は、あくまでも賃料に関する事項だけであり、賃貸借契約の有効性や賃借期間にまで影響を及ぼすものではありません(もちろん、法律を離れた人間関係が気まずくなるという問題はありますが)。したがって、賃料減額請求権を行使したから、自動更新が無くなる、期間満了前までに賃貸借契約が当然に終了するという訳ではありません。
ところで、賃貸借契約の期間満了前に中途解約する権利は当然には認められていません。つまり、中途解約をするのであれば、賃貸借契約書に中途解約に関する条項が定められている必要があります。したがって、賃借人において、賃料減額請求を認めてもらえないのであれば他の物件に移ると主張したところで、賃貸借契約は継続しているわけですから賃料支払義務を負担することになります。上記でも記載した通り、賃料減額請求を行ったものの失敗に終わった場合のことが心配である、というのであれば、中途解約が可能か、引越し先の目途が立っているか等の環境を整備してから権利行使をした方がよいかもしれません。
4.支払のタイミング
(1)支払いを遅らせることによるキャッシュの確保
取引条件をどのように定めるかは当事者間の自由です。したがって、商品・サービスの先渡し、その対価の支払いを10年後とすることも、当事者間で了解しているのであればまったく問題ありません。
ただ、表面的には当事者の納得を得ていると言っても、実際には取引上の力関係の優劣や、取引の依存性など様々な事情が絡んできます。特に、下請業者と呼ばれる事業者にとっては、親事業者の意向を無視することはできませんし、無視をすれば取引を打ち切られてしまい、たちまち明日からの生活に困ってしまうという非常に弱い立場にあります。
こういった実態を踏まえて、下請イジメを防止することを目的とした法律が下請法となります。そして、この下請法に該当する取引の場合、たとえ、当事者間が真意で了解していたとしても、支払いサイト(期間)は、商品の引渡し・サービスの提供を受けた日から60日以内の支払いを行わないと違法とされてしまいます。
したがって、下請法に該当する取引であるか否かは、常に意識を持っている必要があります。なお、下請取引と聞くと、建築や製造現場をイメージするかもしれませんが、下請法が対象としている取引はこのようなものに留まりません。システム制作、修理、清掃サービスなど「え!?こんなの下請取引なんて普通言わないよ」というものまで含まれています。要注意です。
(2)支払い期日前の支払いに応じる条件としての値引き要求
繰り返しになりますが、取引条件をどのように設定するかは当事者間の自由です。したがって、早期現金化を理由とした値引き要請等も原則的には問題ありません(その典型例が手形割引です)。
ただ、上記でも記載したとおり、取引関係の実情(優劣や依存度など)によって、本当は値引きなど応じたくないのに、承諾せざるを得なかったということは現実に発生しています。そこで、一定の取引については下請法により、値引き要請の禁止が定められており、これについてもたとえ当事者間で合意していたとしても違法と判断されてしまいますので、注意が必要です。
<2020年6月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
|
|

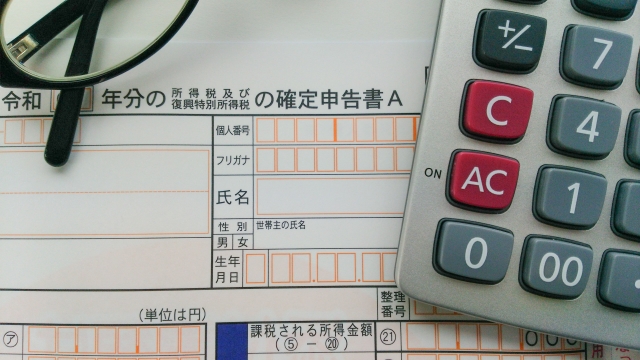




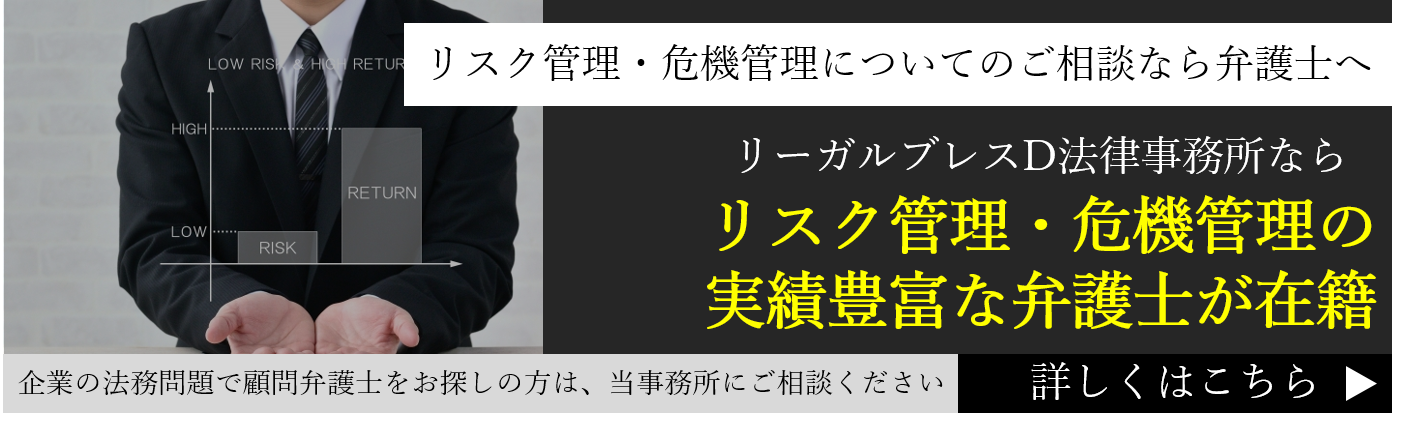

 弁護士 湯原伸一
弁護士 湯原伸一




































