Contents
【ご相談内容】
当社の従業員が自死(自殺)したとの一報が入りました。今後、ご遺族への対応を検討するにあたり、何か注意するべき事項があるのであれば、教えてください。
【回答】
葬儀への参列などご遺族に対する社会常識的な対応はもちろんのこと、社内の動揺や困惑をなるべく少なくするための従業員向け説明会の開催などが必要となるのは、直ぐに思いつくかと思います。
ここでは、会社が遺族と今後の対応を行うに際して、問題となりやすい法的事項について解説を行います。
具体的には、金銭の清算(未払い賃金、死亡退職金、生命保険など)に関する問題、自死・自殺を会社の責任であると遺族が主張してきた場合について検討を行います。
【解説】
1.一報を受けた直後の対応
従業員の遺族からすれば、突然の出来事に混乱・狼狽等していると予想されます。当然のことながら、遺族の感情を逆なでするような言動、故人を揶揄する等の会社に敵意を向けられても仕方がないような言動は現に慎むべきです。また、会社内にある私物の処理はどうすればよいか、健康保険証の返還、社会保険の手続き等の説明といった会社側の事情(会社にとっての事務的作業)について、いきなり話をすることは回避するべきです。
まずはお悔やみ申し上げると共に、遺族の意向があるのであれば話を聞く(聞くのみで、その場で判断する必要はありません)といった、社会常識として求められる対応を行うことを意識する必要があります。
そして、葬儀等の一連の手続きがひと通り終了し、遺族が落ち着き始めるタイミングで(早くてもだいたい葬儀終了後10日以降が目安でしょうか)、私物の引取りや社会保険手続きなどの説明などを順次進めていくといった方針をとればよいと考えられます。
2.従業員の地位に基づいて発生する金銭の清算
従業員が死亡した以上、労働契約は当然終了となります(一身専属的な契約)。
その後の処理は、就業規則等の社内規程に従って処理することになりますが、死亡した従業員に関係する金銭面の問題について、押さえるべきポイントを解説します。
(1)未払い賃金
未払い賃金は死亡した従業員の相続財産となります。したがって、相続人に対して、法定相続分に従って支払うことが原則となります。会社としては、遺族より、相続人及び法定相続分が計算できる資料(戸籍謄本など)を提出してもらい、当該資料を確認の上、支払い手続きを行うことになります。
なお、相続人間の協議により代表受取人と名乗る者が出現する場合があります。また、賃金を支払う前に遺産分割協議が成立したとして、賃金債権を単独取得した相続人が出現する場合もあります。前者については、相続人全員によって代表受取人を指名したことを裏付ける資料(戸籍謄本以外に、代表受取人として指名したことを証する指図書、印鑑証明書など)の提出を求め、確認が取れたら速やかに支払い手続きを行うという対応でよいと考えられます。一方後者については、遺産分割協議書(遺産分割協議書の原本のみならず、遺産分割協議書に押印してある印影に対応する印鑑証明書を含む)の提出を求め、やはり確認が取れ次第、速やかに支払うという対応になると考えられます。
ちなみに、相続人の意向を確認することなく、死亡した従業員が給料振込先として指定した金融機関口座に振込んで支払うという対応をとる会社もあるようですが、リスクがあります。なぜならば、仮に金機関口座に振込んで支払ったとしても、後日、当該口座が名義人死亡を理由に凍結された場合、相続人は直ぐには当該口座から引き出すことができないからです。相続人の中には従業員の賃金が唯一の生活資本である場合も想定されます。こういった方から強いクレームを受け、会社業務に支障をきたすことにもなりかねませんので、死亡した従業員の金融機関口座に振込むのは回避するべきです。
(2)死亡退職金
会社によっては、死亡した従業員の家族への支援等を目的として、独自に死亡退職金制度を設けていることがあります。この死亡退職金の取扱いですが、単純に相続財産として処理するわけにはいかないこと要注意です。
まず、死亡退職金の受給権者の範囲・順位について、相続法(正確には民法の相続編に規定されている内容)と異なる内容が定められている場合があります。例えば、「死亡退職金は遺族に支払う。遺族の範囲及び順位は労働基準法施行規則42条から45条までを準用する。」といった規定です。この場合は、相続財産として取り扱わないことになります(※労働基準法施行規則42条から45条に定める遺族の範囲・順位は、相続法に定める相続人の範囲・順位と異なるため)。したがって、相続特有の問題(相続人の範囲や順位、法定相続分など)を考慮することなく、規定に従って支払い手続きを行えば問題ありません。
次に、死亡退職金の受給権者の範囲・順位について、相続法と同様の場合があります。例えば、「死亡退職金は遺族に支払う。」といった規定です。このような受給権者の範囲・順位について特段の定めがない場合は、相続人に対し、法定相続分に従って支払いを行うことが原則となります(その後の対応は上記(1)と同様です)。
(3)退職金
前述の死亡退職金ではなく、ここでは単純に支払い未了となっていた退職金を意味します(例えば、定年退職したものの、嘱託として引き続き勤務する場合、退職金の支払いが保留となっていることがあります)。
この退職金については、相続財産として取扱うことになります。したがって、前述の(1)と同様の処理を行えば対処可能です。
(4)団体生命保険
ここでいう団体生命保険とは、保険契約者である会社が、従業員を被保険者とし、保険金受取人を会社として掛けている生命保険のことを意味します。
純粋な理屈でいうと、保険契約者と保険受取人が会社、保険料負担者も会社である場合、従業員が死亡したことによって発生する保険金を会社が受け取り、会社のために使用することは何ら問題がないはずです。しかし、被保険者が従業員であるという倫理面、本来このような団体生命保険は従業員の遺族への福利厚生目的があること等から、会社が全額保険金を受領することについては違和感を持つ人も多くいました。この結果、過去には社会問題化し、遺族が会社に対して保険金相当額を支払うよう要求する多数の裁判が起こされる事態にまで至りました。
一連の裁判の結果、会社が無条件に全額保険金を受領するのはおかしいということにはなりました。もっとも、どの程度遺族に支給すればよいのか等の具体的な基準は現在も不明確なままです。現在の保険実務では、このような団体生命保険に加入させるに先立ち被保険者である従業員の意思確認はもちろんのこと、会社が遺族に対し、受領した保険金のうちいくら支給するのか社内規程の策定を条件とし、これらの条件がそろわない限り団体生命保険に加入させないといった運用が行われていますが、遺族への支給額があまりに低額の場合、やはり問題視されるリスクは残ると考えられます。
いずれにしましても、団体生命保険に基づく保険金については、当然に保険金全額が会社に帰属するとは考えず、遺族や相続人に対して、死亡退職金や弔慰金等の名目で一定額を支払う必要があると考える必要があります。
(5)相続人が不明の場合の対応
上記(1)から(4)までは、遺族や相続人が存在することを前提に開設しました。
しかし、死亡した従業員の中には身寄りがなく、相続人も不明という場合もあり得ます。この場合、法務局へ供託することで支払い義務を消滅させることができないか検討することになります。
なお、供託する際の手続きについては、各法務局によってローカルルールがあるようです。したがって、事前に供託を行う法務局に直接問い合わせて確認をとった方が無難です。
3.自死・自殺原因と会社の帰責性の調査
死人に口なし…というのは非常に悪い言葉にはなってしまうのですが、なぜ、自死(自殺)したのか従業員本人に語らせることができない以上、直接的な原因は明らかとはなりません。もちろん、遺書が残っていた場合はそれを手がかりとすることはできますが、本人が書いた遺書といえるのか、遺書の内容を全面的に信用してよいのか等の問題があり、遺書だけを根拠とするというのも難しいところがあります。
とはいえ、会社としても、遺族から自死(自殺)原因は会社にあると主張されることに備え、ある程度の準備は進めていく必要があります。ここでは典型的な2つのパターンを解説します。
(1)過労自死(自殺)
過重な業務等を原因として、従業員が精神疾患となることで自死(自殺)するといった事例が存在します。仮に会社が、自死(自殺)した従業員に対して過重な業務等を負わせていたというのであれば、安全配慮義務違反を問われることになります。過重な業務等を原因とした精神疾患の発症はともかく、そこからさらに自死(自殺)まで予見可能か等の疑問を持たれるかもしれませんが、具体的な事情によっては自死(自殺)に至ったことまで会社が責任を負うといった裁判例は複数存在するところです。
さて、過労自死(自殺)の可能性を検討するにあたっては、まず過重な業務等の有無を調査することになります。最初に取り掛かる事項としては、客観的に把握しやすい従業員の勤務時間の調査が考えられます。最低でも1年分、できれば過去2年分程度の勤怠記録(タイムカード、出退勤簿等)を準備すると共に、パソコン等の端末の稼働状況(ログイン、ログアウト時刻など)で実働時間を把握することが望ましいと考えられます。また、上司・同僚・部下など関係者へのヒアリングすることによる実働時間の把握も行うべきです。
その上で、厚生労働省が公表している「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」にある精神疾患発病の原因となる長時間労働に該当するか否かの判断を行い、会社としての見通しをつけることになります。
ところで、過重な業務等の該当性は、上記のような実働時間の長短だけで決まるものではありません。例えば、会社経営に影響する重大なミスを犯したがための事後対応に当たっていた等の業務の内容・質も考慮対象となります。実働時間と同じく、最低でも過去1年程度の具体的な業務内容の把握(業務日報やパソコン等の端末に保管されている情報の収集、上司・同僚・部下など関係者へのヒアリング等)を行う必要があります。その上で、同様に「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」への該否を検討することになります。
これらの検証を踏まえ、会社の責任の有無について、会社内部としての見解を整理し、万一遺族等より問い合わせがあった場合は、説明ができるように準備しておくことが肝要です。
なお、遺族は遺族なりに何らかの証拠(例えば遺書など)を保有している場合があります。いかなる場合も事前の内部調査の結論を押し通すというスタンスではなく、遺族側の主張や裏付け証拠を確認しつつ、再検討を行うという対応も当然必要となります。
(2)ハラスメント
パワハラに代表されるように、例えば上司からの嫌がらせ等を苦にして自死(自殺)するという事例も存在します。
具体的にどういったハラスメントがあったのか、遺族側の主張を待たない限り、事前に社内調査を行うことは難しいところがあります(調査対象範囲が際限なく広がるため、人的リソースや時間等の関係で、調査のしようがないという意味です)。
もっとも、「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」に記載のあるような事象はなかったかだけでも、とりあえずは上司・同僚・部下など関係者へのヒアリング調査を行っておくのが無難です。また、会社が貸与していたパソコン等の端末に残されている情報(特定のWEBページへのアクセスログを含む)も念のため取り出し保管するといったことも検討してよいと考えられます。さらに、過去1年程度を振り返り、例えば、深刻さまでは感じられない愚痴ともとれるような相談を同僚にしていなかったか、匿名によるパワハラの告発がなかったか等の周辺事情も探れるようであれば、情報収集したいところです。
上記のような調査を行いつつ、万一、遺族側よりハラスメントを原因とした自死(自殺)の主張が出てきた場合は、遺族側より、具体的なハラスメントの内容の聞き取りと証拠の確認を行いつつ、社内での本格調査(再調査)を実施し、対処することになります。
弁護士へのご相談・お問い合わせ
当サイトの記事をお読みいただいても問題が解決しない場合は
弁護士にご相談いただいた方がよい可能性がございます。
下の電話番号もしくはメールにてリーガルブレスD法律事務所までお問い合わせください。
06-4708-7988メールでのご相談4.遺族より労災申請があった場合の対応
会社からの説明に納得がいかない遺族が、労災申請を行うという場面は十分想定されます。この場合、会社として絶対にNGの対応が、労災申請自体に協力しないことです。労災申請は労働者(遺族側)の権利であり、会社の関知しないところで手続き自体は進めることが可能です。また、会社が労災申請自体に協力しないとなると、かえって会社が労災隠しを行っているのではないか等の余計な疑いを遺族や労働基準監督署等に持たれかねません。
したがって、遺族側が労災申請を行うのであれば、その手続きを妨害するような対応はとるべきではありません。
もっとも、遺族側が作成した労災の申請書の内容について、会社として承服できないような記述もあり得ます。この場合、遺族側の記述それ自体はそのままにしておき、会社の意思表示として、「申請書記載内容には異議がある」旨意見を新たに書き込むなどして対処するべきです。これは時々あるのですが、会社としては異論があるものの、特に対処することなく労災申請手続きに協力したところ、「会社は労災申請書に記載された内容に異議を出さなかった以上、記載内容を認めていた」という遺族側の後日の主張を防止するためです。
ちなみに、労災として認定された場合、会社としては極めて不利な立場になります。理屈の上では、労災認定と民事上の責任(安全配慮義務違反)は別々に判断されます。しかし、実際には労災として認定されてしまうと、安全配慮義務違反ありという流れになってしまうのが実情です。このため、会社としては責任があることを前提に、具体的な損害賠償額の算定で協議を進めるという方針を取ったほうが良いと考えられます。
<2020年10月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
|
|






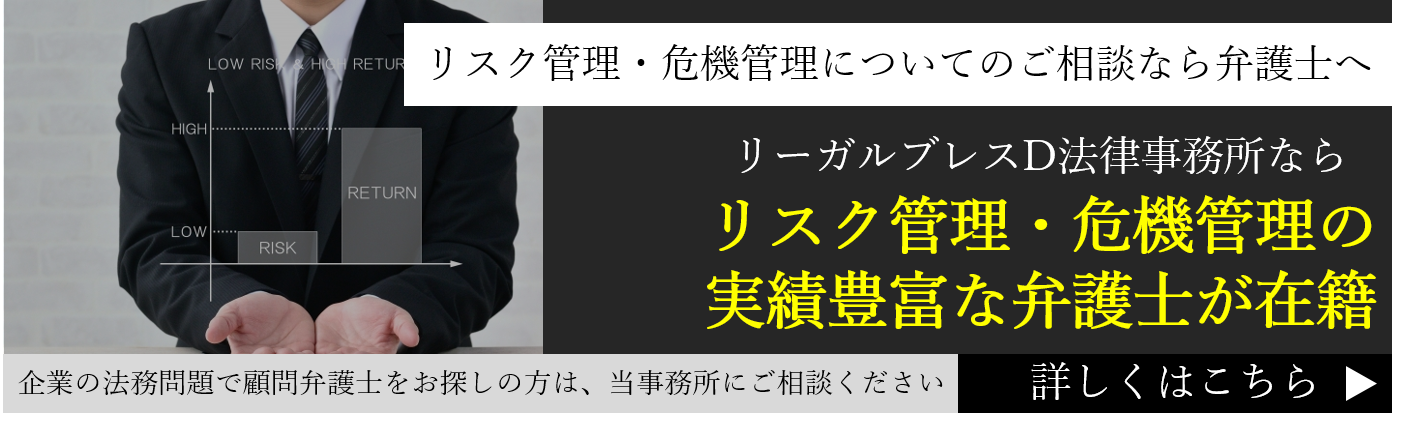

 弁護士 湯原伸一
弁護士 湯原伸一




































