Contents
【ご相談内容】
いわゆるBtoC取引を行うに指し、取引条件を明記した契約書を当社で作成した上で、お客様であるお客様にサインしてもらおうと考えています。
サインしてもらった契約書に書いてある契約内容は有効になることを考慮し、なるべく当社有利の契約書を作成しようと思うのですが、契約内容を定めるに当たり何か法律上制限はあるのでしょうか。
【回答】
法律上の大原則論は、契約書に定めている内容が有効であるという点です。
ただ、事業者がお客様(消費者)と間で何らかの契約書を取り交わす場合、事業者側が契約書を作成することが多いことから、契約書の内容はどうしても事業者側有利な内容になりやすいのが実情です。このため、お客様(消費者)の権利が不当に害される等の問題が生じます。
こういった問題を解消するため、消費者契約法や特定商取引法が定められています。
事業者が契約書を作成する場合、コンプライアンスの観点からこれらの法律を意識する必要があります。特に昨今では、あまりに一方的な契約内容の場合、SNS等で情報が拡散され、いわゆる炎上騒ぎになるなど風評被害をもたらすこともありうることから要注意です。
以下では、特に問題となりやすい条項を解説します。
【解説】
1.契約の成立段階で注意したい条項
(1)勧誘段階での事情を原因とした取消を認めない条項
事業者としては、何とか契約にまでこぎつけた以上、できる限り契約は解消されたくないと考えます。そこで、例えば次のような条項を定める場合があります。
(例)
お客様は、本契約成立前に当社が行った説明内容及び勧誘行為を原因として、本契約を取り消すことができないものとします。
ただ、こういった条項を定めたとしても、消費者契約法4条に該当するような行為、すなわち消費者が誤認した場合(消費者契約4法条1項、2項)、消費者が困惑した場合(消費者契約法4条3項)、契約の目的となる分量等が過量である場合(消費者契約法4条4項)には、こういった条項を定めても効力がなく、お客様(消費者)は消費者契約法に基づき契約を取消すことができます。
また、取引類型が特定商取引法に定める訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売に該当し、事業者がお客様(消費者)に対して不実告知を行う又は故意に事実を告知しなかった場合、やはりお客様(消費者)は特定商取引法に基づいて契約を取り消すことが可能です。
以上のことから、上記のような条項は定めるべきではないと考えられますが、あえて定めるのであれば、せめて「但し、法令による場合はこの限りではない。」といった一文を挿入したいところです。
(2)自動的に契約申込みを行ったものとする条項
事業者としては、一度つかんだお客様を手放したくないとして、お試し・キャンペーン期間を経過すれば自動的に本契約に移行するといった条項を定めることがあります。また、なるべきお客様よりたくさんの注文を受けたいとして、付加商品・サービス等のオプションが自動的にセットになっているといった条項を定めることがあります。例えば、次のような条項です。
(例)
商品に関する無料お試し期間が経過する期間内にお客様よりご連絡がない限り、有料定期便による商品の提供契約となることをお客様はあらかじめ同意するものとします。
上記内容は消費者契約法10条前段に違反するものであり無効となります(ちなみに、消費者契約法10条前段では「消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす」条項は無効と定めています)。
契約内容に変更が生じる場合は、事業者としては契約書の内容で対処するのではなく、お客様(消費者)より積極的に申込みを受けるといった作為対応が求められることに注意が必要です。
(3)法定書面の省略を認める条項
事業者としては契約書を適切に用意し、お客様(消費者)と取り交わした以上、特に問題にはならないと考えていることが多いのですが、特定商取引法に定める取引類型、具体的には訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売、訪問購入に該当する場合、契約書とは別に特定商取引法が定める書面をお客様(消費者)に交付する必要があります(本記事執筆当時である2020年12月時点では電子データでの交付は認められていません)。
この点を意識しつつ、せっかく契約書を作成する以上、特定商取引法が定める書面までは交付不要とする条項を定める事業者も存在するようです。例えば、次のような条項です。
(例)
お客様は本契約書の交付を受けることで、特定商取引法が定める書面の発行を要求しないものとします。
厳密には、本契約書の内容が、特定商取引法に定める事項をすべて漏れなく記載しているのであれば、特定商取引法違反にはならない可能性があります。ただ、特定商取引法が求める記載事項はかなり細かな事項も含まれており、また文字の大きさや文字の色等も指定があることから、別書面を作成の上、お客様(消費者)に交付したほうが賢明です。
なお、特定商取引法が定める書面を発行していない場合、事業者にとって一番の痛手となるのは、どれだけ時を過ぎても理屈の上ではクーリングオフを主張されてしまう点にあります。
弁護士へのご相談・お問い合わせ
当サイトの記事をお読みいただいても問題が解決しない場合は
弁護士にご相談いただいた方がよい可能性がございます。
下の電話番号もしくはメールにてリーガルブレスD法律事務所までお問い合わせください。
06-4708-7988メールでのご相談
2.お客様(消費者)からの中途解約に関して注意したい条項
(1)解除権の放棄or解除の可否を事業者に委ねる条項
事業者としては、お客様に少しでも長く契約を続けてもらいたいと考えます。このため、お客様からの契約解除を制限するべく、次のような条項を設ける場合があります。
(例)
お客様は、本契約成立後、いかなる理由があっても返品・返金・交換を申し立てることができないものとします。
上記条項例ですが、たしかに、お客様都合による中途解約について制限したいというのであれば理解はできます。しかし、上記条項例の場合、事業者に契約違反がある場合(欠陥のある商品を引き渡した等)までお客様(消費者)は契約解除を主張することができず、明らかに不当です。そこで、消費者契約法8条の2では、「事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させる」条項と「事業者に解除権の有無を決定する権限を付与する」条項を無効と定めています。
したがって、上記条項については、お客様都合による契約解除は認めないといった内容に修正するべきです(但し、後述(3)で解説する特定商取引法により付与されたお客様(消費者)の中途解約権は別途考慮する必要があります)。
(2)クーリングオフを認めない条項
クーリングオフは事業者の責任の有無を問わず、お客様(消費者)の一方的都合により契約解消の効果を生じさせる、事業者にとっては極めて都合の悪い条項です。しかもクーリングオフの場合、事業者は全額(満額)金銭を返還する必要があるのに対し、お客様(消費者)は現存利益の範囲内で返還すれば足ります(つまり、商品が一部でも利用されていると利用済みの商品しか戻ってこないことを意味します)。
このため、事業者としてはクーリングオフを阻止しようと、次のような条項を定める場合があります。
(例)
お客様は、特定商取引法等の法令に基づき認められるクーリングオフ(無条件解除)について、その権利を行使しないものとします。
特定商取引法等に基づいて認められるクーリングオフの権利は強行法規であり、これを当事者の合意によって変更することは不可です。したがって、上記のような条項例を定めても無効です。
クーリングオフ対策は非常に悩ましいところがありますが、事業者にとって根本的な対処法は皆無であり、契約書の修正だけでは如何ともしがたいことをむしろ確認したほうが良いと考えられます。
なお、時々勘違いされる方がいるのですが、クーリングオフは特定商取引法に定める取引類型全てに適用されるわけではありません。すなわち、訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入においては8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日間と定められていますが、通信販売についてはクーリングオフの適用はありません。代わりに後述(5)で記載する法定返品制度が認められるにすぎないこと、注意が必要です。
(3)お客様(消費者)都合による中途解約を認めない条項
上記(1)では、事業者に契約違反等の責任がある場合にまでお客様(消費者)の契約解除権を制限するのは不当であるとして、消費者契約法8条の2により契約が無効となる旨解説しました。逆に言えば、事業者に責任がなくかつ上記(2)のクーリングオフの適用もない場合において、お客様(消費者)の一方的都合で中途解約が可能となると、これは事業者にとって不都合です。
したがって、例えば次のようなお客様(消費者)の一方的都合による中途解約を認めないことは原則有効です。
(例)
お客様は、当社に契約違反がないにもかかわらず、お客様の都合のみを理由とした本契約の解約を行うことができないものとします。
もっとも、法令によりこの原則に修正が入る場合があります。
例えば、特定商取引法に定める取引類型のうち、連鎖販売と特定継続的役務提供がその典型例です。特定商取引法に基づく中途解約権を認めない旨の契約内容を定めても、その契約は無効となります。連鎖販売(いわゆるネットワークビジネス)はともかく、特定継続的役務提供(英会話教室や学習塾、エステ、美容医療など)を行う事業者は意外と特定商取引法の適用対象であることに気が付いていないことも多くみられることから注意が必要です。
(4)過量販売による契約解除を認めない条項
過量販売とは、顧客に対して通常必要とする分量を著しく超える商品等を販売することをいいます。事業者としては、少しでも多くの商品等を売ることで利益を確保したいところ、お客様と適切に交渉して販売したにもかかわらず、あとでこの過量販売規制に基づく契約解除を主張されてしまうと辛いところがあります。そこで、過量販売規制を免れるべく、契約書に次のような条項を定める場合があります。
(例)
お客様は自らの意思と判断に基づいて複数の商品を購入したことを確認し、本契約成立後において過量であることを理由に本契約の解除を申立てないものとします。
特定商取引法に定める取引類型である訪問販売や電話勧誘販売に該当する場合、上記のような条項を定めても無効となります。訪問販売や電話勧誘販売に該当しない場合、当然に無効と判断されるわけではありませんが、結局のところ過量か否かでお客様(消費者)トラブルになる可能性は否めません。
何をもって過量と判断するのかは難しいところがありますが、事業者としては、なぜこの数量を販売することになったのかその交渉過程を記録化すると共に、事業者から見ても冷静に考えれば数量が多くないか検討するなどの現場対応が必要になると考えられます。
(5)通信販売における中途解約条項
上記(2)でも記載しましたが、特定商取引法に定める取引類型のうち通信販売についてはクーリングオフの適用はありません。したがって、通信販売における契約書では、上記(3)のような規定を設けることは問題ありません。
ところで、仮に上記(3)のような中途解約を禁止しない旨の契約内容を定めなかった場合、特定商取引法に基づき、商品引渡し日から8日間に限ってお客様(消費者)都合による中途解約が可能とされています。ただし、この通信販売における中途解約権は強行法規ではありません。すなわち、当事者間の合意に基づいて特定商取引法の適用を排除することが可能です。
したがって、通信販売において、特定商取引法に基づく中途解約を排除したいのであれば、その旨契約内容として定めることで対策を講じることになります。
3.事業者からの中途解約に関して注意したい条項
契約書を作成する際、事業者による契約解除に関する条項はある程度テンプレート化しているところあり、それを参照しながら作成することも多いと予想されます。そして、そのテンプレートの条項には、お客様において成年後見等の開始した場合には、事業者は契約解除可能と定めている場合があります。例えば次のような条項です。
(例)
お客様が成年後見開始の審判、保佐の開始の審判、または補助の開始の審判を受けた場合、当社は本契約を解除することができるものとします。
ただ、上記のような条項は、消費者契約法8条の3により無効となります。比較的最近(2018年)改正のためか、成年後見等を原因とした解除事由を定めている契約書はまだまだ世に出回っているようです。しかし、上記で記載した通りですので、成年後見等を事業者による契約解除事由とする契約内容は削除するべきです。
4.事業者の損害賠償責任に関して注意したい条項
(1)全部免責条項
事業者としては、契約に基づく業務を遂行する上で細心の注意を払いつつも、万一何かあった場合はできる限り損害賠償責任を負わないようにしたいと考えがちです。そこで、次のような条項を契約書に定める場合があります。
(例)
当社は、本契約の遂行により生じたお客様の損害について、債務不履行・不法行為その他の原因の如何を問わず、一切の責任を負わないものとします。
この条項は事業者にとっては大変魅力的ではあるものの、消費者契約法8条により無効となります。したがって、原因に関わらず一切の責任を負わないとする契約内容は定めるべきではありません。事業者としては、後述(2)で解説するように責任範囲をどこまで限定できるのかを検証するべきです。
なお、責任の有無について事業者に決定権を委ねるという条項を設けるといった対処法を行う事業者もいるようですが、やはり消費者契約法8条により無効となります。
ところで、上記条項にある債務不履行責任の1つである「契約不適合」については一定の例外があります。すなわち、契約不適合に基づく損害賠償責任を事業者が負担する代わりに、履行の追完(例えば商品の交換など)若しくは不具合の程度に応じた代金減額を行う、又は他の事業者が履行の追完若しくは損害賠償責任を負担する場合には、損害賠償責任をすべて免責する条項も有効と定められています(消費者契約法8条2項)。
商品売買等で不具合品があっても直ぐに適合品に交換対応ができるというのであれば、事業者が負う責任を代品交換に限定する旨の契約条項とするといった対処が考えられます。
(2)一部免責条項
上記(1)と同様に、事業者としては損害賠償責任をできるだけ軽減したいと考えがちです。そこで、負担するべき損害賠償額について一定の制限(上限)を設けるといった条項を定める場合があります。例えば次のような条項です。
(例)
当社は、本契約の遂行により生じたお客様の損害について、債務不履行・不法行為その他の原因の如何を問わず、商品代金額を超えて責任を負わないものとします。
一見すると合理的なようにも思われるかもしれませんが、このような条項についても消費者契約法による制限があります。すなわち、事業者が「故意又は重大な過失」によりお客様に損害を与えた場合、上記のような一部を免責する条項は無効となります。裏を返せば、「軽過失」の場合のみ一部免責条項は消費者契約法上も有効となります。したがって、上記条項例であれば、末尾に「但し、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。」といった一文を挿入する等の対応が必要となります。
なお、上記(1)でも触れましたが、責任の程度(範囲)について事業者に決定権を委ねるという条項を設けるといった対処法を行う事業者もいるようですが、同様に消費者契約法8条により無効となります。
5.お客様(消費者)の損害賠償責任に関して注意したい条項
(1)解除に伴う違約金・損害賠償額の予定を定めた条項
何らかの事由により契約が解除となり事業者が損害を被った場合、事業者はお客様に対して損害賠償請求することが可能となります。ただ、実際の損害賠償実務を経験すれば分かるのですが、具体的な損害額を算定することは結構難しい場合があります。そこで、損害賠償請求を容易にするために、あらかじめ損害賠償の金額や算出方法を定めておき、それを契約内容とすることがあります。例えば次のような条項です。
(例)
当社が、お客様の責めに帰す事由に基づき本契約を解除した場合、お客様は当社に対し、違約金として1億円を支払うものとします。
契約解除に伴う違約金や損害賠償の予定を行うこと、それ自体は問題ありません。ただ、一般的なBtoC取引において、事業者が1億円もの損害を被ることは通常想定しづらく、異常に高額の違約金等をお客様(消費者)に支払わせるのは不当と考えられます。そこで、消費者契約法では「解除の事由、時期等の区分に応じて」「同種の契約の解除に伴い生ずべき平均的な損害」を超える違約金等については、その超えた金額分については無効と定めています(消費者契約法9条1号)。
現場実務で問題となるのは「平均的な損害」をどのように算出するかです。これは取引内容ごとで精査するほかありませんが、事業者としては、契約を履行するために要する費用や逸失利益等を考慮しながら金額設定を行うことになります。
なお、消費者契約法9条1号は、あくまでも「契約解除」によって生じた「違約金・損害賠償額の予定」に関するものです。したがって、解除を伴わない単なる契約違反による違約金・損害賠償の予定については適用が無いことに注意が必要です(ちなみに、契約違反に基づく違約金・損害賠償額の予定が不当である場合、後述6.で解説する消費者契約法10条の問題となります)。
ところで、消費者契約法以外でも契約解除に伴う違約金・損害賠償額の予定について一定の歯止めをかけているのが特定商取引法となります。特定商取引法が定める取引類型のうち訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売、訪問購入については、それぞれ違約金等について上限規制がありますので、事業者が行う取引内容が特定商取引法に定める各取引類型に該当する場合、上限規制を確認しながら契約内容を定める必要があります。
(2)遅延利息に関する条項
事業者が後払いの条件で商品を販売したにもかかわらず、お客様が商品代金を支払わない場合、ペナルティとして遅延損害金を付加するということは現場実務で行われており、これ自体は当然に違法という訳ではありません。例えば次のような条項です。
(例)
お客様が当社に対する金銭支払いを遅滞した場合、お客様は遅滞した日の翌日から金銭支払いが完了する日まで間、年30%の遅延損害金を支払うものとします。
年30%の遅延損害金は非常に高利であり、ペナルティとしてはやりすぎの感があります。そこで、消費者契約法では遅延損害金の上限率を年14.6%と定め、これを超える部分については無効としています(消費者契約法9条2号)。
なお、消費者契約法9条2号は、あくまでも金銭債務の支払いに限定されて適用されます。例えば、レンタル品の返却が遅れた場合の遅延損害金については適用対象外となること注意が必要です。
6.お客様(消費者)に対する不当条項として気を付けたい条項
(1)消費者契約法が定める不当条項
消費者契約法10条後段では、「法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。」と定めています。
非常に抽象的な条項であるため、どういった条項が問題になるのか一律に解説することができないのですが、争いになりがちなものとして、例えば、
・事業者が提供するサービス内容について、事業者が事後一方的に変更可能とする特約
・事業者の債務不履行以外を理由とするお客様(消費者)からの契約解除権の制限特約(なお、その一部は上記2.(3)で解説)
・事業者が定める約定解除事由に関する特約(なお、その一部は上記3.で解説)
・契約更新時の更新料支払特約
といったものが想定されます。
(2)定型約款(民法)が定める不当条項
契約内容が民法上の定型約款に該当する場合、定型約款によって取引を行うお客様について、「権利を制限し、又は…義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第1条第2項に規定する基本原則に反して(お客様の)の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。」と定められています。
民法上の規定であるため、BtoC取引だけではなく、BtoB取引やCtoC取引など幅広く適用されることになりますが、上記(1)で解説した消費者契約法に定める不当条項規制を同趣旨の内容が、2020年4月より施行された民法に定められていること、注意が必要です。
<2020年12月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
|
|






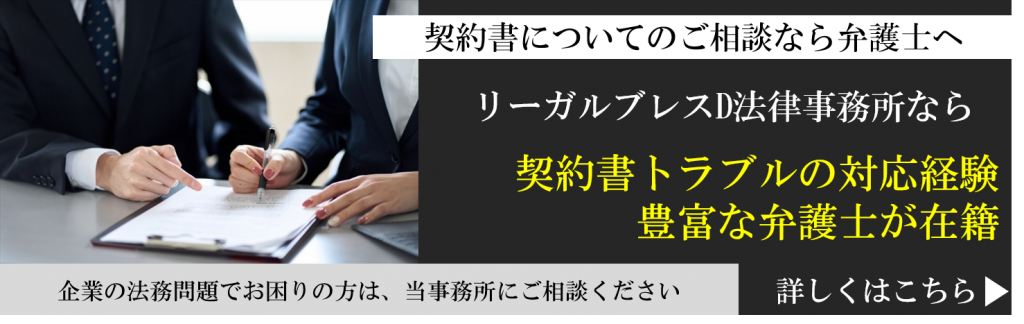

 弁護士 湯原伸一
弁護士 湯原伸一





































