【ご相談内容】
法務担当になったのですが、業務担当者から持ち込まれる案件処理のみならず、自ら積極的にリスクを探し出し、対処するための提案を行おうと考えています。ただ、何から手に付けていけばよいのか分からないのも事実です。
法務リスクを検証する上での視点等があれば教えてください。
【回答】
様々な回答が考えられるところですが、執筆者が弁護士という属性であるため、企業活動において頻発しているトラブルを知った上で、自社に当てはめてみるという視点で検証を進めるのも一案ではないかと考えます。
もっとも、やみくもにトラブル事例をあげるだけでは整理しづらいところがあります。そこで、ここでは企業の経営資源である「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」に分類した上で、それぞれ代表的な5つの検証事項につき、解説を試みることにします。
【解説】
1.ヒトに関するリスク
①労働時間の算定を適切に行っているか
従前より長時間労働に起因する過労死や過労自殺といった問題があったほか、最近では働き方改革により労働時間の上限枠の設定や罰則が定められたこともあって、労働時間管理は重要な経営課題になっています。
しかし、未だにタイムカード等による客観的な労働時間管理が行われていない企業が多いと言われています。客観的な労働時間管理ができていない状況下で、万一過労死等の問題が発生した場合、企業側が正当性を主張することは不可能であること肝に銘じるべきです。
また、上記のような問題以外にも、残業代請求に対する適切な対応ができない(労働者側の言い分に沿った残業時間が算定されるリスク)といった問題も起こりえます。
したがって、労働時間を客観的に算定できているか、十分にチェックするべきです。
なお、新型コロナの影響により在宅勤務・テレワークが増加しつつあるところ、在宅勤務・テレワークの場合、従来とは異なる労働時間管理方法が求められることにも注意が必要です(少なくとも事業場外みなし労働時間を形式的に適用するといった対処はNGです)。
②就業規則に定める労働条件と労働契約書に定める労働条件とに相違がないか
知らない方も多いのですが、労働契約法では、就業規則に定める労働条件を下回る労働契約を締結しても、その労働契約は無効とであり、就業規則に定める労働条件が適用されると定められています(労働契約法第12条)。
中小企業でのあるある話として、就業規則は存在するものの、実際の現場では用いられておらず、就業規則を下回る労働条件にて勤務しており、普段は労働者もこの点につき異議を唱えない(そもそも相違があることにつき知らないということもあります)という状況下において、何らかのきっかけで労使紛争が勃発した場合、ついでに労働契約法第12条違反を指摘されて、企業が予想もしていなかった金銭負担を強いられた…というものがあります。誤解を恐れずにあえて指摘するとすれば、労使紛争が勃発する前の平常時に就業規則と個別労働契約に定める労働条件に差異がないかチェックし、差異があれば速やかに就業規則の変更手続きを済ませてしまう…といった対策を行うことも検討する必要があります。
③残業代込みとする賃金支給となっていないか
いわゆる固定残業手当、定額残業手当、みなし残業手当などと称される、残業代は予め手当に含まれているという建付けの企業は多く存在すると思われます。
ただ、この残業代込みの賃金体系を運用する場合、残業代として支払う賃金額がいくらであり、何時間分の残業代に相当するのか、明確に区分することが重要となります。この観点からすると、基本給の中に残業代が含まれるという運用は、法律上有効な残業代の支払いにならない可能性が極めて高いと考えられます。また、当然のことながらみなし残業手当等の名目で支給していたとしても、当該手当に含まれる残業時間を超えた場合は別途超過分を支払う必要があります。この超過分を支払っていない(=残業時間管理ができていない)企業がかなり多いように思いますので、この点も注意が必要です。
なお、部長や課長等の役職についている者に対して、一切残業代を支払わないという企業もまだまだ多いようです。企業にある1つの誤解として、管理職は管理監督者(労働基準法41条)に該当すると認識している、というものがありますが、現状の裁判例を踏まえると、管理監督者に該当することはまずあり得ません。管理職手当を支給しているのであれば、その管理職手当を一種のみなし残業手当として制度構築したほうが、まだ対処しやすい場面があることに留意していただければと思います。
ちなみに、未払い賃金については消滅時効期間が3年(将来的には5年)に延長されています。塵も積もれば山となる…ではありませんが、100万円単位での未払い賃金が発生することもしばしばですので、残業代込みとする賃金体系の場合、想定される残業時間を超えていないか今一度チェックを行うべきです。
④社長の気分次第でクビにしていないか
これも中小企業でのあるある話となりますが、社長が気にくわないとして従業員を好き勝手にクビにするといった事後的対処が難しい事例や、企業としては能力不足と考え解雇したものの後で覆された(解雇無効の判決が出た等)という事例など、解雇に関するトラブルは非常に多くあります。
どこかで耳にしたことがあるかと思いますが、法律上有効な解雇となるための要件は非常に限定されており、実際に不当解雇で争われてしまうと企業が負けるリスクが極めて高いというのが実情です。解雇するのであれば、事前準備と対策を十分に練ってから実践する必要があること、何も準備をせずに気分次第で解雇を言い渡すには危険極まりないこと(予想もしない金銭負担を強いられること)に十分に注意していただきたいところです。
⑤ハラスメント対策を行っているか
セクシャルハラスメント(セクハラ)やパワーハラスメント(パワハラ)は日常用語として定着しました。最近ではマタニティハラスメント(マタハラ)やカスタマーハラスメント(カスハラ)といった新しい用語例が生み出されつつ、一方でセクハラの概念の拡張(LGBTなどの性的少数者への嫌がらせを含む概念に拡張)など、変化の激しい分野でもあります。
ところで、ハラスメント問題ですが、現場実務を通じて感じるのは、意図的なものは意外と少なく、加害者と指摘された者はハラスメントを行っているという認識は持っていないことが相当多いようです。もちろん、被害者と主張する者の過剰反応であるパターンも存在するのですが、何をもってハラスメントに該当するのか認識共有ができていないことが根本的な原因になっていると考えられます。
したがって、ハラスメント問題への対応は事前教育が重要であり、企業としてどこまで事前教育にエネルギーを注ぐことができるのかが肝要と考えられます。
弁護士へのご相談・お問い合わせ
当サイトの記事をお読みいただいても問題が解決しない場合は
弁護士にご相談いただいた方がよい可能性がございます。
下の電話番号もしくはメールにてリーガルブレスD法律事務所までお問い合わせください。
06-4708-7988メールでのご相談
2.モノに関するリスク
①所有権があっても、所有者自らが自由に使えない資産がないか
典型的には、従業員に対して企業が所有する端末を貸渡していたところ、当該従業員のみ知りうるパスワードが設定されていたため、当該従業員が休職・退職等した場合に、端末内の情報を取得することができないといった事例があげられます。
企業の所有物である以上、企業の裁量によりいつでもアクセス可能な状態にすること(上記例であれば、パスワードの届け出をさせること、パスワードの設定を従業員が勝手にできないようにシステム変更を行うこと)はもちろん、たとえ当該従業員の了承がなくても、企業がいつでも自由にモニタリングできることを周知しておくことが、トラブル回避のためにも重要となります。
②所有権が留保された重要資産はないか
企業活動を行うために必要不可欠な機械器具等について、企業自らが所有権を有していない場合、所有者との関係がこじれた場合、最悪使えなくなる可能性があります。こういった事態は割賦販売等の取引上の問題のみならず、取引先から機械器具等を借り受けている場合や、従業員個人が機械器具等を持ち込んでいる場合にも発生します。あるいは、
個人事業主から法人成した場合に、個人から法人への名義変更を放置した結果、当該個人が死亡し相続問題に絡んで生じる場合もありえます。
必要不可欠な資産であるのであれば、お金を払ってでも早期に当該資産の所有権を取得することを意識するべきです。
なお、上記例とは異なりますが、取引先負担で制作した成果物について、当然に金銭負担した取引先に所有権が帰属すると考える自体疑う必要があるケースもあります。たとえば、本格的な取引開始前の試作品制作の場合、取引先が金銭負担するといっても材料費等の実費のみであり、工賃や成果物に詰め込まれたノウハウ移転費用等は含まれていないということがよくあります(当然、受託者側の利益も考慮されていません)。こういった場合、材料費等の実費のみで成果物の所有権を取引先に帰属させるのは、著しく対価均衡を欠くと考えられます。したがって、所有権の帰属について適切に交渉を行うことが重要です。
③金型や図面などの資産を無償提供させられていないか
金型や図面は、ものづくり企業にとっては重要な独自ノウハウです。これが外部に漏れた場合、他社に模倣されてしまうなどして、自らの存続基盤を揺るがしかねない重大なリスクを背負うことになります。
とはいうものの、取引先との力関係上、やむを得ず金型や図面を提供する、しかも何らの対価を得ないで提供することを強いられている実情もありうる話です。新たな取引開始時点であれば、取引機会の喪失を招く可能性を考慮しつつ提供NGを明確に主張する、既に取引関係が構築されている場合は、タイミングや言い方の問題を考慮しつつ、下請法違反などの根拠をあげながら交渉を試みるといったことを検討することが重要です。
④他人所有物の利用契約(リース、賃貸借)において中途解約が可能か
ときどき勘違いされている企業があるのですが、賃借人やリースのユーザーには、自らの一方的都合により契約を途中で解約する権利は保証されていません。あくまでも契約に定められている場合に限定されます。
ところで、リース契約はともかく、一般的な居住目的の賃貸借契約の場合、むしろ中途解約に関する条項が定められていることが多いので、この感覚で対処する企業担当者もいるようなのです。しかし、リースはもちろんのこと賃貸借であっても、事業使用目的の場合、中途解約がそもそも禁止されていたり、中途解約が可能であっての契約残存期間に相当する賃料の一括払いを違約金として支払うことになっていたりする等、居住目的の場合とはかなり内容が異なることに注意が必要です。
賃貸借やリース契約締結時には気が付きにくいのですが、損失をなるべく被ることなく契約関係からの離脱可能かという視点で、契約内容を確認することが重要となります。
⑤原状回復義務の範囲について確認したか
他人所有物を借り受けて利用し、必要がなくなったので返還する場合に問題となってくるのが原状回復の問題です。特に問題が大きくなりやすいのが建物賃貸借契約の場合であるため、以下では建物賃貸借を例に解説します。
まず、日本語のややこしいところなのですが「ゲンジョウ」という音読につき、原状回復の場合は元通りに戻すこと、すなわち賃貸借契約締結時に戻すことを一般的に意味します(スケルトン状態に戻すことでも用いられる場合もあります)。一方、現状という用語例の場合、現在の状況で退去すれば足りるという意味になります(現状有姿、いわゆる居ぬき状態)
「現状」での退去でよいのであれば、あまりトラブルとならないのですが、企業が賃借人のとなる場合における「原状」回復となると、どこまで戻さなければならないのか(新品同様に戻すよう特約で定められる場合あり)、経年劣化等は考慮されないのか(経年劣化は考慮しないと定められる場合あり)、原状回復の施工業者を賃借人が指定できないのか(賃貸人指定の施工業者以外はNGと定められている場合あり)等々いろいろ問題が出てくることが多いようです。
したがって、契約終了時の措置としての原状回復の有無及び範囲について契約書の内容をしっかり確認すると共に、可能な限り、引渡し時の賃借物件の状況を写真や動画等で撮影し、引渡し時(=原状)にすでに生じていたキズや不具合等を証拠で残しておくことが重要となります。
3.カネに関するリスク
①債権の消滅時効が到来していないか(民法改正に注意)
売掛金や貸付金、委託報酬など事業活動を通じて発生する債権は様々ですが、いずれに債権についても回収し現金化しないことには絵に描いた餅です。そして、回収手続きを行わないまま一定期間放置していると、法律上は回収不可となってしまう消滅時効制度が存在することに注意が必要です。
このようなことから債権管理が重要となるわけですが、2020年3月31日までに発生した債権と2020年4月1日以降に発生した債権とでは、消滅時効の期間について異なる取扱いをする必要があります。これは民法が改正されたことで消滅時効期間の取扱いが変更となったためです。改正民法では消滅時効期間は原則5年となりましたが、例えば2020年3月31日までに発生した売掛金であれば、旧民法が適用されますので引き続き消滅時効期間は2年となります。
消滅時効期間について、安易に5年に延長されたと考えてはならないことに留意が必要です。
②保証に関するルールを守っているか
いまだに保証契約は書面で締結する必要があること(書面で締結していない場合は保証契約自体が成立したとは言えないこと)について、十分に認知されているとは言い難い状況下において、2020年4月1日に改正された民法では、保証契約が有効となるためのさらに細かな条件が追加されるに至りました。
口頭での保証契約では話になりませんが、せっかく書面で保証契約を締結したにもかかわらず、民法改正の内容を十分に認識できていなかったため、結果的に保証契約は不成立・無効となってしまうと、回収のためのこれまでの努力が無駄になるばかりか、回収自体が危ぶまれることにもなりかねません。
保証に関してはかなりややこしい法制度となってしまったため、専門家とも相談しつつ慎重に事を進めるのが重要です。
③保険契約上の免責事由に該当しないか
何らかに事故が発生し損害賠償責任を負う場合に備えて保険に加入する、いざ損害賠償金の支払いを求められた場合は、保険金で支払いを行う、これが損害賠償保険制度の概要です。自動車保険や火災保険が代表例ですが、企業活動向けの損害保険であれば、店舗賠償責任保険、生産物賠償責任保険、情報漏洩(サイバーセキュリティ)保険など様々な保険が存在します。
当然のことながら、全ての損害保険に加入することは難しいので、事業活動する上で想定されるリスクに応じた損害保険を選択し加入することになるのですが、カバーされていると思っていたリスクが実は保険でカバーされていなかったというトラブルは、意外とあったりします。もちろんモラル事案と呼ばれるような、偶然に事故が発生したのか疑わしい事例もあったりするのですが、企業活動に関連する保険トラブルは、保険約款に定める免責事由に該当するため、加入当初からそのリスクは保険でカバーできていなかったというパターンです。
正直なところ、保険の営業担当者も約款内容を十分に理解しているとは言い難く、適切な説明が行われていないと思われる事例も多々あるのですが、しかし、保険契約を締結する際に企業も約款内容を十分に確認したとする誓約書面を提出しているため、なかなか保険会社に対して責任追及しづらいところがあります(いわゆる自己責任として取り扱われてしまうということです)。
保険の加入前に、どういったリスクを想定しカバーしてほしいと思っているのかを紙に書きだすなどして保険会社側に提示し、保険会社からの回答を書面等の後が残る形で受け取ることで保険ニーズに関する双方の齟齬を解消するといった対策を講じること、そして当然のことながら保険約款をしっかり企業側も確認することが、きわめて重要となります。
④一方的な減額や支払延期などに応じていないか
取引先との力関係上、取引先から減額要請や支払い延期要請があった場合は、仕方なく受け入れているということは、中小しかも下請企業という立場であれば多かれ少なかれ経験していることが多いと思われます。
ちなみに、一方的に減額や支払い延期を要求するばかりで理由の説明がないという場合、たいていは当方側に非はなく、法律上は要求を受け入れる義務がありません。ただ、理屈はともかく、現場ではなかなか抵抗しづらいのも事実ですので、下請法違反等を理由に行政機関に匿名通報するといった間接的な抵抗手段がないかを検討することも重要です。
⑤無償での試作品提供などを強いられていないか
取引を行うか否かの検討段階として試作品の制作と提供を依頼されることがあります。もちろん受託企業側として、試作品の制作費用を無視できるのであれば無償で引き受けることは何ら問題ありません。
しかし、たいていの場合、試作品とは言っても決して簡易なものではなく、仕様等が細かく定められ、要求事項に応えるためには相応の研究と検証時間が必要となり、原材料費や人件費を負担しつつ、取引先の要求水準を満たすまでは何度も制作する羽目になる場合が多く、文字通り手間・時間・金をかけて制作することになりがちです。一昔前のフリーミアム戦略をしっかり練っているのであればともかく、なかなかフリーミアム戦略を実行することは難しいはずですので、試作品とはいえ適切な制作対価を要請することが重要となります。なお、取引先が費用負担することと所有権の帰属の問題は必ずしも連動するわけではないこと、上記2.②もご参照ください。
4.情報に関するリスク
①ネーミングやロゴについて、事前に商標権侵害の調査ができているか
いわゆるブランド化戦略を意識する企業が多くなってきており、自社の商品・サービスに対するネーミングに趣向を凝らしたり、特徴的なロゴを付すなどすることが多くなってきているようです。ブランド化を目指すこと自体は法律上特に問題にはならないのですが、自社で用いる名称やロゴ等につき、同一又は類似する先行利用者が存在する場合、本当に使用してよいのかよくよく検討を行う必要があります。
特に先行利用者が商標権登録を行っている場合、商標権侵害であるとして法的手続きに打って出てくる可能性が非常に高くなります。商標登録の有無は、特許庁のデータベース等を用いれば無料で検索可能ですので、あらかじめ調査を行っておきたいところです。また、商標登録がなかったとしても、それで安心という訳にはいきません。先行利用者の名称やロゴ等がそれなりに有名である場合、不正競争防止法(混同惹起、著名表示冒用)違反としてやはり法的手続きの対象になってしまう可能性があるからです。有名かどうかまでは調査できませんが、同一又は類似の名称やロゴ等が存在しないかについては、インターネット等を駆使してできる限り情報を収集したいところです。
なお、先行利用者が見当たらない場合、名称やロゴ等の使用を独占化したいのであれば、商標出願の手続きを行い、誰よりも早く商標登録を受けることが重要です。
②職務発明・職務著作への対応はできているか
一昔前の青色発光ダイオード訴訟などの話をすると思い出す方もいるかと思うのですが、従業員が業務遂行中に発明・考案した特許権等は当然に企業に帰属するわけではありません。むしろ法律上の原則は従業員個人に帰属するとなっています。こういった業務遂行中の発明・考案に関する取り扱いを定めた法制度を一般的に職務発明と呼ぶのですが、企業としては、たしかに従業員の貢献は認められるものの、研究施設の提供や必要経費を負担していること、何より企業の維持発展を目的とした発明・考案である以上、特許権等は企業に帰属させ、企業活動のために使用したいと考えるのが通常です。
もしこの考えを実現したいのであれば、業務遂行中の発明・考案にかかる特許権等は企業に帰属すること、帰属させる代わりに相当な代償を支払うことを定めた社内規程を整備する必要があります。研究開発型の企業であれば、早急に対処することが重要です。
一方、著作物の創作については、上記の発明考案とは真逆の法制度となっています。すなわち、業務遂行中に創作した著作物(職務著作)については、原則として企業に帰属し、代償の支払も不要となっています。
ときどき職務発明と職務著作を勘違いされている企業担当者もいますので、適切に区分して理解をしたいところです。
③他社との協業などにおける成果物の権利帰属について意識できているか
近時は企業単独でアイデアを出し、技術開発して、商品化することが困難となっていることから、他社とのコラボ又は共同研究開発という形で活路を見出そうとする動きが目立つようになっています。
ただ、こういったコラボレーションを大企業と中小企業(スタートアップ、ベンチャーを含む)が行う場合、往々にして、中小企業が保有するノウハウや権利が、大企業に帰属する内容の契約書を締結させられていたり、あるいはあえてその点を明確に定めないことで大企業がいつの間にか単独で権利化のための出願手続きを進めていたりする、といった問題事例が散見されます。
「最初から相手を疑ってどうする」とお叱りを受けるかもしれません。しかし、特にこれまで取引実績がない取引先と協業を行う場合、どういった役割分担となるのか、協業により得られた成果物の権利帰属や取扱いはどうなるのか、協業前から持ち合わせているノウハウ等が事実上先方による自由使用できる状態となっていないか等、疑ってかかるべきです。そして、疑問に感じたらその点を明示的に質問し、先方からの回答内容を記録化しておくことが、後々のトラブル発生時に役立つことを十分に意識しておきたいところです。
④アイデアを保護するための方策に限界があることを意識できているか
現場の実務担当者とお話しすると驚かれることが多いのですが、実は現行法上、企業活動に関するアイデア(情報)を包括的に保護する法律は存在しません。現行法上存在するのは営業秘密に関する不正競争防止法くらいです(なお、個人情報保護法もたしかに個人に関する情報を保護する法律ですが、企業活動という視点では企業における個人情報の利用に制限を設ける法律ですので、今回は検討対象外としています)。
ちなみに、ときどき著作権法で保護できるのではないかというご質問を受けます。しかし、著作権法は、強いて言えば、頭の中にあるアイデア(情報)を何らかの表現行為を通じて創作物となった場合に保護される法律にすぎません。頭の中にあるアイデア(情報)それ自体を保護する法律ではありませんし、仮にアイデア(情報)が外部に発せられたとしても、創作性が認められない限りは著作物にはならない以上、著作権法の保護が及びません。
アイデアを守るためには、アイデアを権利化する方向で保護するのか(特許出願や不正競争防止法上の営業秘密など)、アイデアを外部に漏らさない完全秘密体制を構築するのか、あるいはアイデアを知っている人物に対して開示漏洩しない旨約束させるのか(秘密保持契約の締結)、3つのパターンしか存在せず、いずれの方法もアイデアを保有する企業が積極手に対策を講じないことには、法律上の保護を受けられないことに意識する必要があります。
⑤一方的な秘密保持契約を締結していないか
何らかの取引を行おうとする場合、秘密保持契約を締結することが当然という風潮になってきました。しかし、一口に秘密保持契約といってもその内容は千差万別、もっといえば契約書案を提示する側のビジネススタンスが見え隠れするといっても過言ではないくらい色々なものがあります。
個別の契約条項に対する考え方については、たとえば次に記載する別記事などをご参照いただくとして、秘密保持契約を締結する場合、企業として最初に検討しておきたい事項は次の通りとなります。
・秘密保持義務を負担するのは当方のみか、先方も負担するのか
・当方は専ら秘密情報を開示する側なのか、受領する側なのか
・当方における秘密情報とは何か意識できているか
たとえば、当方も秘密情報を開示する側になるのであれば、先方にも秘密保持義務を負担させる必要がありますので、個別の契約条項に対するチェック以前の問題としてその旨指摘し、双方が秘密保持義務を負担する形での再提案を要請する必要があります。
契約を締結する前であれば交渉の余地はありますが、契約締結後であればほぼ交渉の余地はありません。この点を意識しながら秘密保持契約の締結交渉を進めることが重要となります。
<2021年3月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
|
|






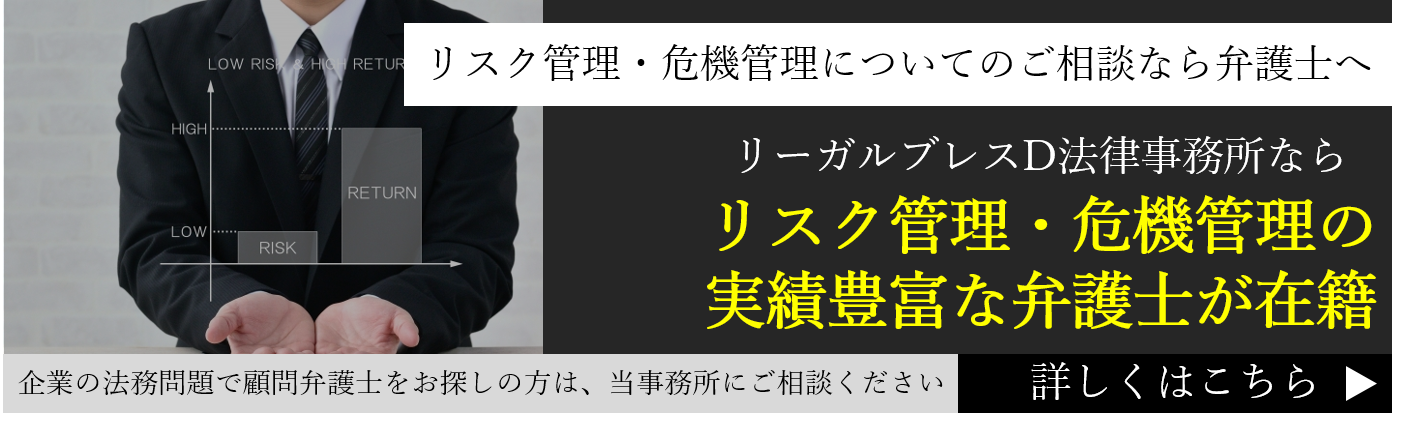

 弁護士 湯原伸一
弁護士 湯原伸一




































