Contents
【ご相談内容】
今後新たな取引を開始しようと考えている会社より、秘密保持契約書の締結を求められたが、どういった点に注意すればよいでしょうか。
【回答】
秘密情報として取り扱いたい情報が秘密情報の定義から漏れていないか定義を確認すること、秘密情報をベースに新たな発明等がなされた場合の権利処理を明確にすること、秘密保持義務を課す契約期間が適切か確認すること、以上の3点は必ず意識したい事項です。
この3点を含む具体的なチェック事項については以下の【解説】で確認します。
【解説】
専ら情報を開示する側になるのか、専ら情報を受領する側になるのかによって、見方が変わってきます。具体的な条項例を見ながら、ポイントを解説していきます。
第×条(秘密情報)
本契約において、「秘密情報」とは、文書、口頭その他方法のいかんを問わず、開示者が受領者に対し開示した一切の情報をいう。但し、次のいずれかに該当するものについては、秘密情報から除外されるものとする。
①本契約締結前既に受領者が保有していたもの
②本契約の締結後に受領者の責によらずして公知となったもの
③受領者が正当な権限を有する第三者より秘密保持の義務なく入手したもの
④開示者の秘密情報を使用もしくは参照することなく受領者が独自に開発したもの
よく見かける秘密情報の定義に関する条項です。
情報発信(開示)者側からすれば、方法を問わず一切の情報が秘密情報の対象となるので、問題無いと考えるかもしれません。しかしながら、要保護性の強い情報が特定できるのであれば、具体的に明記する方が絶対に良いと断言できます。
なぜならば、「一切の情報」と規定したところで、情報受領者側は全ての情報を適切に管理することは負担であるとして、いつのまにか管理がおろそかになってしまいがちであるからです(情報漏洩の危険性)。
また、いざ裁判となった場合、それほど価値のない情報まで保護の対象にしている以上、単なる形式論に過ぎない契約ではないのか(秘密に管理されているのか疑いが生じる)、価値ある情報とそれほど価値のない情報を同列に扱っている以上、情報の重要性や経済価値を裁判所が理解してくれないという弊害(情報の価値低下)も出ているからです。
したがって、例えば、「秘密情報とは、開示者が受領者に開示する××技術に関するマニュアルに記載された情報、××技術を解説したDVD媒体物、及び文書…」、「開示した情報のうち秘密である旨明示した情報」とできる限り具体的に記述するのがベストです。
次にチェックする点は、①から④で示される秘密情報の例外・除外に関する内容です。
非常に一般的なものであるためほとんど意識しないこともあるのですが、顧客情報や特許出願中の発明に関連する情報などを開示する場合には注意が必要です。なぜならば、個人情報保護法上は公開の有無にかかわらず、秘密保持契約の内容以上の義務が課せられるからです。また、特許出願中の発明に関する情報は、出願手続き上を進めていくと必然的に公開されてしまうところ、万一特許査定とならなかった場合、発明に係る技術情報が秘密情報から除外されるリスクが生じうるからです。
したがって、例外の例外とでも言えば良いでしょうか、例外に該当しつつも要保護性が高い情報が無いのか確認を行い、必要に応じて次のような条項を規定するべきです。
<追加を検討したい条項の一例>
2 開示者が、受領者に対して開示した次の情報については、前項の除外規定を適用せず、常に「秘密情報」に該当するものとして取り扱うものとする。
・開示者のデータベース上に格納されている顧客の氏名、住所、電話番号、年齢等に関する情報
・上記情報の印刷物
第×条(秘密保持)
1.受領者は、秘密情報を善良なる管理者の注意義務をもって秘密として管理し、事前に書面による開示者の承諾を得ることなく、秘密情報を第三者に開示又は漏洩してはならない。
2.受領者は、秘密情報を自らもしくは第三者の利益のために、又は目的取引の履行以外の目的で使用してはならない。
3.受領者は、法令規則等により、政府機関、証券取引所その他公的機関に対して秘密情報を開示することが要求される場合、当該開示を行うことができる。但し、その場合、受領者は、できる限り事前に情報開示者にその旨を通知し、かつ秘密情報の秘密が保持されるよう合理的な努力を行うものとする。
これもよくある文言なのですが、意外と見落としがちなのが2項にある「目的取引」といった形で用いられる「目的」についてです。
酷い契約書になると、どういった「目的」なのかが全く明記されていないものもあるのですが、例えば、製品化の可能性を探索するために情報開示を行うというのであれば、「製品化の可能性を探索することを目的(以下「目的取引」という)として…」といった形で目的を記載しておくべきです。
逆に目的が不明確の場合、ありとあらゆる場面が目的に含まれるという主張を許すことにもなりかねず、2項による目的内利用という歯止めが一切きかなくなるので注意が必要です。
弁護士へのご相談・お問い合わせ
当サイトの記事をお読みいただいても問題が解決しない場合は
弁護士にご相談いただいた方がよい可能性がございます。
下の電話番号もしくはメールにてリーガルブレスD法律事務所までお問い合わせください。
06-4708-7988メールでのご相談
第×条(役員・従業員に対する開示)
1.受領者は、秘密情報を、目的取引の履行に携わりかつ当該秘密情報を知る必要のある自己の役員又は従業員に対してのみ、秘密であることが客観的に認識しうるよう必要な措置を施した上で、開示するものとする。
2.受領者は、前項の役員又は従業員に対して、自己が本契約に基づき負担するのと同等の義務を遵守させることを要するものとする。
第×条(複製)
1.受領者は、目的取引の履行に必要な範囲を超えて、秘密情報の全部又は一部を複製してはならない。
2.秘密情報の複製物(電子データ等を含む)は、本契約における秘密情報として取扱うものとする。
この条項はもし明記されていないのであれば、明記した方がよいという意味での例示になります。
開示する人的範囲をできる限り狭めること、情報が化体されている媒体物の数を制限することで漏洩リスクを回避する狙いがあります。
第×条(権利の不発生)
1.本契約又は目的取引に基づく開示者の秘密情報の開示によって、受領者に対して、いかなる意味においても、秘密情報の所有権の移転や秘密情報に係る著作権、特許権等の知的財産権の譲渡、実施許諾又は使用許諾等の効果が生じるものではない。
2.成果物に秘密情報が化体された場合であっても、当該秘密情報はなお開示者に帰属するものとする。
秘密情報が開示されることにより、情報受領者側は当該秘密情報を用いて実験を行ったり、研究開発を行ったりするなどしますが、その過程で様々な成果・ノウハウが得られる場合があります。
こういったものについて情報受領者側は、自分達の研究成果だから自分達で権利化して当たり前という発想を行う場合があるところ、これを許してしまうと、結果的には、合法的に秘密情報を奪い取られてしまうことにもなりかねません。
そこで、幹となる秘密情報の権利関係を明確にしておくことで、情報受領者側へ秘密情報が帰属することを回避する方策として、上記のような条項を入れておくべきことになります。
第×条(秘密情報の返還等)
1.受領者は、本契約が終了したとき又は開示者から請求があったときは、開示者の指示に従い、秘密情報及び秘密情報が化体された成果物を直ちに開示者に返還又は破棄するものとする。
2.前項に定める場合において、秘密情報が受領者の図面等に含まれているときは、受領者は、当該秘密情報を消去するとともに、消去した旨(受領者の図面等に秘密情報が含まれていないときは、その旨)、開示者に報告するものとする。
これについてもよく見かける条項かと思いますが、発信した情報に対する監督を徹底させるのであれば、1項にある「返還又は破棄」という部分について「返還」を原則化し、返還できない情報については情報開示者の指示に従って「破棄」させる、そして全てを破棄したことを宣言する誓約書を提出させることまで、検討するべきでしょう。
第×条(損害賠償等)
1.受領者が本契約に違反した場合、受領者は開示者に対し、開示者が被った損害を賠償するものとする。
2.秘密情報が受領者以外の第三者に漏洩等した場合、受領者は、開示者と協議の上、有形の秘密情報の回収等の適切な処置を講ずるとともに、秘密情報の漏洩を最小限にとどめるよう善後措置に最善を尽くすものとする。
2項については問題ありません。
1項については民事上の原則論を記載したものであり、ある意味法的には問題は無いのですが、実効性を欠く文言になってしまいます。
なぜならば、損害を被った場合は損害賠償を請求する者が、その具体的な損害内容と損害額を立証する必要があるところ、開示した情報の経済的価値を客観的に算定することが困難である以上、実際には損害賠償請求が認められない可能性が生じてしまうからです。
可能であれば、1項については、具体的な金額を明記した違約金規定(例:受領者が本契約に違反した場合、受領者は開示者に対し、違約金として金500万円を支払うものとする。)を設けるべきでしょう。
第×条(有効期間)
本契約の有効期間は1年間とする。
この有効期間については、どういう訳か1年間となっていることが多いのですが、そもそも論として、情報発信(開示)者側からすれば、情報を取引中はもちろん、取引終了後も情報受領者側に利用されては困る立場のはずです。そうであれば、秘密保持契約に規定された内容を半永久的に義務づける方向で検討するべきであって、果たして契約の有効期間が必要なのかという観点から検討が必要になると考えられます。
もっとも、契約の有効期間を規定しないとなると、法律上は「期間の定めの無い」契約となり、いつでも解約可能という理屈が成り立ち得ます。
こうした理屈を回避するためには、①契約が終了した場合も一定期間は契約の効力は維持される旨の残存条項(例:終了事由の如何を問わず、本契約第5条については本契約終了後もなお効力を有するものとする。)を入れておく、②本契約終了後も2年間は効力を有するものとすると一律に明記しておく、等の対応を行うべきでしょう。
<2020年1月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
|
|






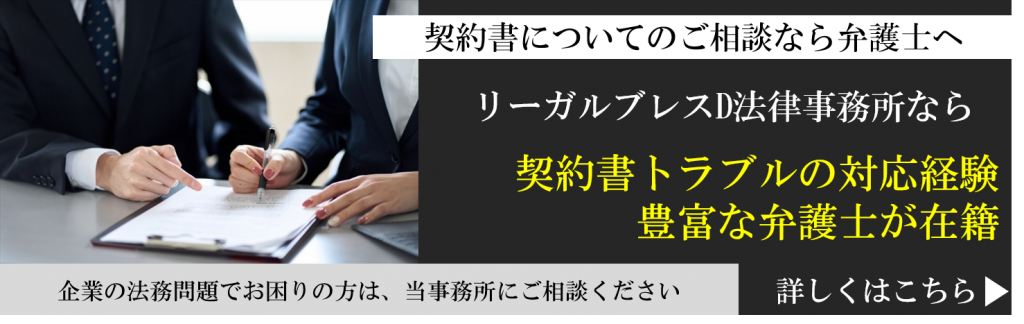

 弁護士 湯原伸一
弁護士 湯原伸一




































