Contents
【ご相談内容】
ものづくり展示会にて当社の技術を披露しアピールを行ったところ、上場企業より業務提携ができないかという提案を受けました。
非常にありがたい話であり、是非前向きに進めていきたいと考えているのですが、一方で当社はこれまで上場企業と取引を行ったことが無く、何をどのように交渉し進めていけばよいのか勝手がわかりません。
今後の業務提携交渉に向けて、どのような点に注意すればよいのか法務視点で教えてください。
【回答】
中小零細企業からすれば、取引先に大手企業があるということは1つのステイタスになります。このため、大手企業との取引話があった場合、前のめりになりがちです。
一方、大手企業の中には、中小零細企業が保有する技術・ノウハウ・情報等のみが欲しいのであって、必ずしも取引開始を念頭に置いていないこともあったりします。このため、浮かれがちな中小零細企業を手玉に取り、必要な技術・ノウハウ・情報等を抜き出しさえすれば、あとは用無しとして切り捨てるといったことも実はあったりします。
したがって、中小零細企業としては、大手企業との取引開始を望みつつも、一方で押さえるべきところは押さえて言いなりにはならないという気構えが必要です。
本記事では、業務提携話があった場合に、一般的なフローである、秘密情報開示の場面、技術検証(PoC)の場面、共同研究開発の場面に分けて留意するべき事項について解説を行います。また、最後に、大手企業と何らかの契約書を締結する場合、契約の名称如何にかかわらず注意したい条項について解説を行います。
なお、本記事では触れていませんが、独占禁止法の観点から検討した資料として、次のようなものがありますので、必要に応じてご参照ください。
スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針(公正取引員会)
【解説】
1.秘密情報の開示を行う場面
大企業が中小零細企業に対して声をかけてくるのは、中小零細企業が保有する技術・ノウハウ・情報等が“金になる”と考えているからです。
大企業から声を掛けられた中小零細企業の中には、有頂天になって技術・ノウハウ・情報等を何も考えずにどんどん開示してしまうこともあるようですが、そのような対応を取ってしまうと、技術・ノウハウ・情報等を抜き取られてしまい、後は用無しとして切り捨てられてしまいます。
したがって、中小零細企業が大企業に対し、技術・ノウハウ・情報等を開示する場合は、必ず秘密保持契約を締結するべきなのですが、現場実務では一筋縄ではいかないようです。
以下では、よく生じる問題を3点取り上げます。
(1)秘密保持契約を締結してくれない
中小零細企業が大企業に対し、秘密保持契約の締結を要請した場合、あからさまに契約締結の必要性なしとして拒絶されることは少ないかと思います。
しかし、中には、大手企業側より契約書案の提示があるはずだがいつまでも提示してこない、提示された契約内容の修正協議に応じてもらえない、社内の決済が必要だから契約締結に時間がかかる等々の理由で、なかなか秘密保持契約の締結にまで至らないということもあります。しかし一方で、大企業は中小零細企業に対し、秘密保持契約締結未了であるにもかかわらず、ビジネスの迅速性を理由に、技術・ノウハウ・情報等の開示を要求してくることもあります。
当然のことながら、秘密保持契約を締結してから技術・ノウハウ・情報等を開示することが望ましいのですが、諸事情により秘密保持契約の締結未了であっても、先行して技術・ノウハウ・情報等を開示せざるを得ない場合も想定されます。
この場合、例えば、開示する前に「××は秘密情報なのでくれぐれも取扱いにご注意ください」と注意喚起し、了解を得た場合に開示するといった手順を踏むことで、少しでも法的保護を受けられそうな状況を作出するといった対策が考えられます。また、開示に際して不正競争防止法上の営業秘密であることをメール等履歴が残る方法にて告知する、著作物であることを告知するなどして、大手企業をあえて牽制することも考えられます(法的に営業秘密や著作物に該当するかは分かりませんが、無断使用に対する心理的抵抗感を持たせることが目的となります)。
(2)片務的な秘密保持契約が提示される
大企業が中小零細企業に対し、雛形であるとして開示する秘密保持契約書の内容が片務的なもの、すなわち中小零細企業のみが秘密保持義務を負担するといったものも現場実務ではよく見かけるものです。
この場合、悩んでいても仕方がないので、思い切って、「当事者双方が秘密保持義務を負担する契約書に変更してください」と伝えるべきです。
あくまでも執筆者個人の感覚となりますが、意外と大企業の現場担当者は何も考えずに秘密保持契約書を提示していることが多いので、すんなり変更してくれることが多いという印象を持っています。また、大企業の現場担当者の反応がいまいちの場合、「フェアな契約を結んでほしい」と言えば、たいていは修正に応じてくれるようです。
大企業も、本格的な協議が始まる前にイザコザを起こすことは避けたいと考えていますので、中小零細企業は遠慮なく物申すというのが、解決への一番の方策だと考えます。
(3)秘密保持義務違反への対策が不十分
秘密保持契約を締結しただけでは、実のところ安心ではありません。あえて誤解を恐れずに指摘すると、大企業は確信的に秘密保持契約に違反する(秘密保持契約の穴をつく)動きをとる場合があるからです。
例えば、秘密情報の定義として「秘密である旨明示した情報」と定義されている場合、中小零細企業が開示した情報は明らかに秘密性があるものであるにもかかわらず、明示を行わなかったことを理由として、大企業は秘密情報として取り扱わない、すなわち自社の情報として自由に利用してしまうということが現実に起こりえます。
また、大企業の子会社が契約当事者の場合、秘密情報の開示可能な人的範囲を明確に限定しないことで、中小零細企業が開示した情報が、当然のように親会社や別の子会社(関連会社)にまで拡散し、いつの間にか秘密情報の秘匿性が失われているという事態が発生することもあります。
さらに、秘密情報の漏洩が発生した場合、契約違反であることは間違いないものの、それによる具体的な損害額を立証することが困難であることを理由に漏洩事故を起こした大企業が開き直り、中小零細企業が泣き寝入りするということもあります。
最後に、秘密保持契約の契約期間及び契約終了後の秘密保持義務残存期間が極端に短いことで、中小零細企業が大企業に開示した秘密情報を、数ヶ月後には大企業が自らの情報として使用し始めるということもあり得ます。
これらの問題はいずれも秘密保持契約を締結するに際しての事前チェックが不十分であったことから発生する問題であり、正直なところ発生してからでは対処のしようがありません。秘密保持契約のチェックポイントについては、次の記事をご参照ください。
2.技術検証を行う場面
中小零細企業が保有する技術・ノウハウ・情報等について、大企業が想定するような機能・性能を有しているのか、究極的には商業的価値を有するのかを検証し、製品化に向けた共同研究開発を進めるのかを事前に判断する段階のことを、技術検証やPoCと呼んでいます。
一昔前に流行したテレビドラマ等では、採算度外視で、昼夜を問わず、社長と従業員が一緒になって実験を成功させる…といったものがありましたが、残念ながら感動を獲得しただけでは企業経営を成り立たせることはできません。
以下では、最近問題視されている事項を3点取り上げます。
(1)費用負担が不明確であること
例えば、中小零細企業が保有する技術・ノウハウ・情報等を活用した試作品・プロトタイプの制作を大企業から依頼された場合、試作品・プロトタイプだからということで無償対応することが多いようです。
たしかに、中小零細企業にとっても、営業活動の一環であり無償で実施することに納得しているというのであれば問題はありません。
しかし、試作品・プロトタイプを制作するに当たり、高価な原材料使用の指定や専門技術者の配置、膨大な工数や厳しい日程管理等の負担が生じた場合、中小零細企業は痛手を被ることになります。また、試作品・プロトタイプの制作を完了させたとしても、改良依頼を何度も受け時間と労力を取られるとなると、やはり中小零細企業にとっては損失が生じることになります。
きっちり対応するのであれば、技術検証契約書(PoC契約書)の締結を行うべきですが、現場実務を見ていると、なかなかそこまで協議することは難しいようです。
そこで、仮に無償で行うのであれば、例えば、「試作品・プロトタイプの制作は1回に限る」、「作業工程は当社の裁量による」、「納期は×月×日とする」、「試作品・プロトタイプを踏まえての改良制作は別途協議する」といった条件をメール等で提示し、大手企業の担当者からの了解の返信をもらうといったことだけでも行っておけば、対処しやすいと考えられます。
また、無償での作業が辛いと思うのであれば、大手企業の担当者に対し、明確にこれ以上は無理ということを伝えることも重要です。たいていの場合、伝えることで費用交渉に応じてくれますし、逆に費用交渉に応じないようであれば、今後お付き合いを続けても“くたびれ損”になると判断し、早めの損切りとして関係を終了させることも検討したいところです。
(2)エンドレスに検証作業が継続すること
上記(1)でも少し触れましたが、試作品・プロトタイプを制作した後、大手企業より「この点を改良してほしい」、「あの点に不満があるのでやり直してほしい」等の要望を受け、繰り返し作業を強いられるということがあります。
中小零細企業にとっては、時間・労力・費用がかかると共に、これがいつ実を結び利益に変わるのか分からない状況下での作業継続となるため、色々と苦労することになります。
これについても、上記(1)で記載した通り、担当者レベルであっても条件提示を行い、了解を得ておくといった方法をとることが有用です。
また、場合によっては、「これ以上の無償作業は続けられない」として、今後の作業を拒絶するといった強硬策を取ったほうが良い場合もあります。場合によっては大手企業より、「今になって中止となると当社も迷惑を被ることになる。損害賠償問題となるがそれでもよいのか」と脅してくる場合もありますが、多くの場合は単なる脅し文句であり、深刻に考える必要はないと思われます(もちろんケースバイケースの判断になってしまうのですが)。なぜなら、技術検証が中止したことにより、大手企業が被った法律上の損害を立証することは困難だからです。
ちなみに、大手企業が上記のような脅し文句を言ってきた場合にこそ、中小企業庁等の行政機関に相談すれば、行政機関も比較的動きやすい事案として対処してくれるようです。また今後の交渉につき弁護士を介入させることで、大手企業の横暴にブレーキをかけることも期待できます。
色々方策がありますが、黙っていては事態が好転しないことを理解しておく必要があります。
なお、逆のパターンとなりますが、中小零細企業が大企業に対し、これまでの作業に対して報酬を請求することは困難と考えるべきです。たしかに、商法第512条では「商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。」という規定があるのですが、実務上“相当な報酬”を立証することが困難という問題があるからです。他にも、大手企業が中小零細企業に対し、契約の成立(製造業であれば量産注文が行われることなど)を期待させたにもかかわらず、その期待を裏切るような行為をした(一方的に量産計画を打ち切ったなど)場合に、不法行為責任(契約締結上の過失)を追求できる場面も考えられますが、かなり専門的な検討が必要となりますので、弁護士に相談するべきです。
(3)得られた知見・ノウハウの流出
例えば、技術検証や実証実験の結果レポートを大企業に提出する場合、中小零細企業は、自社が保有する技術・ノウハウ・情報等の優位性や有用性をアピールするべく、ついつい色々なことを書きがちです。そして、この色々と書かれたレポート内容を分析することで、大企業はこれまで開示対象となっていなかった知見等を入手することができ、自社開発の可能性を見出すこともあり得る話です。
こうなると、大企業との連携話は頓挫し、中小零細企業にとっては新たな取引先を確保する機会を逸するほか、守りたかった技術・ノウハウ・情報等を丸ごと大企業に持っていかれてしまうリスクを負うことになります。
実際の対策としては、レポート記載内容について秘密情報に含めること、レポートに余計なことまで書かないといった事前対策が重要であり、一度漏れてしまうと防ぎようがないと考える必要があります。
また、何より安易に技術検証を受入れるのではなく、しっかりと条件を詰めた上で実施するというのが肝要です。PoC契約のチェックポイントについては次の記事をご参照ください。
3.共同研究開発を行う場面
中小零細企業が保有する技術・ノウハウ・情報等が有用であり、商業的価値も期待できるという場合、量産化のための製品開発を共同で実施することになります。
ここまでくると中小零細企業にとっても、新たな取引先確保と利益獲得まであと一歩のところまで迫っていると言えるのですが、ここで気を抜いてしまうと、大企業の巧みな戦術(?)により梯子を外されてしまい、今までの努力が水の泡となって泣きを見る中小零細企業も存在したりします。
ここでは深刻なトラブルとなりやすい事例を3つ取り上げます。
(1)知的財産権の帰属に問題がある
製品量産化のための研究開発業務を専ら中小零細企業が担当し、その創意工夫を行う中で特許になりそうな発明等が出てきた場合、中小零細企業としては自らを発明者として出願等を行いたくなるのですが、大手企業より待ったをかけられることが通常です。
そして、よくよく確認すると、締結済みの共同研究開発契約書において、特許等の知的財産権については持分均等の共有とする、あるいは大企業に全部帰属するということが定められていたりします。
契約書の規定については事前に契約書の内容をチェックしてください!と言うほかないのですが、契約書の内容を読んでも理解ができないというのであれば、是非弁護士に相談し、どのようなリスクがあるのか、そのリスクを転嫁する手段はないか等の検討を行ってほしいところです。
一方、知的財産権の帰属について特段の取り決めがない場合、当該発明への貢献度を考慮し権利帰属を決めることが理想なのですが、中小零細企業の場合、大手企業との交渉力格差等もあるため、なかなか思うように協議を進めることができないのが実情です。ただ、大手企業も量産化に向けた共同研究開発段階にまで至っている場合、中小零細企業との連携を簡単に打ち切るわけにはいきませんし、どちらかというと後には引けない状況になっていることが通常です。すなわち、中小零細企業が思っているほど、連携打切りの危険性が高いわけではありません。
そこで、やや強気の交渉方針として、「貢献度に応じた帰属交渉が認められないのであれば、独占禁止法違反(優越的地位の濫用)として中小企業庁に相談させてもらう」といった行政の介入があり得ること指摘し、大企業からの譲歩を狙うといったことも考えても良いかもしれません。
ただし、権利帰属については譲歩してもらっても、次にライセンスの範囲でシビアな交渉になると予想されます(例えば、事実上大手企業に対する独占的使用許諾権を付与するよう迫られる等)。中小零細企業にとっては、せっかく取得した知的財産権を活用して、取引先の拡大を図りたいところですので、独占的ライセンスを付与することについては強く抵抗したいところです。この場合、落しどころとして、事業ドメインを限定した独占的ライセンスの付与に留めることができないか、期間を定めた独占的ライセンス付与に留めることができないか、一定の事由が生じた場合に独占的ライセンスが消滅することを定めることができないかといった観点から、合意を探ることが考えられます。
(2)成果物の利用に制限が設けられる
共同研究開発により得られた成果物(商品化可能なもの)につき、大手企業より、他社へ使用することを禁止するよう要請される場合があります。
たしかに、成果物の制作にあたって、大手企業より開示された秘密情報(技術・ノウハウ・情報等)が用いられている場合、秘密情報保護の観点から大手企業の要請も一定の合理性があると言わざるを得ません。
しかし、中小零細企業がこれを安易に受け入れてしまうと、成果物を制作するにあたって、自らが提供した秘密情報やアイデア等について、事実上他社で利用することができなくなってしまい、これはこれで困るという状況に追い込まれます。
結局のところはどこで折り合いをつけるのかという話に集約されてしまうのですが、上記(1)で記載したようなライセンス範囲を制限することと同じ発想で利用範囲の制限を設けることで対応する、成果物の利用制限を受け入れる代わりに適切なライセンス料を大手企業より徴収する、成果物の利用制限自体は受け入れつつ、中小零細企業が保有する秘密情報やアイデアの転用は可能にする、といった合意を取り付けることが考えられます。
(3)人材・協力先の引き抜きリスク
現場実務で意外と多いのが、成果物を制作するに際して、中小零細企業の再委託先である協力事業者がいつの間にか大手企業と直接取引を開始し、当該中小零細企業が梯子を外され、大手企業との取引は開始できず、協力事業者の取引は解消してしまうといった事例です。あるいは、共同研究開発においてキーパーソンとなる人物が大手企業に引き抜かれてしまい、やはり当該中小零細企業との連携協議が中断してしまうといった事例も現実に起こります。
厄介なのが、協力事業者及び人材の引き抜きについて、商道徳的にはケシカランといえても、法的には当然に違法とは言い難いという点です。
引抜きに対する抜本的な対処法は、残念ながらないというのが実情です。もちろん大手企業との契約において、人材引抜きや協力事業者との直接取引を禁止する条項を定めておくことで一定の効果は見込めます。
しかし、従業員については職業選択の自由があることから、従業員自らが大手企業にアプローチをかけてきた場合にまで、果たして当該条項が実効性を有するのかはやや疑問が残ります。同様に、協力事業者も経済活動の事由があることから、別の機会を通じて大手企業(の関連会社等)との取引を開始したという体裁を取られてしまうと、やはり実効性を欠く場合があります。ちなみに、従業員に対して、特定の企業への就職を禁止する合意書を締結したとしても法的有効性に疑問が残りますし、協力事業者との間で大手企業との直接取引を禁止する契約を締結すること自体が困難と考えられます。
従業員及び協力事業者との普段からの信頼関係を構築することが重要と言えます。
なお、共同研究開発に限定したものではありませんが、共同研究開発を含む業務提携契約を締結する場合のチェックポイントについては、次の記事をご参照ください。
業務提携契約書を確認するに際して注意するべきポイントを弁護士が解説!
4.その他大手企業と契約書を作成する際に注意したい事項
中小零細企業が大手企業と連携する手続きの進行具合に応じて、秘密保持の開示場面、技術検証の場面、共同研究開発を実施する場面に分けて検討を行いました。
この各種場面において、大手企業より各種の契約書の提示があることも多いのですが、いずれの場面においても共通して気を付けておきたい契約条項が存在します。以下では3例取り上げます。
(1)完全合意条項
契約書の後ろの方に定められていることが多いのですが、次のような条項です。
(例)
本契約は、本契約の対象事項に関する当事者間の完全な合意を示すものであり、本契約締結までに当事者間でなされた書面、口頭又は黙示的になされたあらゆる合意はその効力を失う。
要は、契約書に書いてあることが全てであり、口頭やメール等で約束していたとしても法的効力は生じないという意味です。
大手企業との交渉過程で合意した事項をすべて網羅した契約書を作成できるのであれば、この完全合意条項を定めることは意義があります。しかし、現場実務を見ている限り、残念ながら中小零細企業において、合意内容を網羅するだけの契約管理能力を持ち合わせていないのが実情です。
また、大手企業が提示する契約書の内容を修正しようとする場合、大手企業内の手続きが面倒である等の理由でなかなか応じてもらえず、担当者同士で、“契約内容はともかく、実際の運用は××とする”といった約束をすることがむしろ通常です。
このような実情を踏まえると、中小零細企業にとって完全合意条項は有害無益であり、削除を要請したい条項となります。
(2) 損害賠償条項
契約違反等があった場合、契約違反等を行った当事者が損害賠償責任を負うことは当然のことです。ただ、大手企業が提示する契約書に定めている損害賠償条項は、中小零細企業にとっては厄介な内容となっていることが通常です。
(例)
・(大手企業)が、第三者より知的財産権その他権利侵害を主張されたときは、(中小零細企業)の責任と負担においてこれを解決するものとし、(大手企業)に金銭的その他一切の損害を生じさせないものとする。
・商品の欠陥に起因して、第三者の生命、身体又は財産に損害が生じたときは、(中小零細企業)はその処理解決にあたり最善の努力をするものとし、これにより(大手企業)が被った一切の損害を補償するものとする。
上記は損害賠償問題が発生した場合、一切の責任は中小零細企業が負担し、大手企業は何らの責任を負わないとする一方的な内容でありアンフェアと言わざるを得ないのですが、大手企業から契約書が提示される場合、むしろこのような定めがおかれていることの方が通常です。
この場合、中小零細企業としては、①責任範囲を限定する(例えば、「但し、(大手企業)の責めに帰す事由がある場合はこの限りではない」という一文を追加するよう要請する)、②損害の範囲を限定する(例えば、逸失利益等の特別損害や間接損害、弁護士費用等の経費については損害から除外するよう要請する)、③損害額に上限を設ける(例えば、「(中小零細企業)は委託料を上限として損害賠償責任を負う」ことを明記するよう要請する)、といった契約交渉を検討したいところです。この契約交渉に際しては、独占禁止法上の優越的地位の濫用等のキーワードを指摘するのも一案と考えられます。
(3)契約終了後の措置条項
これから大手企業との連携協議を進めるのに、契約終了した場合のことを想定するのはちょっと…と抵抗感を持つ中小零細企業も多いかと思われます。しかし、残念ながら連携協議が上手く進み、商品量産等の取引が成立する可能性は極めて低く、どこかの場面で頓挫することが多いのが実情です。
したがって、出口戦略の1つとして、連携協議が不調となった場合にどうなるのかという視点は常に持ちながら契約交渉を行い、契約書に定めておくことでダメージコントロールを図ることは極めて重要なこととなります。
様々な内容が想定されることから、ここでは問題となりやすい事項を箇条書きで記述するに留めます。
- 競業禁止条項(研究開発自体が禁止されることを含む)が定められていないか
- 成果物や研究成果を第三者向けに転用することが禁止されていないか
- 知的財産権の帰属が大手企業に帰属することになっていないか、大手企業にライセンスを付与し続けることになっていないか
- 秘密情報以外に機械設備や資材等が返還・破棄対象となっていないか
- 中小零細企業が大手企業へ提供した物(データを含む)につき、返還・破棄対象となっているか、また目的外使用の禁止を定めているか
<2022年9月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
|
|






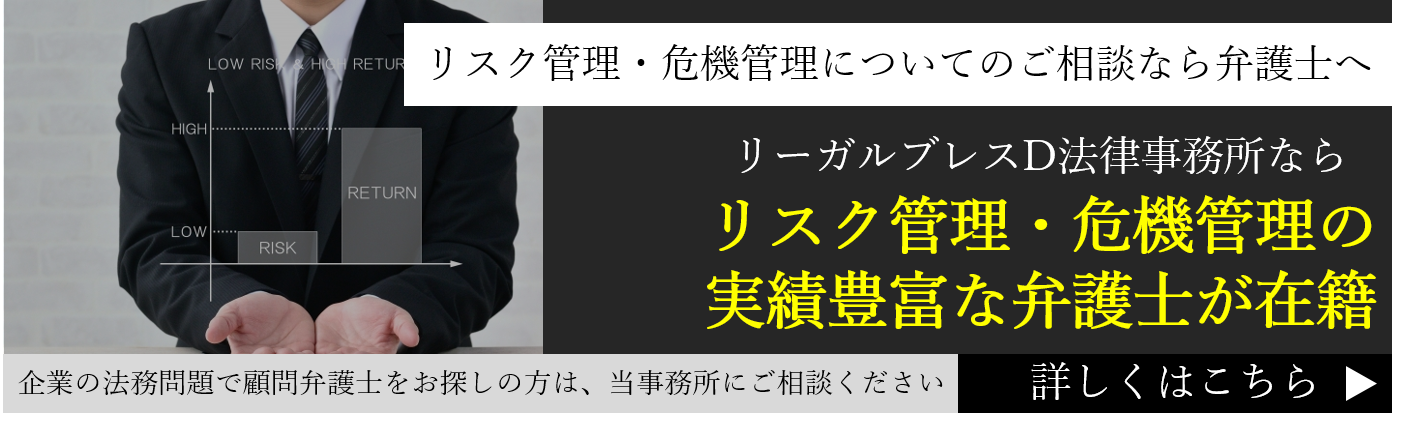

 弁護士 湯原伸一
弁護士 湯原伸一



































