Contents
【ご相談内容】
運送会社である当社は、これまで各ドライバーにおける走行距離や水揚げ高等を考慮した完全歩合給(出来高払)による賃金支払いを実施していました。
ところが、先日退職した元労働者より、完全歩合給の賃金制度は違法であるとして、500万円を超える未払い賃金(残業代)の支払いを求める訴訟を提起してきました。
完全歩合給(出来高払)を前提とした未払い賃金支払いであれば、解決に応じようと考えているのですが、このような考え方は通用するのでしょうか。
【回答】
労働者に対して完全歩合給(出来高払)を適用したから当然に違法という結論は考えにくいところです。なぜなら、裁判例を見る限り、完全歩合給(出来高払)だからという理由だけ違法と形式的に判断したものはないと考えられるからです。
本件の場合、完全歩合給としての実態が伴い、かつ保障給を上回る歩合給の支払いが行われていたのかを検討することで、十分その有効性を立証することが可能であると考えられます。
以下では、完全歩合給を検討する上での注意点やポイントを解説します。
【解説】
1.完全歩合給とは
(1)定義
完全歩合給(出来高払)とは、①固定給が支払われず、②賃金の対象が労働時間ではなく、労働者が製造した物の量・価格、契約件数・契約高、売上額などに応じた一定比率で額が定まる賃金のことをいいます。
世間一般では「フルコミッション」などと呼ばれることもあるようです。
完全歩合給は、生命保険募集人として従事する労働者や、トラックドライバーとして従事する労働者に適用されることが多いとされています。
(2)使用者にとってのメリット
労働者に対する賃金を完全歩合給とした場合に使用者が得られるメリットは、主に次の3つと考えられます。
①人件費の抑制につながること
詳しくは後述3(1)で説明しますが、歩合給と固定給とでは、法定時間外労働に対して支払うべき残業代の計算方法が異なります。
例えば、1ヶ月の総労働時間が200時間(所定労働時間が170時間、残業が30時間)、月給40万円(歩合給であれば計算結果、固定給であれば基本給)という労働者がいた場合、残業代は次のようになります。
・歩合給の場合…15,000円
・固定給の場合…88,235円
上記の通り、同じ残業時間であっても、固定給と比較して、歩合給の場合は残業代が相当低減することになり、人件費の抑制=経営改善につなげることが可能となります。
②成果に応じた賃金体系が可能となること
完全歩合給の特徴は、成果を出す労働者に対して手厚く賃金を支給するというものになります。
使用者は、ダラダラ時間をかけて業務従事する労働者よりも、テキパキ仕事をこなして短時間で成果を出す労働者に対し多くの賃金を支給したいと考えます。しかし、現行の労働法は、労働時間に応じた賃金支払いをルールとしているため、ダラダラ時間をかける労働者に多くの賃金を支払う必要性が生じ、テキパキ仕事をこなす労働者に多くの賃金を回すことができないジレンマを抱えています。
完全歩合給の場合、成果に応じた賃金体系となることから、上記のような経営者の悩みを解決することになります。
③均等待遇・均衡待遇(同一労働・同一賃金)対策になること
2020年4月より「均等待遇・均衡待遇」義務付けられることになり、あちこちの事業者が阿鼻叫喚状態になると言われていました。ところが、2020年4月は新型コロナの問題で日本中がパニックとなり、そもそも雇用を維持できるか分からないという状況となったため、「均等待遇・均衡待遇」の義務化はあまりクローズアップされることなく、今日に至っているようです。
しかし、新型コロナ問題が落ち着いたことから、「均等待遇・均衡待遇」が再び日の目を見ると予想されます。特に、近年は定年後再雇用の有期雇用労働者と正社員との均等待遇・均衡待遇の問題がジワジワと表面化しているところです。
正社員と有期雇用労働者との間で業務内容や責任の程度に大きな差異が見いだせない場合、両者とも完全歩合給を適用すれば、賃金資源の適切な分配を図りつつ、均等待遇・均衡待遇の適切な運用が可能となります。
(3)労働者にとってのメリット
上記(2)で記載した“使用者にとってのメリット”は、労働者視点ではデメリットであり(特に上記(2)①は賃金減額につながる)、労働者にとって完全歩合給のメリットはないのではと思われるかもしれません。
ただ、完全歩合給の具体的な賃金体系にもよりますが、やはり「成果を出せば出すほど賃金がアップする」という点は、労働意欲を湧き立てると共に、結果に対する満足度も得られるので、デメリットばかりではありません。また、成果という客観化しやすい基準で労働者ごとの賃金に差異を設けることができるため、他の労働者から不平不満を言われるリスクも低いと言えます。さらに、何らかの理由で成果が出ないときがあったとしても、労働者である以上、保障給の支払いが使用者には義務付けられており、賃金がゼロになる心配もありません。
以上の点を考慮すると、完全歩合給は労働者にとっても、魅力ある賃金体系といえるのではないでしょうか。
2.完全歩合給に対する誤解
完全歩合給とする賃金体系は珍しいためか、色々と誤解があるように感じます。
例えば、労働者に完全歩合給を適用することは当然に違法であり、認められないという見解が巷では言われているようです(インターネット上でも違法である旨の記述がたくさん出回っています)。
しかし、少なくとも執筆者が調べた限り、完全歩合給だから当然に違法であるとする裁判例は存在しないように思います。むしろ、札幌地方裁判所平成23年7月25日判決のように、完全歩合給であることを前提に賃金支払いを命じている裁判例も存在するところです(なお、控訴して札幌高等裁判所平成24年2月16日判決、上告して最高裁判所平成24年7月6日決定と続きますが、完全歩合給での賃金計算は否定されていません)。
したがって、労働者に完全歩合給による賃金体系を採用すること自体は何ら問題ありません。
これ以外にも、執筆者が体験した“誤解”について、以下記述します。
(1)完全歩合給はどのような業種・職種でも適用できる?
完全歩合給は、理論的にはあらゆる業種・職種に適用することが可能です。
しかし、現実的には難しいように感じます。
なぜなら、もともと歩合給は「労働者が製造した物の量・価格、契約件数・契約高、売上額などに応じた一定比率で額が定まる賃金」であるところ、例えば、バックオフィスを担う事務職に対して成果を定め、それに対する金銭評価をすることは困難だからです(一書類を作成するごとに金銭評価するという考え方もあり得ますが、かなり無理があると思います。また、来客対応や雑務などの成果を見出せない業務について、賃金支払いの対象とならない以上、事務職の担当者は従事しなくなるおそれが生じます)。
したがって、完全歩合給を適用できるのは、トラックドライバー、保険募集人、営業職といった労働者個人の力量のみで成果を算出できる業種・職種に絞られるように思います。
なお、労働者個人の力量のみで成果を算出できるという点を考慮すると、在宅ワーカーやSE(システムエンジニア)など個々人の作業が重視される場合にも適用可能になると考えられます。
(2)歩合給の計算方法は自由に定めてよい?
完全歩合給の場合、例えば「売上×一定料率」で賃金計算を行うことが多いのですが、これ以外の計算方法を用いてはならないとする法律はどこにもありません。
したがって、完全歩合給として支払うべき賃金の計算方法は、使用者が自由に定めることができるのが原則です。
ただ、当然のことながら物事には例外が存在します。
すなわち、歩合給は「労働者が製造した物の量・価格、契約件数・契約高、売上額などに応じた一定比率で額が定まる賃金」と定義される以上、“製造した物の量・価格、契約件数・契約高、売上額など”が増加すればするほど、支払うべき賃金は比例的に増加するという関係になることが前提となります。このため、この比例的な増加が見込めない計算方法を定めている場合、そもそも歩合給ではないと評価されることになります。
例えば、「(加算項目-減算項目)×料率」にて歩合給を算出すると定めていた運送会社において、次のような判断を行った裁判例が存在します(原告は労働者、被告は使用者)。
【東京地方裁判所平成18年1月27日判決】
被告の給与制度では、契約社員が全歩合者として、加算項目の金額を常に減算項目が上回り、歩合の達成が現時点ではほとんど不可能であること、他の原告らについても同様にいくら1日8時間を超過して勤務しても、さらに休日労働をしても、それが固定給とされる基本給は当然として歩合給に反映されることは少なくとも同人らの過去2年間の実績からはなく、むしろ頑張れば歩合保障金額との差が多少縮まるものの10万円に届かない実態にあることからすると(仮に、原告らの一日の労働が8時間を超過するとすると、被告が残業代固定給とする金額がこれら原告らの実際の残業相当時間と単価による賃金分を常にカバーできているとまでは認めることはできないのではないか。被告は他の班の過去の歩合実績やA以外の原告らの過去の歩合実績を主張・立証するが、上記判断に照らして有効とは思われない。)、このような被告の賃金体系によったのでは、原告らの労働量と労働時間に見合う賃金を支払うことを法によって使用者に命じている労働基準法の趣旨に背馳する余地があるものというべきである。
上記は、労働者がいくら業務従事しても、減算項目(ガソリン代、車両修繕費など)が高額すぎて、常に加算項目を上回る状態になっている場合、比例的な増加が見込めない以上、歩合給とは言い難いとして、歩合給該当性を否定した裁判例となります(ちなみに、上記裁判例の背景事情として、歩合給が出ない以上、何時間勤務しても最低保障給しか支払われていなかったというものがありました)。
以上のことからも分かる通り、完全歩合給を算出するための計算方法は使用者の自由裁量であるとはいえ、“製造した物の量・価格、契約件数・契約高、売上額など”が増加すればするほど、支払うべき賃金は比例的に増加するという関係性に注目する必要があり、これを逸脱すると、そもそも歩合給として認められないという点に注意する必要があります。
(指摘するまでもありませんが、歩合給であることが否定された場合、残業代の計算方法は一般的な固定給の場合と同様となり、高額の残業代支払いを余儀なくされます)。
(3)保障給の定めがないと無効?
労働基準法では、完全歩合給を含む歩合給制について詳細な規定が定められておらず、唯一あるのは次の規定となります。
【労働基準法第27条】
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
この労働基準法第27条を受けて、使用者が労働者に対して最低限支払わなければならない賃金を「保障給」と呼ぶのですが、この保障給について就業規則や労働条件通知書・労働契約書に明示していなかった場合、果たして(完全)歩合給は否定されるのかという問題があります。
実は、執筆者が調査した限り、この点について明確に結論を指摘している文献等が存在しないようで、唯一見つけたのが次の裁判例となります。
【名古屋地方裁判所平成14年5月29日判決】
一般に、賃金の支払が、出来高払制その他の請負制による場合は、時間賃金の場合と異なり、仕事の供給量に伴う事業の繁閑によって賃金額が左右され、あるいは仕事の単位量に対する賃金の切下げ、仕事の完成度に対する厳しい評価などとあいまって不当に低い賃金をもたらして、労働者の生活の安定を確保することが難しくなると認められる。
そこで、労基法27条は、上記のような弊害のあることを考慮して、実収賃金の確保ないし減少防止を通して労働者の生活を保障すべく、一定額の賃金保障を使用者に義務づけたものであると解される。
そして、同条が定める保障給とは、「労働時間に応じた一定額」であるから、時間給であるのが原則であり、実労働時間に応じて支払われなければならないものであるから、労働者の実労働時間とは無関係に一定額を保障するものは固定給であって、同条にいう保障給とはいえない。
同条は、使用者に対し、上記のような保障給の定めをし、かつ、当該保障給以上の給与を労働者に支払う義務を課しているというべきである。
ただし、当該労働契約が労基法27条に反して無効となるか否かの判断にあたっては、保障給の定めが明確にはなされていなくても、現実に同条の上記の趣旨に合致するような給与体系が確立されており、適正に運用されていると認められれば、当該労働契約が無効であるとはいえないと解される。
上記裁判例のポイントは、保障給の定めは必須ではなく、現実の運用として保障給以上の賃金を支払っている実態があるのであれば、歩合給は無効ではないと判断している点です(なお、上記裁判の事例では、運用実態がないとして結論的には歩合給が否定されています)。
労働者の賃金体系として完全歩合給を適用するのであれば、保障給について明確に定めておくことが無難なのですが、定めがない場合であっても、上記裁判例を参照しながら、完全歩合給の有効性を主張することが可能と考えられます。
ちなみに、保障給に関する規定例ですが、次のようなものが考えられます。
(保障給に関する規定例)
当月の歩合給について、過去3ヶ月分の歩合給をその期間の総労働時間数で除した金額の6割に満たない場合、その差額分を上乗せして歩合給を支給する。
なお、保障給が最低賃金にも満たない場合、最低賃金を上回るように支給する必要があることに注意を要します。
3.完全歩合給による賃金支払いの注意点
(1)残業代(割増賃金)の計算方法
上記1.(2)①でも少し触れましたが、(完全)歩合給の場合、残業代の計算方法について、基礎賃金の計算方法と割増率が特殊なものとなります。
まず、基礎賃金の計算方法ですが、これは労働基準法施行規則第19条第6号に根拠があります。
【労働基準法施行規則第19条第6号】
法第37条第1項の規定による通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額は、次の各号の金額に法第33条若しくは法第36条第1項の規定によって延長した労働時間数若しくは休日の労働時間数又は午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの労働時間数を乗じた金額とする。
(1号から5号省略)
⑥出来高払制その他の請負制によって定められた賃金については、その賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間、以下同じ)において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における、総労働時間数で除した金額
つまり、基礎賃金を算出するに際して、法定労働時間で除するのではなく、総労働時間で除することになります。したがって、固定給の場合と比較して、基礎賃金が低くなることが通常です。
次に割増率ですが、例えば、次のような裁判例が存在します。
【名古屋地方裁判所平成3年9月6日判決】
労基法37条1項の規定による割増賃金の計算は、通常の労働時間の賃金の一時間当たり金額に2割5分を最低とする一定の割増率及び労働時間数を乗じて行われ、労基法施行規則(規則)19条はその一時間当たり金額の求め方を賃金の種類ごとに規定しているが、日によって定められた賃金についてはその金額を一日の所定労働時間数で除した金額(同条2項)、月によって定められた賃金についてはその金額を月における所定労働時間数で除した金額(同条4項)であるのに対し、出来高払制その他の請負制によって定められた賃金については、その賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額(同条6項)である。右規定の趣旨は、請負給の場合には一定の労働時間に対応する一定の賃金が定められておらず、常に実際の出来高等に対応する賃金が請負給として支払われるから、時間当たり基礎賃金額の計算方法上も日給、月給等の場合と異なり、実際の支払賃金総額と総労働時間数によって算定することとしたものである。総労働時間数は実労働時間の総数であり、所定労働時間の内外を問わず、時間外又は休日労働時間数も含まれる。また、日給制や月給制によって賃金が定められている場合には、通常の労働時間の賃金に2割5分以上の加給をした金額が支払われなければならず、一時間当たりの金額に掛けるべき割増率は1.25であるのに対し、出来高払制その他の請負給制によって賃金が定められている場合には、時間外における労働に対しても通常の労働時間の賃金(右割増率の一に相当する部分)は既に支払われているから、割増部分に当たる金額、すなわち時間当たり賃金の2割5分以上を支給すれば足りるのである。
つまり、固定給の場合、法定時間外労働に対して125%の割増率で残業代を算出する必要があるのに対し、(完全)歩合給の場合、法定時間外労働に対して25%の割増率で算出すれば足りると、上記裁判例は指摘しています。
この結果、上記1.(2)①で記載した例、1ヶ月の総労働時間が200時間(所定労働時間が170時間、残業が30時間)、月給40万円(歩合給であれば計算結果、固定給であれば基本給)という労働者がいた場合、残業代の計算方法は次のようになります。
・歩合給の場合…400,000円÷200時間×30時間×0.25=15,000円
・固定給の場合…400,000円÷170時間×30時間×1.25=88,235円
なお、偶にですが、個別の労働者に配布する労働条件通知書や労働契約書において、割増率を125%と明記しているものを見かけたりします。
おそらくは固定給の労働条件通知書や労働契約書を修正せずにそのまま用いていることに原因があると思われるのですが、この場合、せっかくの歩合給のメリットである低い割増率を適用することは難しいと考えられます(使用者があえて労働者有利の特約を設定したと考えられるため)。
せっかく完全歩合給を適用するのであれば、細部の記載内容を含めて注意したいところです。
(2)歩合給の全部又は一部を固定残業代として支払うことの可否
この問題は完全歩合給よりも、一部歩合給(固定給と歩合給とを組み合わせた賃金体系)でよく起こる問題となります。
すなわち、歩合給をあらかじめ一定時間分の残業代の支払いに充てるというものですが、結論から申し上げますと、現在の裁判例の流れからして不可能と考えられます。
なぜなら、歩合給は実労働時間における成果に対して支給するものであり、この一部又は全部より残業代を抽出し支払うということが観念できないからです。なお、固定残業代については、残業代部分との明確区分性が重要となりますが、仮に歩合給のうち、一部について残業代である旨明確に賃金規程等に定めたとしても、その定めは無効になりますので、注意が必要です。
結局のところ、完全歩合給は残業代の支払い自体を消滅させるという制度ではなく、法定時間外労働に対する残業代は上記3.(1)で記載したような特別な計算方法で別途支払うことが大前提であると考えておくべきです。
(3)年次有給休暇について
完全歩合給の場合、成果に対して賃金を支給するのであって、業務遂行に要した労働時間に対して賃金を支払うわけではありません。
したがって、そもそも欠勤控除という概念が存在しないのですが、だからといって年次有給休暇の取得不可という結論にもなりません。たとえ完全歩合給が適用される労働者であっても、労働基準法が適用される以上は年次有給休暇を取得することが可能です。
使用者において誤解していることが多いので、注意を要します。
4.完全歩合給制導入への注意点
上記1.から3.までで記載した通り、特に使用者視点では、完全歩合給の賃金体系を適用することは大きなメリットがあり、是非導入したいと考える使用者も多いと思います。
しかし、固定給から完全歩合給に賃金体系を変更する場合、労働条件の不利益変更に該当すると言わざるを得ません(労働者の賃金が減少する可能性がある以上は不利益変更に該当すると考えたほうが無難です)。
したがって、完全歩合給を導入するに際しては、次の3点を抑える必要があります。
①労働者より書面の同意を取得すること
②就業規則の不利益変更手続きを念頭に置くこと
③経過措置を設けること(激変緩和措置を講じること)
なお、詳細については次の記事をご参照ください。
労働条件を変更する場合の手順とは? 手続きの進め方等について弁護士が解説!
5.当事務所でサポートできること
当事務所では、一部歩合給(固定給と歩合給の併用制)はもちろん完全歩合給の賃金体系を採用している使用者より依頼を受け、未払い賃金(残業代)の裁判手続きを複数取り扱っています。そして、これらの実務経験により、完全歩合給の賃金体系を適用されている労働者側からの主張に対してどのように反論するべきかもとより、裁判官がどのような観点より有効性を判断してくるのか等の様々な知見とノウハウを蓄積できていると自負しています。
上記知見とノウハウにより、紛争が生じた場合の解決法のご提案はもちろんのこと、紛争予防の観点から賃金体系構築のお手伝いなどの様々なサービスをご提供することが可能です。
完全歩合給に関するご相談等がございましたら、是非当事務所をご利用ください。
<2023年8月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
|
|






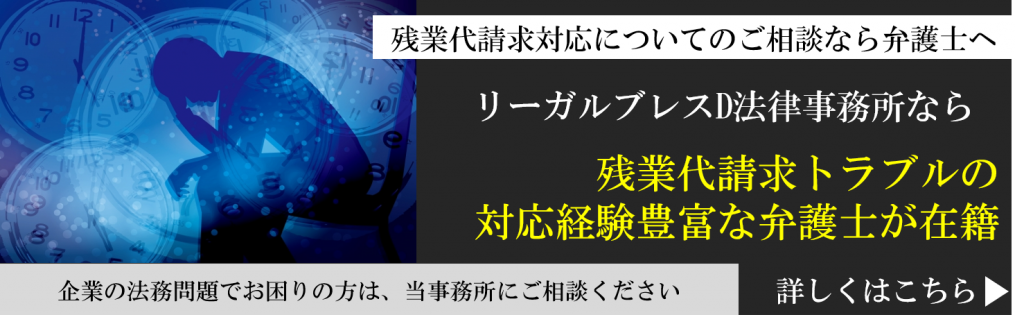

 弁護士 湯原伸一
弁護士 湯原伸一



































