Contents
【ご相談内容】
当社が取扱う商品について、メーカーと通謀し品質偽装を指示している部長がいること、これに気が付いた部下に対し部長が口止め工作を図っていること等の内部通報が入りました。事実だとすれば由々しき事態であるため、当社としても徹底的な調査を行う方針なのですが、これまで社内調査を行った実例がないため、どういったことを想定しながら進めていけばよいのか皆目見当がつきません。
社内不祥事が発生した場合の社内調査の進め方について、教えてください。
【回答】
会社として必要かつ十分な調査を行う場合、担当者を決め、時間・労力・費用をかけて行うことになります。
この点、中小企業の場合、いわゆる第三者委員会を立ち上げて社内調査を行うことは現実的ではないため、本記事では会社内の従業員で構成される社内調査チームを念頭に解説します。
視点としては、社内調査チームの構成員はどうするのか、何をどこまで調査するのか、調査する場合の注意点は何か、調査結果に関する留意事項は何かがポイントになります。
【解説】
1.誰が調査するのか
社内調査を行うに際しては、世間一般では第三者委員会と呼ばれるものを立ち上げる場合と、社内調査チームを立ち上げる場合の2通りがあります。
(1)第三者委員会とは
第三者委員会とは、会社と利害関係のない(全く会社と縁もゆかりもない)第三者のみで構成される調査部隊とイメージすれば分かりやすいかと思います。
何らかの不祥事が発生し、マスコミ等に取り上げられることで世間一般の重大な関心事となった場合、謝罪はもとより、徹底的な原因調査と、それを踏まえての対策の公表が急務となります。そして、公平性に欠く中途半端な調査では、取引先等のステークホルダーからの疑義や世間からの批判・非難に耐え切れないことから、第三者委員会を立ち上げることが最近では多くなってきています。
ところで、上記のようなニーズは会社の規模を問わず、いずれの会社でも当てはまるものです。しかし、中小企業(非上場企業)の場合、第三者委員会を立ち上げることはまずありません。なぜなら、中立公平な第三者を探索するノウハウもなければ、費用負担面で第三者委員会を立ち上げることが困難だからです。執筆者が知る限りですが、最低でも数百万円、場合によっては1000万円超の費用負担が生じると言われています。
したがって、中小企業の場合、社内従業員を中心とする社内調査チームを立ち上げて、調査を実施するという選択肢しか残されていないのが実情です。
(2)社内調査チームの構成員
本記事では「社内調査チーム」という言葉を用いていますが、名称について法令上の根拠があるわけではありません。要は、会社内の担当者(役職者等)を中心にメンバーが構成される調査部隊と考えれば足ります。なお、場合によっては、外部の弁護士や会計士等が構成員となることがありますが、当該弁護士・会計士等も利害関係が全くない第三者として選任されるわけではないことも見受けられます(例えば、会社の顧問弁護士や会計士が構成員となる場合など)。
ところで、会社内の担当者が中心になるとはいえ、調査を行う以上、不祥事の疑いがかけられている者を構成員に選出するようでは中立・公平性を担保できません。また、いくら適切な調査を行ったとしても、世間一般から見ればどこまで行っても疑義を挟まれることになります。社内調査チームの構成員を選出するに際しては、次のような事項に留意するべきです。
- 不祥事疑義のある当事者は選任しない(上記記載の通り)
- 不祥事による被害者と称する者は選任しない(例えばハラスメントの被害者など。やはり中立公平性を欠くことになるため)
- 不祥事疑義のある加害者及び被害者のいずれかの当事者と人間関係の深い人物を選任しない(私情による調査の歪みが生じる恐れがあるため)
- 不祥事疑義のある当事者の直属の上司はなるべく選任しない(むしろ当該上司は不祥事を見過ごしていたとして調査対象になるのが通常であるため)
- 不祥事疑義のある当事者より社内職位が低い者をなるべく選任しない(少なくとも社内調査メンバーのトップが下位者の場合、調査に遠慮・忖度が生じる、あるいは疑義対象者が見くびることがあり得るため)
なお、疑義対象者が会社内で一定の影響力を有する役職員である場合、社内調査チームに弁護士を関与させることで、一定の威厳を保つといった工夫が必要となることもあります。
(3)社内調査チームと弁護士の関与
上記(2)で記載したような、社内調査チームに一定の威厳を持たせる場合に弁護士に関与させることがありますが、それ以外にも、例えば次のような場合は弁護士を関与させた方がスムーズに社内調査が進むものと考えられます。
- 書類証拠(電子データを含む)が散逸又は膨大となる場合
- 多数の関係者よりヒアリング調査を行う必要がある場合
- 不祥事疑義のある当事者が事実関係について否認することが予想される場合
- ハラスメントのような「評価」が中心となる調査の場合
- 会社外に被害者が存在する場合
ところで、弁護士の関与のさせ方として、①調査(例えば関係者からのヒアリング等)それ自体は会社内の担当者が行い、弁護士は収集した証拠の検証のみを行う方法、②弁護士自らが調査に積極的に関与し検証も行う方法、の2通りが考えられます。どちらが正解というわけではないのですが、特にヒアリング調査については、ある程度の勘と経験が必要な調査となるため、できれば弁護士に主導的に関与してもらった方が良いものと思われます。
(3)社内調査チームはどこまで深堀するべきか
社内調査チームの役割論となるのですが、社内不祥事が疑われる事態となった場合、必要な証拠を収集すること、収集した証拠に基づき事実関係を明らかにすること、事実関係に基づき法的評価を行うこと(違法性の有無、(違法とは言いきれなくても)不当性の有無、判別不能事項の有無など)、原因の究明を行うこと、以上4点については社内調査チームとして最低限行わなければならない事項となります。
ここからさらに、再発防止策を提案すること、不祥事を起こした人物に対する社内処分を提案すること、法律上の責任追及を行うよう提案すること、被害回復措置を提案すること等については、会社が社内調査チームに対して何を依頼しているかによって判断が分かれることになります。
ちなみに、社内調査チームの具申内容について、会社は逐一遵守しなければならない義務を法律上負っているわけではありませんが、特段の事情がない限り、会社は当該内容を尊重しないことには、対外的には説明が付きません。ただ、中小企業の場合、社内調査チームが先走ってあれこれ提案した場合、会社として当該提案内容は理解できても、現実的には処理しきれないことがあり得ます。そして、対応ができないことによって、ステークホルダー等より更なる非難と反発を招くといった事態も生じえます。このため、社内調査チームが何をどこまで対外的に明らかにするのかについては、調査依頼時に事前に検討しておく必要があります。
2.何を調査するのか
(1)調査権の根拠
社内不祥事が発生した場合、第三者委員会であれば社内調査チームであれ、何らかの調査を行うことが通常です。しかし、法律の明文上、会社は社内調査を行うことができる旨定められているわけではありません。
この点については、実は裁判例により解決されています。例えば、最高裁昭和52年12月13日判決では、「企業秩序に違反する行為があつた場合には、その違反行為の内容、態様、程度等を明らかにして、乱された企業秩序の回復に必要な業務上の指示、命令を発し、又は違反者に対し制裁として懲戒処分を行うため、事実関係の調査をすることができることは、当然のこと」と判示されているところです。
したがって、社内不祥事が疑われる事態となった場合、会社が従業員を調査すること自体は、法律上の権利として認められていると考えて間違いありません。
(2)調査権の限界
会社が調査権限を有することは上記(1)の通りですが、当然のことながら無制限に認められるわけではありません。この点については、やはり上記引用の最高裁昭和52年12月13日判決でも、「当該労働者が他の労働者に対する指導、監督ないし企業秩序の維持などを職責とする者であって、右調査に協力することがその職務の内容となっている場合には、右調査に協力することは労働契約上の基本的義務である労務提供義務の履行そのものであるから、右調査に協力すべき義務を負うものといわなければならない」、「右以外の場合には、調査対象である違反行為の性質、内容、当該労働者の右違反行為見聞の機会と職務執行との関連性、より適切な調査方法の有無等諸般の事情から総合的に判断して、右調査に協力することが労務提供義務を履行する上で必要かつ合理的であると認められ」る場合は調査協力義務を負うと判示されています。
さて、上記判例を前提とする場合、会社による調査権の限界は次のようなものが考えられます。
1つ目ですが、直接の労働契約がない派遣労働者に対し、派遣先が調査することは難しいことになります。建前論としては派遣元が派遣先より委託を受けて、派遣労働者に対して調査を行うのが筋論です。しかし、現場実務の観点からすると、何をどこまで調査したいのか具体的な要望・要求事項を持っているのは派遣先であり、派遣元が全てを肩代わりして調査することは困難と言わざるを得ません。したがって、派遣先と派遣元は、不祥事が生じた場合の派遣労働者に対する調査権について、別途業務委託契約を締結する(委託者が派遣元、受託者が派遣先)といった方法で対処することを検討する必要があります。
2つ目ですが、労働契約とは切り離された領域、すなわち従業員のプライベートに関する事項について会社が調査を行うことは原則できないことになります。古典的なものとしては社内恋愛を含む従業員同士の人間関係、最近では従業員の持病に関する事項や性的指向・性自認に関する事項などが例としてありますが、これらを調査することは原則できません。もちろん、これらが原因となって社内秩序に乱れが生じた場合(例えば、社内恋愛の揉め事からセクハラ騒動に発展する等)、例外的に社内調査を行うことができますが、結果的に表沙汰になることで、業務に関連する事態となったことを理由として調査対象範囲になるにすぎません。あくまでも事後的な調査対応となることに注意が必要です。
3つ目ですが、労働契約に基づかない従業員の行為、すなわち私生活上の言動についても、会社が調査を行うことは原則できません。古典的には業務外での犯罪歴の有無、最近では従業員個人のアカウントを用いたSNS上での投稿といったものがあげられますが、これらを調査することは原則できません。上記(2)と同じく、これらが原因となって社内秩序に乱れが生じた場合は、例外的に社内調査を行うことができますが、やはり事後的な対応となります。もっとも、例えば反社勢力との交友関係が疑われるといった事例の場合であれば、事前の調査を行っても差し支えないと考えられます。
3.どうやって調査するのか
(1)申告者の意向確認
調査開始に先立ち、まずもって優先確認するべき事項があります。それは、社内不祥事を申告した者に対するフォローです。
なぜフォローが必要なのかというと、申告者は、申告により社内調査が進むことで自分の身に何か不利益が発生しないかを危惧していることが多いからです。特に、社内不祥事に関与した者から、後で何らかの嫌がらせを受ける可能性があると考え、申告はするものの社内調査を行うことには消極的な意向を示すということが結構な頻度であったりします。
例えば申告者が、ハラスメントの被害者と主張する場合、たしかに申告者の意向を尊重しなければならないというのは理屈として間違っていません。しかし、申告はしたものの、それ以上の社内調査が進められないという事態となると、今後さらに被害が拡大してしまう恐れもあり、会社として不祥事を認識しながら未然に拡大防止ができなかったという点において、後々不都合なことにもなりかねません(被害が拡大してから、申告者が会社に対して責任追及を行ってくる等)。
したがって、申告があり、社内調査を進める方針となった場合は、申告者より社内調査を進めることの了解を取り付けるべきです。そして、さらに次の点の意向確認を必ず行うべきです。
・申告を受けた者が関係部署に報告を行うことについての了解
・追って担当者がヒアリング調査を行うこと及び証拠提出依頼を行うことの了解
・関係部署への報告に際し、申告者の氏名を明らかにすることについての了解
・関係者からヒアリング調査等を行う場合、必要に応じて申告者の氏名を告げる場合があることについての了解
・(調査期間中の一時的措置として)職場の変更又は業務内容を変更することに関する了解
なお、会社によって様々な事情があるかと思いますが、申告内容が社内調査チームの構成員以外の不特定多数に漏れ出さないよう適切な措置を講じることについて、できる限り具体的に申告者に説明をすること、申告によって会社が不利益措置を講じることは無いことを説明することも、重要なポイントとなります。
(2)初動
何らかの社内不祥事が発生したと疑われる事態となった場合、まず最初に行うべきは客観的証拠の確保、すなわち書類や電子メール、最近であればチャットツール等の保存と収集となります。なぜなら、書類や電子メール等は原則そこに書いてある内容が“動かしがたい事実”となり、証拠価値が非常に高いからです。そして、証拠価値が非常に高いゆえに、不祥事が疑われる対象者において、社内調査が開始されたと気付いた場合、書類や電子メール等を書き換えたり破棄したりする等の証拠隠滅工作を図ることになります。
したがって、対象者が動き出す前に、書類や電子メール等の客観的証拠を確保することがセオリー中のセオリーとなります。
次に、客観的証拠の収集がある程度進んだ段階で(又は収集と同時並行で)、時系列表を作成することを執筆者はお勧めしています。時系列表というと何か難しいものを想定する方もいるようなのですが、執筆者が会社担当者に説明するに際しては、「いつ、どこで、誰が、誰に対し、どういった方法で、何をしたのか、(それはなぜか)」をそれぞれ箇条書きでいいのでまとめるよう要請しています。何か理路整然とした美しい文章を作成することに拘る担当者もいるのですが、短文殴り書きのようなものでも構わないと執筆者個人は考えています。そして、時系列表と確保した客観的証拠との対応関係を明記すれば、初動としては事足ります。
時系列表を作成することで、本来あるはずの書類がないことや、不自然な事実経過を可視化することができ、どこにターゲットを当てて証拠の確保を図ればよいのか見えてくるようになります。
ちなみに、不祥事に関与した関係者が複数名、社外にも関係者がいる場合は、当事者関係図を作っておくと便宜です。
(3)関係者からのヒアリング
・順番
よほどのことがない限り、不祥事に直接関与していると疑われる者については一番最後となります。基本的には不祥事があることを申告してきた者からヒアリングを行い、そのヒアリングの中で不祥事に関する情報を持ち合わせていると考えている者(但し不祥事に直接関与して者と交友関係がある者、また不祥事を行った者の直接の上長は後回し)からヒアリングを行うことが通常です。これは不祥事に直接関与していると疑われる者による証拠隠滅(関係者への口封じ)を防止するためです。
なお、セクハラ等の場合、申告者である被害者が精神的に不安定な状態(申告直後ではヒアリング調査に耐えられない)の場合もあります。この場合は、申告者が所属する部署内関係者から先にヒアリング調査を行うといった順番変更もあり得ます。
・時間
社内調査は業務に関連して行われるものである以上、原則的には就業時間中に行うべきです。もっとも、ヒアリング調査の対象者となっていることを知られたくないと考える従業員も存在します。その場合は、当該従業員の意向を確認の上、就業時間外で行うことも検討するべきです。
ちなみに、就業時間外でヒアリング調査を行った場合、調査を行う担当従業員及び調査対象となる従業員とも時間外労働を行っていることになりますので、その分の割増賃金が必要となります。
次に、ヒアリング調査を行う時間ですが、執筆者個人の見解としては90分を原則、長くて120分以内を1つ目安にすればよいのではないかと考えています。あくまでも執筆者の経験則に過ぎませんが、調査を行う者も調査を受ける者も2時間以上は集中力が続かないからです。また、長時間拘束して調査を行って得られた証言については、後で「調査を早く終了させたいと思い、嘘の証言をした」等の主張が出やすく、色々と問題が起こりがちです。
複数の日時またがって対象者からヒアリング調査できないといった事情等もあるかもしれませんが、なるべく効率よくヒアリング内容をまとめるのがポイントになるように思われます。
・場所
基本的には社内で行うべきです。もっとも、ヒアリング調査内容をオープンにするわけにはいきませんので、会議室などの執務室は異なる場所を用いて行う等の対応が必要となります。
なお、中小企業の場合、音が外に漏れない会議室自体が社内に存在しない、普段使わない会議室に出入りすること自体が社内に異様な雰囲気を与える等の事情もあったりします。その場合は外部の貸会議室を使用する等して対処するほかありません。
また、最近ではWEBシステムを利用したヒアリング調査を行うことが可能な環境となっていますので、当該システムを利用することも一案です。ただ、WEBシステムの場合、顔の表情や声色、仕草等の微妙な証言者の変化を感じ取りにくいところがあります。したがって、第三者的立場にある者からのヒアリングであれば支障はないかと思いますが、不祥事の疑義がある者からのヒアリング調査の場合は、直接会って調査を行う方が良いのではないかと考えます。
・人数
色々考え方はあるかと思いますが、執筆者個人としては2名、多くても3名以内にするのが無難ではないかと考えています。
まず、調査担当者1名でヒアリング調査を行うことは回避するべきです。たしかに、中小企業の場合、人数を確保できない等の事情はあるかもしれません。しかし、ヒアリング調査を行っている最中に不測の事態が生じた場合に対処できる者を配置しておくのが安心であること、質問を行う主担当者による不適切な調査(暴言など)を防止できること、聞き漏れや補足質問などのフォローアップが期待できること、といったメリットがありますので、適切かつ効率の良い調査を実現するためにも複数名でヒアリング調査を行うべきです。
逆に4名以上となると、調査対象者からすればかなりの圧迫感を感じ、言いたいことも言えないという空気になりがちです。フランクに証言してもらうためにも、あまり多数でヒアリング調査を実施するべきではないと考えます。
・聞き方
まず指摘しておきたいのが「結論ありきで話をしない」という点となります。少なくともヒアリング開始直後に結論ありきで切り出してしまった場合、調査対象者が変に迎合してしまう、あるいは妙な反発心が生まれる等の弊害が大きく、調査対象者が認識している事実を聞き出すことが難しくなるからです。
また、ヒアリング時に、調査担当者が何らかの結論を明言したり、対象者の証言を踏まえて主観的評価を加えて発言することも禁物です。なぜなら、ヒアリング調査はあくまでも調査対象者が認識している事実を拾い上げる作業であるところ、調査担当者の主観的認識を押し出した調査となると、後日証言の信用性に疑義を挟まれやすくなるからです。
ところで、ヒアリング調査を開始するに当たり、どういった切り出し方をすればよいのかという問い合わせを受けることがあります。色々やり方はあるかと思うのですが、なぜこの場に呼ばれたのかその理由、ヒアリング調査を行う目的といったオーソドックスなことを簡単に説明した上で、事前に調査対象者がどういった事項を認識しているのか知っている場合は、「事前に××とお伺いしています、よろしいでしょうか」と調査対象者の認識を確認するところからスタートするのが無難ではないかと考えます(要は、調査対象者に対して肯定的な評価も否定的な評価もしないという点が重要です)。なお、事前に調査対象者がどういった事項を認識しているのか情報が得られていない場合、例えば「××という従業員が××という不正な行為を行ったという話が出ているのですが、こういった話は聞いたことがありますか」といった概括的な結論から聞き出すと、比較的スムーズに調査を進められるのではないかと思われます。
一方、聞き方として、例えば「××について、あなたの知っていることを全部述べてください」といったオープンクエスチョンは避けるべきです。なぜなら、聞かれた方も、何から答えればよいのか整理がつかないからです。社内調査チームが把握している事実関係について、1つずつ聞き取ったほうが無難です。
なお、質問の仕方や進め方、内容、予想外の回答が来た場合の切り返し方、想定問答等については、裁判手続きで尋問を日常業務として行いノウハウを蓄積している弁護士に相談し、対策を講じることを強くお勧めします。
(4)NGなヒアリングとは
上記(3)でも少し触れましたが、その他にも次のようなヒアリング手法はNGとなります(証言の信用性に疑義が生じます)。なお、そんな手法は用いないと考えるかもしれませんが、ヒアリング調査担当者がヒートアップして、ついつい言ってしまうことは結構あり得る話です。今一度ご確認いただければと思います。
- 脅迫を用いたヒアリング(例:「素直に認めないとクビにするぞ」、「否定し続けるなら告訴するぞ」等の圧力をかける言い回しで証言させる場合など)
- 欺いて行うヒアリング(例:「(証拠がないのに)証拠はあるのだから否定しても無駄だ」、「(関係者は証言していないのに)××は不祥事を認めているぞ」等の嘘をついて証言させる場合など)
- 発言を遮る(被せる)ヒアリング(例:(調査対象者が証言途中であるにもかかわらず)「そんなことは聞いていない」、「あなたは間違っている」等して、言いたいことを言わせずに証言させる場合など)
(5)録音の可否
まず、調査対象者に対して録音禁止である旨伝えること自体は問題ありません。ただ、録音禁止である旨伝えていたにもかかわらず、調査対象者が無断録音していた場合、その録音内容が後日証拠して用いることができないという訳ではありません(ちなみに、民事裁判手続きであっても、無断録音した内容が証拠として提出され、その内容を元に審理が進んでいくのがむしろ通常です)。したがって、録音禁止を伝えつつも、無断録音されている可能性があると調査担当者は常に認識し、ヒアリングを実施するという心構えが必要となります。
一方、ヒアリング調査を行う場合、調査担当者側が録音を行うことは必須と考えるべきです。言った言わない論争防止はもちろんのこと、無理やり言わされた等の反論を防止することができるからです。なお、基本的にはヒアリング調査開始前に録音している旨告知すれば足りるかと思いますが、事情により告知することが憚れることもあるかもしれません。この場合、秘密録音(隠し録音)を検討することになりますが、様々な見解があるものの、執筆者個人としては、上記のようなメリットがある以上、原則行ったほうが良いと考えています。但し、録音しているか否か調査対象者より質問を受けた場合、録音していないと虚偽の回答を行うことは問題なので、録音していることを回答するべきです。
4.調査結果の出し方
社内不祥事の疑いがかかった者が自白した場合、スムーズに結論付けることができるかと思います。
問題は、社内不祥事の疑いがかかった者が認めなかった場合です。この場合、客観的証拠から裏付け可能な事実を抽出した上で、事実と事実の間を結び付けるためには本来あるべき事実を推測し、推測した事実に適合すような証言があるのか、いったん結論付けたストーリーに不自然さはないか、不自然性が残れば再度一からやり直す…という作業を繰り返しつつ最終結論を出すことになります。ただ、この検証作業(民事裁判で言うところの事実認定)は高度な専門知識と経験が必要であり、残念ながら素人が簡単にできるものではありません。判断に迷う場合は弁護士からアドバイスをもらいながら検証する、又は弁護士に資料等を見せて判断してもらう(いわゆる意見書の作成)といったことも検討したほうが良いと思われます。
なお、社内調査チームの性質上、中立公平な判断を行う必要があります。したがって、あえて指摘しますが、どんなに疑義があったとしても裏付け証拠が不十分である場合、勇気をもって「真偽不明」と結論付けなければならない場面もあり得ます(特に目撃者のいないセクハラ案件等の場合は、どう結論付けるか困難を極める作業になりがちです)。
社内調査チームによる我田引水の強引な結論付けは、会社を誤った方向に導いてしまうことを肝に銘じるべきです。
<2022年1月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
|
|






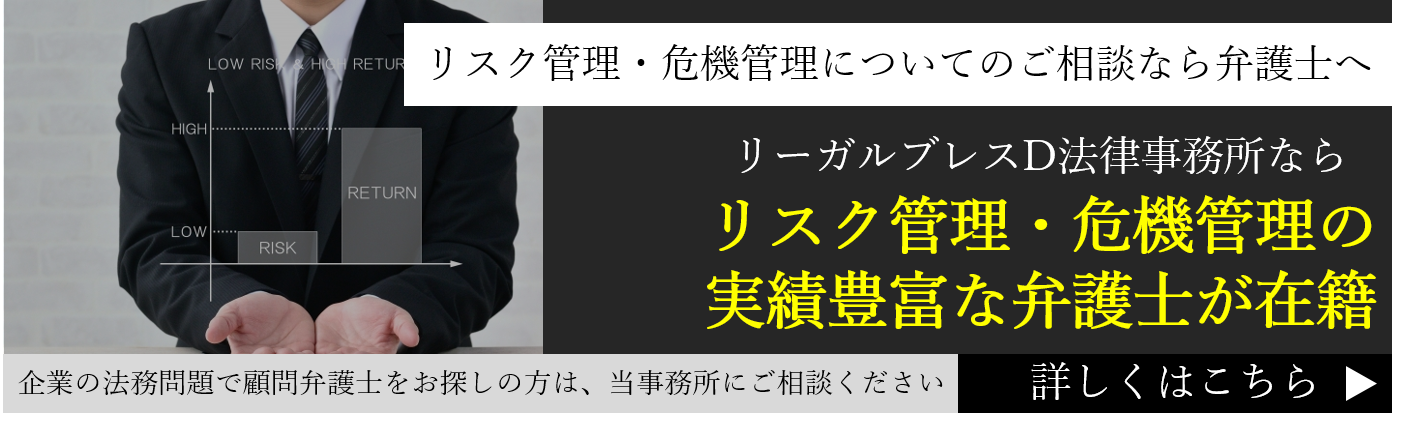

 弁護士 湯原伸一
弁護士 湯原伸一

































