Contents
【ご相談内容】
契約書のような条項が多数連なる重厚なものではなく、2~3程度の約束事をまとめた簡易な合意書を作成しようと考えています。このような合意書を作成するに際し、どういった点に注意を払えばよいのでしょうか。
【回答】
まず、確認していただきたいのが、契約書と合意書・覚書・示談書等の合意文書とは、法律上の優劣関係はありません。したがって、簡易な合意文書とはいえ、作成手順や方法は契約書に準じて考える必要があります。
以下では、形式面と内容面とに分けてポイントを解説しています。
具体的には、形式面として、どういったタイトルを付ければよいのか、前文・後文はどう書けばよいのか、番号の振り方にルールがあるのか等の意外と知られてない事項について解説を行っています。また、内容面として、どのような合意内容を定めるべきなのかその絞り込み方、条項の作成の仕方、清算条項の要否等について解説を行っています。
【解説】
1.形式面について
(1)表題・タイトル
契約書というタイトルが付いている場合、数ページ以上の重厚感のある書面で、難しい用語が羅列されているものというイメージがある一方、覚書・合意書・示談書等というタイトルが付された書面の場合、1枚程度の簡易な書面がイメージされることが多いようです。
ただ法律上は、契約書や覚書等のタイトルによって何か相違が生じるという訳ではありません。また、表題・タイトルがないから法的に無効となるわけでもありません。「表題・タイトル」で悩むのであれば、単純に合意書と名付けておけば足ります。
なお、この点については、以前記事を作成しているので、次の記事もご参照ください。
【動画解説】会社担当者が知っておきたい契約書と覚書との違いとは?弁護士が徹底解説!
(2)前文
前文とは、表題・タイトルと各契約条項の間に挿入されている文章のことです。この前文をどのように作成すればよいのか悩むという担当者は結構いらっしゃるようです。しかし、そもそも前文を必ず明記しなければならないという法的決まり事はありません。極論すれば、前文それ自体を明記する必要はありません。
ただ、当事者と「甲、乙…」と略したりする必要上、明記の必要性があるというのであれば、端的に「××(以下「甲」という)と○○(以下「乙」という)とは、以下の通り合意した。」という一文を明記するだけで十分です。
(3)条・項(数字の振り方)
複数の合意内容を書面に明記する場合、第1条、第1項、第1.…といった数字を割り振って、内容を区分することがあります。実はこの数字の割り振り方についても法律上は特段の決まり事はありません。単純に「1、2、3…」と算用数字で割り振るだけで問題ありません。
ちなみに、割り振った数字の横などに見出し(条項タイトル)をどのように付ければよいのか分からないと悩まれる担当者もいらっしゃるようですが、見出し(条項タイトル)についても法律上定める義務はありません。もちろん、見出し(条項タイトル)を付けたほうが情報整理しやすい、各条項に何が書いてあるのか分かりやすい等のメリットはありますが、あえて無理して付ける必要はありません。なお、見出し(条項タイトル)と各条項の内容に齟齬がある場合はどうなるのかという質問もよく頂戴しますが、基本的には各条項の内容に記載されていることが法的に効力を有することになります。すなわち、見出し(条項タイトル)はあくまでも参考程度に過ぎないと考えるのが原則的解釈となります。
(4)後文
後文とは最終条項の後に付記される一文であり、一般的には最終条項と署名押印欄の間に明記されることが多いようです。例えば、「以上の通り合意したので、本合意書2通を作成し、甲乙署名押印の上、各1通を保管する。」といったものが代表的な言い回しとなります。
この後文についても、法律上明記する必要性はありません。ただ、署名押印欄の近くに上記のような一文を挿入することで、署名押印者に対して合意書等の内容の確認を促すといった事実上の効果はあるようですので、明記したほうが無難かもしれません。
(5)作成年月日
厳密には作成年月日を明記する義務まではないものの、できる限り作成年月日は明記したほうが無難です。なぜならば、合意書成立日の明記は次のような意義・効用を有するからです。
①合意成立日が法的意味を持つ場合がある
(例えば、本合意成立日より1年間効力を有する…といった規定がある場合、合意成立日が明記されないことで契約期間を確定することができないという問題が生じる等)②合意成立日の記載が前後で矛盾する合意内容を解決する場合がある
(例えば、1つの事象に対して複数の合意書が存在し内容が矛盾する場合、原則的には最新の日付の合意書が法的効力有りとされ、過去の合意書は効力を有しないと解釈されることになります)③合意成立日が法的有効性に影響を与える場合がある
(例えば、根保証に関する合意について、2020年3月以前の合意しているのであれば極度額の明記は原則不要、2020年4月以降に合意しているのであれば極度額の明記の無い根保証は無効といった真逆の結論になります)
ところで、実際に合意した日と合意書等の作成日が異なることが現場実務上ありうる話です。この場合、ついつい実際の合意した日にバックデイトする(=日付を遡らせる)といった対応を行うこともあるかもしれません。一般的にはこういった対応を行っても問題は生じないことの方が多いのですが、正確には「本合意は、合意書作成日に関わらず×年×月×により効力を有する。」といった条項を設置した上で対処するのが望ましいと考えられます。
(6)当事者の表示・署名押印欄
合意書等の内容に当事者が同意したことを証明する手段として、署名押印が重要であることはご存知の通りです。
ところで、署名と記名の違いについて質問を受けることがあるのですが、署名は当事者自らがサインすること、記名はいわゆる印刷文字とイメージすれば分かりやすいかと思います。なお、署名と記名について厳密に使い分けられていないため若干混乱が見られるのですが、署名と記名とでは次のような取り扱い上の差異が生じます。
①署名のみであっても、当事者が同意したことを証明する手段となりうる(押印は絶対に必要という訳ではない)
②記名のみの場合、当事者が同意したことを証明する手段にはなりえない
③記名と押印があって、初めて当事者が同意したことを証明する手段となりうる
なお、記名押印の際、法人が当事者である場合、角印と丸印のどちらが良いのかという質問を受ける場合があります。角印でも一応は問題ないのですが、できれば丸印=代表者印をもらうほうが、証拠力の高さという点では望ましいと考えられます。
(7)印紙
合意書、覚書、示談書などの文書タイトルによって印紙の有無及び金額が決まるわけではありません。あくまでも、合意書等に記載された合意内容から導かれる法律関係に基づき、印紙の有無及び金額は判断されることになります。
なお、基本となる契約書が存在し、その契約内容を一部変更するために覚書を作成したという事例において、基本となる契約書に印紙を貼付したから、覚書には印紙不要という結論にはなりません。印紙税はあくまでも各文書ごとで判断する必要があること、注意が必要です。
弁護士へのご相談・お問い合わせ
当サイトの記事をお読みいただいても問題が解決しない場合は
弁護士にご相談いただいた方がよい可能性がございます。
下の電話番号もしくはメールにてリーガルブレスD法律事務所までお問い合わせください。
06-4708-7988メールでのご相談
2.内容面について
覚書、合意書、示談書等の表題・タイトルによって、合意(条項)内容に何らかの縛りが生じるわけではありません。したがって、表題・タイトルに関わらず、内容面については合意した事項を漏れなく記載することに尽きるわけですが、合意(条項)内容を作成するに際して、執筆者自身が意識している事項を以下ポイントとして記載します。
(1)合意した内容を洗い出す
合意書等を作成する目的は、合意内容を媒体物に表現し、その内容を当事者が確認し了承したことを裏付ける証拠を確保する点にあると考えられます。
したがって、どういった事項について合意したのかを抽出する作業がまずもって必要となります。時々、合意した内容を明らかにすることなく合意書等の作成依頼を受けることがあるのですが(おそらく依頼者は形式的な雛形があると思い込んでいるようです)、どういった事象を前提に具体的に何を合意したのか、先に明らかにしてもらわないことには作成のしようがありません。
以下具体例を用いて検討します。
【事例1 不法行為の示談書】
何らかの違法行為に対する示談解決を行ったことを確認する合意書の場合、違法行為の特定、違法行為内容の当事者双方の確認、加害者による謝罪(場合によって被害者からの宥恕の表明)、違法行為への許しを得るための金銭支払い(金額、支払い名目、支払い時期、支払方法)、合意書記載事項ですべて解決済みであることの確認、といった合意内容が想定されます。
【事例2 労働契約の合意解約】
退職勧奨に伴う正社員との労働契約の終了を確認する合意書の場合、労働契約の終了原因(離職票上の記載内容も含む)、労働契約の終了時期、労働契約の中途解約に伴う金銭支払い(金額、支払い名目、支払い時期、支払方法)、秘密保持(口外禁止)、合意書記載事項ですべて解決済みであることの確認、といった合意内容が想定されます。
【事例3 賃貸借契約の条件変更】
賃借人による賃料支払いを一部猶予することを確認する合意書の場合、賃料の支払いを猶予する期間、支払猶予となる賃料の金額、猶予した賃料の清算方法(猶予期間が明けた後の賃料に上乗せして支払う等)、賃料以外の契約条件には変更がないことの確認、といった合意内容が想定されます。
(2)「誰が」「誰に対して」「いつまでに」「何を行うのか」を当てはめてみる
合意した内容をやや法律的な文章に置き換える際のポイントは、誰が誰に対してどういった権利を有するのか、逆に誰が誰に対してどういった義務を負担するのかを、いわば5W1H等を意識しながら組み立てることがあげられます。金銭の動きを着目すれば分かりやすいことが多いので、上記(1)で記載した具体例をもとに検討します。
【事例1】
・加害者が被害者に対し、×年×月×日までに、損害賠償金として×円を、被害者が指定する金融機関口座に振込んで支払う。
【事例2】
・労働者は使用者に対し、×年×月×日までに退職届を提出する。
・使用者は労働者に対し、×年×月×日までに、退職金として×円を、労働者が指定する金融機関口座に振込んで支払う。
・労働者は、×年×月×日以降も、業務を従事するに際して知り又は知りえた使用者の秘密情報を第三者に開示・漏洩してはならない。
【事例3】
・賃貸人は賃借人に対し、×年×月から×年×月かでの間に係る賃料×円について、その支払いを猶予する。
・賃借人は賃貸人に対し、×年×月から×年×月以降までの間、賃料として×円(但し、約定の月額賃料及び支払猶予に係る賃料の一部である×円の合計額)を支払う。
(3)権利義務以外の内容で、双方が確認するだけに留まる事項を抽出する
上記(2)では誰が誰に対してどういった権利を有するのか、誰が誰に対してどういった義務を負担するのかを検討しましたが、権利義務以外の事項を合意書の内容に盛り込む場合があります。当然のことながら、何でもかんでも盛り込んでも意味がありませんので、何を盛り込み、何を盛り込まないのか精査する必要がありますが、上記(1)で洗い出した内容を踏まえると、例えば次のようなものが考えられます。
【事例1】
・×年×月×日×時×分頃、××において、加害者は被害者を殴打したことを認める。
・被害者は加害者より謝罪を受けたことを確認する。
【事例2】
・使用者と労働者は、自己都合退職として退職手続きを進めることを確認する。
【事例3】
・賃貸人及び賃借人は、賃料の支払い方法以外の契約条件について、何ら変更がないことを確認する。
(4)清算条項の必要性を検討する
清算条項とは、例えば「甲及び乙は、本合意書記載事項以外に何ら債権債務がないことを相互に確認する。」といった一文で表現されるものであり、要は“ここに書いてあること以外は、以後お互いとやかく言うことはできない”という紛争の蒸し返しを防止することを目的とした条項となります。
この清算条項については、2点注意するべき事項があります。
まず、1つ目は、そもそも清算条項を設ける必要性があるのか検討する必要があるという点です。時々、何でもかんでも清算条項を明記しようとする方がいるのですが、例えば、上記であげている【事例1】や【事例2】では、清算条項を設ける必要性はあると考えられます。しかし、【事例3】については、清算条項を設けることは有害であると考えられます。なぜならば、【事例3】の場合、賃貸人と賃借人との賃貸借契約関係は合意書を締結して以降も継続するからです。つまり、清算条項を入れてしまうと、賃貸借契約それ自体まで清算=契約終了されたような誤解を生むことになり、これでは当事者の意思に適った内容とはなりません。あえて例えていうのであれば、「当事者間で今後の関係を構築する必要性がない」という場合には清算条項を入れて双方の関係性をきれいすっきり消滅させる、「引き続き当事者間での関係を継続する必要がある」という場合には、清算条項を入れないと整理すれば分かりやすいかもしれません。
次に、2つ目は、清算条項に「本件に関し」という限定文言を入れるのかという点です。
例えば、「甲及び乙は、『本件に関し』本合意書記載事項以外に何ら債権債務がないことを相互に確認する。」と定めた場合、あくまでも清算するのは「本件」に限定されることになります。このため、【事例1】については、本件の内容を絞り込みすぎると、時間的に近接したときに生じた暴行(殴打)以外の違法行為(例えば現金を奪い取った等)については示談解決していないことになります。また、【事例2】では、本件を労働契約終了に関する問題と定義した場合、例えば未払い残業代の問題や勤務中のパワハラ被害等の問題などを労働者より後で主張された際には別途解決を図る必要が生じます。一方、【事例3】については、本件を支払困難となった期間中の賃料支払いという定義づけを行った場合、本件に絞った清算条項をいれることで、上記1つ目で指摘したような賃貸借契約それ自体の清算という懸念は生じなくなります(ただ、今後も関係性が継続する場合にあえて清算条項を入れるべきかは検討が必要です)。
清算条項については、①そもそも入れるべきなのか、②入れるとして「本件に関し」という限定を付すのか、限定を付するのであれば本件の定義を精査する、といったことをよく考えながら合意書等に明記する必要があります。
(5)条項案の作成と並び替えを行う。
上記(2)と(3)である程度の条項案は出来上がっているはずなのですが、より分かりやすい言い回しに変更するといった作業が必要になります。なお、個別に作成した文章を、1つの合意書にまとめ上げる場合、例えば当事者を甲乙と言い換えるのであれば、それに合わせて修正する必要があります(事例1では加害者・被害者という用語例、事例2では使用者・労働者という用語例、事例3では賃貸人・賃借人という用語例)。
次に、条項の並び替えですが、そもそも論として、どの条項から順番に書いていくという決まりごとはありません。ただ、上記(4)で記載した清算条項は、通常は一番最後に設置することが多いかと思われます。執筆者個人としては、時系列に沿って条項の並び順を決めることが多いように思います(例えば、【事例2】でいえば、退職事由の確認と退職届の提出に関する条項、退職に伴う金銭支払いに関する条項、退職後に負担する義務の確認条項、清算条項、といった一連の退職手続きに沿って条項を並べるというイメージです)。
<2021年1月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
|
|






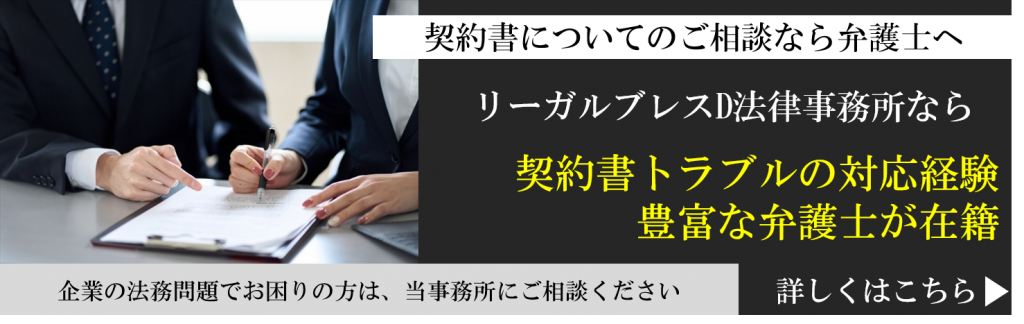

 弁護士 湯原伸一
弁護士 湯原伸一



































