Contents
【ご相談内容】
卸売事業者向け販売事業部門、消費者向けネット直販事業部門、海外販売事業部門の三事業部門を有する某企業より、消費者向けネット直販事業部門を当社で買い取らないかと打診されています。当社としては前向きに検討する方針なのですが、会社・法人それ自体ではなく、一事業部門のみを買い取ることは法律上可能なのでしょうか。
【回答】
会社・法人それ自体を買い取るのであれば、株式譲渡を行う、又は吸収合併を行うといった手法が考えられます。しかし、本件では会社・法人の一部を構成する一事業部門にすぎないことから、これらの手法を用いることはできません。
そこで、従来から、一事業部門を財産に見立てて売買取引により当該事業部門を買い取る事業譲渡(営業譲渡)という手法が用いられてきました。また、2001年(平成13年)からは会社分割という手続きにより、一事業部門を組み入れるという手法を講じることが可能となりました。
以下では、事業譲渡(営業譲渡)と会社分割について解説を行います。
【解説】
1.一事業(営業)部門を取得するための手段
2001年(平成13年)3月より前では「事業譲渡」と呼ばれる、いわば事業部門を売却するという方しか取れませんでした。しかし、会社分割という手続きが新たに設けられ、一事業部門を法人から切り離して売却するという方法ができるようになりました。
ちなみに、なぜ2種類の手法が存在するかというと、事業譲渡の場合は第三者との取引関係について当然に承継しないことに対し、会社分割の場合は第三者との取引関係について、第三者の意思に関わらず当然に承継ができるという点で違いがあるからです。これだけを書くと会社分割の方がお得と感じるかもしれません。ただ、お得である以上、法律上の手続きは非常に厳格であり重負担です。この辺りを調整しながら、どちらの手段を用いた方が簡易かつ費用対効果が高いのか、検討することになります。
ところで、事業譲渡の場合、事業を譲り受ける側の法人内部に事業譲渡の対象となる一事業部門を吸収することになります。しかし、当該事業部門にどのようなリスクが潜んでいるのか、調査し尽くしても分からないことが多く、いきなり自社内に吸収することに抵抗を持つこともあります。
一方、会社分割の場合、吸収分割という手続きであれば自社内に事業を吸収することになりますが、新設分割と呼ばれる新たな受け皿法人(この受け皿法人については事業を譲り受ける側が支配できるよう株式持分の調整を行う必要があります)を作り、そちらに当該事業部門を移すということもできます。
したがって、吸収する事業部門に潜むリスクを遮断したいのであれば、会社分割の一類型である新設分割を行ったほうが無難と考えることになります。
弁護士へのご相談・お問い合わせ
当サイトの記事をお読みいただいても問題が解決しない場合は
弁護士にご相談いただいた方がよい可能性がございます。
下の電話番号もしくはメールにてリーガルブレスD法律事務所までお問い合わせください。
06-4708-7988メールでのご相談
2.事業譲渡(営業譲渡)
(1)何が譲渡されるのか
事業譲渡の特徴の1つが、事業それ自体を売買する点にあります。この事業には、事業を行うための機械器具や不動産といった有形財産はもちろん、事業を継続するためのノウハウ等の無形財産など、事業を構成するあらゆるものが含まれるのですが、そのうち何を譲渡対象とするのかは当事者間の協議により定めることになります。
もっとも、譲渡人のみで譲渡対象としうるのは、あくまでも譲渡人に権利が単独で帰属する財産のみです。つまり、第三者が関係する財産については、譲渡人が自由に譲渡することは不可能となります。
この第三者が関係するものとしては、事業を継続する上で欠かせない仕入先や販売先といった取引先との契約関係はもちろん、賃貸人・リース業者やライセンサーなどとの権利保有者との契約関係、さらには労働者との契約関係があります。これらは譲渡人と譲受人との間で事業譲渡に関する合意を行ったとしても、当然に移転するわけではありません。
したがって、事業譲渡に当たり、譲受人側において、取引関係や権利関係をどうしても引き継ぎたいというのであれば、個別に取引先や権利者と交渉し、新たな契約を締結する必要があります。そして、実務上は、当該交渉に際し、譲渡人側に協力義務を課して、譲渡人に積極的に交渉に参加してもらう形で対処することが多いといえます。
同様に労働者についても、譲渡人に対して、労働者を説得する義務を課し、できる限りスムーズに譲受人と新たな労働契約を締結(転籍)できるように取り計らうことが対処します。なお、労働者のスムーズな承継を果たすべく、譲受人側に対しては、これまでの労働条件を下回らないよう事業譲渡契約書の中に明記することも多く行われます。
ところで、事業譲渡の検討に際し、「譲渡対象となった事業部門にて勤務している労働者については、事業譲受人に引き継がれるが、当該事業部門にて勤務していない労働者については、引き継がれない(譲渡人の元に残る)」と考えている方もいるようです。しかし、事業譲渡と労働者との関係性では誤った考え方となります。上記のような考え方は、次の3.で解説する会社分割における労働者の取扱いとなりますので、ご留意ください。
(2)債務は承継されるのか
上記(1)で記載した通り、第三者が関係する契約関係については、事業譲渡によって当然に譲受人に移転するわけではありません。したがって、譲渡人と第三者との間で発生している債権債務についても、やはり当然に移転しないこととなります。
もっとも、譲渡人が当該事業で用いていた“看板(屋号を含めた商号)”を譲受人がそのまま用いた場合、対外的には営業主が変わったようには見えません。このため、譲受人において看板を続用した場合は、債権者に対して債務を負担する可能性があること注意が必要です。
(3)どのような社内手続きが必要か
・譲渡人における社内手続き
事業を譲渡する側からすれば一事業部門を失うわけですから、会社のオーナーである株主から経営委託を受けているだけに過ぎない取締役だけの判断ではなく、きちんと会社のオーナーである株主の意向を確認する必要があります。そして、非常に重要な問題であるため、少数株主の意向も十分に尊重しなければなりません。
したがって、譲渡人側の法人においては、原則として株主総会での特別決議(いわゆる2/3決議)が必要となります。なお、例外的に、譲渡対象となっている事業部門の総資産額が20%以下の場合や、譲受人側の法人が譲渡人側の法人株式を90%以上支配しているのであれば、株主総会決議は不要とされています。
以上が一応の解説になるのですが、実務上問題となるのは、実は社内手続きの以前の問題、すなわち、そもそも株主総会決議の対象となる「事業譲渡」といえるのか、という点です。これはどういうことかというと、会社法は「事業の全部譲渡」と「事業の重要な一部譲渡」の場合は株主総会決議が必要と定めています。裏を返すと「重要ではない」一事業部門の譲渡にすぎないであれば、株主総会決議は不要となります。ただ、何をもって「重要」に該当するのか実は法律上の基準は定められていません。したがって、この点については、弁護士のみならず税理士・会計士等の専門家を交えて協議を行った方が無難です。
・譲受人における社内手続き
事業を譲り受ける側からすれば、プラスの価値があると思われる事業を受け入れるだけですので、あえてオーナーである株主の意向を聞かずに、取締役(会)の判断で手続きを進めることが可能です。
ただし、事業譲渡という形を取りながらも、譲渡人の事業部門の全部を譲りうけるという場合、実質的には吸収合併と同じであり、やはり色々と問題があり得ます。そこで、この場合は株主総会の特別決議が必要とされています。もっとも、純資産割合20%以下の場合や議決権90%以上といった条件がある場合は、株主総会決議が不要となります。
3.会社分割
(1)何が承継されるのか
事業譲渡と会社分割とは、共に一事業部門を譲り受けるという点で共通するのですが、両制度の大きな相違点として、労働者を除く第三者との契約関係が当然に承継されるか否かの違いにあります。すなわち、会社分割の場合、当該第三者の意向に関わらず、当該第三者との契約関係を承継することが可能となります。
ただ、ご留意いただきたいのが、会社分割の場合、“当該第三者の意向”に関わりなく承継されるのですが、“全て”の契約関係が承継されるわけではありません。
非常に細かい話になってしまうのですが、実は、会社分割の対象となる事業部門と取引のある当該第三者のうち、契約関係を承継させるか否かは、会社分割の当事者が決めることができる、つまり会社分割契約書(新設分割の場合は新設分割計画書)に記載された当該第三者のみ承継がされる、というのが法制度になっているのです。したがって、会社分割契約書等において、承継対象とされてしまった当該第三者については、その意向に関わりなく、事業を吸収する側の法人と契約関係が承継されるというのが正確な内容となります。
さて、会社分割契約書等において承継対象となる当該第三者については、その承継に対して異論を挟むことができず、会社分割それ自体はもちろん、承継を無効とする法的手段を持ち合わせていません。もっとも、当該第三者が債権者に該当する場合、債権者保護手続きにより、少なくとも債権回収に悪影響が生じないようにするという保護制度があります。これについては、後述(4)で解説します。
(2)労働者の承継について
会社分割契約書等において承継対象となる旨記載された第三者である労働者との契約関係は、事業を吸収した側の法人に承継されることになります。そして、この理は労働者にも当てはまるはずなのですが、労働者にとっては、ある日突然、勤務先が変わったことを意味します。法律の基本的発想は、労働者は弱者であり、単なるBtoB取引と比較して保護の要請は強いというところがありますので、この原則的理屈を特別法によりやや修正しています。
場面としては3つのパターンを想定することになります。
①会社分割契約書等で承継(転籍)対象であり、かつ労働者の主たる業務が分割対象となる事業の場合、当然に承継される(労働者は異論を挟めない)。
②会社分割契約書等で承継(転籍)対象であり、かつ労働者の主たる業務は分割対象ではない事業の場合、原則承継されるが、労働者が異議を述べれば承継されない。
③会社分割契約書等で承継対象外であり、かつ労働者の主たる業務が分割対象となる事業の場合、原則承継されないが、労働者が異議を述べれば承継される。
ちなみに、あまりにも当然すぎるのですが、会社分割契約書等で承継対象外となっており、かつ労働者の主たる業務が分割対象となっていない事業であれば、事業を分割する法人にそのまま残ることとなります。
なお、労働者に関しては、その他特別法に基づく労働者保護手続きが別途定められていますので、そちらについても注意が必要です。
(3)どのような社内手続きが必要か
・事業を分割する(譲渡する)側の社内手続き
会社分割を行った場合、事業を分割する側の法人における社内手続きとしては、原則として、株主総会での特別決議が必要となります。必要となる理由は、上記2.(3)で記載した事業譲渡と同じものとなります。なお、会社分割により事業を分割する側の法人における総資産額の20%以下の場合や、会社分割により事業を吸収する側の法人が議決権の90%以上を保有している場合は株主総会決議が不要となることも、やはり同じです。
・事業を承継する(譲り受ける)側の社内手続き
会社分割を行う場合、事業を吸収する側の法人における社内手続きですが、事業譲渡の場合と異なり、原則として、株主総会での特別決議が必要となります。これは、事業譲渡の場合は原則的に債務を含めた第三者との契約関係が当然に承継されないのに対し、会社分割の場合、会社分割契約書等に定めている範囲内とはいえ、第三者の意向に関係なく当然に第三者との契約関係を承継することとなり、その影響が大きいからです。
(4)債権者保護手続きとは
会社分割における特徴的な手続きとして、債権者保護手続きというものがあります。
この手続きが設けられたのは次のような点が考慮されたためです。すなわち、債権者(この債権者には承継対象となった契約関係の第三者も含まれる場合があります。例えば、第三者が会社分割を行おうとしている法人との取引により何らかの請求権を有しているのであれば債権者に該当しうるからです)にとっては、会社分割によって、回収対象となる責任財産に変動を来す恐れがあり、非常に由々しき事態となる可能性があります。そこで、会社分割による責任財産の変動によって不利益を被りたくないと考える債権者は、異議を述べることで、もともとの債務者(会社分割の当事者)より弁済を受けるか又は担保の提供を受けることができるようになります(なお、一部例外が有りますが省略します)。
上記のように債権者については、会社分割の効力を否定する権限までは付与されていないものの、会社分割によって債権回収に悪影響が及ばないよう一定の法的保護制度が設けられています。
ところで、債権者保護手続きによって異議を述べることができる債権者の範囲については制限が有ります。この範囲ですが、事業を分割する側の法人と取引している債権者のうち、会社分割によって事業を吸収する側の法人への請求に限定される債権者、及び事業を吸収する側の全債権者となります。裏を返せば、事業を分割する側の法人と取引を行っていた債権者のうち、引き続き事業を分割する側の法人に対して請求ができるのであれば、債権者保護手続きにおける債権者より除外されます。これは理屈の上では、事業を分割する法人は、分割対象となった事業に見合う財産を手に入れているので、責任財産に変動が無いから保護する必要が無いからです。
やや分かりづらいですが、債権者保護手続きから除外される債権者が誰かを認識しておけば、間違いは防げるのではないかと考えられます。
<2020年12月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
|
|





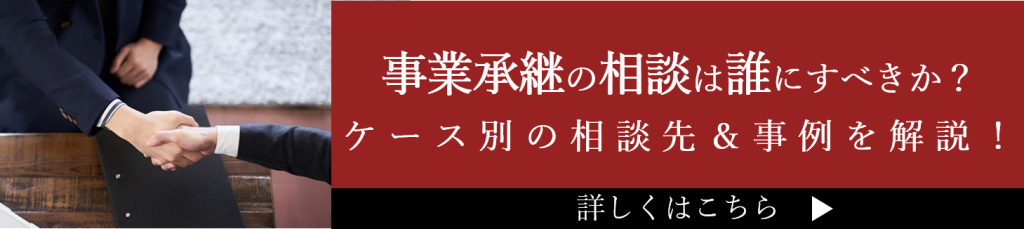


 弁護士 湯原伸一
弁護士 湯原伸一




































