Contents
【ご相談内容】
起業を検討しているのですが、トラブルに巻き込まれたという話を耳にします。どういったトラブルがあるのか、またどのように対処すればよいのか、教えてください。
【回答】
起業・創業・スタートアップなど色々な言い方がありますが、経営者として独立した場合、最初の時期はとにかくお金を稼ぐ必要があることから、対外的な営業活動や商品・サービスを提供に力を入れることになります。一方、営業活動に直接関係しない問題、特に社内で生じる内部問題についてはついつい後回しになる、見て見ないふりといった対応になりがちです。
この結果、早期に意識的に対処していれば大きな紛争にはならなかったと思われる事例が多数あります。以下では、その中でも典型的な事例と対処法について解説を行います。
【解説】
1.元勤務先からの営業差止警告
(例)
起業前に勤務していた会社で培ったノウハウを元に、退職後、同業種にて開業し営業を行っていた。開業してしばらくしてから、元勤務先より、営業差止めと損害賠償を求める警告書が送付されてきた。
元勤務先との関係が切れている以上、原則として元勤務先から何か言われる筋合いはないはずです。しかし、入社時又は退職時に誓約書などにサインをした記憶はないでしょうか。そして、この書面の中に、「会社の機密情報は開示・漏洩しません」とか、「退職後2年間は競業会社に就職しません。競業会社の立ち上げを行いません」等々書いていなかったでしょうか。
もし、この様な内容が書いてあり、サインしてしまった…というのであれば、本件のようなトラブルに巻き込まれるリスクが高くなります。したがって、その様な書面にサインしないことが一番の対抗策なのですが、色々な都合上、サインせざるを得ない場合も想定されます。
さて、この様な警告書を受けた場合、対処法としては次の2点となります。
①相手方が主張している「秘密情報」は本当に秘密情報といえるのか検証する。
②相手方が主張している「競業避止義務」は有効といえるのか検証する。
まず、①についてですが、例えば、会社で知り得た一切の情報は秘密情報であると規定されていた場合、裁判所は情報一切合切が秘密であるという考え方はしません。たしかに、マル秘技術やお客様リストなど通常外部に漏れることのない情報であれば、秘密情報に該当する場合もあり得ます。しかし、たとえば勤務先のWEB等で取引先企業一覧という形で掲載されている場合、取引先企業は誰でも閲覧可能な状態となっている以上は秘密とはいえないと考えられます。
ちなみに、不正競争防止法では「営業秘密」という概念が定められています。この営業秘密を無断で持ち出す、あるいは無断使用等した場合、民事はもちろん刑事制裁も受けることになります。ただ、「営業秘密」の該当性は、単に秘密保持の誓約書等にサインしただけで決まるものではありません。とはいえ、勤務先の警告書の中に「不正競争防止法」や「営業秘密」というキーワードがあった場合、刑事上の問題も生じるリスクがあることから、早期に弁護士に相談したほうがよいと考えます。
一方、②については、職業選択の自由という憲法上の要請から、サインさえしていれば常に競業避止(禁止)が有効という判断を裁判所は行っていません。期間の限定があるか、職種の限定があるか、地域の限定があるか、代償措置が取られているか等々の諸事情を考慮し、相当限定された場面でしか競業避止(禁止)義務の有効性を認めないという判断が定着しています。例えば、永久に同業で就労することは不可となると、競業禁止に関する取り決め自体が無効と判断される可能性が高いと考えられます。
さて、上記は勤務先を退職した後で起業した場合を想定して記載しました。
ただ、最近では副業・兼業解禁という時代の流れもあり、勤務をしながら独立開業するということも増えてきています。この場合でも、やはり秘密情報の無断使用や競業禁止の問題が同様に発生します。基本的には同じ考え方・対処を行うことになりますが、在職中の場合は、労働者として勤務先に対して様々な義務を負担している点で上記2点以外の問題が生じることがあることに注意が必要です(例えば、兼業・副業の事前許可を得ていない場合の懲戒問題など)。
弁護士へのご相談・お問い合わせ
当サイトの記事をお読みいただいても問題が解決しない場合は
弁護士にご相談いただいた方がよい可能性がございます。
下の電話番号もしくはメールにてリーガルブレスD法律事務所までお問い合わせください。
06-4708-7988メールでのご相談
2.共同して起業したが、後に退社した者からの残業代請求
(例)
起業時より一緒にやってきた、社長にとって「右腕」の人物が退社することになった。退社後、未払い賃金等の支払いを求める通知書が送付されてきた。
起業時から苦楽を共にしてきた以上、社長としては、それ相応の待遇・自由な活動をさせていたので、トラブルになることはないと信頼していたにもかかわらず、退職した途端、牙をむいてきた…という事例は残念ながらよく見かける事例です。
上記例はいわゆる未払い残業代の問題です。経営者からはよく愚痴のように(?)言われてしまうのですが、たしかに日本の労働法は労働者有利の法律です。このため、社長・会社の常識が裁判では一切通用しないということが頻繁に生じます。
(1)右腕が役員であった場合
例えば、社長の右腕と呼ばれていた方が役員として就任していたというパターンがあります。最近でこそ役員は1名でOKとなっていますので少なくなってきていますが、昔は株式会社を設立するに際しては3名以上の取締役が必要とされていました。このため、数を満たすためにも名義を借りていたということは結構多かったりします。ところで、役員=取締役は役員報酬であり、従業員のような賃金・給料ではない以上、未払い残業代の問題など生じないのでは?と思う方もいると思います。しかし、上場している大企業であればともかく、中小企業の場合、従業員しての地位と役員としての地位が併存している従業員兼務取締役であるとして、未払い残業代が発生してしまうことがあります。
役員であった者からの未払い残業代請求に対して検討するべき事項としては、次のような点がポイントとなります。
①当該人物に対して、税務上役員報酬扱いにしていた、労働保険は加入していない等、取締役として扱いと矛盾しない手続きを行っていたこと
②勤務時間や勤務場所の拘束性がないこと(裁量に委ねられていたこと)
③経営判断に参画、関与していたこと
上記2点を充足していた場合、従業員兼務取締役ではなく、純粋な取締役と認められる可能性が高くなります。取締役として認められた場合は、未払い残業代が発生する余地はありませんので、対処がしやすくなります。
(2)右腕が重役であった場合
次に、昔でいう番頭さん、今でいう部長等の重役クラスとして扱っていた以上、管理監督者に該当するので、未払い残業代は発生しないという反論が考えられます。なお、管理監督者の議論で間違えてはいけないのが、深夜残業(10時から5時)については割増賃金の対象ですので、これは支払わざるを得ません。
さて、管理監督者の議論については、一昔前のマクドナルドの店長に関する判決で非常にホットな話題になりましたが、管理監督者該当性のハードルは高いと言わざるを得ません。それでもなお、管理監督者に該当する旨の反論を行いたい場合のポイントは次の通りとなります。
①管理職手当などそれなりの特別手当が支給されていること
②出退勤について拘束されていないこと
③職務内容が統括的な立場にあること
④部下に対して一定の裁量権を有していること
ただ、繰り返しますが、管理監督者に該当する事例はかなり限定されます。したがって、管理監督者という反論は有効打にならない可能性が高いことに留意するべきです。
(3)残業代込みという主張
さらに、よくある言い分として、「うちは残業代込みの賃金だ」というものがあります。もっとも、法律上は、残業代込みの支給であれば、きちんと要件を満たさないことには残業代込みと認めてくれません。この手の反論を行いたい場合のポイントは次の通りとなります。
①基本給とは別の手当項目を設けること(基本給の中に残業代部分が含まれているパターンは原則要件を満たさないと考えたほうがよい)
②当該手当が何時間分の時間外労働に対する賃金に当たるのか明示すること
③就業規則、賃金規程、給料明細に明示すること
ちなみに、年俸制について、最近では少なくなってきましたが、以前は残業代を支払わなくても良いと誤解されていたようです(年俸制であっても当然残業代支払い義務はあります)。これについても、上記固定・定額残業代と同じく、適切に区分されていたかがポイントとなります。
3.元従業員からの不当解雇、パワハラに基づく損害賠償請求
(例)
能力不適格と思われる従業員に対して、「このままでは会社にはいられない」と伝えたところ、次の日から出社しなくなった。その後、解雇無効とパワハラに基づく損害賠償請求を求める通知書が送付されてきた。
時代の流れと言ってしまえばそれまでかもしれませんが、最近は「熱い指導」が敬遠される傾向が強く出ています。ただ、起業時はまさに生きるか死ぬかの瀬戸際で経営を行っている場合が多く、経営者もかなり熱くなっています。このため、ついついきつめの口調での指導が行われることも多いようです。
(1)解雇するつもりはなかった場合
さて、本件の事例でも、そもそも上司の発言の意図が「会社を辞めてくれ」、つまりクビだ!というつもりだったのか、叱咤激励のつもりだったのか、はっきりしないところがあります。したがって、会社側としては、辞めさせるつもりではなかったというのであれば、
①解雇の意思表示を行った訳ではない
この点を明確に主張することがポイントとなります。
なお、解雇していないとなると、当然のことながら、従業員は復職できることになります。
しかし、小さな会社であれば、「公然と会社に反旗を翻すような態度をとってきた従業員と顔を合わせるのも嫌だ!」という心情的な問題もありますし、他の従業員の士気低下にもつながりかねないという悩ましい問題があります。したがって、本当に復職させるべきか否かの本音も考慮しつつ、解雇の意思表示を行ったとするのか方針を決める必要があるということも頭の片隅に置いたほうが良いかもしれません。
(2)指導方法とパワハラ
では、解雇の意思表示ではないという場合、言い方や指導教育方法に問題がなかったかという点が問題となります。
これについては、世代格差・ジェネレーションギャップが存在しますし、いわゆる体育会系で育ってきたヒトとそうではないヒトとでは受け止め方が違いますので、一律に決めることは大変難しいのが実情です。そして、最近では、叱咤激励のつもりだったのが逆にパワハラであると反撃されてしまい、上司が萎縮してしまって会社内の秩序が保てなくなってしまうと言う大変悩ましい事態が出てきています。
この様に限界線を設けることが大変難しいのですが、あえてポイントを上げるとすれば
①叱咤激励を行う背景事情を細かく検証すること(必要性)
②手段・方法として常識を越えていないこと(相当性)
を主張し、あくまでも問題となっている従業員の主観的なとらえ方に過ぎないとして対処していくしかないと思われます。
(3)解雇を言い渡した場合
一方で、解雇の意思表示という場合、次に問題となるのが、いわゆる不当解雇に当たらないかという点です。おそらく経営者仲間でも必ず1回は話題になると思うのですが、日本の労働法は会社経営者にとって非常に厳しい、特に解雇についてはハードルが高すぎて、実際にはほとんど勝ち目が無いのが実情です。その解雇問題の中でも、特に本件のような能力不足となると、あるべき能力とは何か、本人の業務遂行状況はどうだったのか等々、客観化しづらい問題があるため、裁判所がなかなか会社の実情を分かってくれない…という大変悩ましい問題が出てきます。
それでもなお、闘って行く必要がありますので、
①同僚や同じ部署の担当者から導き出される、会社が求めている能力とは何かの基準確定
②問題となっている従業員の業務遂行状況、結果
③問題となっている従業員の具体的な問題行動
をとにかく上げていく細かな作業がポイントとなってきます。
ただ、不当解雇で会社側が勝つというのはかなり難しいと言わざるを得ません。解雇を撤回しつつ合意退職で解決を図るというパターンが多いのですが、この場合、多額の金銭支払い(解雇から合意退職までの期間中の賃金相当額、及び転職活動期間等を考慮した一定期間の将来補償分)が条件となることが多いので、その点の覚悟が必要となります。
4.仕入先からのクレーム
(例)
仕入れ先より商品を受領したが、不具合があることを理由に返品又は交換を要望したが拒否された。このため代金を支払わずに放置していたところ、売買代金の支払いを求める通知書が送付されてきた。
起業時は色々やることが多く、面倒な交渉は後回しにすることは残念ながらよく見かけることです。そして、気に入らないから代金を支払わないでおく…理屈はともかく、意外とこういった対応をとる方は少なからず存在するようです。
さて、売買契約書が締結されている場合、不具合の有無について検査期間が設けられていないか確認する必要があります。例えば、商品の受領後3日以内に検査結果を通知し、通知しない場合には合格したものとみなすと規定されていた場合、形式論としてはこの期間を過ぎてしまうと、不具合があったとしても何も言えなくなってしまうということも想定されるからです。
では、契約書がないor契約書はあるが検査期間の問題がクリアーできる場合、次に問題となるのが、「法律上、不具合が存在したと言えるか?」という点です。何を馬鹿なことを…と思われるかもしれませんが、例えば商品の性能に関するクレームの場合、買い主が期待していた性能評価と売り主が把握していた性能評価が異なっているがために紛争が勃発すると言うことは良くあり得ることです。あるいは中古品の商品売買の場合、一般的には「現状有姿」といって、通常使用には問題ないと思われるけど、中古品なので何があるか分からないので、あるがままの状態で受け入れて下さい…という事例を想定した場合、不具合と主張したところで、現状有姿で受け入れることが約束である以上、不具合があることも想定していたでしょ!、と反論されてしまうことだってあり得るわけです。
したがって、この手の問題が生じた場合にはポイントとして
①契約書の有無、契約書が存在するのであれば内容の確認(特に検収期間と契約不適合(旧瑕疵担保責任))
②不具合の内容、外観や見た目などで直ちに発見しうるものだったか
等を検討する必要があります。
なお、何をもって不具合と判断するのかは究極的には法的評価の問題となります。
例えば、プログラム開発の事例が典型なのですが、100%バグのないプログラムは存在しないと法的には考えられています。このため、バグがあるから不具合あり、支払いを拒絶しても問題なし、という結論にはなりません(バグの程度を検証しないことには、契約違反=支払拒絶してもよいという結論を導くことができません)。支払金額が多額となる場合などはややこしい問題となりがちですので、早期に弁護士等の専門家と相談して対処するべきです。
5.知的財産権侵害のクレーム
(例)
パソコン用のソフトウェアを1個購入し、複数のパソコンにインストールして使用していた。ある日、ソフトウェアの管理団体と名乗るところから、ソフトウェアの使用差止と違法仕様に基づく損害賠償の支払いを要求する通知書が送付されてきた。
起業時にはお金がないので端末ごとにソフトウェアを購入することができない、一方で正規に購入したソフトウェアであり会社内で使用しているにすぎない以上、著作権法上の私的複製で問題ないのではと考える方も一定数いるようです。しかし、私的複製は事業目的の場合は適用されません。そして、おそらくはソフトウェアの使用上の注意事項の中に、1端末(台)にしかインストール不可と記載してあるはずで、その使用細則に同意クリックをしないことにはソフトが起動しないようになっているはずです。
したがって、ソフトウェアを正規に購入したとしても、複数台にインストールことは著作権法違反として取り締まられる対象となります。なお、パッケージソフト購入の場合、パッケージソフトを購入している以上、ソフトウェアをどのように使おうと購入者の自由ではという主張をされる方もいるのですが、パッケージソフトという有体物の所有権の問題とパッケージソフトの中に組み込まれているプログラム等(無体物)の著作権の問題は、全く別の話です。所有権を有するか著作権も当然に有するという話にはならないことに注意が必要です。
ところで、この著作権管理団体とは何者でしょうか?代表的な団体としては、音楽関係のJASRAC、ソフトウェアであればACCSやBSAなどが有名です。
理屈で考えていった場合、ソフト上の著作権を有するのは各ソフトウエアメーカーのはずであり、団体ではありません。したがって、メーカーから著作権侵害を主張するのであればともかく、団体から言われるのは解せない、さらに損害賠償金を支払えと言われても本当に支払うべき相手なのか不安である…等々の問題があります。
たしかに、懸念されている事項は当たっている部分があり、しかもこの様な団体は往々にして高圧的な態度で来るため、心情的にも対処したくないというところも理解できなくもありません。しかし、上記で記載したような団体であれば、信託等の正当な法的根拠に基づいて請求してきていますので、法律上の問題はクリアーされているのが通常です。また、実際に指摘されている違法コピーが存在するのであれば、あまり争うことは得策ではないのが実情ですので、冷静に考え、違法状態が存在するのであれば、修正していくのが筋ではないかと考えられます。
もっとも、何らかの事情により訴訟提起されることもあり得ます。違法コピーをしていないというのであれば、
①シリアルナンバー等のライセンス付与の証拠を集めること
②従業員が会社の知らないところで勝手にインストールしていないか、コンピュータごとにインストール履歴を調査すること
で、自らの「シロ」を立証していくことがポイントとなります。
なお、余談ですが、何故管理団体にバレるかと言いますと、内部告発が非常に多いと言われています。実際、各種の団体のホームページを見ると、匿名での告発を募集しています。残念ながら、会社にとって不利益な情報は身内から漏れる時代であると考えた方が良いかと思います。
<2020年9月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
|
|






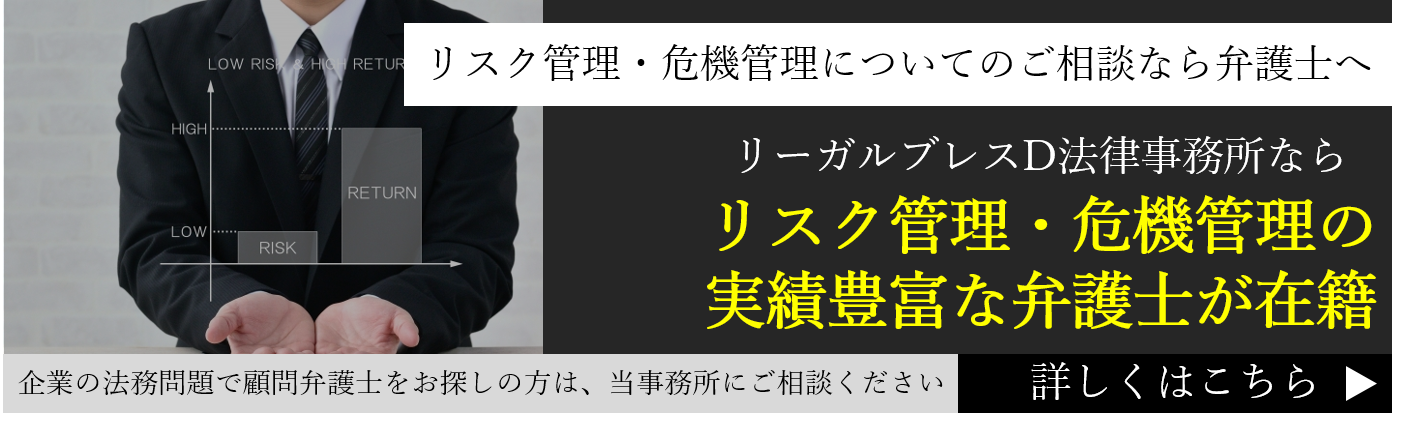

 弁護士 湯原伸一
弁護士 湯原伸一





































