Contents
【ご相談内容】
当社は先代(現専務の父親)が立上げ、現在では専務の配偶者である私が社長、先代の子が専務、配偶者の親族がその他役員に就任している、非上場の家族経営型の会社です。
最近、私(社長)と専務の関係が険悪となっており、離婚に向けた協議が進んでいるのですが、事業経営にどういった影響が及ぶのか気になっています。離婚に際して、社長特有の注意点があれば教えてください。
【回答】
経営者・社長が離婚する場合、特に注意しておきたい事項は次の通りです。
・配偶者の処遇をどうするのか
・個人名義の事業用財産をどう処理するのか
・財産分与、特に株式をどう処理するのか
・婚姻費用、養育費の算定をどうするのか
上記について、押さえておきたいポイントにつき【解説】にて説明します。
【解説】
1.配偶者の社内での処遇について
離婚を検討する場合、経営者・社長とその配偶者の関係は悪化しており、信頼関係もないというのが通常です。したがって、配偶者の方から、会社業務に従事したくないとして退職申出あることが多いのですが、中には引き続き業務従事したいと考える配偶者もいます(当面の生活費を稼ぐ目的など)。この場合、経営者・社長としては気まずいので、配偶者を退職させようと試みることになります。
以下、配偶者が役員(取締役、監査役)の場合、従業員(労働者)の場合、そして会社内での地位に絡んで株主の場合も含めて、以下で検討します。
(1)役員(取締役、監査役)
従業員としての地位を兼務しない役員である場合、株主総会の決議さえあればプライベートな離婚を理由として退任させること自体は可能です。
ただ、解任することは自由なのですが、解任に「正当な理由」がない場合、配偶者より損害賠償請求されるリスクがあります。これは会社法第339条が次のように定めているからです。
1 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
この点、離婚するという事由だけでは「正当な事由」には該当しないと考えられます。例外的に、配偶者が会社業務の一切に従事しておらず、名目的な役員にすぎない場合であれば「正当な事由」に該当する可能性もありますが、ケースバイケースの判断と言わざるを得ません。
正当な事由がない場合の損害賠償ですが、一般的には残任期間に相当する役員報酬相当額が認められることが多いようです。
結局のところ、損害賠償リスクを回避するためには、①任期満了時期が近いのであれば、任期満了をもって退任扱いとする、②配偶者より辞任届を提出してもらえるよう条件交渉を行う、のどちらかを選択せざるを得ないと考えられます。
(2)従業員(労働者)
従業員(労働者)としての地位を有する場合、プライベートな離婚を理由として解雇することは難しいといわざるを得ません。これは、労働契約法第16条が次のように定めているからです。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
プライベートな離婚問題は業務遂行能力との関連性が乏しいため、「客観的に合理的な理由」がないと判断されることが通常です。辞めさせることができないという点では、上記(1)で記載した役員の場合とは真逆の結論となります。
ちなみに、名目上の従業員(?)と呼べばよいのでしょうか、会社業務に一切従事していないことを根拠に、解雇の有効性を主張したいと考える経営者・社長もいるようです。しかし、会社の為に自らが能動的に動かなければならない役員の場合と異なり、従業員の場合は会社からの指揮命令に基づき業務従事するにすぎません。会社(経営者・社長)は、配偶者に対して仕事を与えていない=会社業務に従事させていないことによる不利益を甘受するべき立場にありますので、やはり解雇の有効性を維持するだけの主張にはなりづらいことに注意が必要です。
結局のところ、退職勧奨を行いつつい、条件交渉を行った上での合意退職を図ることが一番穏当な解決策になると考えられます。
(3)株主
配偶者が株式を保有している場合、プライベートな離婚を原因として会社及び経営者・社長が配偶者より、株式を強制的に取得することは原則不可能です。もっとも、配偶者が保有する株式の持分割合が少ない場合、いわゆるスクイーズアウトの手続きをとることで、強制的に取得できる場合があります。詳細については、次の記事もご参照ください。
少数株主を排除(スクイーズアウト)するための方策について、弁護士が解説!
なお、株式については、経営者・社長が保有する株式が財産分与の対象となることを前提にした紛争も起こりやすいこと、注意が必要です(後述3.参照)。
2.配偶者名義の事業用財産の処理について
会社の業務運営に関係して、配偶者が第三者と契約を締結している、配偶者名義の資産があるといった場合に、離婚を機にどう対処するのかという問題となります。
(1)連帯保証
例えば金融機関から融資をしてもらうに際し、経営者・社長ではなく配偶者が連帯保証人となっている場合があります(個人事業の場合であれば配偶者が連帯保証人になっている事例などがあります)。配偶者は離婚を機に会社経営には一切関与しないことから、連帯保証を外してもらって当然と考える方も多いのですが、連帯保証契約を解除するか否かの判断は金融機関であって、当事者間で取り決めることは不可能です。
金融機関からは、配偶者に代わる連帯保証人を立てるよう要請されることが通常ですので、経営者・社長としては、別の連帯保証人を探し出すことができるのかが重要となります。
(2)配偶者名義の不動産
例えば、配偶者が結婚前より土地を所有していたため、土地については配偶者名義、建物については会社名義といった事例は散見されます。こういった場合、会社が土地を利用するための使用権原(借地権など)が離婚を機にどういった影響を受けるのか、検討する必要があります。特に、借地料が事実上無償であるような使用貸借関係にすぎない場合、離婚を機に配偶者が使用貸借関係の終了を主張した上で建物収去土地明渡しを求めてくる可能性もあるからです。
結局のところ、正規の土地使用権原を設定するか、又は土地そのものを買取る等の対応をせざるを得ないのですが、配偶者はそもそも交渉に応じる義務がありませんので、どうしても交渉は難航します。なお、上記のような事例の場合、財産分与による取得を検討することも不可能です。
足元を見られがちとはなりますが、経営者・社長としては粘り強く交渉するほかないかもしれません。
(3)配偶者名義の事業用動産
例えば、配偶者の先代が個人事業として経営し、先代名義で取得した事業用動産を配偶者が相続等で取得しつつ、婿養子がその後の社長として経営を行っているといった事例などで、こういった現象は起こりえます。
事業用動産ですので、維持管理に要する費用は会社にて負担していることが多いものの、名義は配偶者となっている以上、配偶者の資産(特有財産)として考えざるを得ません。当該事業用動産が会社経営において重要である場合、買取りや賃貸借の交渉を行うほかありません。
なお、上記のような事例の場合、離婚に伴う財産分与の対象とすることも難しいため、交渉が整わない場合、事業運営に重大な支障を来すことになりかねません。この場合は、当該事業用動産に代わる新たな物を購入するといった対処も必要になることを念頭に置く必要があります。
3.財産分与
財産分与は婚姻関係破綻時点において、婚姻期間中に当事者で築き上げた共有財産を清算するというものであり、近時は50対50、つまり同等割合を基準に清算することが通例となっています。しかし、一方当事者が経営者・社長である場合、一方当事者の才覚によって事業を発展させたという側面が強く、同等割合で共有財産を清算することはかえって不公平ではないかという問題があります。
(1)個人事業における事業用財産
個人事業の場合、事業用財産は当事者のいずれかの名義になっていることが通常です。このため、婚姻期間中に取得した事業用財産についても財産分与の対象と考えざるを得ません。
もっとも、事業用財産に対する財産分与の割合を同等と考えてよいかは別問題です。経営者・社長の配偶者がどの程度事業に関与し貢献してきたのか個別具体的な事情を考慮せざるを得ませんが、経営者・社長の分与割合が高くなる可能性は十分にあるといえます。
なお、よほどの特殊事情がない限り、配偶者の分与割合がゼロということはあり得ないと考えるべきです。そのため、一般的には配偶者の分与割合分に係る事業用財産を金銭評価し、経営者・社長が買い取る形で清算することが多いのですが、支払資金を準備できない等の事情で、事業用財産について持分割合はともかく共有にするという解決を行おうとする経営者・社長も一定数いるようです。ただ、財産分与について共有としたところで、元配偶者より後で共有物分割等の手続きを取られてしまうと、再びこの問題が発生することになり、紛争の蒸し返しとなってしまいます。したがって、事業用財産を共有にするという解決法は正直お勧めできません。
(2)法人名義の財産
財産分与は、あくまでも当事者が婚姻期間中に築き上げた共有財産を対象に清算を図ろうとする制度です。この点、法人は第三者に該当する以上、法人名義の財産は共有財産にはならず、財産分与の対象とならないというのが論理的帰結となります。
もっとも、例えば婚姻期間中に購入した自動車について、会社名義とはなっているものの、事業運営上での使用実態はなく、専らファミリーカーとして使用されていたという場合には、実質的な関係を重視して財産分与の対象にするという場合もあります。また、いわゆる法人格否認の法理が適用されるような場面、例えば双方関係が悪化しつつある段階で将来を慮って経営者・社長名義の個人財産を意図的に会社名義に変更していった等の特殊事情があれば、会社名義の資産について財産分与の対象になるという場面もあり得ます。
以上の通り、基本的には法人名義の資産が財産分与の対象となる場面は限定されるものの、念のため、経営者・社長としては、法人名義の財産について、その取得経緯や使用実態、配偶者の関与がないこと等を主張できるよう準備しておいた方が無難かもしれません。
(3)事業経営と密接に関連する財産について
法人名義の資産ではないものの、事業経営に密接に関係する財産というものがあります。例えば、株式、生命保険、貸付金などです。
①株式
経営者・社長名義の株式である場合、財産分与の対象となります。もっとも、事業経営への関与・寄与度等を考慮して、分与の割合を決めること(必ずしも平等割合になるとは限らない)、前述した通りです。
株式について交渉が難航するのは、株式の評価額についてです。株式上場を果たしている株式であれば市場評価を基準にすることができますが、非上場会社の場合、株式の評価方法が複数あること、1つの評価方法を選択しても鑑定人による評価額に幅が生じることから、激しく主張が対立しがちです。また、経営者・社長の立場からすれば、株式を保有する代わりに現金で清算しようとするのが通常であることから、一定のキャッシュアウトは避けられないことも覚悟する必要があります。
②生命保険
税金対策で生命保険に加入することが多いためか、経営者・社長が共有財産として認識していないことが多いのですが、例えば、婚姻期間中において、会社が保険契約者、受取人が経営者・社長となる生命保険において、保険契約期間満了と同時に一定の保険金が支給(返戻)されるといった形態のものあります。
この場合、保険金自体が財産分与の対象になるという事例が存在します。
もっとも、経営者・社長としては、もともと保険料は法人が負担していたことから、支給される保険金も法人に当然帰属するものと勘違いしていることが多いようです。しかし、財産分与されてしまった結果、想定していた保険金を受けとることができず、会社の資金繰りに充てようと考えていたのに思惑が外れといった話があったりします。
かなり盲点になりがちですので、経営者・社長としては事前に確認しておきたいところです。
③会社への貸付金
中小企業の場合、実態を伴わないにもかかわらず、様々な事情で経営者・社長が会社に貸付金を有していることが決算書に記載されたりします。この場合、理屈の上では経営者・社長名義の財産となりますので、やはり財産分与の対象になると考えざるを得ません。
貸付金としての実態がないのであれば、経営者・社長において積極的に主張立証する必要がありますので、なぜ貸付金勘定を設けたのか経緯を含め、事前に十分な対策を練る必要があります(会社の顧問税理士の協力が必要不可欠になると考えられます)。
4.家族(プライベート)関係
上記1.から3.までは、離婚を検討又は手続きを進めている経営者・社長において、会社との関係で考慮するべきポイント事項を解説しました。ここでは、経営者・社長以外の方でも離婚の際には問題となるものの、経営者・社長であるが故に、一般的な議論が当てはまりづらい事項につき、解説を行います。
(1)離婚前
離婚手続きが完了する前に配偶者と別居するという事例は多いのですが、この場合気を付けなければならないのが婚姻費用の分担についてです。婚姻費用という用語例を用いるとイメージしづらいところがあるのですが、要は離婚手続きが完了するまでは、配偶者を含む家族の生活費を支払わなければならないという点です。
具体的な金額算定ですが、原則的には裁判所が公表している算定表を用いることになります。ただ、経営者・社長において、算定表上の上限を超える収入がある場合、算定表上の上限値で頭打ちとするのか結論が出ておらず、裁判例を紐解いてもケースバイケースで判断されているのが実情です。したがって、経営者・社長にとっては想定外の婚姻費用の分担と求められる可能性があることに注意が必要です。
以下、経営者・社長の場合における特有の注意点です。
①収入操作
婚姻費用の具体的な金額を算定するに際しては、経営者・社長の収入額が重要となります。この点、経営者・社長であるが故に役員報酬をあえて減額し、収入額を低く見せるといったことを考える方もいるようです。しかし、前年度以前の役員報酬額と比較してあまりに減額している場合、なぜ減額しているのか合理的理由(例えば、会社の売上が激減し、役員報酬をとれなくなった等)を示すことができない限り、操作(減額)した収入額をベースに婚姻費用を算定するということはありませんので、あまり下手に対策は取らないほうが良いと考えられます。
②特有財産からの収入
経営者・社長の収入額を算出するに際し、特有財産からの収入(例えば、親から受け継いだ不動産の賃料収入、株式の配当収入など)を含めるべきかという議論があります。原則的には特有財産からの収入は含めるべきではないと考えられていますが、婚姻中の生活実態として、特有財産からの収入で家計を賄っていたとなると結論が異なってきます。経営者・社長の中には、特有財産からの収入は含めなくてもよいと安易に判断している方もいるのですが、この点は注意が必要です。
③個人事業主の場合
個人事業主の収入を算定する場合、一般的には確定申告書にある「課税される所得金額」を参照することになります。但し、この「課税される所得金額」は税務政策的な観点から所得より控除される費目が存在するため、この点を考慮する必要があります。例えば、配偶者控除や青色申告控除等は現実に負担した経費ではないにもかかわらず、税務上の所得算定の上で控除されています。
したがって、配偶者控除等については「課税される所得金額」に加算した上で、収入算定を行う必要があることに注意が必要です。
(2)離婚手続き中
離婚手続きを進めていく中で、必ず取り決めなければならない事項として「親権」があります。経営者・社長の一部の方からは、後継者として考えているので親権を取りたいと要望を受けることがあるのですが、残念ながら、この要望だけでは親権を取るだけの根拠にはなり得ません。結局のところ、後継者になるかどうかは子供本人の意思にかかってきますので、親権の問題とは別に、面会交流を含め、離婚後どれくらい子供と接触することが可能なのかを考えたほうが良いのかもしれません。
ところで、親権を取得することが想定される配偶者が、離婚手続きの時点では定職についておらず収入が不安定(又は無収入)という場合があります。経営者・社長の中には、この経済的事情を指摘した上で、親権を取りたいと要望される場合もあります。しかし、現在の裁判実務を考慮する限り、経済的事情は重視して親権を決めるということはほぼあり得ないというのが実情です(経済的問題が懸念されるのであれば、配偶者に対してもっと高額の養育費を支払えとカウンターパンチ(?)を浴びることさえあります)。したがって、配偶者の経済的事情と絡めて親権をとるという方針はとらないほうが無難です。
(3)離婚後
離婚後に問題となり得るパターンとしては、面会交流が実施されないことと養育費が多いように思います。この点、面会交流の実施については、経営者・社長であるという属性によって特殊な問題が生じるわけではないと考えられることから、この記事では省略します。
一方、養育費については、上記(1)でも解説したような、養育費の具体的金額を定める上で、①収入操作があった場合はどうするのか、②特有財産からの収入を考慮するのか、③個人事業主の場合の収入算定方法という問題が当然あります。
しかし、養育費については、離婚後の生活環境の変化、典型的には再婚等により新たな家族を持つことで、従前の養育費を支払い続けることが難しくなったという相談が圧倒的に多くなります。養育費を受け取る側からすれば、相手の事情で知ったことではないという感覚になりがちであるため、なかなか協議がまとまらない傾向があるようです。養育費の減額調停手続きを通じて協議する方が、結果的には早期解決につながりやすいように思いますので、経営者・社長としては面倒くさがらずに調停手続きの対応を行った方がよいのではないかと考えられます。
<2021年10月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
|
|
;






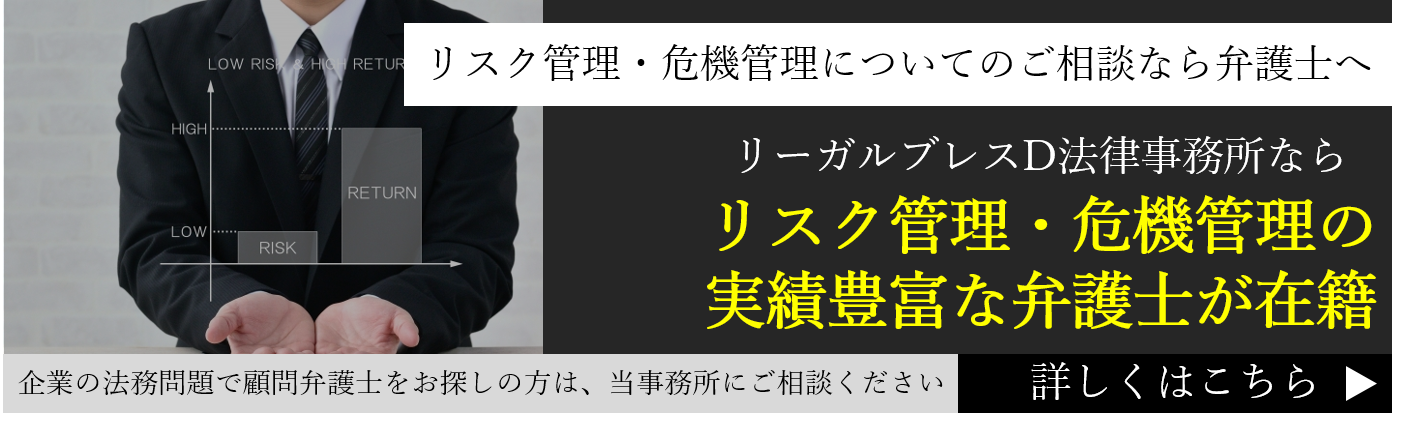

 弁護士 湯原伸一
弁護士 湯原伸一




































