Contents
【ご相談内容】
特に揉めることもなく自主退職した従業員がいたのですが、当社と競業する事業を立ち上げたり、当社顧客との接触を試みたり、ありもしない当社の悪い噂を流したり等、とにかく当社に対して様々な嫌がらせを行っているようです。
当社としても然るべき対策を講じたいのですが、どういった手順で進めていけばよいでしょうか。
【回答】
元従業員による退職後の言動が、会社業務に支障を及ぼす、悪影響を与えるので何とかしたいというご相談は最近多くなってきているように感じます。そして、雇用の流動化が進むにつれ、この種の相談は増加するのではないかと予想しています。
さて、会社にとって都合の悪い、元従業員の言動には様々なものがあります。本記事では、「取引先の奪取(競業行為)」、「情報漏洩」、「従業員の引抜き」、「誹謗中傷」に分けて解説を行います。また、最後に、会社が対応することで新たな紛争が生じる場合もあることにも触れます。
【解説】
1.取引先の奪取(競業行為)
退職後に元従業員が取引先に働きかけ、取引先を奪っていく行為を会社としては見過ごすことができません。しかし、心情的に許せないという点は理解できるとしても、では元従業員に対して、当然に取引先の奪取行為を止めるよう法的に請求(差止請求)ができるという訳ではありません。これは、元従業員は会社を辞めている以上、会社からあれこれ言われる筋合いはないというのが原則となるからです。
そこで、会社としては、元従業員に対し、退職後も引き続き競業避止義務を負わせることができないかを考えることになります。
(1)退職後の競業避止義務の有無
退職後において競業避止義務を負わせるためには、会社と元従業員との間で何らかの合意が必要となります。この合意を取得するタイミングですが、一般的には、①退職時、②雇用期間中、③入社時、で取得を試みることになります。
①退職時
まず、退職に際して競業避止に関する合意書面を取り付けることが考えられます。ただ、競業避止に関する合意書面を締結しなければならない法的義務はありませんので、従業員が拒絶した場合は対処できないという問題があります。
なお、合意書面を締結しない場合は退職を認めない、又は退職金を不支給にする等のルールを設定することで、事実上圧力をかけるといった方法も一応は考えられます。もっとも、会社が退職を認めないと主張したところで、民法第627条の適用、すなわち退職申出日より2週間経過すれば法的に退職の効力が発生するため(無期雇用の場合)、実効的な対策とはなりません。また、一般的な退職金の性格は賃金の後払い的性格を有するものとされていますので、合意書面を締結しなかったことを理由に全額不支給とすることの有効性は疑義があるものと言わざるを得ません。
したがって、競業避止に関する合意書面を取り付けることが難しい場合があることを想定する必要があります。
ところで、従業員が競業避止に関する合意書面に署名押印した場合、これによって常に競業避止義務が発生すると考えることも、実は誤りとなります。なぜならば、裁判実務上、競業避止義務の有効性は制限的に解釈するというのが支配的見解となっているためです。具体的な考慮要素は次の通りです。
- 競業避止義務を課すだけの正当目的があること
- 元従業員の社内での状況(例えば業務内容、役割、権限などからして平社員にすぎないのであれば、競業避止を課すのは行き過ぎであるなど)
- 時間的な制限(例えば2年を超えると無効となるリスクが高い)
- 地理的な範囲(例えば会社の事業展開地域外まで制限を課すことは行き過ぎであるなど)
- 禁止される内容(例えば会社が展開する事業内容のうち、元従業員が従事していない業務や業種についてまで制限するのは行き過ぎであるなど)
- 代償措置(競業避止を課す代わりに退職金を上積みするなど)
特に近時の裁判例では、職業選択の自由を制限するだけの「代償措置」を講じているのかにつき、非常に重視している傾向があると分析されています。もちろん、代償措置の程度・内容によっては、なお有効性を担保できないということもありますが、何らの代償措置を講じていないとなると、競業避止の有効性を裁判で争われた場合、会社は苦戦する可能性あることも考えておく必要があります。
②雇用期間中
例えば、従業員が秘匿性の高い特定プロジェクトに参加する場合、部署移動や昇進する場合などのタイミングで、競業避止に関する合意書面を徴収するといったことが考えられます。
退職時よりは合意を取付やすいとは考えられますが、結局のところは、上記でも解説した競業避止義務の有効性を判断するための考慮要素を念頭に置く必要があります。もちろん、雇用期間中ですので代償措置を講じることは考えにくいため、他の考慮要素について一定の絞り込みを行うこと(競業避止の範囲を従業員が従事する業務と関連付けて具体的かつ明確化する)が重要なポイントとなります。
③入社時
例えば、入社時に提出してもらう誓約書等に競業避止義務を明記し、従業員に署名押印させることで、比較的簡単に合意を得られることになります。ただ、入社時の場合、従業員が従事する業務内容が特定できておらず、上記で解説した競業避止義務の有効性を判断するための考慮要素を想定した内容で、競業避止に関する合意を行うことが困難という問題があります。
したがって、入社時に徴収した競業避止に関する誓約書等のみでは、競業避止に関する裏付け根拠として不安定なところがあることに注意をする必要があります。
なお、入社時の誓約書等では競業避止義務の有効性を判断するための考慮要素を十分反映できていないという問題は、就業規則等の社内規程に定める競業避止に関する事項も同様です。どうしても画一的かつ抽象的な内容とならざるを得ず、絞り込みがでてきないと評価されるからです。
(2)現場対応
元従業員による取引先奪取行為が発覚した場合、どういった現場対応が考えられるのかですが、次のようなことを検討することになります。なお、いずれも一筋縄ではいかない対処法ですので、弁護士に相談しながら対処していくことをお勧めします。
①元従業員に対して
退職後の競業避止義務がある場合、契約違反であることを根拠にした警告書の送付、民事裁判(仮処分を含む)による差止請求、といったものが考えられます。
ただ、警告書を送付しても無視された場合はもちろんのこと、民事裁判は最低でも数ヶ月の時間を要することから、即効性のある現場対応とは言いづらいところがあります。
②取引先に対して
元従業員との間で退職後の競業避止に関する合意があったとしても、その合意の効力が及ぶのはあくまでも元従業員限りであり、取引先に対して効力が及ぶものではありません。したがって、取引先に対して、直接的に取引中止要請等を行うだけの法的根拠がないということをまずは押さえる必要があります。
さて、取引先に対して、元従業員による会社への妨害行為をどこまで説明するのかという悩ましい問題があるのですが、時間的な制約や実効性確保の見地からは、元従業員との関係性をある程度説明しつつ、取引先への説得(取引継続のお願い)を図ったほうが功を奏することが多いように思われます。
ただし、取引先への説得を行うに際して、元従業員を誹謗中傷するような言動は行うべきではありません。これを行ってしまうと、元従業員側より名誉・信用棄損として、さらなる攻撃を受けてしまうリスクが生じるからです。なお、既に元従業員に取引関係を奪われてしまった場合であっても、当該取引先より話を聞けるのであれば聞いてみるべきです。会社に対する誹謗中傷的な言動を行っていることが多く、それを根拠に損害賠償等の別手段による圧力をかけることも検討できるようになるからです。また、競業避止義務違反以外の別の合意違反(例えば秘密保持義務違反など)も発見できることもあります。
③差止以外の方法(損害賠償請求)
元従業員との間で競業避止に関する合意がなかったとしても、元従業員による顧客奪取行為が社会的相当性を欠く場合、損害賠償請求することが可能となります。
証拠の集め方など工夫が必要となりますが、損害賠償請求を行うだけでも、元従業員に対する一定の抑止力となることもありますので、たとえ合意がなかったとしても、諦めることなく対処したいところです。
2.情報漏洩(無断持ち出し、不正利用)
会社によっては情報が重要な資産となっている場合があります。例えば、営業系の会社であれば顧客情報、製造系の会社であれば技術情報、食品系であればレシピ情報などです。こういった情報を元従業員が無断で持ち出し、利用しているとなると、会社としても黙っているわけにはいきません。しかし、情報それ自体は無体物であるため所有権が発生するわけではありません。また、無体物を権利の対象とする知的財産権も一定の条件をクリアーする必要があり、全ての情報を権利化することは難しいというのが実情です。
この結果、退職した従業員に対して、情報の無断持ち出しや利用を禁止するための法的根拠を作り出すことが、必要となってきます。
(1)退職後の秘密保持義務の有無
上記1.で解説した競業避止とは異なり、情報については一定の条件を満たすことで法的保護を受けることが可能です。例えば、次のような場合です。
・不正競争防止法に基づく「営業秘密」に該当する場合
・不正競争防止法に基づく「限定提供データ」に該当する場合
・著作権法に基づく「著作物」に該当する場合(情報を創作的に表現した場合)
不正競争防止法に基づく営業秘密や限定提供データに該当する場合、情報の破棄や使用差止を法的に行うことが可能となります。また同様に、著作物に該当する場合も、著作権法に基づく使用差止を法的に行うことが可能となります。
なお、元従業員に対して直接的な請求権が発生するわけではありませんが、例えば、個人情報保護法に定める「個人データ」を無断で持ち出した場合であれば、個人情報保護法違反として処断される可能性があることを指摘しながら元従業員に圧力をかけつつ、任意での返還や破棄、利用禁止の誓約といった対処ができることがあります。また、一例ですが、有料職業紹介事業であれば、職業安定法第51条に基づき従業員に秘密保持義務が定められており、いわゆる業法と呼ばれるものには業法特有の秘密保持義務が課せられることがあります。これを元従業員に指摘しつつ、任意での破棄等といった対処ができることがあります。
次に、上記で記載したような法令上保護される情報に該当しない場合であっても、元従業員との間で退職後も秘密保持義務に関する合意を行うという方法も取ることが可能です。
ところで、競業避止義務に関する合意の場合、様々な考慮要素を踏まえて有効性を検討することを上記1.で解説しましたが、秘密保持に関する合意の場合、ここまで厳格な考慮要素が求められているわけではありません。しかし、秘密保持に関する合意の場合、どういった情報が秘密保持の対象となるのか具体的かつ明確に記載することが求められます。例えば、経営上の情報といった抽象的な内容しか合意書に書いていない場合、過度に広範な内容であり合意が無効と判断されるリスクがありますので、注意が必要です。その観点からすると、秘密保持に関する合意を得やすい入社時の段階、就業規則による秘密保持条項については、一般的・抽象的な内容となりがちですので、例えば、担当業務に変更がある都度、当該担当業務に関係する具体的な秘密情報を明記し、かつ秘密保持の期間は退職後も継続することを定めた契約書の取り交わしを行うといった対応が必要になると考えられます。
ちなみに、従業員が退職時に秘密保持に関する合意を行うことができれば、タイミング的には一番望ましいといえます。しかし、退職後も秘密保持義務を負う旨の合意を取り交わす義務を従業員が負担しているわけではない以上、当該従業員より拒絶されてしまうと対処することが困難となること、競業避止に関する問題と同様です。
(2)現場対応
①事前準備の重要性
元従業員が、会社の保有する情報を無断で持ち出し、利用していた場合、どういった対処を行うべきかですが、上記(1)で記載した通り、当該情報が法的保護に値する情報と言えるのか(法令上の根拠があるのか、秘密保持に関する合意対象となる情報と言えるのか)を検討することは当然必要となります。
しかし、それ以上に現場対応で厄介なのが、そもそも会社が保有する情報を持ち出した・利用したといえるのかという点です。なぜ、こういったことが問題となるのかですが、元従業員側からの反論として、会社が指摘する情報は他ルートからも入手可能であり持ち出していないといったものがあるからです。こういった反論を想定し、元従業員に警告等を行う前に、情報持ち出しに関する証拠収集を行うことが肝要となります。なお、証拠収集の方法については詳述しませんが、情報をデジタル化して保管することが多い昨今の状況を踏まえれば、元従業員が使用していた端末のログ履歴の調査はもちろん、場合によってはデジタルフォレンジック技術を用いるといった、相応の費用と時間をかける必要があることも想定する必要があります。
②従業員に対して
不正競争防止法や著作権法など法令上の根拠がある場合は、当該法令を根拠に使用差止や廃棄等を請求することになります。ただ、例えば、営業秘密の該当性は評価を伴う以上、元従業員より管理体制からして営業秘密に該当しない等の反論を受け、会社からの請求に従わない可能性もあります。したがって、一筋縄では済まないことを前提に対策を練る必要があります。
また、秘密保持に関する合意を根拠にする場合も、秘密保持契約の有効性を争われたり、秘密保持の対象外の情報である等の反論が考えられます。やはり一筋縄ではいかないことを想定しての対応が必要となります。
③取引先に対して
基本的な考え方は、競業避止に関する上記1.(2)②の解説と同じとなります。
もっとも、競業避止と異なり、情報漏洩の場合、法令上保護される情報の場合、取引先に対しても直接使用差止や損害賠償請求等を行うことが可能という違いがあります。例えば、会社が取引先に対し、元従業員と取引することは営業秘密侵害や著作権侵害となりうることを警告するといった対処です。
ただし、実際に営業秘密侵害等が成立すれば問題にはならないのですが、前述した通り、営業秘密や著作物の該当性は評価が伴う以上、裁判等になった場合に該当性が否定される可能性も否定できません。確定的な結論が出ていない状況下で、上記のような指摘・警告を行い、後で該当性なしと裁判所で判断されてしまうと、今度は元従業員側より、会社が不正競争防止法に定める信用棄損を行ったとして損害賠償請求等を受けるリスクを負うことになります。
したがって、取引先に対して、権利侵害を行っていることを警告するのか、元従業員との間でトラブルが生じていることをあえて指摘するのか、単に今後の取引継続の依頼に留めるのか、法的事前検証と取引先の態度も考慮しながら、状況に応じた判断を行う必要があることに注意が必要です。
④損害賠償について
元従業員が無断で情報を持ち出し使用するという違法行為によって、会社が損害を被ったという理屈は一見すると分かりやすいのですが、現場実務で悩ましいのは、当該違法行為によって、会社は具体的にどのような損害が発生し、具体的金額はいくらなのかを算定することが困難という点です。これは、情報それ自体の経済的価値を客観的に算定することが難しく、特に裁判手続きを念頭に置いた場合、損害額を立証することが極めて困難だからです。
したがって、情報漏洩による損害賠償は、実際には行いづらいところがあることを知っておく必要があります。なお、現場実務の知恵としては、情報それ自体の損害ではなく、情報漏洩によって会社の信用が棄損されたとして信用棄損による損害賠償を請求する、あるいは情報持ち出しに伴う取引機会の損失に伴う損害賠償請求を行う、といった形に置き換えて請求することが多いように思います。
⑤まとめ
情報漏洩を原因とする法的請求を行う場合、高度な法的判断と実効性のある調査が必要不可欠となります。弁護士のアドバイスを受けながら対処するのが得策と考えられます。
3.従業員の引抜き
退職した元従業員が会社の同僚等に対して声をかけ、元従業員が所属する組織に転職させる(させようとする)ことが明らかとなった場合、何らかの対抗策を打ちたいと考えるのは当然のことと思われます。しかし、元従業員は当然に引抜き禁止義務を負っているわけではありませんし、また元従業員の誘いに応じた従業員も転職の自由があることから、やや対策を講じにくい問題となります。
(1)引抜き禁止義務の有無
上記で記載した通り、元従業員は、引抜き行為を禁止する義務を法律上当然に負担することはありません。したがって、元従業員に対して、引抜き行為を禁止させたいのであれば、何らかの合意を行うほかないのが実情です。
この点、入社時に提出させる誓約書や就業規則にて、退職後に従業員の引抜きを禁止する旨定めることで、一応合意があったということはできるかと思います。上記1.で解説した競業避止に関する合意ほど厳しい考慮要素が求められるわけではありませんが、とはいえ、例えば半永久的に勧誘することを禁止する、元従業員が所属せず関係性もない事業者が人材募集を行っている旨案内することを禁止するといった場合は、過度に広範な規制であるとして合意が無効と判断される可能性があります。
したがって、引抜き禁止の合意を行うにしても、どの程度のことまで禁止するのか内容面での検討が必要となります。
(2)現場対応
①元従業員に対して
引抜きを禁止する合意がある場合は、端的に当該合意違反であることを根拠にした警告を行うことになります。ただ、既に会社従業員が転職してしまった後に引抜き行為が発覚した場合、今後の抑止目的で警告を行うという対応も必要ですが、既に転職してしまっている以上、如何ともしがたいところがあります(従業員を会社に強制的に連れ戻すという訳にはいかないため)。
したがって、既に転職してしまったという場合は、後述の損害賠償問題として処理するほかありません。なお、そもそも元従業員と引抜き禁止に関する合意がない場合も、損害賠償の問題として処理できないか検討することになります。
②転職先に対して
転職先の代表者が引抜き禁止の合意をした元従業員であるといった場合であればともかく、転職先は引抜き禁止の合意の効力が及びませんので、何らの対策を講じることができないというのが原則論となります。
もっとも、転職した(引き抜いた)従業員が営業秘密を保有している場合は不正競争防止法違反の可能性を転職先に指摘するといった対抗策をとることができる場合もあります。また、転職した(引き抜いた)従業員が退職後も秘密保持義務や競業避止義務を負担している場合、転職先に対して、当該従業員が負担している義務内容をあえて告知することでプレッシャーを与えるといった方法も一応はあります(厳密には、告知したにもかかわらず、当該従業員が従事する業務内容を変更せずに義務違反を継続させた場合、転職先は当該従業員と共に違法行為を行っているといった法的構成をとれないか検討することになります)。
いずれにせよ、転職先に対して直接的な請求を行うことは原則難しいことを押さえる必要があります。
③損害賠償請求について
まず注意して頂きたいのが、引抜き禁止の合意がない場合はもちろん、当該合意があったとしても、引抜き行為に対して当然に損害賠償請求が認められるわけではないという点です。これは、引抜き対象となった従業員の転職の自由を考慮する必要があるため、勧誘行為自体を当然に違法とするわけにはいかないからです。
こういった事情もあり、多くの裁判例では「引抜きが社会的相当を逸脱した」場合に限り、引抜き行為の違法性が認められるという考え方を示しています。この社会的相当性についてですが、次のような事由を考慮していると考えられます。
- 元従業員が引抜きによる会社への悪影響度(対象となる従業員の地位・役割、従事していた業務内容、人数、時期などから影響度を考慮する)
- 引抜きの態様・方法の悪質性(計画性、密行性、会社への誹謗中傷、扇動的な言動などを考慮する)
- 元従業員の目的や動機(嫌がらせ目的、事業活動の妨害目的などを考慮する)
なお、引抜き行為の違法性が認められたとしても、現場実務で悩ましいのは引抜き行為によって生じた損害の内容と金額の算定です。新たな従業員を採用するためのコストや従業員が転職しなければ得られであろう利益といったものが考えられますが、前者については因果関係があるのか、後者については確実に利益が発生する状況だったのか等の現場特有の問題があったりします。
損害賠償の問題に限った話ではありませんが、元従業員による引抜き行為が行われた場合の対処法については、よくよく弁護士と相談しながら実効性ある手段を選択することをお勧めします。
4.誹謗中傷
最近多いパターンとして、例えば、元従業員が転職サイトの掲示板等に、会社を誹謗中傷する(時には虚偽の)口コミ投稿を行い、世間一般からの評判を落とそうとするといったものがあります。また、従来からあるパターンとしては、取引先等に会社内の不祥事や揉め事を吹聴し、会社と取引先との信頼関係を傷つけるといったものがあります。
(1)誹謗中傷禁止義務の有無
ややタイトルが不自然なのですが、誹謗中傷という言い回しではなく、会社の名誉を毀損すること、信用を棄損すること、業務を妨害することは法律上当然に禁止されています。したがって、誹謗中傷という一般用語ではなく、元従業員の個々の言動が名誉・信用棄損に該当するか、業務妨害に該当するかを判断し、該当する場合は民事上の請求(差止、損害賠償、名誉回復措置など)及び刑事告訴を行うといった対策を講じることができます。
なお、誹謗中傷を行わない旨合意することも当然有効です。ただ、せっかく合意をするのであれば、誹謗中傷といった抽象的な内容ではなく、社内で不祥事があった場合の口外禁止といった具体的な内容を想定した合意を行うことを検討するべきです。
(2)現場対応
①インターネット上の投稿に対して
インターネット上の掲示板等への投稿情報が名誉毀損等に該当する場合はもちろん、掲示板等の管理運営者が定めるポリシー(削除要請に対する方針など)に該当する場合、当該運営者に対して削除申請を行い、投稿情報を削除してもらうというのが初動になるものと考えられます。
万一、管理運営者が削除しない場合は裁判手続きを用いるほかありません。また、削除の有無を問わず、投稿者の特定を図る場合、裁判外での手続きで特定することは現状困難であることから、裁判手続きを用いることになります。なお、詳細については次の記事もご参照ください。
ネット炎上・風評被害が生じた際に会社がとるべき対応を弁護士が解説!
②取引先に対して
取引先等へ吹聴された場合ですが、残念ながらこれといった有効策はないというのが実情です。重要な取引先に対しては面談の上で説明を行い信頼関係の回復に努めるという、地道な対処法がもっとも功を奏するものと思われます。
なお、吹聴された内容がある程度公になってしまっている場合、取引先等に対して説明文書を配布する、会社のWEB上にて説明文書を掲載するといった対応も考えられます。
③元従業員に対して
上記(1)で解説した通り、名誉毀損等の法令違反に該当する場合には、その旨を指摘した上での警告書の送付が一般的です。もっとも、どうしても事後対応とならざるを得ないことから、いきなり訴訟提起を行うということも十分に考えられます。
なお、訴訟提起を行ったことを対外的に公表することで、会社として適切に対処していることをアピールすることができ、事実上の信頼回復につながるといったことも実はあったりします。一種の対外広報戦略ですが、元従業員に対しては断固たる対応をとったほうが信頼回復につながりやすいことも念頭に置くべきです(あえて記載しておきますが、費用対効果の点では割に合わないのが通常です。ただ、お金では買えない信頼回復には役立つこともあるという趣旨です)。
5.元従業員からの反撃
上記1.から4.では、元従業員が、退職後に会社へ行う嫌がらせの類型とその対処法について解説しました。
当然のことながら、会社としては必要な対処を講じたつもりなのですが、この対処をきっかけに更に新たなトラブルを招来することがあります。ここでは典型的な3事例を取り上げておきます。
(1)未払い賃金(残業等)請求
会社からの警告書を受領した元従業員が弁護士に相談したところ、本来の相談事項とは別観点でアドバイスすることにより、未払い残業の問題が新たに生じてしまうというのが典型的パターンです。
会社としては、未払い賃金が発生しないように事前に対策しておくことが必要不可欠ですが、未払い賃金の請求があった場合、元従業員による嫌がらせ行為とは別問題と認識し、適切な対応を行うべきです。なお、未払い賃金請求への対処法については、次の記事もご参照ください。
残業代を請求された場合に、会社が検討・対処するべき事項を弁護士が解説!
(2)パワハラ等の損害賠償請求
元従業員が会社で勤務していた当時、上司から暴言を受けた等として損害賠償請求を行ってくるということも、実際にはよくあります。これについても別問題として捉え、元従業員が主張するようなハラスメントがあったのか調査を行い、是々非々で対処する必要があります。なお、パワーハラスメントについては、次の記事もご参照ください。
会社が従業員よりパワハラと言われないために対処法を弁護士が解説!
(3)退職強要
既に退職しているにもかかわらず、退職は自発的意思ではなく、会社から強要されたものであり実質的には解雇であるとして、解雇無効あるいは損害賠償請求を行ってくる例も現実にはあったりします。
会社に対する嫌がらせ行為を行っているにもかかわらず、会社に戻りたいと主張するのは何事かと思われるかもしれませんが、元従業員の本心はともかく、これについても別問題として適切な調査の上、対処する必要があります。なお、退職に際して起こりがちなトラブルへの対処法については、次の記事もご参照ください。
会社が従業員を辞めさせようとする場合に注意するべきポイントを弁護士が徹底解説!
<2021年10月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
|
|






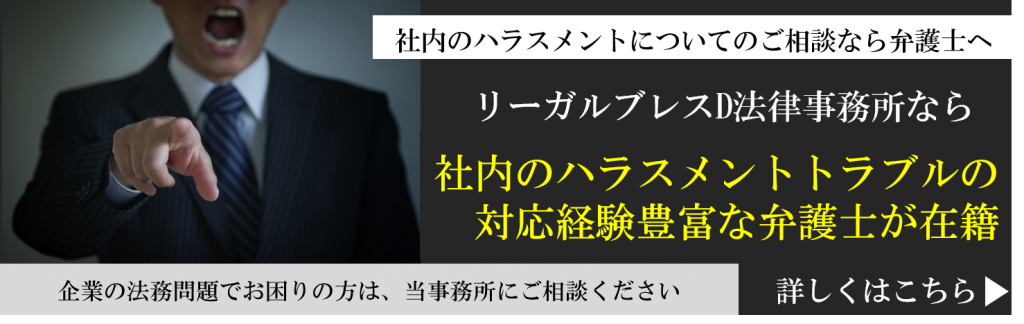

 弁護士 湯原伸一
弁護士 湯原伸一




































