Contents
【ご相談内容】
従業員に辞めてもらう場合、色々なパターンがあるかと思うのですが、次のようなパターンの場合、人事担当者としてはそれぞれどういった点に注意をするべきなのでしょうか。
①採用内定取消を行う場合
②試用期間満了と同時に辞めてもらう場合
③リストラ(人員削減、整理解雇)により辞めてもらう場合
④勤務成績不良を理由(普通解雇)に辞めてもらう場合
⑤非行を理由(懲戒解雇)に辞めてもらう場合
⑥退職のお願い(退職勧奨)を行う場合
【回答】
①採用内定通知を出し、入社誓約書も徴収しているのであれば、貴社と労働者との間には労働契約が成立したと法的には評価されます。したがって、貴社の都合のみで自由に採用内定の取り消しを行うことができず、むしろ解雇に準じて検討する必要があります。
②試用期間中といえども、労働契約は成立していますので、試用期間満了と同時に従業員を辞めさせるということは「解雇」に該当します。したがって、解雇に値するだけの客観的かつ合理的な解雇事由が必要となります。
なお、14日を越えて雇用されている場合には、即時解雇の場合は解雇予告手当の支給が必要となりますし、即時解雇しないのであれば30日前の解雇予告を行う必要があります。
③整理解雇については直接的な法律上の規定はありません。しかし、これまでの裁判例の蓄積を踏まえ、整理解雇が有効となるための検討事項としては次のようなものを総合考慮するという判断が確立しています。
・人員陣削減の必要性があること
・解雇回避努力が尽くされていること
・解雇される者の選定が合理的であること(人選の合理性)
・事前の説明・協議を尽くしていること
④勤務成績不良による解雇を行う場合、会社が期待する能力について労働者と認識共有し、期待値を下回っても何度も指導を繰り返し、それでも改善が見込まれない段階に至って初めて解雇の正当性を維持できると考えたほうが無難です。
⑤懲戒解雇手続きを選択する場合、形式的に懲戒解雇事由に該当しても、やむにやむを得ない(重大かつ悪質)ものといえる場合のみに限定して、慎重に懲戒解雇手続きを実施したほうが無難です。
⑥会社が特定の従業員に対し、退職をお願いすることは、法律上の制限はなく、全く自由となります。このため、退職勧奨に応じない労働者に対し、繰り返し説得することは、必要に応じて再度説得することは問題ありません。
ただし、行き過ぎると退職強要として違法行為(パワハラなど)となり得ますので、注意が必要です。また、例えば、労働組合嫌悪による組合差別や妊娠・子育て等を理由(マタハラ)とした退職勧奨する場合は、法律上問題になってきますので注意が必要です。
※解雇する場合は予告解雇又は解雇予告手当の支払いが必要となります。予告解雇を行ったこと又は解雇予告手当を支払ったこと、これらのみで解雇が正当と判断されるわけではありません。
>>元従業員が残業代請求した場合における会社が検討するべき事項とは?
【解説】
採用内定取消を行う場合
採用内定によって労働契約が成立したと言えるか否かは、個別具体的な事情によって判断されます。
ただ、裁判例の傾向としては、採用内定決定を出しているのであれば、特段の事情がない限り、始期付解約権留保付労働契約(=「始期付」とは、就業開始時期が将来の一定日に定まっていることです。また、「解約権留保付」とは、採用内定から就業開始日までは、入社誓約書等に予め明示された採用取消事由が生じた場合に、労働契約が解約されることが条件となっていることを意味します。)が成立したと認定することが多いのが実情です。この点、入社誓約書まで徴収しているのであれば、ほぼ間違いなく始期付解約権留保付労働契約が成立したと認定されるでしょう。
そして、始期付解約権留保付労働契約といっても、労働契約であることには変わりありませんので、雇い主側の事情で労働契約を終了させること、すなわち(普通)解雇の手続きを踏むのであれば、解雇権の濫用に該当しないよう、客観的かつ合理的な解雇理由が必要となります。なお、程度問題はありますが、あまりに一方的な採用内定取り消しの場合、慰謝料の支払いを命じられる可能性もあります。慎重な検討が必要です。
弁護士へのご相談・お問い合わせ
当サイトの記事をお読みいただいても問題が解決しない場合は
弁護士にご相談いただいた方がよい可能性がございます。
下の電話番号もしくはメールにてリーガルブレスD法律事務所までお問い合わせください。
06-4708-7988メールでのご相談
試用期間満了と同時に辞めてもらう場合
試用期間は本来的には正式採用決定前の期間であり、当該期間中に労働者の勤務態度、能力、技能などを検証し、正式採用の判断を行うために設けられます。したがって、会社の従業員として不的確であれば正式採用しないという判断を行っても良いはずではと考えられるかもしれません。
しかし残念ながら、法律的には試用期間と正式採用期間とで別個の労働契約が成立しているとは考えません。つまり、1つの労働契約が成立していることは間違いなく、その一部の期間を試用期間、残りの期間を正式採用期間と会社が独自に名付けているに過ぎないと考えることとなります。したがって、試用期間満了時であっても労働契約の中途解約である以上、「解雇」と評価されることになりますので、客観的かつ合理的な解雇事由が求められます。
よくある事例として、作業ミスの程度・回数が酷い(いわゆる能力不足)というものがあるのですが、実際の裁判の場では、作業ミスを少なくするための指導措置など会社の対応が大きな考慮要素となります。このため、単に作業ミスが多いという理由だけでは正式採用を拒絶する、つまり解雇の正当性を主張するというのは難しいと言わざるを得ないでしょう。
ところで、試用期間中の本来の目的を重視して、一般的な解雇よりも広く認められても良いとする裁判例もあります。しかし、何を持って「広く」と解釈して良いかは非常に微妙な判断を伴いますので、弁護士等の専門家に相談した方がよいでしょう。
また、そもそも「客観的かつ合理的な解雇事由」とは何かという問題はきわめて専門的な判断が必要となりますので、紛争を防止したいのであれば、専門家に相談し対応を検討した方が無難でしょう。
リストラ(人員削減、整理解雇)により辞めてもらう場合
【回答】に記載した4つの検討要素(要件)について、具体的な検討を以下で行います。
(1)人員削減の必要性が存在すること
そもそも人員削減の必要性がないのに、何の問題もない従業員を解雇するわけにはいきません。従って、人員削減の必要性という要件は当然の前提になるのですが、では、必要性の程度はどの様な場合を言うのでしょうか?
実は、この人員削減の必要性の程度については、企業が倒産必至の状態であることまで必要という見解もあれば、企業の合理的運営上の必要性があれば足りるとする見解もあり、定まった見解が存在していない状況です。ただ、一般論としてという言い方になりますが、倒産必至までとは言えなくても、高度の経営危機が生じていることまで説明できた方が、対外的な説明はしやすいですし、有効性は高くなると思われます。
そこで、例えば過去3期分程度の決算書、今期の月次決算書などの資料を準備しつつ数字の裏付けを取ること、同時に景気動向、企業の将来予測などを見ながら該当性の検討を行うといったことが必要となってきます。
(2)解雇回避努力が尽くされていること
日本の法制度上、労働者の解雇は簡単には認められません。従って、整理解雇を認めるにしても、解雇の前にまずは代替的な雇用調整手段を取ったかという点が有効性を判断する上での検討材料となります。
この検討材料としては、経費削減(役員報酬のカット等)、新規募集・採用の停止、労働時間の短縮、賃金カット、配転・出向、一時帰休の実施の有無などがあげられますが、比較的重要視されているのは、「希望退職の募集を行ったか」という点です。これはどういうことかと言いますと、整理解雇の場合、どうしても従業員の意向に反して雇用契約を打ち切ることになってしまうこと、解雇後の補償が必ずしも十分ではないという問題が生じてしまいます。一方、希望退職の場合、従業員が自ら退職を申し出る以上、従業員の意向もある程度は尊重されますし、希望退職の募集を行うに際しては、会社側も退職後の補償について一定程度行うことが通常ですので(退職金の割り増しなどが代表例です)、まだ従業員のダメージも少ないというデメリットの回避を図ることができます。
この様なことから、「希望退職の募集」を行うと共に、経費削減等の有無・程度を検討の上、該当性の検討を行った方が無難ということになります。
(3)解雇される者の選定が合理的であること(人選の合理性)
「あいつは生意気だから、クビにしよう」といった恣意的な判断は許されません。解雇という従業員にとっては重大な効果をもたらす行為を行う以上、何故、その人を対象としたのか合理的に説明できる状態にする必要があります。そこで、人選基準については、事前に作成することは当然の前提となります(できれば書面化して、取締役会等で決済を取った方が良いでしょう)。
また、具体的な基準内容については、勤務成績・能力等の評価を基準にする場合、勤続年数・売上実績などの会社貢献度を基準とする場合、年齢を基準とする場合、再就職可能性や家族状況などの労働者の属性(生活状況)を基準とする場合、雇用形態(正社員かパートか)を基準とする場合、など色々な組み合わせがあると思います。この様な基準を事前に設定し、公平に各従業員の該当性を検討の上、対象者を絞り込んでいくということで、該当性の判断を行う必要が生じます。
なお、(1)とも関連しますが、基準への該当性を検討した結果、該当者が複数生じた場合、全員を整理解雇するのかは、さらに検討を要します(人員削減の必要性の検討に際して、削減する人員数を算出するはずです。このため、当該人員数を大きく上回る人員を解雇するとなると、かえって該当者全員を解雇する必要性はないということで整理解雇が結果的に全部無効と判断される可能性が生じるからです)。
(4)事前の説明・協議を尽くしていること
上記(1)~(3)については、会社(使用者)側で検討することになりますが、対象となる従業員側はほとんど事情を知らないため、ある日突然「整理解雇するので辞めてくれ」と言われても、大変困ることとなります。そこで、整理解雇を実施するのであれば、事前に労働者、労働組合に対して、なぜ整理解雇が必要なのか、時期・規模・方法といった内容などを説明し協議することで、納得を得られるよう努力する必要が生じます。これらの事前の説明・協議の内容を踏まえて、該当性の検討を行うことになります。
勤務成績不良を理由(普通解雇)に辞めてもらう場合
会社から見れば、全く役に立たないしミスばかりしている、指導しても耳を貸さない又は指導しても全く治らない、その結果、他の従業員があおりを受けて士気低下にもつながっている、といった問題従業員について、辞めさせたいと思うのが本音だと思います。
たしかに、一般論として勤務成績不良・能力不足による解雇、それ自体は認められています。ただ、実際に解雇が法的に有効と判断されるためには、残念ながら非常に高いハードルがあるため、ほとんどの会社ではこのハードルを乗り越えることができず、結果として解雇無効という判断に流れてしまうというのが実情です。
このハードルが、解雇する理由として「客観的に合理的な理由」があること、及び解雇という選択肢を取ることが「社会通念上相当であること」という労働契約法16条の規定です。この具体的内容として、1つの裁判例では「単なる成績不良ではなく、企業経営や運営に現に支障・損害が生じ又は重大な損害を生じる恐れがあり、企業から排除しなければならない程度に至っていることを要し、かつ、その他、是正のため注意し反省を促したにもかかわらず、改善されないなど今後の改善の見込みもないこと、使用者の不当な人事により労働者の反発を招いたなどの労働者に宥恕すべき事情が無いこと、配転や降格ができない企業事情があることなども考慮」すると示されています。つまるところ、やるべきことを尽くしたが如何ともしがたいという最終状況にまで陥らなければ、解雇は困難という話になってしまいます。
では、ハードルは高いものの、やはり現場としては解雇を実施せざるを得ないという場合、具体的にどういったことを検討するべきなのでしょうか。
一番のポイントは、勤務成績不良なり能力不足を判断するための一定の基準はどこに設定すればよいのか、という点です。実は、この一定の水準について会社が求めている内容と、労働者が認識している内容とがかみ合っておらず、この認識の相違を発端として深刻なトラブルになってしまうことが多いように感じています。したがって、一定の水準については労使双方の認識の共有を図ることがポイントとなります。能力不足による解雇を検討するのであれば、例えば、次のような手順を踏むべきではないかと考えます。
- 従業員のどの点に問題があるのか具体的に指摘する(改善点の指示)
- 改善点がクリアーできていない場合は業務指導を行う(業務指導)
- (上記を踏まえた)会社が求める基準を従業員に認知させる(基準の共有化)
- 基準を充足しなかった場合の改善命令と懲戒処分(軽い懲戒処分から順に選択)
- (懲戒処分が複数回続いた場合)普通解雇
なお、どうしてもこういった手順を踏むことが難しい場合は、退職勧奨(会社から辞めてもらえないか提案すること)を行なうことになります。ただ、無理な退職勧奨は、違法ないし退職強要として損害賠償責任を負わされることにもなりかねませんし、またパワーハラスメントと言われてしまうリスクもありますので、細心の注意が必要です。
ちなみに、基準設定に関連し、PIP(業務改善プログラム)を設定する会社が増加しているようです。ただ、一方的にPIPを設定することは、上記裁判例でいう「使用者の不当な人事により労働者の反発を招いたなどの労働者に宥恕すべき事情」があると言われかねませんし、そもそも労使において共有化された基準とは言い難いところがあります。
したがって、PIPについては、従業員とじっくり話し合って設計することが肝要です。
非行を理由(懲戒解雇)に辞めてもらう場合
解雇手続き、特に懲戒解雇処分は、あえて例えるなら、刑事裁判でいうところの死刑判決を下すようなものです。死刑判決を行うのはやむにやまれぬ場合に限定されていることからもイメージができるかと思うのですが、懲戒解雇についても、単純に懲戒解雇事由に該当したから懲戒解雇有効というロジックを裁判所は用いません。特に、実際の裁判例では、懲戒解雇は厳しすぎるが、普通解雇であれば有効性を認めるというものまで存在しますので、安易に懲戒解雇を選択することはリスクがあると考えたほうがよいかもしれません。言い換えれば、いわゆる不当解雇リスクを回避するのであれば、できる限り自主退職に持って行く方が賢明という点では、普通解雇、懲戒解雇ともに同じと考えられます。
ところで、懲戒解雇について、上記のようなやむにやまれぬ事情があるのかという点を検討する必要があることはもちろんなのですが、現場実務では、意外と懲戒解雇を行うための手続きが実行されておらず、この手続き違反を理由とした懲戒解雇無効と判断せざるを得ない事例が一定数存在します。
例えば、懲戒解雇を実施するに際しては、労働者本人に弁明の機会を与えたか、就業規則上懲罰委員会にて結論を出すことになっていないか、労働組合との労働協約上団体交渉を事前に行う必要があるのではないか、懲戒解雇処分を行う前に、同じ問題行動を原因とした懲戒処分(懲戒処分としての降格や賃金カット等)を実施していないか、問題となっている行動について従前発生した類似事例の懲戒処分とバランス・均衡がとれているかといったことを検討する必要があります。
また、非常に細かい話にはなってしまうのですが、特に裁判の場合にポイントになるのが、懲戒解雇を言い渡した時点で会社が問題視した懲戒解雇の原因事由のみ対象として、解雇の有効性が判断される点があります。つまり、あとで他にも問題行動が発覚し、追加主張しても裁判所には聞き入れてもらえません。この点からも懲戒解雇処分は非常に限定されていることがお分かり頂けるかと思います。
最後に、万一不当解雇と主張されて裁判となり、使用者側が敗訴となってしまった場合、労働契約はいまだに成立していたことという取り扱いになります。そして、労務の提供を拒絶したのは使用者の一方的都合に過ぎないこととなってしまい、たとえ就労していなくても解雇を言い渡した日まで遡って賃金全額を支払う必要があります。また、職場復帰を認める必要もあります。このような状況下になってしまうと、社内の雰囲気は最悪になってしまうこと間違いないのですが、残念ながら間違えた解雇手続きを行ってしまうと、このような事態が発生してしまいます。
懲戒解雇については、とにかく慎重かつ弁護士等の専門家の見解も踏まえて対処する必要があります。
退職のお願い(退職勧奨)を行う場合
退職勧奨とは、あくまでも「辞めてもらえませんか?」という会社からのお願い・要請であって、労働契約の終了という法的効果を伴うものではありません。したがって、法律上は何らの定めが無く、退職勧奨を行なうこと自体は事業主・会社の自由となります。
ただ、現場実務でよくあるパターンとして、退職勧奨を行う側の担当者も仕事熱心のあまり(?)、退職に応じない従業員に対し、あの手この手でだまし討ち的に(?)、あるいは脅迫して(?)、強引に退職を迫ることも事実として存在します。このような禁じ手を使った場合は、詐欺による退職の意思表示の取消という問題や、退職強要・パワハラとして違法であると後で言われかねません。実際のところ、その線引きは非常に難しいのですが、どうしても退職勧奨に応じないのであれば、普通解雇にできないか証拠固めや証拠づくりを行うという方針に切り替えた方が良いかもしれません。
また、退職勧奨を行う場合、特に注意したいのが労働組合が絡む案件の場合です。
事業主・会社としては、業務命令に従わない反抗的態度や業務怠慢などの能力不足を根拠に退職勧奨を行なうことが多いのですが、必ずと言っていいほど「組合差別だ」「組合嫌悪だ」として、労働組合法上の違法行為である不当労働行為であるという反論が行われてきます。当然のことながら、本当に能力不足があるのであれば退職勧奨を行なうことも適法ですし、場合によっては普通解雇することも適法です。しかし、組合に加入した従業員は労働組合法という強力な反論材料を持ち合わせていますし、また、事業主・会社側も多かれ少なかれ労働組合に対する悪感情を持ち合わせているのも事実だと正直思います。その意味で、組合員に対する退職勧奨を行うのであれば、事前に綿密な作戦を立てた上で実施する必要があります。あと、最近特に問題になりやすいものとして、妊娠や子育てを理由とした退職勧奨はマタハラとして別の問題になりえますので、注意が必要です。
<2020年1月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
|
|






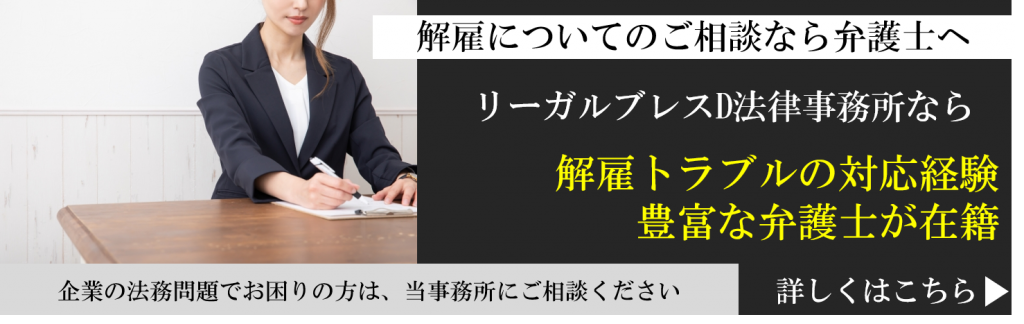

 弁護士 湯原伸一
弁護士 湯原伸一


































