Contents
【ご相談内容】
未払い残業代の請求を受けたため、当社でも再計算を行い、未払い残業代の提示を行ったのですが、諸々見解の相違が発生しています。
次のような手当について、算定基礎となる賃金より控除して良いのでしょうか。
①家族手当、住宅手当
②皆勤手当
③営業手当、役付手当
また、次のような場合、残業代をそもそも支払う必要があるのでしょうか。
④部長職または課長職など役付の従業員
⑤時間外労働分を毎月定額で支払っている従業員
⑥代休を付与した従業員
【回答】
①法律上列挙されている手当のみ控除対象となります。この点、家族手当については労働基準法37条5項に、住宅手当については労働基準法施行規則21条に該当しますので、形式的には控除できそうですが、手当の内容(算出方法)によっては控除できない場合もあります。
②皆勤手当は労働基準法37条5項及び労働基準法施行規則21条に定める手当に該当しないため、控除不可です。但し、皆勤手当支給の制度設計如何によっては控除可能な手当になる場合も考えられます。
③営業手当及び役付手当は労働基準法37条5項及び労働基準法施行規則21条に定める手当に該当しないため、控除不可です。但し、当該手当の内容が、いわゆる固定残業代(定額残業代、みなし残業代)に該当する場合は、控除可能です。
④役付=管理監督者に該当するわけではないため、残業代支払い義務が生じることが多いと考えられます。
⑤いわゆる固定残業代(定額残業代、みなし残業代)として有効要件を充足した場合は、その定額分については残業代支払い済みと主張することが可能です。
⑥代休を付与した従業員に対して残業代を支払う必要があることはもちろんですが、割増率(法定休日に就労した場合は35%)にも注意する必要があります。
【解説】
1.家族手当、住宅手当について
上記回答にも記載した通り、割増賃金の算定基礎となる賃金より除外できる手当は法定列挙されています。現行法上は、次の7種類です。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金
そうすると、設問の「家族手当」も「住宅手当」も法定列挙されていますので、算定基礎賃金より控除してもよさそうに考えられます。もっとも、法律が定めている「家族手当」と「住宅手当」は日常用語として用いられているものより、かなり狭い範囲の概念となっています。すなわち、
- 家族手当=扶養家族又はこれを基礎とする家族手当額を基準として算出されているもの
- 住宅手当=実質的に住宅に要する費用に応じて支給されているもの
と定義づけられています。
したがって、例えば、扶養家族の有無や人数に関係なく一律に支給されている場合は、算定基礎から除外できる家族手当には該当しないことになります。また、住宅手当についても、例えば、一律支給される場合、扶養家族の有無によって金額変動させる場合(住宅以外の要素で額を決める場合)、賃貸と持家の区分にしたがって一律に支給する場合には、算定基礎から除外できる住宅手当に該当しないことになります。
なお、実質的な算出方法によって除外の有無を決めますので、例えば、家族手当ではなく、物価手当や生活手当という名称であっても上記のような算出方法に従うのであれば、控除可能です。
弁護士へのご相談・お問い合わせ
当サイトの記事をお読みいただいても問題が解決しない場合は
弁護士にご相談いただいた方がよい可能性がございます。
下の電話番号もしくはメールにてリーガルブレスD法律事務所までお問い合わせください。
06-4708-7988メールでのご相談
2.皆勤手当
皆勤手当は法定列挙された手当に該当しませんので、算定基礎となる賃金から除外される手当には該当しません。もっとも、皆勤手当の支給要件を、例えば3ヵ月を一単位として支給の有無を決する場合には、「1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金」に該当しますので、理論的には算定基礎となる賃金から除外される手当に該当することになります。
ただし、皆勤手当という日常イメージからすれば、一賃金計算時期(1ヵ月)によって区分されるのが通常ですので、何故、1ヵ月を超えて支給の有無を決するのか合理的な理由が無い限り、脱法行為と言われてしまう可能性がありますので、注意が必要です。
3.営業手当、役付手当
営業手当及び役付手当はいずれも法定列挙された手当に該当しませんので、算定基礎となる賃金から除外される手当には該当しません。もっとも、最近の賃金体系で見受けられる、いわゆる固定残業代(定額残業代、みなし残業代など色々な呼び方があります)として位置付けられているのであれば、算定基礎となる賃金から除外できることになります。これは、固定残業代それ自体が割増賃金として支給されている以上、算定基礎となる賃金に含めてしまうと二重評価となってしまうからです。
なお、いわゆる固定残業代として有効性を維持するためには、最低でも賃金のうちどの部分が残業代として支払われているのか明瞭区分されていることが必要であり、具体的には、社内規程上に根拠を有すること、何時間分に該当するのか労働契約書等で明示すること、手当をおける時間外労働が発生した場合には精算を行うことが、必要になると考えられます。
4.部長職または課長職など役付の従業員と残業代について
部長職や課長職の役付の従業員については、一般的には管理職と呼ばれます。このため労働基準法41条2号に定める「管理監督者」に該当するのではないかと思われるかもしれませんが、一般的な「管理職」という概念と法律が定める「管理監督者」は全く概念が異なります。労働基準法41条2号に定める「管理監督者」は、経営者と一体的な立場にある者とされています。この点、多くの会社では、部長職や課長職の場合、部下を監督する権限は付与されています。が、社長や役員のような、経営者として会社経営を左右するような権限まで付与されているわけではありません。
従って、多くの場合、単に部長や課長という職制が付与されていたとしても、「管理監督者」に該当しないことになります。例えば、世間で注目を浴びたマクドナルドの店長について裁判所は、管理監督者に該当しないと判示したことは記憶に残っているかと思います。
以上のことから、会社としては、部長職や課長職だから残業代を支払わないという対応は避けるべきです。そして、部長職や課長職に対して役付手当を支払っているのであれば、当該手当を次に述べる「固定残業代」として位置付けることでリスクヘッジを図ることが、現行の労働法にマッチングするかと思われます。
5.時間外労働分を毎月定額で支払っている従業員と残業代について
固定残業代(定額残業代やみなし残業代など色々な呼び方があります)については、色々と誤解がされているのですが、(1)基本給に定額の残業代を含めた場合、(2)基本給とは別に定額の残業代を支払う場合、とでは有効と判断されるか否かの結論が大きく異なってくると考えた方が良いかと思います。というのも、裁判所が有効性を判断するに際しては、賃金のうちどの部分が残業代として支払われているのか明瞭区分されていることを最重要ポイントして検討しています。
この点、(1)の場合、基本給に含めて残業代を支払っていますので、「何時間分に該当する残業代なのか」が明確になりません。従って、(1)の場合は、ほぼ固定残業代の有効要件を充足せず、固定残業代としての支払いは無効、結果として全額の割増賃金支払義務を負うことになると考えられます。一方、(2)の場合、上記有効要件を充足した制度設計さえ行い、従業員への周知を図れば、固定残業代として有効と判断される可能性が高いと考えられます。
なお、この様な相違点に着目するのであれば、手当を固定残業代として位置付けたい場合はもちろん、会社としては固定残業代として支払っているつもりという場合であれば、有効要件を充足するよう、今すぐ社内規程の整備などを行うべきかと思います(よくあるパターンとして、未払い残業代紛争が生じてから固定残業代制度を整備するという対応をとることがあるのですが、整備後のリスクヘッジにはなっても、整備前の残業代支払い義務を免れる根拠にはならず、手遅れと言わざるを得ません)。
6.代休を付与した従業員と残業代
代休と振替休日は、世間でよく誤解されているのですが、
- 代休=休日労働を行った後で、代償として他の労働日を休日とすること。
- 振替休日=事前に休日と労働日の交換を行うこと。
と全く概念が異なります。
要は、休日付与の手続きが「前」か「後」という違いに過ぎないのですが、残業代の支払いの有無では大きな違いが生じてきます。それは、代休の場合、休日労働を行った事実が存在しますので、法定休日であれば35%増しで割増賃金を支払う必要があります。一方、振替休日の場合、休日労働を行った事にはなりませんので、少なくとも休日分の割増賃金を支払う必要はありません(もっとも、週40時間を超過した場合の時間外労働割増賃金の支払義務は生じます)。
したがって、代休の場合は、残業代(就労日が法定休日か法定外休日なのかによって割増率が異なります)が必要となります。
<2020年1月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
|
|






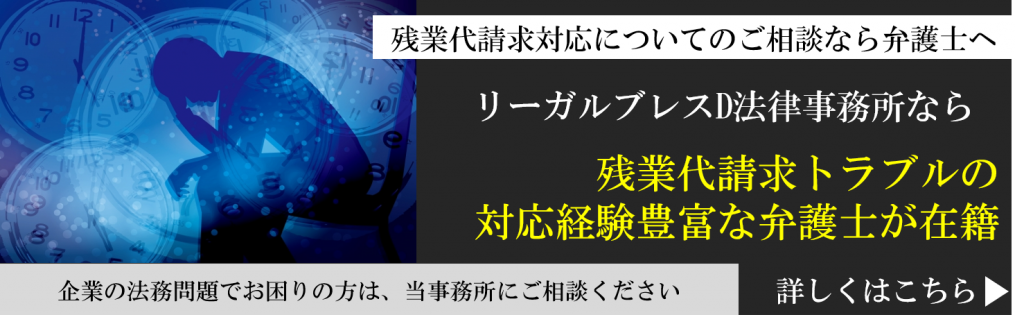

 弁護士 湯原伸一
弁護士 湯原伸一




































