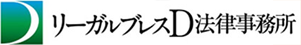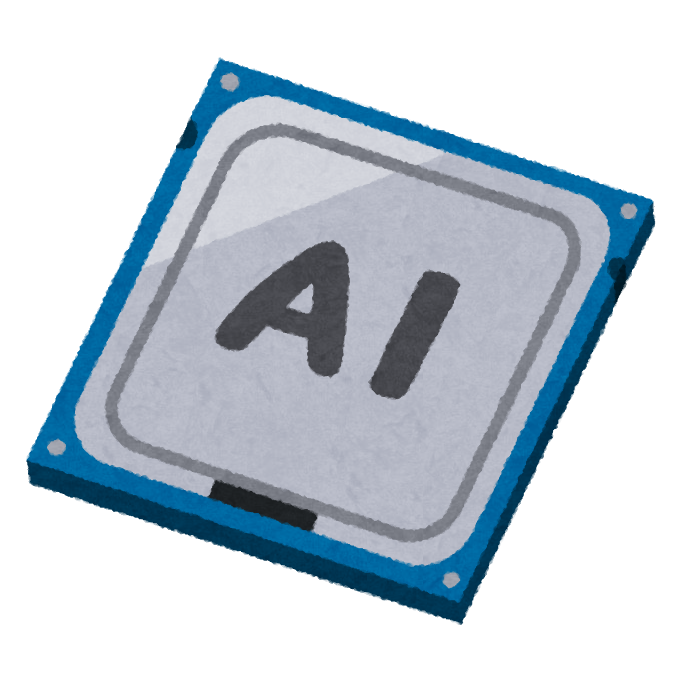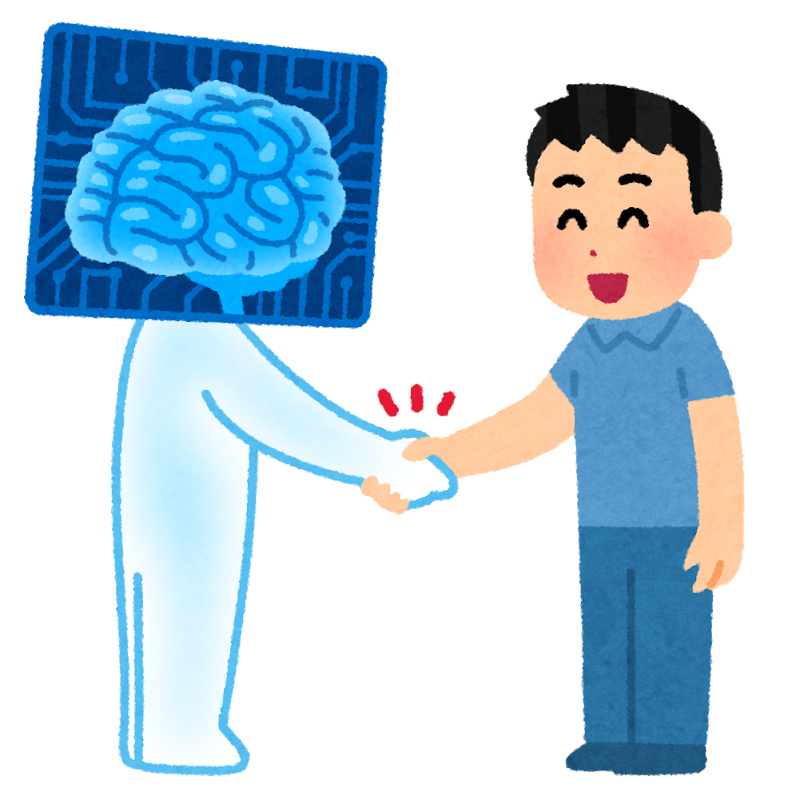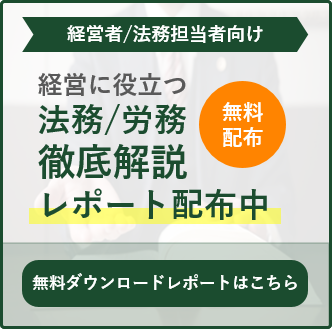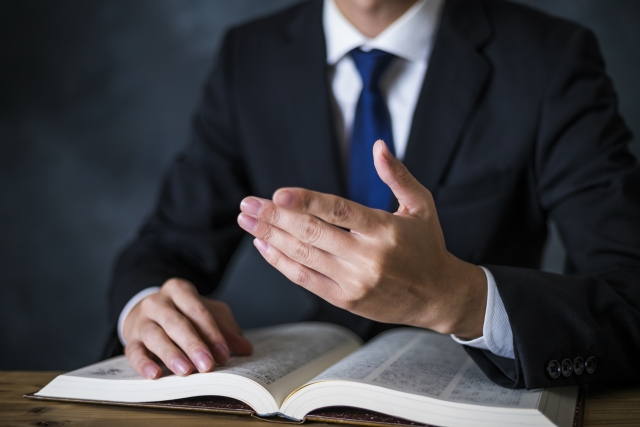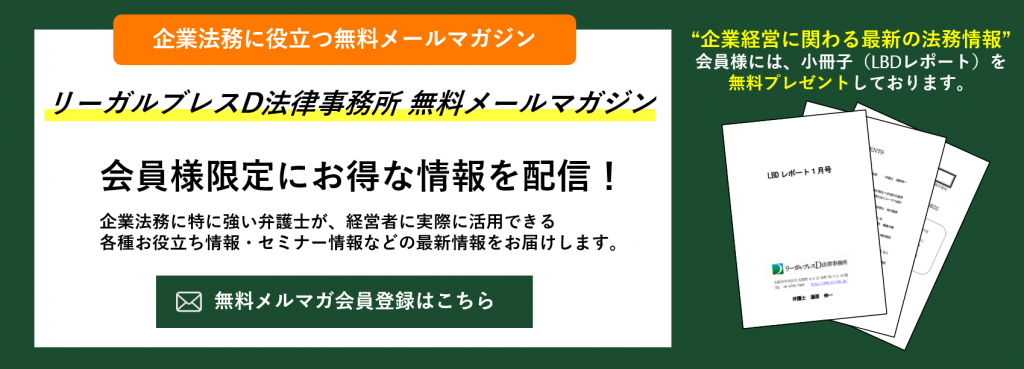
当事務所が運営する他のWEBサイトに掲載した記事の中で、閲覧者の皆様において役に立つと思われる記事をあげておきます。
【コメント】IT業界というタイトルを付けたため、IT企業ではない事業者の方はあまり関係が無い記事と思われるかもしれません。
しかし、IT企業ではなくても、例えば、WEB制作やシステム開発、運用保守、WEB広告運用代行など、大多数の事業者はITに関係する取引を行うことが当たり前となっています。
そこで、本記事では、委託者視点と受託者視点に分けて、ITに関係する業務委託契約を締結する場合に、どのような視点で契約書チェックを行えばよいのか、そのポイントを解説します。
◆Web制作(更新)、保守運用、広告運用代行に関連する契約書作成のポイントを解説
【コメント】WEBサイト(ホームページ)を作成したいと考えている事業者であれば、現状ではほぼ既に作成済みという状況のようです。
このため、知り合いのホームページ制作会社の担当者に聞いても、完全新規でWEBサイト(ホームページ)を作成することはほとんどないとのことでした。
もっとも、既に作成済みとはいえ、いわゆるお飾りになっていることが多く、もっと積極的にWEBサイト(ホームページ)を活用したいと考える事業者が多いようで、ホームページ制作会社もWEBサイトの更新(刷新)、WEBサイトの保守運用、WEBサイトの広告運用代行に力を入れているとのことです。
そこで、本記事では、WEBサイトの更新(刷新)、WEBサイトの保守運用、WEBサイトの広告運用代行関する契約書作成のポイントにつき、「委託者(ユーザ)」と「受託者(ベンダ)」とを分けて、それぞれの立場から解説を行います。
◆ソフトウェア使用許諾(ライセンス)契約書作成のポイントについて解説
【コメント】一昔前は、量販店等でソフトウェアが組み込まれたCD-ROM等の媒体物(パッケージ)を購入する、WEBサイトよりダウンロードする、といったものが主流であり、これらの取引を念頭に置いたソフトウェア使用許諾(ライセンス)契約が用いられていました。
しかし、今はクラウド型(SaaS、ASP)が主流です。
そこで、本記事ではクラウド型(SaaS、ASP)を前提にしたソフトウェア使用許諾(ライセンス)契約の条項例とそのポイントを解説していきます。
なお、本記事はサービス提供者(ライセンサー)視点、いわゆる一般条項には触れていないことにご注意ください。
◆アプリのプライバシーポリシー作成に際しての注意点とポイント解説
【コメント】アプリプライバシーポリシーとは、その名の通り、「アプリケーション」の「プライバシーポリシー」です。
このアプリプライバシーポリシーは、法律上作成義務があるわけではありません。
しかし、行政からの作成推奨があることや、ユーザの納得を得る1つの手法として公表したほうが事業者にとってメリットがある、といった理由で、作成することが多くなってきています。
そこで、本記事では、プライバシーポリシーとは別にアプリプライバシーポリシーを作成する意義と、作成するに際しての内容面でのポイントにつき解説を行います。
◆システム開発取引で裁判沙汰、損害賠償請求を受けてしまう原因とは?
【コメント】近時、システム開発取引がもめにもめてしまい裁判になってしまう事例が増加しています。そして、その裁判権結果については、日刊紙などでも報じられるくらい社会的関心事にもなってきています。
さて、システム開発取引に関する裁判は、実は様々なタイプがあるのですが、大まかには、①開発範囲・条件につき、ベンダとユーザの認識が異なる場合、②開発業務が途中で頓挫することで、費用の清算が問題となる場合、③システム引渡し後に不具合が発覚する場合に分類できるようです。
そこで、本記事では、上記3パターンにつき、裁判例などを引用しながら、主としてベンダ視点でそのポイントを解説します。
◆プログラムは著作権法でどこまで保護されるのか。注意点とポイントを解説
【コメント】プログラムの著作物は、著作権法第10条第1項第9号で著作物の例示として規定されているものの、他の著作物のような表現の鑑賞や享受を目的とするものとは言い難く、やや異質であることは否めません。
このため、プログラムの著作物については、著作権法上の取扱いも特殊なところがあります。
本記事では、まずはプログラムの著作物とは何を指すのかを検討したうえで、著作権者を判断する上での注意事項、権利行使が制限される場面、プログラムの著作物の侵害判断に関するポイントにつき、解説を行います。
◆オープンソースソフトウェア(OSS)利用時に注意すべき事項について(法務視点)
【コメント】近時は、制作会社がゼロからプログラムを書き起こしてソフトウエア等を制作するという手法は用いられず、オープンソースソフトウェア(OSS)を取り入れることが多いとされています。
費用や労力を抑えるためには非常に有用な方法と言えるのですが、一方でオープンソースソフトウェア(OSS)には厳しいライセンス条件が定められています。
万一、ライセンス条件に違反した場合、ベンダが制作した製品は今後提供することができなくなり、また既に提供済みであればユーザが今後使用できなくなる等の重大な問題に直面します。
オープンソースソフトウェア(OSS)を用いるのであれば、それ相応の覚悟が必要であることを十分ご理解いただきつつ、その注意点につき解説を行います。
◆検収完了後にシステム不具合が発覚した場合のベンダの責任、ユーザの対処法について
【コメント】契約書のリーガルチェックを行っていると、「検収」という用語をよく見かけるのではないかと思います。
しかし、「検収」は法令用語ではありません。
あくまでも契約実務で使われる用語に過ぎず、実際のところは、契約書において「検収」をどのように位置づけているのかを確認する必要があります。
本記事では、まず検収の意義と効果を整理した上で、契約不適合責任の内容、及び契約不適合の具体例と判断基準に関するポイントをまとめていきます。
本記事を読むことで、システム開発における検収の重要性、検収後の責任追及の在り方についてご理解いただけるかと思います。
なお、本記事では、システム開発契約の法的性質につき、請負契約を前提にしていること予めご承知おきください。
◆メタバースをビジネス・事業で活用する上で知っておくべき著作権の問題
【コメント】「メタバース」という言葉自体は、どこかで耳にしたことがあるかと思います。
また、最先端を行くIT企業をはじめ、最近では流行に乗り遅れまいとばかりに、様々な会社がメタバースに参入する動きが生じていることも聞いたことがあるかもしれません。
ただ、じゃ「我が社も直ぐに参入しよう!」になるかというと、そう単純なものではありません。
なぜなら、今後どこまでメタバースを含むデジタル空間内の経済活動が活発化するのかは未知数であり、ビジネス上のリスクは避けて通れないのが実情だからです。
また、メタバースそれ自体を包括的に適用する法律が存在せず、現行法をパッチワークのように当てて適用法令を検討する複雑性に起因したリーガルリスクも潜んでいます。
本記事では、リーガルリスクを少しで減らすべく、メタバースと著作権の関係に絞って解説を行います。
本記事を読むことで、メタバースを含むデジタル空間内で事業活動を行うに際し、著作権法のポイントを理解することができるかと思います。
|
|






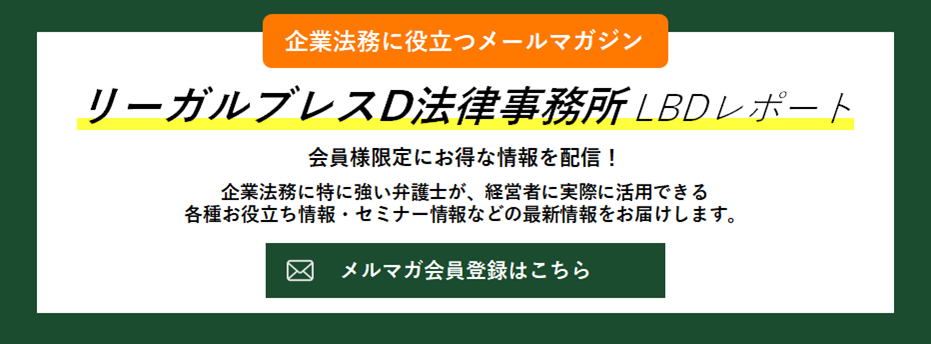
 弁護士 湯原伸一
弁護士 湯原伸一