【ご相談内容】
不動産譲渡や事業譲渡などを行う契約書を作成した場合、印紙税が生じると聞いたのですが、どのような点に注意すればよいでしょうか。
【回答】
不動産、事業(営業)譲渡、無体財産権の譲渡については、基本的には1号課税文書として譲渡価格に応じた印紙税を収める必要があります。一方、債権の譲渡契約については15号課税文書として印紙税を収める必要があります。
以下の【解説】では、特に確認していただければと思う事項につき触れておきます。
【解説】
1.不動産の譲渡に関する文書について
実務上で取扱う事例では不動産売買契約書と考えてまず間違いありません。通常の不動産売買であれば売買価額に応じて印紙税が決まります。
(1)老朽化した建物を解体撤去する前提の場合は?
さて、最近では老朽化した建物を解体撤去することを前提に不動産売買契約が締結されることがあります。いくら老朽化した建物といえども意外と高額な固定資産評価額がついていたりする場合もあり、解体するのに建物評価額分まで印紙税を徴収されるのはバカバカしいなぁ…と思われるかもしれません。
ただ、この問題については通達があり、「建物を解体したことによって生じる素材価額≧売買価額」という値段設定をしている契約の場合は、第1号の1課税文書として取り扱わないとされています。なお、解体撤去する予定の建物と同時に土地の売買契約を締結することが通常と思われところ、土地売買に関しては印紙税の課税対象となりますので注意が必要です。
(2)遺産分割に伴い不動産を譲渡する場合は?
意外と質問が多いので触れておきますが、遺産分割に伴い不動産の帰属を決めることは「不動産の譲渡」ではないと通達で明記されています。
したがって、第1号の1課税文書として取り扱われることはありません(印紙税はともかく、相続税の問題の方が悩ましいことになるかと思いますが…)
(3)担保目的の譲渡の場合は?
例えば、不動産に対して譲渡担保権を設定することで譲渡した場合ですが、通常は担保目的であるため売買金額を書くことはありません。この場合、金額の記載がないものとして取り扱われるため印紙代は200円となります。
次にちょっとややこしいのですが、不動産を提供しつつも、後日再売買することで取り戻す(再売買予約)の方式を取った場合、最初の売買金額と再売買するための予約金額の合計額を基準として印紙税を支払う必要があります。一方、民法上の買戻し特約に基づく売買契約解除という形で不動産を取り戻す場合は、最初の売買金額を基準にすれば足ります。印紙税の負担軽減という観点からすると、買戻し特約を用いたほうがメリットが大きいということになりますが、いろいろな観点からの検討が必要となりますので、何でもかんでも買戻し特約がベターであると判断するのは検討を要します。
2.事業(営業)譲渡に関する文書について
一昔前では営業譲渡と呼ばれていましたが、会社法が制定されたことで「事業譲渡」という言葉も用いられるようになりました。事業譲渡契約書も印紙税法上の営業譲渡契約書に含まれます。
ところで、営業(事業)譲渡はいわゆるM&Aの一手法として用いられるのですが、他の手法として株式譲渡を行うという場合があります。この株式譲渡については第1号の1課税文書に該当するのか、というお問い合わせをよく受けます。
結論からいうと、第1号の1課税文書に該当しません。これは、株式が、第1号の1課税文書の対象となっている「不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業」のいずれにも該当しないからです。
3.無体財産権に関する文書について(第1号の1課税文書)
最近、発明・考案(特許権、実用新案権)や創作(著作権)などに関する権利意識が高まってきているためか、この点に関する問い合わせは増加しています。よくある問い合わせパターンを以下まとめてみます。
(1)特許及び実用新案に関する出願権の譲渡契約書は課税文書?
結論からいうと、第1号の1課税文書に該当しません。
これは特許権及び実用新案権は特許庁に出願して認められて初めて成立する権利であり、出願できるにすぎない権利(地位)は、第1号の1にいう「無体財産権」には含まれないからです。
(2)著作権の譲渡契約書は課税文書?
これは第1号の1課税文書に該当し、譲渡価格に応じて印紙税額が決まります。
先の特許権及び実用新案権と著作権の違いは、著作権の場合は特許庁に出願しなくても創作した時点で権利が成立します。したがって、出願できるにすぎない権利(地位)という概念がありませんので、著作物を譲渡する契約書であれば課税文書として取り扱われることになります。
(3)著作物(ソフトウェア、プログラム、情報など)の使用許諾契約書は課税文書?
これは第1号の1課税文書に該当しません。ソフトウェア、プログラム、情報などのいわゆる無体物については、著作物を使用許諾という形で開示することによって事実上譲渡されたような格好にはなってしまうのですが、あくまでも著作権という権利が譲渡されたか否かによって判断を行います。
したがって、使用許諾(ライセンス)契約書にすぎないのであれば、課税文書として取り扱われることはありません。
(4)商標権の専用実施権を付与する契約書は課税文書?
専用実施権を付与することは実質的には権利者が映ったような格好になるため問い合わせを受けることがあるのですが、これについては第1号の1課税文書に該当しません。端的に実施権=使用許諾にすぎず、譲渡したものではないからと考えて問題ありません。
4.地上権又は土地の賃貸借の設定又は譲渡に関する契約書(第1号の2)
よく誤解されているお問い合わせ内容として、土地の賃貸借契約を締結し、毎月一定額の賃料を定めた場合において、印紙税はいくらになるのかというものです。よく文書を読むと分かるのですが、あくまでも「賃貸借の設定」を行った場合に第1号の2課税文書になると書いてあるだけであり、使用収益の対価である賃料はこれに該当しません。
したがって、地上権設定他の名目の権利金や賃貸借契約更新時の更新料といったものが定められている場合は第1号の2課税文書に該当しますが、一般的にみられる賃料を支払う形式に賃貸借契約の場合は、「設定に関する金額の記載なし」として取り扱われ、結果的には印紙税額は200円として算出されます。
なお、時々、建物賃貸借の場合について問い合わせを受けることがありますが、あくまでも第1号の2課税文書の対象は「土地」のみであることにご留意ください。
5.債権譲渡又は債務引受に関する契約書
上記1.~4.は第1号課税文書に関する解説だったのですが、財産権には債権も当然に含まれます(逆説的ですが債務も含まれます)。ただ、債権の譲渡債務の引受については、15号課税文書の問題として検討する必要があります。
ところで、勘違いしやすいのですが、債権を譲渡する側(譲渡人)が債務者に対して発する債権譲渡通知書(配達証明付き内容証明郵便などで行うことが多い)は、そもそも15号課税文書に該当しません。これは、債権譲渡を行うという意思の通知であって、契約書ではないからです(少なくとも契約というからには両当事者の合意が必要となりますが、債権譲渡通知は一方的な意思の通知にすぎません)。同様に債権譲渡の承諾書についても、15号課税文書に該当しないとされています。
ちなみに、債権譲渡というと、売掛金や請負代金、業務委託報酬といった現金支払いを求める権利を「債権」としてイメージされる方も多いかと思います。しかし、債権とは現金支払いを求める権利だけを意味しません。例えば、不動産物件の賃借権を譲渡する契約書を締結した場合、賃借権も債権ですので15号課税文書に該当するものとして処理する必要があります。
次に、債務引受けについてですが、これについては聞き慣れない方もおられるかと思います。細かいことを言い出すときりがないのですが、端的に申し上げれば、他人の債務を移転させることで、自らの債務として負担するということです。例えば、Xが100万円の借受債務を負担している場合、その100万円の返済義務をYに移転させることで、Y自らの債務として100万円の返済義務を負うというというイメージとなります。このような説明を行うと、必ず「保証と何が異なるのか?」という質問が飛んでくるのですが、保証はあくまでも保証債務という独自の債務となります。一方、債務引受けは、元々の債務を移転させるだけにすぎませんので、独自の債務が発生しているわけではありません(ただ、実質的には債務引受けは保証と類似する機能を持っている点は否めません)。
この債務引受けに関する文書については15号課税文書として処理することになります(なお、1万円未満の場合債務引き受けであれば印紙額ゼロですが、それ以外は13号(保証)と15号は同じです)。ちなみに、債務引受けを利用する場面として、いわゆる三角相殺に関する合意書がありますが、この合意書は15号課税文書として処理することになります。
<2021年8月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
|
|
;






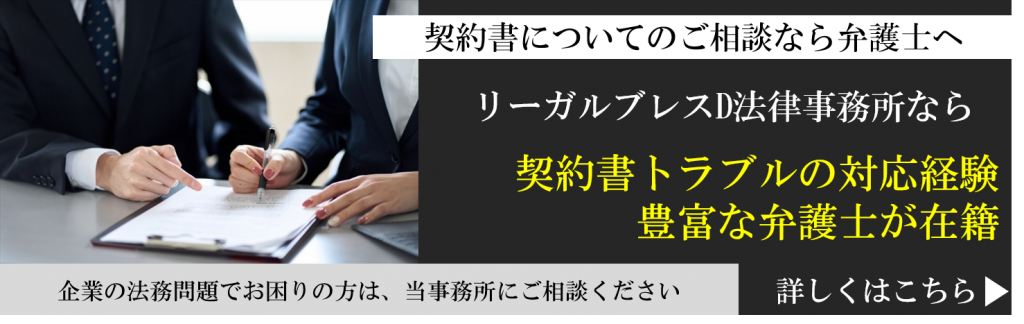

 弁護士 湯原伸一
弁護士 湯原伸一




































