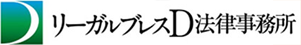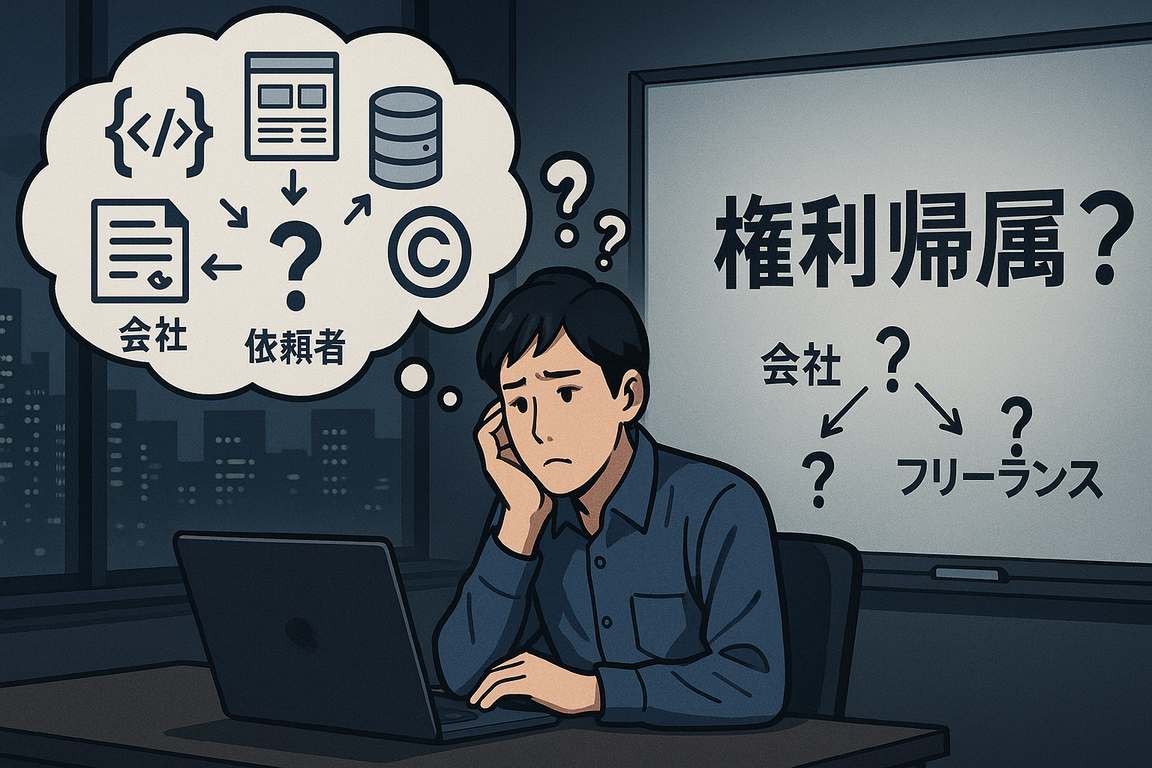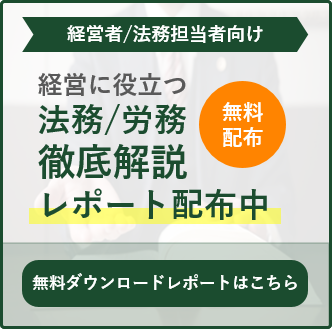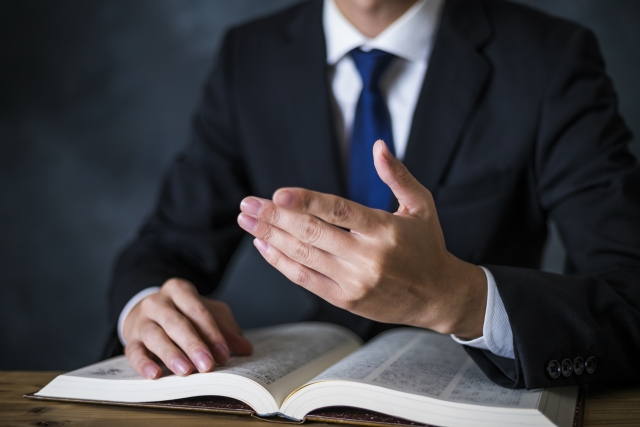近時はスキルシェアなどの用語例に代表される、自らの技術・技能を他人に提供するビジネスが多くなっています。
学習産業以外の異業種が、オンライン学習事業を開始したいというご相談が増えてきたことから、ご参考までに本記事を掲載します。
ご相談
当社はもともと教室に受講者を集めて講義を行う学習サービスを展開していたのですが、リモート学習などのEdTechに影響され、オンラインを用いた学習サービスの提供を計画しています。
どのような法律上の規制があり、どのような法律問題に留意しなければならないのか教えてください。
回答
オンライン学習サービス事業には様々なものが含まれるところ、焦点の当て方によって留意するべき法律が異なってきます。
そこで、本記事では便宜上、
①受講者が未成年者か成年者か利用者に焦点を当てることで生じる法律問題
②ストリーミング(一方通行での授業形式)かインタラクティブ(相互対話による形式)か技能教授方法に焦点を当てることで生じる法律問題
③事業者が直接受講者にサービス提供するのか仲介するに過ぎないのか提供者の立ち位置に焦点を当てることで生じる法律問題
に分類した上で、留意するべき事項につき解説を行います。
解説
上記回答でも記載した分類で検討した場合であっても、民法や商法はもちろんのこと、特定商取引法、著作権法、個人情報保護法など様々な法律上の規制が横断的に適用されるため、やや頭がこんがらかるかもしれません。
誰との間でどのようなやり取りが発生するのかを逐一確認し、1つずつ問題となる法律上の規制につき根気よく検討するほかありませんが、大まかな概要は次の記事の通りです。
ご参考の上、分からない点等ございましたら、弁護士等の専門家にご相談ください。
オンライン学習サービス事業を行う上で知っておきたい法律問題・法的課題
なお、記事の構成は次の通りです。
1.利用者(受講者)による分類
(1)未成年者(主として学生など)
①未成年者対応
②情報開示(概要書面及び契約書面の交付)
③契約内容
(2)成年者(主として社会人)
①情報開示
②契約内容
③申込み手続き
2.技能の教授方法による分類
(1)ストリーミング(一方通行での授業形式)
①教材管理
②コンテンツ管理
③講師管理
④受講者管理
(2)インタラクティブ(相互対話による形式)
①受講者が提供する資料等への対応
②講師と受講者との直接的な接触への対応
3.サービス提供者による分類
(1)事業者が受講者に対して直接サービスを提供する場合
(2)事業者が講師と受講者との取引機会を仲介する場合
①職業安定法との関係
②ユーザ(講師、受講者)管理
③マネタイズの方法
4.弁護士に相談するメリット
5.当事務所でサポートできること
|
|





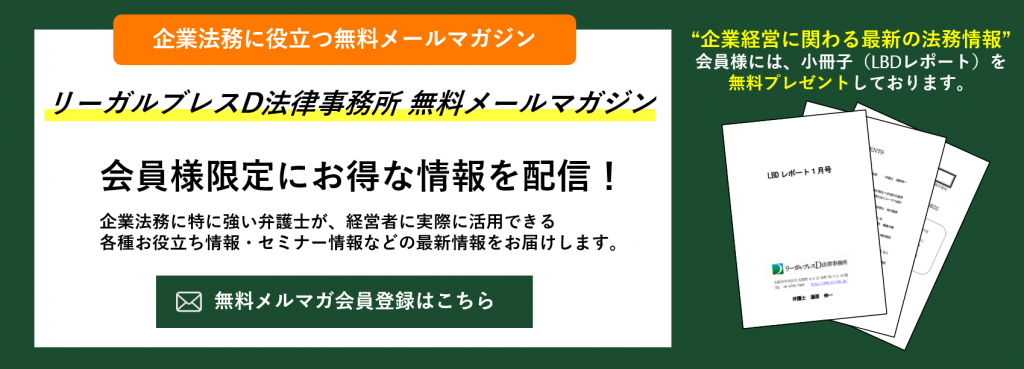

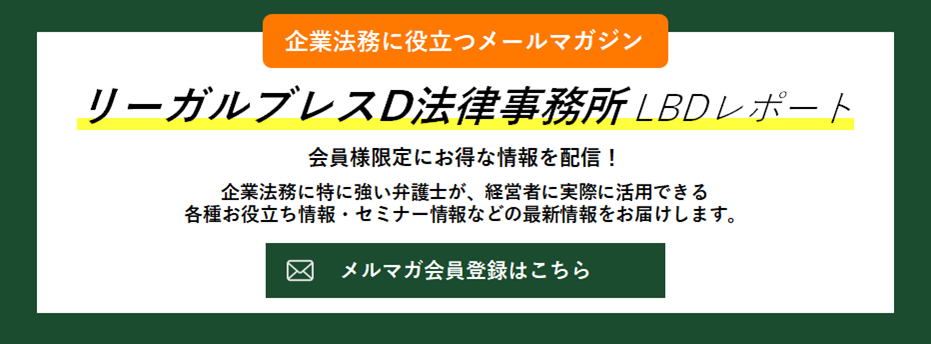
 弁護士 湯原伸一
弁護士 湯原伸一