Contents
【ご相談内容】
私は経営者です。
前配偶者と離婚後、新たなパートナーと出会い共同生活を営んでいますが、事実婚関係です。将来的には結婚も視野に入れていますが、前配偶者との離婚の際、財産分与を巡る紛争が長期化し、思った以上に財産を奪われたことがネックで、いざ結婚となると踏み込めない状態です。
現在は関係が良好とはいえ、将来パートナーとの関係が解消する場合も想定する必要があることから、自分の財産を確保できる対策を講じたいのですが、どのようなことをすればよいでしょうか。
【回答】
まず、誤解が無いよう先に指摘すると、内縁・事実婚等の言い方はともかく、男女の間で夫婦同様の関係が形成されている場合、その関係を解消する場合には財産分与の問題が生じてしまいます。
したがって、結婚していないから財産分与の問題は回避できると考えることは誤りであることを押さえておく必要があり、直ちに対策を講じるべきです。
さて、婚姻届を提出し法律婚を形成することが前提になっている場合、民法第755条に定める夫婦財産契約を締結することで、ご相談者のお悩みは解消できると考えられます。また、いわゆる事実婚状態を今後も継続する場合(婚姻届を提出する予定がない場合)、夫婦財産契約に準じた契約(本記事ではパートナーシップ契約と呼んでいます)を締結することで、やはり対処が可能です。
以下では、パートナーシップ契約を中心にしつつ、夫婦財産契約との関係性も意識しながら解説を行います。
【解説】
1.内縁や事実婚、同性婚に適用される法律関係
法律で保護されているのは「法律婚」のみです。
すなわち、何らかの事情で婚姻届が提出されていない場合、法律婚という取扱いはできないため、氏の統一、子の嫡出性、配偶者相続権などの効果を得ることができません(なお、税務の問題として、相続税に関する配偶者の優遇措置を得ることができない点もあげられます)。
しかし、法律婚には該当しないものの、婚姻の意思をもって共同生活を営み、社会的には夫婦と認められる実体がある場合(内縁や事実婚と呼ばれます)、共同生活による財産関係の処理に必要な法的効果(婚姻費用、財産分与など)は生じると解されています。
したがって、法律婚ではない場合であっても、本件のように自らの財産を保持したいと考えるのであれば、財産分与対策が必須となってきます。
さて、上記は異性間での関係性を前提に記述しましたが、最近では同性間でも婚姻関係に準じた共同生活関係を形成することが社会的に認知されてきています。もっとも、同性婚については、本記事作成時点(2023年1月)では、財産分与請求権を否定する裁判例が存在します。
社会情勢を考慮すると、同性婚であることを理由に財産分与が否定されるという結論が今後も維持されるとは考えにくいと執筆者個人は考えます。したがって、将来的に認められる場合に備えてはもちろん、仮に認められなかったとしても財産分与に準じた紛争を未然に防止するという観点から、同性婚の場合であっても、財産分与対策が必須になると考えられます。
本記事では、法律婚以外の夫婦類似の共同生活関係のことをパートナーと呼び、上記のような財産分与の問題はもちろん、それ以外にも共同生活を行っていく上で取り決めることが望ましい条件等につき、解説を行います。
2.パートナーシップ契約
呼称はともかく、法律婚以外の(夫婦同様の)共同生活関係に関するルールを定めるパートナーシップ契約は、法律上の根拠のある契約ではありません。
したがって、原則として当事者間で自由に内容を決めることができます。
以下は、せっかくパートナーシップ契約書を作成するのであれば、最低限定めておいたほうが良いと考えられる内容となります。
(1)パートナー関係の成立日
法律婚であれば、婚姻届を提出することで結婚の有無につき明確に判断することができます。しかしパートナー関係に留まる場合、いつの時点からパートナーとなったのか判然としません。
したがって、パートナーシップ契約では、いつからパートナーとなったのかを明確に定めておくことがポイントです。例えば、次のような条項です。
甲及び乙は、×年×月×日をもって、婚姻同様の関係を形成したことを確認する。
なお、「婚姻同様の関係」と表現しましたが、「夫婦同様の関係」あるいは「家族同様の関係」など様々な表現があると考えられます(例えば同性婚の場合、夫婦同様の関係…と表現するのに抵抗があれば別の表現を用いるなど)。
要は、いつから、どのような関係が形成されたのかが分かるようにすることがポイントです。
(2)財産の帰属(財産分与対策)
パートナーシップ等の名称はともかく、実態として法律婚に類似する関係が形成された場合、法律婚で認められる法的効果の一部が(類推)適用される場合があります。
その典型例が財産分与となるのですが、本件相談事例では、この財産分与が(類推)適用されてしまうことに強い懸念を持っています。この懸念を解消するためには、
- ①パートナーシップ契約を締結した時点で存在する財産は誰に帰属するかを明確に定めること(一方当事者単独に帰属する財産を「特有財産」と呼びます)
- ②パートナーシップ契約締結時に存在する特有財産のうち、共有財産に組み替えるものは何かを明確に定めること
- ③パートナーシップ契約締結後に生じた財産につき、何がパートナーと共有になる財産となるのか、何が一方当事者に帰属する特有財産となるのかを明確に定めること(その基準を定めること)
が重要なポイントとなります。
◆①について
契約時に存在する財産の帰属を定める条項例
甲及び乙は、×年×月×日前から有する財産のうち、次に定める財産は各人の特有財産であることを確認する。
(甲の特有財産)××
(乙の特有財産)××
パートナーシップ契約締結時点で、全ての特有財産を洗い出すことは難しいという場合、上記条項の末尾に「なお、本契約書に定めたものは例示に過ぎず、特有財産はこれらに限られない。」といった一文を挿入し、たとえ契約書に明示されていない財産であっても、特有財産であることを後で主張できる余地を残すといった対策を講じることになります。
ただ、本当に後で特有財産として認められるのかは疑義が残るところであり、可能な限り具体的に明示したいところです。
なお、特有財産をパートナーに全て開示することに心理的抵抗があると考える方もいるようです。一般論としては、信頼できるパートナーを選んだ以上、心理的抵抗よりも法的な確実性を重視するべきではないかと考えるのですが、最終的にはご本人の判断で決めるほかありません。
次に上記条項例に関連する問題として、例えば、特有財産が収益物件であり賃料収入が発生している場合、あるいは特有財産が上場株式であり配当収入が発生している場合など、特有財産から派生する財産についても、特有財産に該当するのかを決めておくことが無難です。
例えば、次のような条項が考えられます。
- (例)
甲及び乙は、特有財産の果実(利息、配当、賃料等が含まれるが、これらに限られない)についても、特有財産に含まれることを確認する。
さらに上記条項例に関連する問題として、特有財産を担保にした借入金を原資に新たに取得した財産が生じた場合、あるいは特有財産の売却金を原資に新たに取得した財産が発生した場合など、特有財産が別の財産に置き換わった場合についても、特有財産に該当するのか決めておくことが無難です。
例えば、次のような条項が考えられます。
- (例)
甲及び乙は、特有財産を担保、交換、売却、譲渡、その他処分を行うことで取得した金員を原資として取得した財産についても、特有財産に含まれることを確認する。
◆②について
特有財産を共有財産に組み替えることを定める条項例
甲及び乙は、各自の特有財産を下記に定める方法により、共有財産とすることができる。
記
・甲乙が定めた口座(×銀行×支店の×名義口座)に金員を送金する方法
・各当事者が購入した家具及び家電製品を共同生活する住居内に持込む方法。但し、特有財産に該当するものとして本契約書に明記したものは除く。
上記はあくまでも一例にすぎませんが、相当面倒な手続きと考えられます。
しかし、財産分与対策を考えるとどうしても外せない条項であり、かつ必ず条項通りで運用してほしい内容となります。
なぜなら、一方当事者の業務遂行による役員報酬債権や賃金債権は特有財産であることは明らかなのですが、役員報酬や賃金が一方当事者名義の銀行口座に振り込まれ、その銀行口座より共同生活のための費用支出を行っていた場合、その銀行口座は共有財産であるという推定が働くからです。
つまり、パートナーシップ契約締結以前より、一方当事者が利用していた一方当事者名義の銀行口座であっても、パートナーシップ契約締結後は共同生活のために利用していた以上、その銀行口座にある金員はもはや一方当事者のためだけではないと解釈される恐れがあるということです。
当然のことながら、共有財産である以上、パートナーシップ解消の事態が生じた場合は財産分与の対象とせざるを得ません。
この点はかなり疎かになりがちなので、是非注意してほしいところです。
◆③について
パートナーシップ契約成立後の財産帰属の判断基準を定める条項例
1.甲及び乙は、パートナーシップ契約締結後に別居又はパートナー関係解消後のいずれか早い日までに取得又は形成した財産、及び特有財産を共有財産として取り扱うことに合意した財産は、共有財産とすることを確認する。
2.前項にかかわらず、下記財産は特有財産とすることに合意する。
記
・相続又は贈与により取得した財産
・本契約において特有財産と定めた財産。但し、共有財産として取り扱うことに合意したものは除く。
・共同生活する住居内に持込んだ家具及び家電のうち、特有財産を原資として購入したものであって、その購入額が×万円を超える財産
・甲の事業のために取得した車両、及び×内に設置された機器
・甲が取締役に就任している法人が発行する株式、新株予約権及び転換社債
・××
最初に断っておきますが、相続及び贈与により取得した財産は当然に特有財産であり、あえてパートナーシップ契約書に定めておく必要はありません。ただ、当事者間の認識を明確化するためにあえて定めています。
その他については、共有財産に含まれておかしくないものを、あえて特有財産とすることを定めた内容となります。もちろん一例にすぎず、パートナー間の実情に応じて、他にも色々な基準を定める必要があります。
なお、この条項を特に意識していただきたい当事者属性があります。
例えば、個人事業主(例えば個人の開業医など)の場合、事業用資産が財産分与の対象とされてしまうことは今後の事業遂行上大きな問題となりますので、明確に共有財産より除外する旨定めておくことが重要となります。また、ベンチャーキャピタル等より投資を受けている経営者の場合、株式の保有が重要な契約条件となっており、財産分与の対象となった場合は投資契約上の問題も新たに生じかねないことから、やはり明確に定めておく必要があります。
上記以外に、「①」で解説した、
- 特有財産より生じた果実
- 特有財産を原資とした代替物
についても、パートナーシップ契約の締結前後を問わず、特有財産として保有したいというニーズがあるかと思われます。この場合、疑義を避けるためにも、次のような文言を追加することで対処することが考えられます。
- (例)
甲及び乙は、『本契約締結前後を問わず、』特有財産の果実(利息、配当、賃料等が含まれるが、これらに限られない)についても、特有財産に含まれることを確認する。 - (例)
甲及び乙は、『本契約締結前後を問わず、』特有財産を担保、交換、売却、譲渡、その他処分を行うことで取得した金員を原資として取得した財産についても、特有財産に含まれることを確認する。
(3)共同生活のための費用
法律婚の場合は「婚姻費用」という言葉を用いることが通常ですが、内容的には同じことです。例えば、次のような条項が考えられます。
1.甲及び乙は、共同生活のために必要となる費用(食費、衣料費、水道光熱費、通信費、住居費、子の監護教育費、生命保険料、社会保険料などを含む日常生活を維持する上で必要なる費用のこと)として、毎月次の通り負担する。
・甲…月額×円
・乙…月額×円
2.甲及び乙は、前項に定める負担金について、当月分を前月末日までに甲乙が定めた口座(×銀行×支店の×名義口座)に送金して支払う。
3.甲及び乙は、前項に定める口座より、共同生活のために必要となる費用を支出する。
4.甲及び乙は、交際費、高価品の購入費(購入額が×円以上のものをいう)、化粧品購入費、美容医療費、その他自らの便益のみに支出する費用について、各自の特有財産より支出することに合意する。
5.病気又は怪我等により高額の医療費負担が生じた場合など、共同生活のために必要となる費用が増大した場合、甲乙協議の上、第1項に定める負担額を変更することができる。
6.収入の激減など経済事情の変動により、第1項に定める負担額を支払えない事態となった場合、一方当事者は相手方に対し、負担額の変更協議を求めることができる。
いわゆる生活費については、上記のような事細かなルールを定めることは稀かもしれません。しかし、例えば、特有財産と共有財産を明確に分離しておかないことには、特有財産と認識していた財産が共有財産であると認定され、財産分与の対象になってしまうというリスクを避けることができません。
したがって、パートナーと信頼関係をもって生活するとはいえ、一方で自らの財産を保全したいのであれば、上記例のような生活費の負担ルール、支払方法等については適切に定める必要があります。そして、何よりも、契約で定めた通りに運用していくことが極めて重要となります。
なお、パートナー関係の場合、やや考えにくいところがあるのですが、何らかの事情でパートナー関係の解消とまではいかないものの、共同生活を維持することが難しくなる期間(別居期間)というものが想定されるかもしれません。この場合、次のような条項を定めることも考えられます。
ただし、いわゆる婚姻費用は算定表に基づいて算出されることが通常であるところ、パートナー関係の生活費についても、婚姻費用に準じて算定表を基準に算出される可能性は十分想定されるところです。このため、パートナーシップ契約に定めた内容は、合意事項として一定程度尊重はされるものの、その金額が算定表から導かれる金額と乖離する場合、裁判等で変更される場合があり得ることを念頭に置く必要があります。
- (例)
別居からパートナー関係の解消に至るまでの期間中、甲は乙に対し、×円を上限として生活費を支払う。但し、別居が乙の責めに帰す事由による場合、甲は当該費用の支払い義務を負わない。
(4)子供
法律婚ではないパートナー間で子供を授かった場合、まず考えなければならないのは、その子供との間で法的な親子関係を構築するのかという点です。
したがって、次のような条項が必須になると考えられます。
甲は、甲乙間に子が出生した場合、直ちに認知手続きを行う。
ところで、認知手続きは甲と子供との間の親子関係を法的に発生させるにとどまり、甲は親権者となるわけではありません(乙が分娩した場合は、当然に乙が親権者として取り扱われます)。もし甲が親権を取得したいと考えた場合、親権変更の手続きを行うか、法律婚を選択するといった方法を考える必要があります。
上記以外に、子供の教育方針などで取り決めておくべき事項があるのであれば、その点をパートナーシップ契約書に定めておくことも一案かもしれません(いわゆる紳士協定に過ぎず、これ自体に法的効果は発生しないと考えられますが)。
さて、何らかの事情でパートナー関係が終了し、乙が子供の面倒を今後も見続ける場合、甲はその子供に対して養育費を支払う必要が生じます。この点を想定して、パートナーシップ契約書に養育費に関する取り決めを書いておくことも一案かもしれません。
ただし、養育費についても算定表を用いて算出されることが通常であり、パートナーシップ契約書に定める養育費が、あまりにも算定表より導かれる金額と乖離する場合は裁判手続きで変更される可能性が高いことを想定する必要があります。
- (例)
甲は、甲乙間の子である×(×年×月×日生)のための養育費として、次の条件にて支払う。
(支払期間)子が満18歳となる日が属する月まで
(支払額)パートナー関係終了時点における甲乙各自の収入を前提に、家庭裁判所が用いる標準算定方式にて算出される金額
(支払方法)×名義の口座に振込み送金(送金手数料は甲負担)
上記以外にも、いわゆる子供のための塾代・お稽古代等の負担について取り決める、学費の負担について取り決める、といったことが考えられます。
また、乙が再婚等した場合は養育費額を調整することを取り決めることも考えられます。
さらに、金銭以外の子供との関係として、面会交流の方法などを定めておくことも考えられます。
(5)パートナー関係の解消
法律婚の場合、離婚届の提出によって婚姻関係が終了したことを一義的に判断することが可能ですが、パートナー関係の場合、何をもって終了と取扱うのか分からないところがあります。
そこで、パートナー関係の解消を明確化するべく、次のような条項を定めることが考えられます。
甲及び乙は、パートナー関係を解消する場合、次に定める2つの事項を実施する。
①パートナー関係を解消する旨書面で通知すること
②共同生活する住居を退去し、別居を開始すること
別居を開始すればパートナー関係は解消されたと考えてよいのでは…という考えも有り得るところなのですが、明確な判断基準を設けるという観点から、上記例では書面通知と退去した上での別居という2要件を定めました。
もちろん、これにこだわる必要はありませんので、事情に応じて定めることが肝要です。
(6)解消後の処理
上記「(2)財産の帰属(財産分与対策)」と裏表の関係になるのですが、パートナー関係が解消となった場合、財産分与手続きを避けて通ることはできません。
ただ、避けて通ることはできませんが、あらかじめ財産分与に関するルールを定めておくことで、スムーズな処理を行うことが可能となります。
例えば次のような条項を定めておくことが考えられます。
1.甲及び乙は、相手方の特有財産に対し、財産分与請求権及び共有持分権を有しないことを相互に確認する。
2.甲及び乙は、パートナー関係を終了させる場合、協議による場合、裁判所等の第三者機関が関与する手続きによる場合を問わず、共有財産のみが財産分与請求権の対象となることを相互に確認する。
3.甲及び乙は、共有財産に対する財産分与につき、甲が×、乙が×の割合とすることに合意する。
特有財産は財産分与の対象とならないこと、共有財産は財産分与の対象になることを前提に予め割合を定めておくことで、紛争の防止に役立てようとする条項となります。
ただ、繰り返し解説していますが、特有財産を主張するためには、パートナーシップ契約書に定めた通りの運用実績が必要であり、この運用実績がない又は不十分の場合、いくら上記のような条項を定めたところで、財産分与の対象となる共有財産の範囲が変更される可能性(パートナーシップ契約書に定める通りにならないこと)が生じることに注意が必要です。
また、上記例ではあえて財産分与の割合を明記していますが、5:5以外の割合を定める場合、なぜそのような割合を採用したのか合理性を裏付ける説明資料がないことには、裁判手続きでは修正されてしまう可能性が高いことを想定する必要があります。
なお、非上場会社の自社株のような処分困難なもの(処分をしたくないもの)が財産分与の対象となる場合を考慮して、代償金の支払いによって財産分与手続きを進めること、評価に要する費用は双方負担とすること、評価額より算出される分与額について一定期間内に分割して支払うこと等をあらかじめ定めておくことも一案かもしれません。
3.夫婦財産契約との関係
夫婦財産契約という言葉など聞いたことがないという方も多いかもしれません。しかし、いわゆるセレブ層を中心に、最近では徐々に浸透しつつある契約であり、婚前契約やプレナップ契約と呼ばれたりすることもあります。
この夫婦財産契約ですが、実は民法第755条に根拠がある契約であり、法律婚を行うことを前提に、夫婦間で共同生活を営むための合意事項を定めた契約となります。
(1)夫婦財産契約の要件
夫婦財産契約を締結できるのは婚姻前です。
この点が、上記のパートナーシップ契約と決定的な違いとなります。
(2)内容
夫婦財産契約を定める目的は、法定財産制(民法第760条から第762条)の適用を排除し、当事者の合意事項を優先させるという点です。
ちなみに、民法第760条は婚姻費用の分担、民法第761条は日常家事債務の連帯責任、民法第762条は夫婦間の財産の帰属に関する条項となります。
どのような合意内容を定めるべきかについては、上記2.のパートナーシップ契約で解説した
- (2)財産の帰属(財産分与対策)
- (3)共同生活のための費用
- (6)解消後の処理
がそのまま当てはまります(なお、(4)についても、子の認知以外の事項は当てはまります)。またこれ以外にも、婚姻生活に関連した様々な事項・ルールを定めておくことも可能です。
ところで、当初は婚姻届を提出する予定が無かったので、パートナーシップ契約書を作成するだけであったが、事情により婚姻届を提出し法律婚に変更する事態となった場合、パートナーシップ契約を夫婦財産契約に移行させることはできないのでしょうか。
この点、裁判例はもちろん確定的な解釈論もない状態です。
したがって、リスクを完全に排除することはできませんが、パートナーシップ契約書に夫婦財産契約として転用可能である旨定めることで、一応の根拠を持たせるといった対処法が考えられます。例えば、次のような条項が考えられます。
- (例)
パートナー関係が継続中において、甲及び乙が民法に基づき法律上の婚姻をすることに合意した場合、本契約は民法第755条に定める夫婦財産契約として引き続き効力を有することを相互に確認する。但し、第×条についてはこの限りではない。
(3)無効となる場合
上記(2)で記載した通り、夫婦財産契約を締結することで、法定財産制の適用を排除することが可能です。ただ、当事者間で合意した事項が全て優先するという訳ではなく、公序良俗違反などが認められる場合は合意内容が無効となります。
例えば、財産分の割合について0:10と定めたとしても、婚姻後に形成した共有財産について一方当事者の寄与が全く認められないという事態は想定しづらいことから、当該合意は無効になると考えられます。
他にも、例えば、一方当事者が申し入れれば、当然に離婚に応じなければならないといった定めや、扶助義務を否定する定めなども無効になると考えられます。
(4)注意点
婚姻後に夫婦財産契約を行うことはできません。しかし、民法第755条に定める夫婦財産契約ができないだけであって、婚姻後に何らかの合意を行い、その内容を契約化することは当然可能です。
もっとも、婚姻後の契約はいつでも取消可能とされている点に注意が必要です(民法第754条)。
ただ、この取消権については、形式的には婚姻中であっても、実質的には婚姻関係が破綻している場合には行使できないと考えられています)。したがって、夫婦関係が円満なときに合意した事項を、離婚に向けた協議段階で当該合意事項を取り消されるということは考える必要はないと思われます。
ところで、婚姻後の合意事項は夫婦財産契約として取り扱われません。したがって、婚姻後に法定財産制に関する取り決めを行っていると解釈される限り、当該条項は無効と判断されることになります。当事者間では法定財産制に関する取り決めではないと考えていたとしても、法的効果を検証した場合、法定財産制に関する取り決めと解釈せざるを得ない場合がありますので、注意が必要です。
また、婚姻前に夫婦財産契約を締結したとしても、婚姻後にその夫婦財産契約の内容を変更することはできません(民法第758条第1項)。もっとも、民法第758条第1項は、法定財産制に関する合意事項を婚姻後に変更することを認めないというだけに過ぎません。
したがって、法定財産制以外の合意事項については、婚姻後であっても変更可能です。なお、合意事項が法定財産制以外の事項と言えるのかは、当事者では判断しづらいという難点があること、上記の夫婦間の取消権で解説したことと同様です。
最後に、これは巷にある誤解を解くという趣旨ですが、夫婦財産契約を公正証書で作成することは要件とされておらず、公正証書以外の書面であっても有効です(ただし、公正証書を作成したほうが有効性を担保しやすいところはあります)。
ちなみに、登記をしていなくても契約それ自体は有効です。ただし、登記をしない場合、夫婦以外の第三者に対して対効力を有しないことから、例えば日常家事債務の連帯責任などを排除することが難しくなるといった問題が生じ得ます。
4.当事務所がサポートできること
夫婦財産契約及びパートナーシップ契約は、将来関係性を解消することを念頭に置いた契約であり、相手当事者からすれば色々と思うところがあるかもしれません。
しかし、例えば…
- 個人事業主で事業用資産と個人資産の分離が難しい場合
- ベンチャーキャピタル等の第三者と経営者との契約により、特有財産の明確化を図る必要がある場合
- 前配偶者との間に誕生した子供に一定の財産を残したい場合
といった事情がある場合、夫婦財産契約又はパートナーシップ契約を締結しておかないことには、自らの希望を叶えることができません。
契約書の作成はもちろんのこと、相手当事者への提案の仕方や説得法などを相談したい方は、当事務所までお声掛けください。
<2023年1月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
|
|






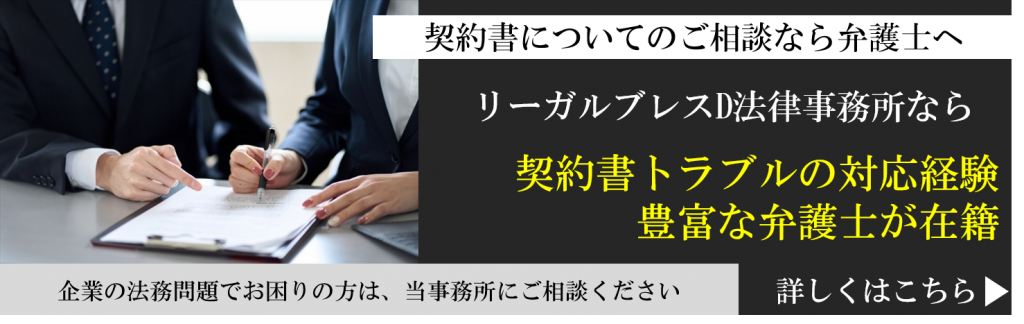

 弁護士 湯原伸一
弁護士 湯原伸一





































