Contents
【ご相談内容】
何らかの法的紛争が発生し弁護士に相談した際、ときどき「費用倒れになりますよ」とか「弁護士費用が無駄になる可能性がありますよ」等と言われることがあります。
もともと無理筋な事案の場合は何となくは理解ができるものの、一方で明らかに当社に理があると認識している場合、何を基準に費用倒れになると発言しているのか分からないときもあります。
法的紛争に対応するために必要となる損得勘定(費用対効果)の考え方について、弁護士からの視点で教えてください。
【回答】
相談者が法的権利を行使したいと考えていても、弁護士は、①法的請求が認められても、現実的なお金を取得することが難しい、②法的請求が認められるものの、相談者が期待するような金額とはならない、③法的請求が認められる可能性が極めて低い、といった様々なことを考慮し、費用倒れになる可能性を含めてアドバイスを行っています。
もちろん、現実にお金をとれるか取れないかの問題ではない(経済的合理性は度外視する)と言う相談者もいます。しかし、結果的に相談者に負担しか生じないような案件の場合、果たして弁護士報酬をもらってよいものかと悩んでしまうのも事実です。
法と経済学といった理屈の話ではなく、あくまでも執筆者個人の「法律問題に対処するために負担しようとしている費用は、割に合うものなのか」という単純発想の考え方をベースに以下解説を行います。
なお、ときどき「弁護士費用は相手から回収してほしい」、「着手金無料の完全成功報酬で対応してほしい」といった希望を述べる相談者もいますが、本記事では検討対象外としています。
【解説】
以下では、具体的な事例を想定しながら、損得勘定の考え方について解説します。
1.金銭請求(債権回収、損害賠償)
(1)債権回収(相手方無資力)
(事例)
取引先に対して商品を売渡したところ、支払約定日を経過しても代金を支払ってこなかった。何度か連絡を取っているものの、最近では連絡さえ取れない状況となっている。
なお、取引先作成の発注書及び商品受領書はもちろんこと、支払い延期要請書などの証拠書類は準備できている。
(現時点で予想される負担)
商品代金が未回収となりますので、次のような損失が生じることになります。
- ①商品の仕入費、商品の製造費などの原価相当分
- ②商品を販売したことに得られた利益相当分
(追加で必要なる負担と損得勘定)
債権回収手続きを行う場合、自社で対処できるものとして通知書(支払催告書)の送付というものがあげられます。そして、警告度合いをあげる意味で内容証明郵便形式にて郵送することが多いと考えられます。したがって、
- ③配達証明付き内容証明郵便(通常は2,000円前後)
が追加費用として発生する可能性があります。
また、自社では如何ともしがたいとなった場合、弁護士に債権回収手続きを依頼する場面が出てくるかもしれません。その場合、当然のことながら弁護士費用が発生します。
- ④弁護士費用
上記のような費用負担を考慮しつつ、いわゆる費用倒れにならないようにするためには、次のような損得勘定を考慮する必要があります。
【実際に回収できる代金額(①②)】 > 【債権回収手続きに要する費用(③④)】+【諸経費(例えば訴訟手続きに踏み切る場合であれば印紙代や郵券代など)】
(金銭負担を軽減するための視点)
請求額にもよりますが、一般的には請求額が20万円以下となると弁護士費用だけで請求額に近い金額となる場合もあり、費用倒れになる可能性は否めません。
本件事例のような証拠書書類がそろっており、請求額が60万円以下であれば簡易裁判所管轄となりますので、弁護士に書類作成のみ依頼し、裁判所への出頭は会社担当者に行ってもらうといった方法で費用削減を図るということも一案です(会社担当者は簡易裁判所の許可を得て代理人になることができます)。
また、裁判手続きの1つとして、書面の提出だけで判決同様の効果が得られる支払督促手続きというものもありますので、やはり書類作成のみ弁護士に依頼し、費用削減を図るということも検討してよいかもしれません。但し、支払督促手続きの場合、取引先より当該手続き中に異議を出されてしまうと、通常の裁判手続きに移行してしまいます。この場合請求額が60万円を超えている場合は会社担当者が代理人となることができませんので、社長自らが裁判所に出頭して対応するか、または弁護士に費用を支払って代理人に就任してもらい対処してもらうことが必要となることに注意が必要です。
(2)損害賠償(具体的な損害額の算定)
(事例)
運送業を営んでいる会社の代表者が、荷主より預かった商品等を配送するため自ら配送車両を運転していたところ、追突事故の被害にあった。なお、社長は、自ら配送ドライバーとして現場業務に従事する者であると共に、会社内で唯一の営業担当者でもあった。
上記交通事故の結果、社長個人の人身損害及び車両の物件損害の発生は当然のこととして、会社にも様々な損害が発生した(例えば、事故当時に配送中であった商品を届けることができないことで荷主に対し多額の違約金支払い義務が生じたこと、会社がコンペ等を通じて新規の配送案件を受注することができず逸失利益が生じたこと、車両保険を用いたため保険料率が変更となり保険料の負担が増えたこと等)。
社長としては、会社に生じた損害賠償請求を加害者に対して行っているが、加害者は損害賠償義務がないとして協議に応じない状況である。
(現時点で予想される負担)
交通事故損害賠償の問題として検討した場合、次のように整理できます。
- ①社長個人の人身損害(治療費、慰謝料など)
- ②車両の物件損害(修理費など)
- ③会社の経済的損害(上記事例では、配送遅延による違約金、逸失利益、増加保険料など)
(追加で必要となる負担と損得勘定)
加害者が、上記③に関する損害賠償交渉に応じないことから、弁護士に依頼したり、訴訟提起したりする場合は、別途次のような負担が生じる可能性があります。
- ④弁護士費用
- ⑤諸経費(訴訟手続きの場合であれば印紙代、郵券代など)
さて、損害賠償請求に関する損得勘定を検討する場合、
「加害者より回収できる金額>損害賠償要求額(③)+経費(④⑤)」
と考えるかもしれませんが、やや誤りがあります。
なぜならば、損害賠償問題を考える場合、ⅰ)要求する損害費目が法律上の損害といえるのか、ⅱ)具体的な損害金額はいくらと法律上算定するべきなのか、という検証を行う必要があるからです。
本件事例でいうと、交通事故被害にあったのは直接的には社長個人であり、会社ではありません(但し、被害車両が会社名義である場合、車両損害に限っては会社も直接の被害者と言えます)。すなわち、会社は間接的な被害者という位置づけになりますので、会社が被ったと主張する損害費目が、ⅰ)法律上の損害といえるのか大きな問題となりうるからです(間接損害と呼ばれる問題となります)。また、法律上の損害に該当した場合であっても、具体的な損害額の算定方法が法的ルールに則ったもので算出された金額なのかについても、損害賠償の交渉及び訴訟実務では大きな問題となることも多くあります。
したがって、正確な意味での損得勘定の検証としては、次の2ステップを踏まえることになります。
・被害者の主観的期待値を超えるのかという意味で…
【法律上認められる損害額】-【被害者が想定している損害額】>0
(※残念ながら0以上になることはほぼ無いことから、マイナス幅が被害者の許容範囲に収まるのかという視点のほうが重要になってきます)
・法的検証を踏まえての経済的損得という意味で…
【実際に加害者より回収できる金額】-【法律上認められる損害額】≒【経費】
(※経費、特に弁護士費用については、訴訟外の交渉で解決した場合は加害者より回収することはほぼ不可能、訴訟手続きを通じて解決した場合であっても一部の弁護士費用しか認められないため、「<」になることが通常です。差異をどこまで抑えられるかがポイントになります)
(金銭負担を軽減するための視点)
損害賠償問題は、被害者が主観的に考えている損害金額と法律上認められる損害金額とのギャップが大きく、このギャップを理解しないまま損害賠償交渉を進めていくと、被害者にとっては“損した気分”が大きくなることになります(法律上認められる損害額の検証を行わないまま、被害者の要求金額通りに手続きを進めた場合、弁護士費用や諸経費が高額になる傾向があります)。
したがって、弁護士に依頼する場合であれな、いきなり損害賠償交渉や訴訟代理の依頼を行うのではなく、まずは法的な損害として認められる可能性があるのか、上認められるとして具体的な損害額はいくらなのかのシミュレーションすること、すなわち法律相談に限定して対処することが、無駄な費用を抑えるポイントになります。
また、被害者が加入している保険(損害保険のみならず生命保険も含めて)によっては、法律上認められない損害について保険金で一部カバーできたり、弁護士費用について保険金でカバーされていることもありますので、保険内容を精査することも重要です。
なお、損害賠償問題の場合、最終的には、被害者自らが考える損害額と法律上認められる損害額とのギャップをどのように評価するのか(例えばギャップが埋まらない場合、弁護士費用等が無駄になってもいいと割り切って金銭負担を行うのか)が、被害者の負担感に対する大きな考慮要素になるものと考えられます。
2.人事労務(不当解雇、労働組合介入)
(1)不当解雇
(事例)
普段より反抗的な態度を取り続けている従業員(月額賃金25万円)に対し、「もう明日から来なくてもよい」と社長が告げたところ、翌日より出勤しなくなった。そして1週間後、当該従業員の代理人弁護士より、不当解雇であるとして内容証明郵便が送られてきた。
会社も代理人弁護士を選任し、弁護士間で協議を行ったところ、3ヶ月後に合意退職することで解決を図ることができた。
(現時点で予想される負担)
不当解雇=解雇が無効であるという主張ですので、現在も雇用契約は継続していること、会社の責任により業務従事(労務の提供)ができないという内容が主だった事項となります。
なお、パワーハラスメントを受けていたことによる慰謝料等の要求も付随することもよく見かけます。したがって、解雇に正当性がないという仮定で予想される金銭負担としては次のようなものとなります。
- ①解雇した日から職場復帰までの期間中に相当する賃金全額として75万円
- ②(パワハラがあった場合)慰謝料として30万円程度(なお、慰謝料については事案によりますので一律ではありません)
(追加で必要となる負担と損得勘定)
解雇に正当性がないことを前提に、しかし協議の結果、合意退職で解決となった場合は上記以外に次のような金銭負担が見込まれます。
- ③退職してもらうための解決金(手切金?)として150万円程度(賃金6ヶ月分相当額。なお、この解決金については事案に応じて増減するため一律とはなりません)
- ④弁護士費用として30万円程度(弁護士費用についても、各弁護士によって報酬体系が異なるため一律とはなりません)
※事例に関しては合計255万円程度の負担を覚悟する必要あり
なお、従業員に代理人弁護士が就いた場合、未払い残業代の要求が同時に行われることも多い傾向があります。万一、残業代の支払い漏れがあった場合は、⑤未払い残業代の負担(民法改正前の2年の時効期間を前提にしても100万円前後の未払いとなる事例は少なくありません)が追加で発生します。
また、合意退職で解決を図る場合、一般的には会社都合退職として処理します。会社都合とした場合、すでに支給を受けている助成金の返還を行政より求められることもあり、⑤返還相当額の負担も覚悟する必要があります。
以上のような事項を検討し積算すると、最終的には従業員1名に対する1年間の人件費相当額の負担が生じることも珍しくないことになります。
結局のところ、解雇を実行するのであれば、解雇の正当性を十分裏付けることが可能という前提のもと、次のような損得勘定を検討する必要があります。
【不当解雇で支払いを余儀なくされる費用(①~④】-【弁護士費用(④)】≒0
※弁護士費用は必要経費扱いにしています
なお、解雇で争われてしまうと諸々の費用が発生しますので、できる限り退職届を書いてもらって辞めてもらうという作戦をとるのが穏当です。この観点からすると、次のような損得勘定も考慮したいところです。
【不当解雇で支払いを余儀なくされる費用(①~④】 > 【退職勧奨による負担(上乗せ退職金等のプレミアム分を含む)】
(金銭負担を軽減するための視点)
元も子もありませんが、解雇という手続きを取るのではなく、退職後の一定期間の生活保障(数ヶ月分の賃金相当額の支払い)の条件提示を行いつつ、粘り強く説得(退職勧奨)して、退職届を出してもらうことが、負担の少ない対処法となります。
なお、不当解雇であるという要求が出てきた場合、急いで弁護士に相談し、なるべく早期解決を図る方針で臨んだほうが、費用負担の軽減を図りやすくなります(紛争解決までに時間がかかるほど、上記①に記載した金額が膨れ上がるため)。要求を無視し放置する、あるいは法的には難しいといわざるを得ない主張に拘泥し裁判手続きにまで至った場合、上記で記載した金額以上の負担が生じリスクがあることを想定する必要があります。
(2)組合対応
(事例)
問題行動の多い従業員に対し、やや強めの改善指導と退職を促す提案を行ったところ、労働組合が介入し、団体交渉申入れを行ってきた。
部外者である労働組合に対する嫌悪感から、会社は労働組合からの要求を無視し続けていたところ、労働組合は不当労働行為救済申立て(あっせん)手続きを行うと共に、会社の近隣で街宣活動を行うようになった。
(現時点で予想される負担)
労働組合が要求している内容は、本来的には団体交渉すなわち協議の場の設定にすぎません。
しかし、団体交渉を実施しなかった場合、あるいは団体交渉を実施したとしても中身のない協議に終始した場合(不誠実団交)、労働組合の活動はエスカレートします。その結果、街宣活動や労働基準監督署等への調査要請、会社取引先への申入れ等といった(あえて明記しますが)会社に対する嫌がらせ行為を乱発させてきたりします。一方で不当労働行為救済申立と呼ばれる裁判手続きに類似した手続きを申立ててきたりします。
結局のところ、労働組合とどのように向き合えばよいのか分からない、どういった対策を講じればよいのか分からない場合、専門家に相談して対処するほかありませんので、最低でも次の費用は発生することになります。
- ①弁護士等の専門家への相談費用
(追加で必要となる負担と損得勘定)
労働組合が団体交渉要求を行い続ける以上は…
- ②団体交渉開催に要する諸経費(貸会議室利用料として1回当たり2万円程度、出席従業員に対する1回当たり賃金1万円弱など。なお、貸会議室利用料は場所により変動が生じます。また、団体交渉は業務時間外に開催することが多いことから、会社従業員を出席させる場合は残業代が発生することが通常です)
- ③団体交渉対応のために弁護士に依頼した場合は弁護士費用(着手金30万円程度、立会日当として1回当たり5万円程度。なお、弁護士費用は各弁護士によって報酬体系が異なるため一律とはなりません)
が団体交渉開催ごとに負担する必要があります。なお、団体交渉が1回で終わるということは通常ありえないため、複数回の開催を想定する必要があります。
また、不当労働行為救済申立手続きが開始した場合…
- ④不当労働行為事件対応のために弁護士に依頼した場合は弁護士費用(着手金30万円程度、立会日当として1回当たり5万円程度。なお、弁護士費用は各弁護士によって報酬体系が異なるため一律とはなりません)
を想定する必要があります。
ちなみに、不当労働行為救済申立手続きについては、弁護士への依頼が絶対に必要とされているわけではありません。したがって、会社内で担当者を割り当てて対処することも当然可能です。ただ、不当労働行為救済申立手続きは高度な専門的知識が必要となるため、会社内の担当者のみで対処するのは正直難しいのではないかと予想します。
ちなみに、上記は団体交渉や不当労働行為救済申立手続きへの対応費用として想定されるものにすぎず、問題従業員と何らかの解決を図るための金銭負担については含まれていません。仮に合意退職による解決を図る場合、例えば上記(1)で記載したような解決金の支払いが別途必要となります(解決金の相場については、労働組合が介入した分、若干高くなる傾向があります)。
なお、街宣活動等の組合による会社への嫌がらせ行為に何らかの対処を行う場合、対処内容に応じて費用負担が生じることになります(様々な対処法が考えられるため、一律の費用設定を行うことが困難です)
結局のところ、労働組合が介入してきた場合、団体交渉への対応費用は必要経費と割り切ったうえで、次のような損得勘定を検討することになります。
【団体交渉への対応のみで必要となる費用(①~③)】-【団体交渉対応、及び団体交渉以外に紛争が拡大した場合に必要となる費用(④など)】≒0
(金銭負担を軽減するために)
労働組合が介入してきた場合、団体交渉を適切に開催し、協議を十分に行うことが何より肝要です。会社として根拠を示しながら説明を行う限り、労働組合としても、安易に不当労働行為救済申立を行いませんし、街宣活動等の嫌がらせ行為に打って出ることは控えるようになります。紛争を拡大化させないだけでも、かなりの費用削減につながると考えられます。
ちなみに、労働組合が介入した場合、会社として一番失う財産といえば“信用(無形財産)”となります。金銭評価が難しいのですが、労働組合が取引先に対して「救済要請」などと言いながら告げ口する行動は、取引先としても迷惑千万ですし、こんなややこしい会社とは付き合いたくないと考えたくもなってしまいます。もちろん、こういった労働組合の嫌がらせ行動に対する対処法はありますが、費用負担もさることながら、無駄な時間と労力を消費している感も否めません。
団体交渉に対しては適切に対処し協議を行うというスタンスが金銭負担軽減に直結することを念頭に置いていただければと思います。
なお、団体交渉に要する諸経費(弁護士に依頼した場合は弁護士費用)については、あえて言うのであれば、必要経費として割り切るしかないと思われます。
3.取引の一方的打切り
(1)契約締結上の過失
(事例)
小売業者より「PBブランドの商品化に成功した場合には製造発注をお願いしたい」という説明を受け、製造業者は、当該小売業者と協議を約1年行うと共に、試作品の製造、商品製造のための機械工具等の導入、新たな人員の雇入れ等の準備を行った。結果的に商品化に成功したものの、当該小売業者は、製造業者に発注を行わず、第三者に製造依頼を行うに至った。製造業者は抗議したが、小売業者は契約書がないことを盾に一切の話し合いに応じようとしない。
(現時点で予想される負担)
製造業者としては、小売業者からの説明を信頼し、時間と労力そしてお金をかけて商品化の準備を進めてきました。この結果、次のような負担を行い、当該負担分が損失となっている状態です。
- ①商品化のために要した作業賃
- ②機械工具等の購入費及び維持管理費
- ③新たに雇用した人員の人件費
(追加で必要となる負担と損得勘定)
一方、小売業者は話し合いに応じない以上、訴訟も見据えて弁護士に依頼しないことには事態が動くことはないと考えられます。ただし、弁護士に依頼した場合、当然のことながら弁護士費用が発生します。
上記状況下で、製造業者として検討するべき損得勘定としては次の通りであり、この算式通りにならないと見込まれる場合は、かえって損失を拡大させるだけになってしまいます。
【小売業者より回収できるお金】 > 【すでに投資したお金(①②③など)】+【弁護士費用】+【手続き経費(訴訟であれば印紙代、郵券代など)】
(金銭負担を軽減するための視点)
取引候補者の言動を信頼し、お金をかけて取引準備を行っていたところ、ある日突然はしごを外され準備が無駄になったというトラブルは、残念ながら多い事例のようです。取引開始前の検証段階や研究開発段階であっても、役割分担や費用負担及び検証・研究開発終了後の対応に関する契約書を取り交わしておくことが何より重要です。
しかし、こういった契約書の取り交わしを行っていなかった場合、原則的には取引候補者に対して金銭請求(損害賠償請求)を行うことは難しいと言わざるを得ません。但し、例外的に「契約締結上の過失」という理論の適用ができる場合であれば、金銭請求(損害賠償請求)を行うことが可能な場合もあります。
そこで、必要経費として割り切るしかないのですが、例外論である「契約締結上の過失」に該当するかのみ弁護士に検証してもらう、つまり弁護士に依頼する業務を限定し、弁護士費用を抑え込むという視点で対処するのが一案と考えられます(検証の結果、困難であると判断した場合は損切し、これ以上の金銭負担を行わないと発想の転換を図ることも検討するべきです)。
(2)継続的取引の打切り
(事例)
加工業者は、長年某メーカーの専属下請として部品加工業務を行っていたが、某メーカーより「今月末をもって取引を打ち切る」との通告を受けた。加工業者は「突然取引を打ち切られても困る」ことを説明し、取引の継続を訴えたが、某メーカーは一切の話し合いに応じようとしない。
(現時点で予想される負担)
上記事例の加工業者は、専属下請であることからすると、某メーカーに代わる代替取引先を確保できていないと考えられます。したがって、取引が終了する翌月以降、売上が全くない状態となりますので、事業運営に要する費用が今後損失として発生することになります。例えば次のような費用です。
- ①人件費
- ②不動産賃料、リース代
- ③(借入れがあるのであれば)返済資金
- ④材料などの仕入費(予約発注している場合)
- ⑤協力会社への委託費
(追加で必要となる負担と損得勘定)
上記①~⑤を含む事業運営に要する費用は毎日発生しますので、代替の取引先が見つからない限り、当該費用はそのまま損失として発生し続けることになります。
また、メーカーが話し合いを拒絶している以上、メーカーに対して損失補償等を要求するべく弁護士に依頼する、あるいはメーカーへの請求は諦めて事業再生・倒産対応を念頭に弁護士に依頼する、ことも想定する必要がありますが、この場合は当然のことながら弁護士費用が必要となります。
上記のような状況下で、加工業者として検討するべき損得勘定としては次の通りであり、この算式通りにならないと見込まれる場合は、かえって損失を拡大させるだけになってしまいます。
【メーカーより回収できるお金】 > 【代替取引先が発掘できるまでの期間中における損失(経費)】+【弁護士費用】+【手続き経費(訴訟であれば印紙代、郵券代など)】
なお、事業再生・倒産を決断するための損得勘定としては、社長視点となりますが次のようになります。
【事業再生・倒産することにより手元に残るお金(見込)】 > 【事業を継続させることにより手元に残るお金(見込)】
(金銭負担を軽減するための視点)
加工業者は長年にわたって某メーカーの専属下請だったという事情があるとはいえ、未来永劫某メーカーに対して取引を継続させる権利を有しているわけではありません。したがって、某メーカーが突然取引を打ち切ったから当然に損失補償を要求できるということにはなりません。ただし、ケースバイケースですが、損失補償を行うことなく取引を打ち切ることは違法と判断している裁判例もあれば、取引を打ち切ること自体は問題ないが一定期間(代替取引先が発見できるまでの期間よりも短期に設定されていることに注意)の補償は行うべきとする裁判例なども散見されます。
したがって、弁護士への依頼方法として、損失補償的な損害賠償請求ができる見通しが立つのかに限って依頼し、弁護士費用を抑えるということを検討するべきです。
仮に見通しが立つ場合、上記で記載した損得勘定の考え方に沿って、手続きを進めることに経済的な利得があるのかシミュレーションしつつ、一方で、特に訴訟手続きとなった場合、実際の結論が出るまで1年以上の時間がかかることから、事業経営の継続が可能なのかというキャッシュフローも検討する必要があります。万一、事業経営の継続が難しいと判断する場合、早めに事業再生・倒産へのシフトチェンジしたほうが、経済的には得であるということも理解しておきたいところです。
4.情報漏洩・持出し
(1)秘密保持義務違反
(事例)
当社の秘密情報であること及び第三者開示はNGとする秘密保持契約を締結したうえで、取引先に秘密情報である製造レシピの使用許諾を行っていたところ、当該取引先が第三者に製造レシピを開示していることが判明した。取引先に対して、契約違反として何らかの請求を行いたいと考えている。
(現時点で予想される負担)
秘密情報である製造レシピが無断で開示されたことにより、秘密裏にすることで保持していた製造レシピの優位性や有用性が失われたといえます。したがって、現時点で生じている負担としては、次のものが考えられます。
- ①製造レシピ(秘密情報)の経済的価値の低減
(追加で必要となる負担と損得勘定)
現実的には難しい問題があるのですが、秘密情報を取り返す必要が生じます。したがって、
- ②製造レシピ(秘密情報)流出先からの回収費用
が今後発生する可能性があります。
また、単なる秘密情報に過ぎないのであれば難しいところがありますが、当該製造レシピが不正競争防止法に定める「営業秘密」に該当する場合、廃棄や利用禁止等の措置を講じることが可能となりますので、
- ③製造レシピ(秘密情報)流出先に対する使用差止等の対策費用
の発生も想定する必要があります。
なお、回収手続きや使用差止等の対策を行う場合、専門的な法的知識が必要となることが多いことから、必要に応じて
- ④弁護士費用
の負担も考えておく必要があります。
さて、秘密情報を漏洩したものに対して何らかの請求を行う場合、損得勘定としては原則的には次のような検証を行うことになります。
【情報漏洩者より回収できるお金】 > 【秘密情報価値低減による損失(①)】+【情報漏洩対応費用(②③④)】
ただ、現場実務で悩ましいのは、「秘密情報の価値低減」をどうやって金銭評価するのか、すなわち法律上の損害として算定するのかについてです。秘密情報である製造レシピを多方面にライセンスするビジネスを展開していたというのであれば、逸失利益で法律上の損害として算定するということも検討できるのですが(但し、逸失利益という将来分の損失を法律上の損害として認めさせることは難しいところがあります)、そういった情報の経済的価値を前提にしたビジネス展開を行っていない場合、秘密情報の価値低減について具体的な金額算定が不能となってしまいます。したがって、秘密情報の漏洩被害を受けた者の立場とすれば、実際の損得勘定としては
【②③④を含めた情報漏洩者より回収したお金】 > 【秘密情報価値低減に対する主観評価額】
ということになってしまうかもしれません。
(金銭負担を軽減するための視点)
情報漏洩問題で厄介なのは、情報それ自体の経済的価値が難しいこと、つまり法律上の損害として金銭評価することが困難となりがちであるという点です。この問題をクリアーできないことには、費用をかけても得られるものがないとなってしまいますので、仮に弁護士に依頼するにしても、まずは情報それ自体の損害算定が可能かに絞って依頼するといった対処を行ったほうが無難と考えられます。
また、情報漏洩者以外の流出先に対する対応についても、実際のところどこまで実施可能なのか、実効性があるのか等の法律上の限界が存在します。実益の乏しい対策を打ち続けて無駄な費用をかけるよりも、まずは全体像と見通しを示してもらうという範囲に限定して弁護士に法律相談を持ち掛けたほうが、まだ余計な出費を防止できるのではないかと考えられます(弁護士への法律相談料は必要経費と割り切るほかありません)。
秘密情報が漏洩した場合、一般的には損害保険でカバーされることはなく(裏を返せばリスク転嫁が難しい問題と言えます)、何か対策を講じる場合は情報漏洩被害者が自腹を切らなければならないことになりがちです。場合によってはこれ以上の損失拡大を防止するという観点で、費用をかけた対策を講じないという判断をしなければならない場合があることも頭の片隅に入れる必要があるかもしれません。
(2)元従業員による競業行為
(事例)
当社を退職した従業員が同業他社を立ち上げ、当社取引先に対して営業活動を行っているとの情報を入手した。いくつかの取引先が元従業員側との取引を開始している状況であるため、直ちに競業行為禁止措置を講じたい。
(現時点で予想される負担)
元従業員の競業行為により、取引先が奪取されているというのであれば、次のような損失が生じていることになります。
- ①取引減少に伴う売上(利益)減相当分
(追加で必要となる負担と損得勘定)
従業員が当社の信用を傷つけるような言動で競業行為を行っていた場合、取引先に対して事実上の信用回復措置を講じる必要があるため、一定の金銭負担が生じることになります。
- ②信用回復措置のために要した経費(人件費、接待交際費など)
また、元従業員が未だ営業活動を行っていない取引先があるのであれば、当該取引先が奪取されないよう対処するための費用が生じることも想定する必要があります。
- ③営業対策費(人件費、接待交際費、値引き等)
さらに、元従業員側(競業会社)に対して法的対抗措置を講じる場合は、弁護士費用の支払も検討する必要があります。
- ④弁護士費用
以上を踏まえると、競業行為開始から競業行為終了までの期間を念頭に、次のような損得勘定を考慮するという考え方になるかもしれません。
【元従業員側より回収できるお金(取引先奪取分の売上、迷惑料など)】 > 【売上減少分(①)】+【諸経費(②③④)】
ただ、元従業員とはいえ、果たして競業行為が違法と言えるのか十分に検討しておく必要があります。なぜならば、法律上の大原則は「営業の自由」であり、営業の自由を制限するのであれば特別の根拠が必要になるという考え方を採用しているからです。すなわち、元従業員が取引先を奪取することは商道徳的には問題があると言えるかもしれませんが、法律上問題ありとは原則言えません。また、取引先に対して営業活動を行うことための費用は必要経費であり、損害や損失に当然に該当するわけではありません。したがって、法的検証を踏まえた上での損得勘定は次のようになります。
【元従業員側より回収できるお金】 > 【元従業員側の違法行為(※)による当社が被った損害】+【経費(弁護士費用など)】
※競業行為それ自体は原則違法となりません。例えば、当社に対する虚偽の事実を取引先に申出て信用棄損した場合など、競業行為とは別の元従業員側の言動を検証する必要があります。
(金銭負担を軽減するための視点)
仮に元従業員ではなく、全く第三者の競業他社が取引先に対して営業活動を行ってきた場合、取引先を奪われないために、必要なお金を負担して様々な営業施策を講じることが通常かと思います。そして、取引先を奪われなかった場合、当該競業他社に対して、営業施策に要した経費を後日損害賠償請求することはあり得ませんし、一方で取引先を奪われた場合、当該競業他社に対して、売上減少分の損害賠償請求することもあり得ない話です。
したがって、元従業員による競業行為が、本当に法律上問題があると言えるのかの事前検証に限ってまずは弁護士に相談し、弁護士費用を抑えるといった対応を取ったほうが良いかと思われます。
<2021年8月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
|
|






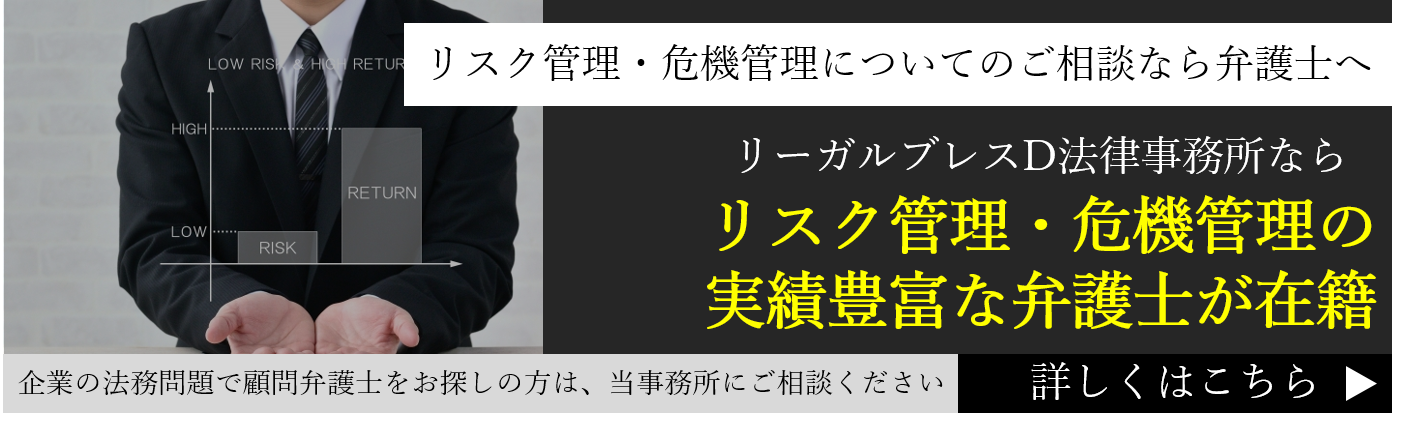

 弁護士 湯原伸一
弁護士 湯原伸一





































