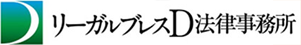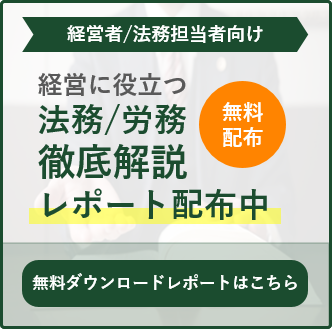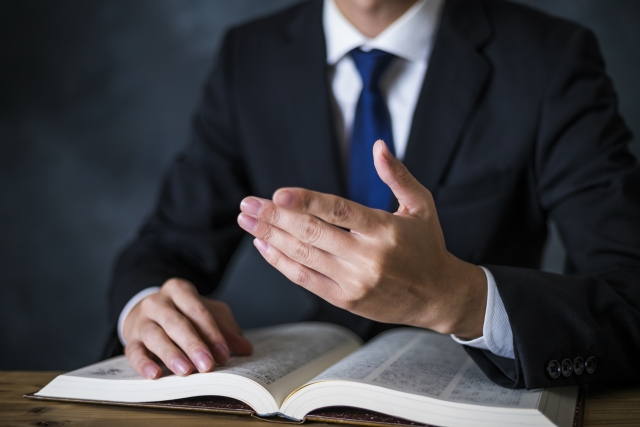【ご相談】
当社とは取引もなく一切面識のない他社が当社に対し、知的財産権を侵害していると主張した上で、使用中止と損害賠償(但し具体的な金額は記載なし)を求める内容証明郵便を送り付けてきました。
驚き、怒り、困惑など色々な感情が沸き立つのですが、冷静になって適切な対処を行いたいと考えています。
警告書を受領した場合の初動対応として、どういった点に注意すればよいのかについて教えてください。
【回答】
初動対応としましては、①事実関係の調査を含めた情報収集を行うこと、②法律上形式的に侵害なしと回答できる抗弁事由の有無を探すこと、③侵害の有無について精査することがポイントとなります。そして、これらの検討を踏まえて方針を組み立て、警告者に対して回答を行うことで、1回目の対応が完了します。
なお、その後は相手の動きを見ながら、方針を都度決定してくことになります。
本記事では比較的件数が多いと思われる商標権、著作権、営業秘密(不正競争防止法)の3つに絞って解説を行います。
【解説】
1.商標権
(1)情報収集
商標権を侵害する旨の警告書を受領した場合、受領者がまず行うべきことは、警告者が主張する商標権に関する情報を収集することです。例えば、特許庁のWEBで検索をかけることで、手っ取り早く情報収集することが可能ですが、特に必要となる情報は次の通りです。
- 商標
- 存続期間満了日
- 権利者
- 商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務
(※場合によっては、包袋(=商標等の出願・審査経過を特許庁でまとめて保存してあるファイルのこと)を入手する必要性あり)
また、警告者における商標の使用状況についても、WEB検索での調査はもとより、可能であれば現物を取得すなどして情報収集を行うべきです。
さらに、警告者が侵害と指摘している受領者の標章を使用した商品・サービスの現物を確保すると共に、当該標章の使用の有無、開始時期、使用方法・形態に関する情報を整理することがポイントです。
(2)類否判断前に非侵害と主張できないか確認する
商標権侵害の有無は、警告者が登録している商標と受領者が使用している標章が類似するか、登録商標の指定商品・役務と受領者使用の標章が付された商品・役務が類似するかを検討することが通常です。
しかし、この類比判断は非常に微妙なことが多く、侵害の有無について予測しづらい場合が多々あります。そこで、商標の類比判断を行うことなく非侵害であることを指摘できるのであれば、その点を先に反論することが有用です。
様々な反論が考えられますが、検討対象になりやすい事項としては次のようなものがあります。
先使用(商標法第32条第1項)
商標登録が行われる以前より、警告書を受領した者が標章を使用していた場合、商標権侵害が成立しないとされています。
おそらく警告書を受領した者が真っ先に検討することになる事項かと思われますが、厄介なのが、単純に先に使用していただけでは不十分であり、標章を付した商品・役務(サービス)の需要者に対して周知されていた、という状態が必要とされている点です。
この周知性については、いくつかの市町村で認識されているというだけでは不十分と考えられており、ある程度の広さの地域(都道府県レベルが1つの判断基準と言われています)で知られている必要があるとされています。最近ではネット通販等もあり、この地域性の要件をクリアーすることは比較的容易になっては来ているものの、需要者にどこまで認知されているのかを裏付けることはかなり難しいところがあります。
商品の宣伝広告状況や需要者(商品購入者、サービス利用者)の地域分布等を分析することで検討を行うことになりますが、どういった調査を行えばよいのか分からないことも多いかと思いますので、弁護士等の専門家に相談しながら検証を進めることが重要です。
商標無効の抗弁(商標法第39条)
警告者が指摘する商標について、商標登録無効事由がある場合、そもそも商標は無効となります。そこで、無効事由がある場合はその旨指摘して、商標権侵害が成立しないと反論することも考えられます。
この種の反論は特許侵害紛争でよく用いられる方法なのですが、実際の現場実務では反論するだけではなく、警告書を受領した者が特許庁に対し、無効審判手続きを別途提起することが合わせて行われることが多いように思われます。したがって、全面対決を想定した反論方法となります。
なお、似て非なるものとして、警告者が商標を登録したのみであって、実際に当該商標を使用していない場合、特許庁に対して不使用取消審判請求を行う場合があります。ただ、これは“取消”であって“無効”ではありません。したがって、この場合は商標法第39条に基づく反論はできないことに注意が必要です(一応、権利濫用の抗弁として反論することが可能とされていますが、実際のところ、不使用審判が認められないことには反論しづらいところがあります)
普通に用いられる方法での表示(商標法第26条1項第1号~同第3号)
例えば、警告書を受領した者が、自らの氏名を商品・サービス名に使用していた場合、たとえ形式的には登録商標と類似するとしても商標権侵害は成立しません。また、例えば、胃腸薬として有名な正露丸という名称については、普通名称化しているとする裁判例が存在するため、正露丸という名称を用いる限りでは商標権侵害は成立しません。
このように、自己の氏名・名称(但し会社の名称の場合は著名なものに限る)、普通名称などを普通に用いる方法で表示する場合は、商標権侵害が成立しません。
現場実務では、警告書を受領した者が用いる標章が、普通名称といえるのかという観点で検討することが多いのですが、世間一般での認識などの事実調査は受領者が行い、その調査結果を踏まえて商標権侵害の成否を弁護士等の専門家が行うといった役割分担を決めた上で、検討したい事項となります。
商標的使用ではないこと(商標法第26条第1項第6号)
例えば、メーカー純正ではないインクリボン(いわゆる汎用品)を市場販売する際に、どのメーカーに対応するインクリボンなのかを示す目的で登録商標であるメーカーの名称を用いた場合、商標権侵害は成立しないとされています。
これは、商標が有する自他識別機能、出所表示機能を犯すわけではないという説明がなされたりしますが、上記事例でいえば、汎用品を販売する業者は、自らがメーカーと誤解されるような態様で登録商標を用いているわけではないという点がポイントとなります。
やや分かりづらいところがあり判別もしづらいところがありますので、弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。
真正商品/並行輸入
登録商標が付された商品が中古品として市場流通する場合、商標権を有する者及びそのライセンスを受けた者以外の第三者が、当該中古品を扱うに際して商標を用いることは商標権侵害となりません。真正商品である以上、商標の出所表示機能を犯すことがないからです。
もっとも真正商品を輸入して取り扱う場合は事情が異なります。いわゆる並行輸入の場合、原則として商標権侵害が成立することになるからです。但し、一定の要件を充足した場合、並行輸入であっても商標権侵害は成立しないと判断した裁判例が存在し、現場実務ではこの要件に該当するかが検討対象となります。
- 外国において適法に登録商標が付され、流通におかれた商品であること
- 日本の商標権者と外国の商標権者と法的・経済的同一性があること
- 日本の商標権者による商品品質管理が実質的に及んでいるといえること
非常に専門的な検討が必要となりますので、必ず弁護士等の専門家のアドバイスをもらいながら検証を進めるべきです。
(3)類否判断を行う
上記(2)に基づく反論が難しいと判断した場合、登録商標との類比判断を行うことになります。この類比判断ですが、理屈の上では次の2つの点を区別しながら行うことになります。
登録商標との類否
名称やロゴ等の登録商標と、警告書を受領した者が用いる標章(名称・ロゴ等)が類似しない場合、商標権侵害は成立しません。
さて、この類似性の判断ですが、判断基準としては「商品・役務の出所の誤認混同を生ずるか」というものになるのですが、非常に抽象的です。そこで、現場実務では、次の事項を検討しながら類比判断を行っています。
- 外観(見た目が紛らわしいといえるか)
- 観念(登録商標と標章からイメージされる意味内容が紛らわしいか)
- 称呼(呼び方・読み方等の発音が紛らわしいか)
- 取引の実情(登録商標が付された商品・役務、標章が付された商品・役務がどのように取引されているのか)
ちなみに、商標登録段階でも上記のような判断基準が用いられていますが、商標権侵害の検討段階の方が「取引の実情」をより考慮する傾向があるとされています。例えば、世間でも話題になった、“フランク・ミュラー”のパロディ商品(時計)である“フランク三浦”の裁判では、形式論では称呼は類似するものといえますので、商標権侵害が成立してもおかしくないと考えられます(実際のところ、特許庁は類似するとして、フランク三浦の商標登録を取消しています)。しかし、裁判所は、フランク・ミュラーは高級時計(100万円超の時計が多数)であるのに対し、フラン三浦は低価格時計(数千円程度)であるといった取引の実情を考慮し、商品・役務の出所を誤認混同することは無い(=要は誰もフランク三浦の時計をフランク・ミュラーの高級時計と間違えることはないし、パチモノと判断することもない)と判断し、特許庁の判断を覆しています。
とはいえ、この類比判断については、かなり主観に左右されやすいところがあるのも事実ですので、少なくとも自社のみで判断することは避け弁護士等の専門家に相談すること、そして可能であれば、複数の専門家から意見を取り寄せた上で判断することが望ましいと考えられます。
指定商品・役務との類否
商標登録に際して指定した商品・役務と、警告書を受領した者が標章を付した商品・役務が類似しない場合、商標権侵害が成立しないことになります。
基本的な判断基準は上記の「登録商標との類比」と同じですが、考慮要素として特許庁が公表している商標審査基準の商標法第4条第1項第11号に関する解説内容を参照することが多いとされています。
(参考)
(4)方針検討
商標権侵害に基づく警告の場合、特許とは異なりラインセンス交渉を行うことは稀だと考えられます。したがって、侵害可能性が低いと判断した場合は、端的に侵害しない旨回答し、あとは警告者の動き待ちとなることが通常です。
一方、侵害可能性ありと判断した場合、最初から白旗をあげてしまうのかは考え物です。例えば、警告者の本音として、損害賠償請求までは考えておらず、単に受領者が使用する標章の使用中止さえ実現できればよいという場合、商標権侵害の有無を争いつつ、一方で無用な争いを行う考えはないとして一定期間経過後に当該標章の使用を中止する旨回答し、警告者と交渉するといった作戦もあるからです。
方針の立て方・見通しについては、弁護士等の専門家とも十分に協議した上で定めるべきです。
(5)(参考)不正競争防止法
ところで、商標権侵害の警告書を受領した場合、その警告書の中に不正競争防止法違反についても記述されていることがあります。例えば、周知表示混同惹起(不正競争防止法第2条第1項第1号)と著名表示冒用(不正競争防止法第2条第1項第2号)と呼ばれる行為類型です。
不正競争防止法違反に関する指摘がある場合、指定商品・役務と類似しないことを前提にした警告となりますので、少し検討方針が異なることに注意が必要です(警告者が指摘する商標等について周知性があるのか、著名といえるのかが主たる検討方針となります)。
2.著作権
(1)情報収集
著作権を侵害する旨の警告書を受領した場合、受領者がまず行うべきことは、警告者が主張する著作権に関する情報を収集すること、前述1.の商標権の場合と同様です。ただ、商標権の場合、登録が必要とされている点で権利情報を収集しやすいのですが、著作権の場合、無登録で発生することから権利情報は収集しづらいところがあります。
そのため、商標権とは異なり、そもそも著作権が発生しているのかという根本論から検討を進める必要があります。
(2)著作権の成立自体を確認する
著作物該当性
著作権は著作物に対して発生する権利ですので、警告者が指摘する表現物がそもそも著作物に該当するのかを検討する必要があります。
もっとも、創作的な表現なのか、ありふれた表現なのかの判断を客観的に行うことは難しく、時には人によって判断が分かれてしまうこともしばしばです。したがって、警告書を受領した者だけで判断せず、必ず弁護士等の専門家に相談し判断してもらうこと、できれば複数の専門家より意見を仰ぐことが重要となります。
警告者は著作権者か
著作権は無登録で発生することから、警告者が本当に著作権者であるのか、警告書を受領した者において客観的に確認する方法がないという特徴があります。例えば、写真画像データであれば、写真撮影をした者、写真を編集加工し画像データ化した者、当該画像データの譲渡を受けた者のうち誰に著作権が帰属しているのか、一律の判断ができないことが通常です。
したがって、警告者が当然に著作権者であると考えることなく、警告書を受領した者は、必要に応じて警告者に対し、著作権者であることの裏付けを求めるというスタンスが必要となります。
なお、いわゆる「コピーライトマーク」が付されているからといって、著作権者であることが保証されるわけではありません。任意に付されるマークにすぎないことに注意が必要です。
(3)著作物の正当利用といえないか確認する
私的利用(著作権法第30条第1項)
これについては、事業活動における著作物の利用の場合は該当しないと考えられていますので、検討対象外となります。
引用(著作権法第32条、第48条)
現場実務において、真っ先に引用に該当しないかという観点から検討することが多いものと思われます。ただ、著作権法上の引用が認められるためには一定の要件を充足する必要があるところ、これに該当しない場合が多くみられるというのも実情です。一般的には明瞭区分性と主従関係が必要とされていますが、例えば、文化庁のWEBでは次のような整理が行われています。
- 他人の著作物を引用する必然性があること。
- かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
- 自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
- 出所の明示がなされていること。
なお、引用の要件に該当するか否かについても微妙な判断を伴いますので、できる限り弁護士等の専門家に相談の上、判断をしたほうが無難です。
(4)侵害不成立と言えないか検討する
ライセンス
著作権侵害紛争で意外と多いのが、著作物の利用許諾は受けているものの、利用許諾の範囲外であるというパターンです。例えば、利用許諾の範囲外の媒体物に著作物を利用していると警告された、著作物を一部加工等して利用していると警告された、利用許諾した対象者以外の者が利用していると警告されたという事例です。
著作権については口頭でライセンス契約を行うことが多いこと、仮に書面等でライセンス契約を締結したとしても、利用許諾の範囲について一義的ではないこと等が主な理由ですが、利用許諾の範囲を決するためには、ライセンス交渉の経過や著作物使用後警告を受けるまでの間の警告者の動向等を含めた全体観察を行い、判断するほかありません。
どのような事実関係と証拠を拾い上げていけばよいのかについては、弁護士等の専門家に必ず相談し、判断を行うべきです。
保護期間
著作権は、原則として著作者の死後70年間で保護期間が満了すると定められています(著作権法第51条第2項)。
ただ、例えば、クラシック音楽であれば、作曲家は100年以上前に死亡しているので、保護期間を経過していると判断するのは誤りです。なぜなら、そのクラシック音楽は編曲されている可能性がありますし、クラシック音楽の演奏者の権利等を別途検討する必要があるからです。
安易な判断はできないこと、保護期間満了を主張したいのであれば、本当に通用するのかにつき弁護士等の専門家に相談し確認を行うべきです。
依拠性
依拠性については同語反復のような定義がなされているところ、要は、既存の著作物(=警告者が指摘する著作物)に全く接することなく、その存在を知らずに同一の著作物(=警告書を受領した者が用いた著作物)を創作した場合は、著作権侵害が成立しないということを知っておけば十分かと思います。
もっとも、既存の著作物を参照することなく創作したか否かは警告書を受領した者の内部事情・主観的事情となるため、判断が付きにくいところがあります。このため実務上、既存の著作物と類似すること及び既存の著作物に警告書を受領した者がアクセスすることが可能であった場合は、事実上依拠したものと推定するという取扱いが行われています。したがって、既存の著作物と類似する場合は、むしろ警告書を受領した者が積極的に独創にて作り上げたことを主張立証する必要があることに注意が必要です。創作者からのヒアリングのポイント等を含め、弁護士等の専門家に相談しながら反論事項として用いるべきか検討を行うべきです。
類似性
著作権侵害を検討する上で一番のメイン事項とはなるものの、一方で侵害の可否につき非常に予見しづらいのが、警告者が指摘する著作物と警告書を受領した者が使用する著作物の類似性についてです。
この類似性の判断がややこしくなっているのは、直感的に似ているか否かで判断されるわけではなく、「表現上の本質的な特徴を直接感得できるか」によって判断されることに由来します。この「表現上の本旨的な特徴を直接感得できるか」については、誤解を恐れずに説明するのであれば、警告者が指摘する著作物の中でもキラリと光る表現(尖った表現といっても良いかもしれません)を抽出した上で、そのキラリと光る表現が、警告書を受領した者が使用する著作物に含まれているかを検討し、類似性の判断を行います。このため、世間一般の感覚では類似していると考えても、著作権法上は類似していないと判断されることもしばしばです。
したがって、警告書を受領した者のみで類似性については判断せず、必ず弁護士等の専門家に相談し意見をもらうこと、できれば複数の専門家の意見を収集することが望ましいといえます。
(5)方針検討
著作権侵害に基づく警告を受けた場合、状況によってはラインセンス交渉を行う場合もあり得ます。したがって、侵害可能性が相応程度あると判断した場合、回答書面上は著作権侵害を争いつつも、一方で別途協議の場を設けた上でライセンス交渉を行うといった多角的視点での対応が必要となる場合があります。
また、警告者の意向として、著作物の使用さえ中止してくれれば満足であり損害賠償等は考えていないこと、警告書を受領した者としても当該著作物の使用が必要不可欠とは言えない場合もあります。この場合、表面上は争いつつも、紛争状態を好まないとして自主的に当該著作物の使用を中止するといった対応も考えられます。
一方、著作権侵害の可能性が低く、当該著作物を利用する必要性ありと判断した場合、著作権侵害に当たらないことを端的に回答し、あとは静観する(警告者の動き待ち)という方針を取ることになります。
なお、あくまでも一般論ですが、もともと有償ライセンスの対象となっている著作物である場合、あるいは警告書を受領した者が当該著作物を用いて利益を得ている場合、単なる使用中止のみならず、経済的価値を毀損されたとして損害賠償まで求めてくる可能性が高まります。警告を行ってきた者の本音を見極めつつ、どこに着地点を見出すか等の方針の立て方・見通しについては、弁護士等の専門家とも十分に協議した上で定めるべきです。
3.営業秘密(不正競争防止法)
(1)情報収集
不正競争防止法に定める営業秘密を侵害する旨の警告書を受領した場合、受領者としては、営業秘密を保有していると思われる者(なお、警告書に人物が特定されていることも多いです)より、情報を保有しているのか事実確認を行うことが、まずもっての対応となります。
ただ、気を付けたいのが、事実確認のためのヒアリングを行うことで、かえって営業秘密が社内の他の従業員等に拡散する恐れがあり、情報拡散が止まらなくなるというリスクです。誰が事実確認を行うのか、事実確認を行う担当者より秘密保持誓約書を徴収する必要がないか等の事前準備が重要なポイントとなる点で、上記1.の商標、上記2.の著作権とは事情を異にします。
さて、警告者が指摘する営業秘密を自社内で保有していることが確認できた場合、次に調査するべき事項は、自社で独自に開発した情報といえないか、という点になります。なぜなら、自社独自で開発した情報であれば、営業秘密を不正に入手したことにはならない以上、営業秘密侵害は成立しないことになるからです。なお、独自情報であると言い切るためには、どういった手法を用いて独自開発したのか、あるいは当該情報を保有するに至ったのかのプロセスが極めて重要となります。この点については十分な調査と証拠確保を図るべきです。
また、一方で、警告者が指摘する営業秘密について、別ルートで簡単に入手できる、業界人であればだれでも知っている等の公知情報と言えなかという視点での調査も必須です。なぜなら、不正競争防止法上の営業秘密に該当するためには、秘密管理性、有用性、非公知性の3要件を充足する必要があるところ、前2つは警告者の内部事情が大きく調査しきれない事項であるのに対し、最後の非公知性については警告書を受領した者においてもある程度調査可能な事項となるからです。調査をすれば、意外と公知となっていることが判明したりしますので、十分な調査を行いたいところです。
なお、例えば中途採用した者に関連し、元勤務先より営業秘密を持ち出したと警告を行ってきた場合、その中途採用者より、元勤務先に対して提出した誓約書等の内容や元勤務先の情報管理体制を聞き出すことで、秘密管理性を充足しない可能性あるといったヒントを得られることも有ります。
(2)営業秘密該当性を確認する
前記(1)でも解説しましたが、不正競争防止法上の営業秘密と言いうるためには、秘密管理性、有用性、非公知性の3要件を充足する必要があります。
上記(1)で記載した情報収集を行うことで要件を1つでも欠くと判断した場合、営業秘密に該当しない以上、警告者の指摘は当たらない旨回答することになります。
もっとも、調査の仕方やヒアリング内容、調査対象事項等については、紛争の実態を知らないことにはピンポイントで行うことは難しいと思われます(余計な情報で溢れてしまい、正確な判断ができない場合さえあります)。弁護士等の専門家を交えながら営業秘密該当性を判断することをお勧めします。
(3)善意無重過失による権限内使用(不正競争防止法第19条第1項第6号)
警告者が指摘する情報を社内で保有し、当該情報の入手経路が警告者を通じであり、しかも当該情報は営業秘密であることを否定する要素を見つけられない場合、営業秘密侵害が成立する可能性が高いということになります。
もっとも、たまたま取引を通じて当該情報を取得しただけであり、警告書を受領するまでは営業秘密であることを知らなかったという場合、不正競争防止法は例外的に営業秘密侵害が成立しないと定めています。詳細な要検討については、次の資料の該当箇所にて知識を整理していただきつつ、必要に応じて弁護士等の専門家にご相談ください。
(参考)
(※ダウンロード資料にある「不正競争防止法逐条解説」を参照してください)
(4)方針検討
営業秘密侵害の場合、警告者が指摘する情報が本当に営業秘密なのか、不正競争防止法が定めるような態様にて取得したのかが明確にならないことが多いという特徴があります。このため、警告書を受領した者の基本的スタンスとしては、侵害なしという回答を行いつつ、あとは警告者の出方を見るということになりがちです。
もっとも、通常では入手できない顧客情報や技術情報である場合、営業秘密である可能性は高くなりますので、安易に侵害なしという回答は行わず、十分調査を行った上で方針を決めるべきです。
ところで、営業秘密侵害に基づく警告の場合、営業秘密の漏洩を問題視しているよりは、中途採用者による競業行為を抑え込みたいという元勤務先(警告者)の意向が見え隠れする場合もあります。この場合、警告書を受領した者としては、当該中途採用者を守るべきかという観点で判断することになり、営業秘密侵害の判断は二の次となりがちです。そして、万一厄介ごとに巻き込まれたくないから当該中途採用者との労働契約を見直すとなると、今度は社内で労使紛争が生じることになるところ、これはまさしく元勤務先(警告者)の思う壺といえます。警告者の本音を探りながら、どのような方針を組み立てるのかについては弁護士等の専門家に是非相談してほしいところです。
なお、中途採用者が保有する情報の取扱いに関する注意点(営業秘密混入リスク等)については、次の記事もご参照ください。
(参考)
中途採用者/退職予定者が保有する情報の取扱いで注意したい事項につき、弁護士が解説!
<2022年3月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
|
|





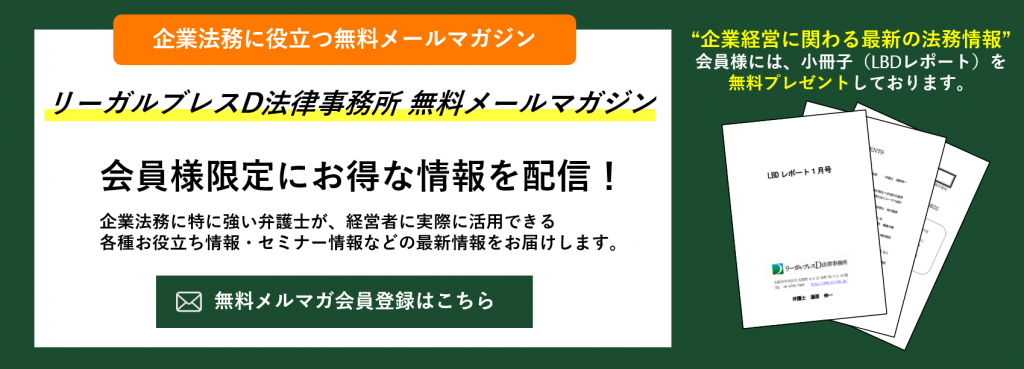
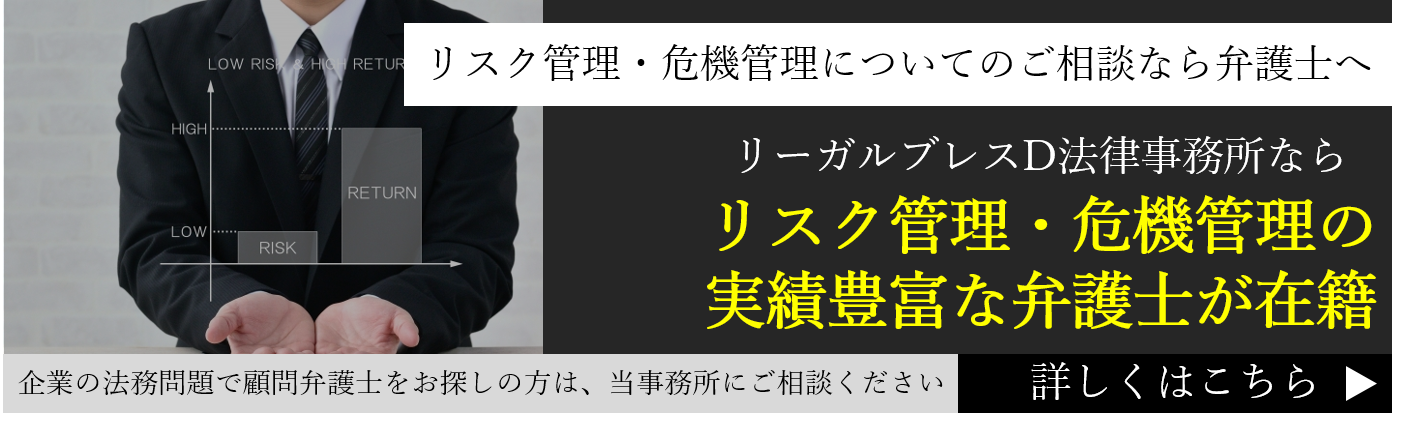
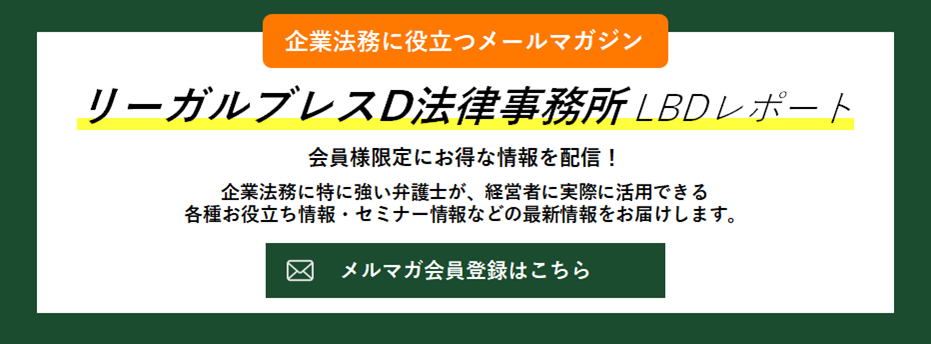
 弁護士 湯原伸一
弁護士 湯原伸一