Contents
【ご相談内容】
古くから付き合いのある者より懇願されたため、当社は当該懇願者に口約束でお金を貸付けました。その後、当該懇願者の資金難も去ったと聞き及びましたので、返済に関する協議を行おうとしたところ、当該懇願者は次のような理由を述べて、返済を拒絶してきました。
当社としては、たしかに貸付けたものであり、訴訟を提起してでも回収を図ろうと考えているのですが、どのような点に注意すればよいでしょうか。
(1)借りたのではなく、もらったものだ
(2)お金を受け取っていない
(3)私は借主ではない
【回答】
理論的には、金銭消費貸借契約が成立したことを前提に、貸金返還請求を行えばよいことになります。
ところで、金銭消費貸借契約が成立したことを裁判官に理論的に説明するためには、①返還約束の合意があったこと、②金銭の交付があったこと、③弁済期の合意があったこと、④弁済期が到来したこと、の4要件を満たす必要があります。
しかし、本件では、返還約束の合意不存在((1)のケース)、金銭交付の不存在((2)のケース)、そもそもお金の貸し借りに関知していない((3)のケース)、となっているところ、決定的証拠となる契約書が存在しない状態です。
このような場合、弁護士としては、金銭消費貸借契約が成立したことを立証できるのか、具体的には上記①~④を基礎づける具体的な周辺事情を見つけ出し、それを裏付ける証拠を準備できるのかという視点で検討することになりますが、この具体的な周辺事情については、検討価値の高い事情とそうではない事情があります。
以下では、どういったものが検討価値の高い周辺事情に該当するのかを指摘しつつ、考え方のポイントを解説します。
なお、以下の解説に記載している周辺事情の1つだけ揃えれば必要十分とはならず、様々な周辺事情を積み重ね、いわば“合わせ技一本”で何とか勝訴できるかもしれない…という程度に留まること、ご注意ください。
【解説】
1.契約書が無いことによる不利益
まず誤解の無いよう念のため触れておきますが、金銭消費貸借契約において、法律上、契約書の作成や借入証の発行は義務付けられていません。むしろ、法律上は、口頭でも金銭消費貸借契約は成立するとされています。
ただし、契約書等がない場合、金銭消費貸借契約が成立したことを証明することが難しいという実情があります。また、裁判という観点から見た場合、貸主がいくら「××にお金を貸した。証拠は私自身だ!」と言ったところで、借主に支払いを命じる判決ができることはまずありません。
したがって、契約書を作成していないこと、それ自体が非常に不利な状況となります。
もっとも、契約書を作成しなかった理由に合理性がある場合は別途検討の余地があります。
例えば、親子や親族間でのお金の貸し借り、付き合いの深い知人に対するお金の貸し借りといった、密接な人間関係がある場合、ついつい契約書を作成することなくお金を貸してしまうということは一定の合理性のある理由と考えられます(なお、後述2.(1)で解説する通り、良好な人間関係だからこそ資金援助目的の贈与であり貸付ではない、という経験則が作用する場合もあること注意が必要です)。
一方で、貸主が貸金業など金融系の事業を営んでいる場合、人間関係の有無にかかわらずお金を貸し出すプロフェッショナルであることから、契約書を作成しないことは通常考えられないという経験則もあり得ます。
また、貸主と借主に密接な人間関係があったとしても、多額の金銭の貸し借りの場合(貸主や借主の経済状況によるため一律の金額を示すことは難しいですが、一般的には100万円を超えると多額といってよいのではないでしょうか)、契約書を作成しないというのは通常あり得ないのではないかという経験則も考えられるところです。
要は、契約書を作成しなかった(できなかった)背景事情を具体的に主張立証できる場合、たとえ契約書が存在しなくても、裁判においても金銭消費貸借契約の成立を認めてもらえる余地があるということがポイントです。
もちろん、背景事情を深く追求していくと、貸主にとって有利な点や不利な点も出てくるかと思いますが、それらの情報の整理については弁護士に任せたほうが確実です。
2.贈与・出資の抗弁に対して
「貸した金を返せ!」と請求した場合に、相手から返さない理由として反論してくる典型的なパターンが「もらったもの(贈与)である」というものです。また、その亜種として「出資を受けただけである(出資であれば返還義務なし)」というものがあります。
要は「返還約束の合意」がないという反論なのですが、契約書が無い場合、当該合意があったか否かは俄かに判断が付きません。そこで、返還約束の合意があるのが通常であるとする経験則を裏付けることができるような立証活動が必要となるのですが、その具体例について以下では解説します。
(1)職業、地位、関係
例えば、貸主が貸金業である場合、金銭の返還を求めないことは通常考えにくいという経験則が成り立ちます(職業に関する例)。
また、今時のドライな(?)労使関係の場合、法的な金銭支払い義務のない経営者が、労働者の求めに応じて金銭交付した場合、お金を貸付けたと考えることが合理的と思われます(地位に関する例)。
一方、親子や親族などの密接な人間関係があり、金銭交付当時の両者の関係性が良好といえる場合、純粋な資金援助であって、金銭“交付時”に返還を求める意図ではなかったという経験則も成り立つところです。例えば、子供が結婚し、マイホーム購入に際して親が子の配偶者に相応の金銭を交付したところ、後で子供夫婦が離婚することになったので、あの時に交付した金銭を取り戻したいという相談が結構あったりします。しかし、金銭交付時の状況からすると資金援助であると考えるのが合理的ですので、後で翻意して返還を求めることは難しいと言わざるを得ません。
ところで、必ずしも密接な人間関係が無い場合であっても、金銭交付時に返還約束の合意があったとは考えにくい事例があります。例えば、好意を寄せる相手に一定額の金銭を提供し、関係性を継続していたところ、何らかの理由で関係性が無くなったという場合であれば、やはり金銭交付時に返還してもらう約束があったと考えることは難しいように思われます。
相手より贈与と反論される場合、贈与するだけの目的・動機が対外的に(裁判官の目から見て)伺われる周辺事情はないか探し出し、1つずつ反論を準備するのか返還を求める側の対応ポイントになると考えられます。
(2)金額の多寡
上記(1)で解説した通り、密接な人間関係があり、かつ金銭交付当時に関係性が良好であった場合、金銭消費貸借ではなく贈与ではないかという経験則が働きやすいといえます。しかし、特別な理由もなく数百万円を贈与するといったことは考えにくいという経験則もあり得るところです。
このように相反する経験則が存在する場合、本件事案に限れば、よりどちらが合理的な経験則といえるのかを探ることになるのですが、裁判官に訴えかける場合の1つの方法として、金銭交付に至るまでのストーリーを適切に主張することがあげられます。
例えば、返還を求める側としては、
- 金銭交付前までの人間関係
- なぜ金銭交付することになったのか(貸す側が金銭交付を発案したのか、借りる側が金銭交付の要請を行ってきたのかなど)
- 金銭交付を実行するまでにどのようなやり取りを行ったのか(貸す側にとって金銭を交付するメリットは何か、借りる側にとって交付された金銭の使途など)
- 貸す側の経済事情はどうであったか(無理してお金を準備したのか等)
- 借りる側の経済事情はどうであったのか(借りる必要性があったのか等)
- 金銭交付後の双方の言動(交付を受けて当然という態度だったのか、感謝を述べると共に将来的な報恩を述べていたのか等)
等々の事実関係を時系列で示し、その時系列に沿う経験則を指摘するといった方法です。
なお、この手法は高度なテクニックと専門知識を必要としますので、弁護士に依頼して行った方が適切です。言い方は悪いですが、素人判断でこの手法の真似事をすると、かえって不利な事情(本人は気が付いていない)を表に曝け出すこととなり、自らの手で首を絞めることにもなりかねませんので、よくよく注意して欲しいところです。
(3)返還を前提とした言動
致命的とまでは言えないのですが、例えば、貸主が借主に対し、訴訟提起に至るまで一切返還請求を行わず、返還交渉も行っていないとなると、本当に金銭消費貸借契約を締結していたのかと疑義が生じることになります。ただ、親子・親族等の密接な人間関係があり、金銭交付当時はもちろん交付後も良好な関係性が継続していたこと、支払期限を特に定めていなかったこと(なお、支払期限を定めていない場合、法律上はいつでも返還を求めることが可能と考えることになりますが、一般的には知られていないようです)等の事情がある場合、疑義を解消する周辺事情として作用することになります。
一方、借主が貸主に対し、支払期限の延期を懇願する、一部で支払に応じるといった対応をとっている場合、金銭をもらい受けた(贈与)という主張とは矛盾する言動となりますので、金銭消費貸借契約が成立していたと合理的に考える事情となります。ただ、実は別の債務に関する言動であったという反論があった場合、本当に他の債務が存在するのであれば、金銭消費貸借契約が成立していたと推認する事情としての価値に乏しいことになります。
なお、返還を前提とした言動については、いわいる“言った言わない”論争に陥りやすく、特に裁判手続きの場面で当該言動を指摘したとしても、相手に否認されて功を奏しないことが多いというのが実情です。
もちろん、だから裁判手続きで主張するべきではないという話にはならないのですが、この種の返還を前提とした言動については、裁判前のまだ相手と話ができる段階、すなわち相手が身構えていない状況下で、何気ない会話の中で言質を取り、それを隠し録音でもよいので記録化するといったテクニックを用いることが肝要となります。
(4)出資について
個人間ではなく、事業者同士での金銭の交付が行われる場合、贈与の抗弁もありますが、共同事業への出資金であることを理由とした返還義務なしと言う反論を受けることもあったりします。
さて、出資契約であるという反論を受けた場合ですが、具体的な共同事業の内容、双方の役割分担、ビジネスの遂行方法、事業に成功した場合の利益分配方法、逆に事業に失敗した場合の損失負担や事業の清算方法など、具体的な取り決めが存在するのかを探ることになります。なぜなら、これらの事項を定めずにして漠然と出資契約であると反論したところで、俄かに信じがたいと考えるのが通常と考えられるからです。
出資契約であるとの反論が出た場合、いつの時点でどういった取り決めを行ったのか、交付された金銭の使途等につき相手に主張させるだけ主張させて、不合理な点や矛盾点を見つけ出しては叩き潰すといった戦略が必要になります。ただ、相手の主張が抽象的なものに留まる場合は、あえて再反論するまでもなく(再反論するとかえって墓穴を掘ることもあり得るため)、淡々粛々と裁判手続きを進めていくということも検討に値します。
3.金銭を受け取っていないとの抗弁に対して
「貸した金を返せ!」と請求した場合、「借りていない!(貰い受けたものだ!)」と反論されるパターンがあることは前述2.記載の通りですが、そもそも「金銭の交付自体受けていない!」という反論も意外とあったりします。
典型的な例として、借用書が存在するものの、借用書に書いてある金銭を受け取っていないといったものがあるのですが、本件のような借用書等の裏付け書類がなく、金銭交付も口座振込など跡が残る方法で行われていない状況下で金銭交付の事実自体を否定されてしまうと、貸主が裁判手続きを経て、借主への支払い判決を獲得することは一苦労となります。
結局のところ、金銭交付が行われても不思議ではない周辺事情を1つずつ積み重ねて主張立証するほかないのですが、その周辺事情として検討しうる事項について以下では解説します。
(1)貸主の資力
お金を貸付ける場合、貸主が主張する貸付金の出所(原資)はどこにあるのか、という点は見落としがちではあるものの、意外と重要な周辺事情となります。なぜなら、逆に貸付金を準備できるだけのお金を貸主が貸付当時持ち合わせていなかった場合、“そもそも他人に貸すことなどできないのでは!?”と考えるのが自然であり、金銭交付の事実を否定する重要な考慮要素となってしまうからです。
貸付金を交付するだけの資産がもともとあったというのであれば預貯金の通帳履歴、貸付金を交付するために貸主が第三者から資金融通してもらっていたのであれば第三者との契約書などを準備し、貸付金の出所(原資)の立証を行うことになります。なお、いわゆるタンス預金でまとまったお金を元々持っており、それを原資として貸し付けたという話も出て来たりします。この場合、貸主の職歴等を踏まえて過去の収入状況を明らかにすると共に、タンス預金を行っていた理由などを明らかにしながら主張立証を行うことになりますが、裁判手続き上はなかなか苦戦することが予想されます。
やはり金銭交付の事実を裏付けるためには、金銭の流れについて跡が残る方法(銀行振込みなど)をできる限り実践し、手渡しによる金銭交付は避けたいところです。
(2)借主における必要性、理由
貸主からすると、借主の内部事情であるため明確なことは分からない…となることがあるかもしれません。しかし、お金を貸す以上、何故必要なのかその目的や動機、使途について問い質し、借主からの回答に納得がいけば貸渡すという流れになるのが通常です。
したがって、ここでいう「借主における必要性、理由」については、貸主が認識している(借主が貸主に説明していた)事項を指摘するに留まり、あまり重みのある周辺事情ではないといえるかもしれません。
しかし、裁判手続きでは、一種のストーリーが大事なので、理由のない貸付は逆に不自然と裁判官に思われるリスクもあることから、手を抜くことなく主張立証したいところです。
(3)借主において金銭を利用・費消したか
これも借主側の事情であり、貸主において十分に確認ができない事情と考えられます。
しかし、例えば、貸主と借主が偶々同じ取引先を利用していたところ、金銭交付後、借主が当該取引先に対して未払いになっていた債務を返済し、取引再開となった等の情報を入手出来た場合、交付を受けた金銭で支払いに充てたことを推認する重要な周辺事情となる可能性があります。あるいは借主が事業者で給料未払いを断続的に発生させていた場合、未払い分をある日突然全額支払ったといった(元)従業員から証言を得ることで、交付を受けた金銭を用いて支払ったことを推認させる周辺事情となり得ます。
また、一種の教科書事例的なものとなりますが、貸主が借主に金銭交付を行ったところ、急に借主の羽振りが良くなった、といった借主周囲の関係者からの情報が得られた場合、やはり周辺事情として検討に値する事項となります。
この辺りは貸主の情報収集能力に頼らざるを得ないとことがあるのですが、「首の回らなかった借主が、急に資金繰りに余裕が出てきた」というストーリーを描けた場合、貸主が金銭を交付したからではないかと裁判官に思ってもらいやすい周辺事情となりますので、できる限り収集したいところです。
(4) 返還を前提とした言動
前述2.(3)で解説した通りですが、例えば、金銭の交付を受けていないにもかかわらず、返済するような言動を借主が取っていたというのであれば、重要な周辺事情となり得ます。逆に返済期限が到来したにもかかわらず、貸主が返金を求める一切の行動をとっていない場合、本当に金銭の交付があったのか疑義を挟む事情となり得ます。
なお、返還を前提とした言動を行っていないことだけを捉えて、金銭消費貸借契約の成否が決定づけられるということは考えにくいのですが、貸主であれば、何故返還を前提とした言動を取っていなかったのか、一定の合理性のある理由を説明する必要があると考えられます。一方、借主が返還を前提とした言動を取っていた場合、それをどうやって証拠化するのかという観点から簡単な書面だけでもいいので、一筆取るといった対策を講じることが後々重要になってきます(例えば、「金●円を借り受けました」という一文だけの文書に署名押印をもらっておきさえすれば、金銭交付の事実を後で争うことはほぼ不可能となります)。
4.借主は別人であるとの抗弁に対して
無断で名義を冒用されて、いつの間にか借主になっていた…という事例が典型的のように思いますが、これは契約書や借用書が存在するパターンです。契約書や借用書が無く借主が争われる事例としてあり得るものとすれば、借主が法人なのか、役員などの個人なのかが争われる事例だと思われます。
この点、金銭の交付を受けた者が借主であると判断するのが原則論と考えられるところ、上記の事例において、法人代表者が金銭の交付を受けた場合、法人代表者として受けたのか、個人として受け取ったのか判然としません。この場合は非常に厄介であり、これといった決め手はないのですが、
- どちらがお金を欲していたのか(どちらの立場で借入の理由・必要性を説明していたかなど)
- 金銭消費貸借に至るまでの交渉に、どちらが関与していたのか(どちらの立場で交渉を進めていたのかなど)
- 金銭交付後の言動(返済猶予を求める際に、どちらの立場の事情を持ち出していたのかなど)
を総合的に考慮して決めていくことになると考えられます。
なお、これはテクニカルな話になってしまいますが、法人か個人か分からない場合、例えば主位的には法人、予備的には個人といった併合訴訟を提起する、法人を借主としつつ、役員に対して取締役の第三者責任を根拠に訴訟提起する(会社法第429条)などして、両当事者を最初から巻き込みつつ、訴訟の進行(相手の反論内容)に応じて、絞り込みを図るといった戦略をとることも検討してよいかもしれません。ただ、イレギュラーな訴訟戦術であることには間違いありませんので、弁護士と十分に相談しながら対応することをお勧めします。
5.(参考)弁済の抗弁に対して
借主により既に返済済みであると反論を受ける場合があります。
この場合、貸主としては金銭の交付を受けた事実があるのかを確認すると共に、金銭の交付を受けたのであれば、別の債務に対する支払いではないか検証することになります。
なお、複数の債務が存在する場合、借主が××債務の支払いに充てると特定したと主張する場合、そもそも当該特定があったのかで争いになりますが、当該特定が無くかつ充当方法について特別な合意がない場合、民法488条から491条の定めに従って処理されます。この場合
- 弁済期のあるものを先に充当
- 全ての債務に弁済期がある、又は弁済期がない場合には、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当
- 弁済の利益が等しいときは、弁済期が先に到来したもの、又は先に到来するものに充当
- 上記に当てはまらない場合は、それぞれの債務に応じて充当
という順に充当されることになります。
<2022年7月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
|
|






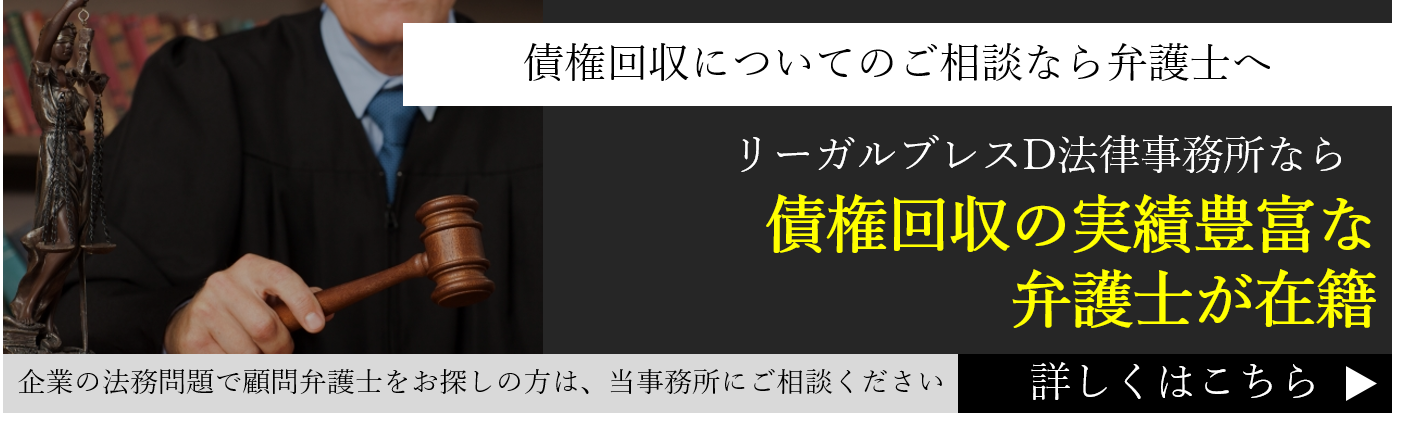

 弁護士 湯原伸一
弁護士 湯原伸一





































