Contents
【ご相談内容】
経費削減の一環として保険の見直しを進めているのですが、リスクヘッジの観点からは残しておいたほうが良い保険もあると考えられ、なかなか要or不要の仕分けができません。
企業活動を継続するにおいて、どういった保険が存在するのか、また保険に加入するに際してどういった点に注意するべきなのか等について、教えてください。
【回答】
保険と一口に言っても、公的保険と民間保険といった分類もあれば、強制保険と任意保険といった分類、生命保険と損害保険といった分類もあります。
それぞれ目的に応じて加入することになりますが、執筆者がこれまで経験した事例をベースに、企業の現場実務において問題となりやすい保険について、以下解説します。
なお、公的保険である労災保険と雇用保険から解説し、民間の保険会社が販売している損害保険と生命保険という順番で解説を行います。
【解説】
1.労災保険
従業員を雇った場合、従業員数や労働時間、非正規雇用(アルバイト、パート)等に関係なく、会社は労災保険に加入する義務が生じます。労災保険料の支払いがもったいないと言って加入したい会社も中には存在するようですが、労災事故が発生した場合の会社の責任軽減が大きなメリットになります。必ず労災保険は加入するべきです。
(1)人的範囲
上記の通り、加入したほうが会社にとってメリットが大きいのですが、加入対象にできない者が存在します。例えば、取締役等の役員職に就いている者は加入できません。もっとも、取締役とはいえ、実際の業務内容や業務遂行方法が従業員と変わりがない(法的には使用従属関係があるといいます)場合は加入可能です。
また、会社の社長(事業主)や一人親方も原則として労災に加入することはできません。ただし、特別加入制度という特例措置がありますので、要件を充足する限り任意で加入することが可能です。建設や運送等における事業主・一人親方が加入することが多いようです。
(2)労災適用の範囲
業務遂行中に発生した事故であれば、原則労災保険の適用範囲となります(但し、休憩時間中に事故が発生した場合は労災保険の適用外となることがあります)。また、通勤途中に発生した事故であっても、原則労災保険の適用を受けることが可能です(但し、合理的な通勤経路から外れたルート上で事故が発生した場合は適用外となります)。
よく問い合わせを受けるパターンとしては、出張中に事故が発生した場合、業務終了後の社内行事中に事故が発生した場合、自然災害により事故が発生した場合などです。
まず、出張中ですが、基本的には労災保険の適用があります。出張中は包括的な支配を受けていると考えるためですが、出張中の全く業務とは関係のない私的行為(例えば、出張ついでに私的に観光をしていた最中に事故が発生した)であれば、労災保険の適用は否定される場合もあります(もちろん最終的には労基署の判断にはなりますが)。次に、業務終了後の社内行事ですが、原則労災保険の適用は否定されます。もっとも、社内行事への参加が事実上強制されていた等の事情があれば、業務の延長であるとして労災保険の適用が認められる場合もあります。最後に、自然災害の場合ですが、業務とは無関係の自然現象であることから原則労災保険の適用はありません。但し、自然災害による事故が生じやすい事情がある場合(例えば、雨天下でも外で工事を行う大工が落雷を受け怪我をした場合など)、例外的に労災保険の適用が認められる事例も存在します。
なお、同僚・上司等からの暴行を受けた場合であっても、被害者の自招行為が原因であったり、専ら加害者の私的怨恨が原因ではない限り、労災保険の適用があるとされています。時々、当人同士で解決するよう指導しただけで、会社が何ら対応しないということがありますが、労災の申請があった場合、会社としては手続きに協力する必要があることに注意が必要です。
(3)労災の認定範囲
問題となりやすい代表例を2つ記載します。
過労死
長時間労働に従事していた従業員が死亡した場合、当然に労災認定が出るわけではありません。労災認定については、厚生労働省が公表している通達に基づいて行われます。過労死の疑いがある事例が生じた場合、会社としても次の通達内容を把握し、当該従業員の勤務状況について調査を行い、認定可能性を事前に予測しておくことが望ましいと考えられます。そして、認定可能性ありと判断する場合、労災ではカバーされない損害賠償問題(後述(5)ご参照)や風評被害対応の事前準備を行うべきです。
なお、通達は2021年9月に改正されていることにも注意を要します。
(参考)
精神疾患
うつ病等に代表される精神疾患が業務により生じたか否かについては、会社と従業員との言い分が異なることが多く、近時は深刻なトラブルになりやすい問題の代表格となっています。労災認定の判断基準については、厚生労働省が公表していますが、過労死の場合と比較するとやや分かりづらいところがあります。とはいえ、事前に認定可能性を予測し、対策を準備することは過労死の場合と同様ですし、精神疾患により従業員がしばらく休職する場合、将来的には復職の問題も視野に入れる必要があります。
かなり高度な専門知識を必要とすることから、精神疾患のある従業員への対応を行う場合、早期に弁護士に相談し対処法を検討することが望ましいといえます。
(参考)
(4)給付期間
従業員から質問を受けて、会社として回答に窮することが多いものとして、労災認定を受けた従業員が退職することとなった場合、引き続き労災保険給付を受けられるのかという問題です。
結論から申し上げると、受給可能です。
なお、会社に在籍し続けるつもりはないにもかかわらず、退職してしまうと労災給付を受けられないと勘違いしている従業員がいます。このような場合、労使双方にとって良い状態ではありませんので、適切に説明の上、必要な退職手続きを行うべきです。
(5)補償対象外の損害
労災保険は、労災事故が発生した場合に会社に代わって国が従業員の損害を補填する制度であり、加入するメリットが大きいことは前述したとおりです。ただ、労災保険により給付される範囲と、法律上会社が従業員に対して責任を負う損害賠償の範囲はイコールではありません。労災保険でカバーされない損害項目として代表的なものは次の通りです。
- 治療に関連して生じた入院雑費、付添看護費、装具・器具購入費(一部労災の給付対象になる場合もあり)など
- 休業損害の4割分(なお、労災では平均賃金の60%と特別支給金として平均賃金の20%の合計80%が支給されますが、特別支給金20%は損害賠償として充当されないこと要注意です)
- 後遺障害逸失利益及び死亡逸失利益(将来給付が予定されている年金等については損害賠償として充当されないことに注意が必要です)
- 慰謝料(労災では一切カバーされていません)
建築や運送など事故が発生した場合に重症となるリスクが高い業種については、労災保険でカバーされない損害を填補するものとして、民間の損害保険会社が提供している労災上乗せ保険と呼ばれる任意保険に加入することが、リスクヘッジ策として有用となります。
2.雇用保険
雇用保険についてトラブルになる場面を想定した場合、本来雇用保険に加入していれば受給できたであろう金銭を得られなかった場合が典型例ですが、現場実務で頻繁に出てくるのは退職の場面となります。
(1)受給の差異
従業員が自己都合退職を行った場合や、従業員の帰責性が重大な理由による懲戒解雇の場合、会社都合退職の場合と比較して、①失業手当が支給されるまでの待機期間が長くなること、②失業手当が支給される期間が短くなる、といった相違が生じます。
したがって、従業員としてはなるべく会社都合による離職扱いにして欲しいという要望が出てきます。一方、会社としても、自己都合や会社都合かによって直接的な利害がないため、従業員の要望を受け入れて会社都合扱いとして離職処理を行う場合もあるようです。
ただ、この場合、会社として留意しなければならない事項があります。それは、助成金との関係です。多数の助成金があるため一律に言い切ることはできないのですが、雇用関係の助成金の場合、過去一定期間において会社都合による退職がないことが要件となっていることが多いのが実情です。また、助成金の支給を受けたのち、一定期間内に会社都合による退職を実施した場合、助成金の返還を求められることがあります。助成金を受けている又は今後申請したいと考えている会社であれば、安易に会社都合扱いとはしないことが重要となります。
(2)会社都合か自己都合かで争いが生じた場合
自己都合が会社都合かで、従業員の失業手当に関して差異が生じることは前述の通りですが、これがために、会社が自己都合扱いとしてハローワークに手続きを行ったところ、従業員が異議を申立てて紛争が生じるということがあります。
この対処法ですが、基本的には会社の認識通りで離職手続きを進めれば問題ありません。従業員より異議申立てがあった場合、ハローワークより会社宛てに問合せ(調査)が入りますが、会社の認識を説明すると共に資料(例えば退職届など)を提出すれば、あとはハローワークにて判断を行います。ハローワークがどのように判断するかは、原則会社に利害はありませんが、上記(1)で解説した通り、助成金が絡む場合、会社としてはハローワークに対して積極的に働きかけたほうがよいものと考えられます。
3.損害保険(民間のもの)
企業リスクを補填するものとして様々な損害保険が存在しますが、企業活動においてよく問題となり得る点を中心に以下解説します。
(1)自動車保険(任意保険)
免責に注意
強制加入である自賠責保険に対して、民間の保険会社が提供している自動車保険は任意保険と呼ばれています。任意保険というからには付保する法律上の義務がないことは間違いないのですが、事業活動において自動車を利用する場合、リスクヘッジの観点から任意保険に加入することは事実上必須といえます。
ただ、必須とはいえ、保険料を負担し続けることが難しい場合、保険で補償される内容を一部削る等して保険料の削減を行うといった対策を講じることがあります。ただ、この対策を講じた場合、意外と多いのが補償されない内容(免責内容)について、会社がきちんと理解していないことです。
よく問題となるのは、物損事故における一部免責(一定額内の損害に留まる場合は保険金が支払われず、会社自らが損害賠償に応じなければならない)、一事故当たりの保険金支払いの上限額設定といったものがありますが、今一度、どういった場合に保険金が支払われないのか確認しておいた方が無難です。
自動車事故すべてに保険は対応しないこと
自動車事故が発生しても、任意保険に加入しておけば後は全て保険会社が処理してくれると考えている会社も多いのですが、これは一部誤りがあります。というのも、損害保険は第三者に発生した損害に対し、保険金で補償するというものです。したがって、自らが被った損害については原則損害保険の対象となりません(人身傷害補償特約や車両損害特約を付保していた場合は対象となりますが、特約であり当然に付保される内容ではありません)。
また、現場実務で起こり得る勘違いとして、自動車事故が発生した場合において、100%相手に責任があり、自らの過失はないと主張する場合、やはり損害保険は原則使用できません。これは、第三者に対して補償を行う意思がない以上、保険会社としては動きようがないからです。この場合、相手が会社に過失があるとして損害賠償請求を行ってきたとしても、保険会社は示談代行等の対応を行わず、会社自らが対処する必要が生じることに注意が必要です。
もっとも、最近普及している弁護士費用担保特約と呼ばれる特約を付保している場合、会社が被害者として損害賠償請求を行う場合の弁護士費用を保険会社が保険金として支払うことになります。そこで、この弁護士費用担保特約を利用して弁護士を選任し、相手との交渉や訴訟対応を行ってもらうという方法が考えられます。
自動車事故と従業員への求償
特に自損事故の場合に問題が生じやすいのですが、従業員が事故を起こし、会社車両が損傷等した場合、当然のことながら修理費等の損害を会社が被ることになります。この損害を穴埋めするために、会社は従業員に対して求償(立替えた修理費等の損害賠償請求)を行おうと考えることが多いのですが、法律上は求償が難しいとされています。なお、従業員に故意重過失がある場合であれば、一定割合で求償可能と考えられていますが、それでも全額負担を求めることは原則難しいというのが実情です。
従業員への求償については高度な専門知識が必要となりますし、仮に従業員が負担に応じたとしても、どういった方法で負担させるのか法的検討を要します(例えば給料からの天引きが可能なのか等)。弁護士に相談してほしいところです。
人身傷害補償特約に加入している場合の注意点
これはテクニカルな話となりますので、結論だけ押さえておいていただければと思うのですが、人身傷害補償特約に加入している場合、先に人身傷害補償特約に基づき保険金の支給を受けた上で、相手に対して損害賠償請求を行う方が、被害者が受け取れる金額が多くなる可能性があります。
もちろん等級変更による保険料負担の増額等の問題もありますので、一概に人身傷害補償特約を先行させたほうが良いとは言い切れないのですが、例えば従業員が業務遂行中に自動車事故を起こした場合、会社が従業員に対して、誰に対してどういった保険金請求を行うべきかをアドバイスする際の考慮要素になると考えられます。
なお、関連して労災保険と自動車保険との関係について触れておきますと、どちらを先に利用するかによって、損害賠償として受け取る金額に差異は生じません。もっとも、労災保険の場合、損害賠償とは関係のない補償があり、それを受給できるという点では事実上の差異は生じます(逆に、上記1.(5)で解説した通り、労災では慰謝料が補償対象とならないため、自動車保険で対応する必要があります)。
自動車事故と等級差損
損害保険を利用することで等級に変動が生じ、翌年以降の保険料が増額となった場合、損害保険を利用する原因となった事故当事者(従業員等)に、保険料の差額分を負担させたいと考える会社もあるようです。
しかし、等級差損については、そもそも法律上の損害賠償の範囲対象外と考えられています。したがって、理屈の上では従業員に負担させることはできないこと、要注意です(無理に負担させても、後で従業員が返還請求を行ってきた場合、会社としては対応に苦慮することになります)。
マイカー通勤
マイカー通勤を認めるか否かについては会社の裁量判断であり、マイカー通勤を認めないという方針を取ることも可能です。ただ、従業員の居住場所の都合により、マイカー通勤を認めざるを得ない場合もあるかと思います。この場合、必ずマイカー通勤については会社の許可制とした上で、許可条件の1つとして、従業員が付保している自動車保険の内容を指定するべきです(例えば、対人保険及び対物保険とも無制限にする等)。
なお、上記のような許可条件を設定した場合、保険料の一部負担を要求する従業員もいたりしますが、会社はこれに応じる義務はありません。
ところで、最近ではマイカー通勤ではなく、マイ自転車(?)通勤を行う従業員も増えてきているようです。自転車の場合、自賠責保険のような強制保険が導入されていない関係上、対人事故及び対物事故に対する保険が一切付保されていないことが多いのですが、昨今の報道でも周知されているとおり、事例によっては重篤な被害が生じる事故となることもあります。したがって、自転車通勤に関しても、何らかの制限や条件を課し、その一条件として自転車保険に加入させるといったことも検討したほうがよいかもしれません。
なお、会社が業務として自転車を従業員に貸出し、利用させている場合、会社において自転車保険を付保することが無難です(施設賠償保険の取扱いになったり、自転車保険として単独の取扱いとなったり、各保険会社にとって様々な取り扱いになっているようです)。
(2)火災保険
テナントとして物件を賃借する場合、家主指定の火災保険に加入させられることがあります。そのため、火災保険に加入した以上、自らの責任で火災を発生させたとしても、保険会社が対応してくれるので安心と考える方もいるのですが、一部誤解があります。というのも、賃借人に故意又は重過失がある場合、保険会社は求償を行ってくるからです。火災発生の原因となった者が完全に免責されるわけではないことを押さえておく必要があります。
さて、以下では会社が事業用の不動産等を所有することで、自らの判断で火災保険を付保する場合に、よく現場実務で質問を受ける事項について解説します。
一部保険と新価実損払方式
やや専門用語となってしまうのですが、一部保険とは、例えば5000万円の物件に対し、3000万円の保険を掛ける場合のことをいいます。このような場合において当該物件が火災で焼失した場合、保険金が支給されることになるのですが、3000万円が支給されるわけではありません。この場合、実損の60%相当額(3000/5000)しか支払われません。かなり勘違いしている会社が多い印象を受けますので、この点はご注意ください。
ちなみに、上記のような保険金支払い方法は保険法上の原則に則ったものなのですが、分かりにくいということで、最近の火災保険では新価実損払方式を採用することが多くなってきています。新価実損払方式とは、保険契約者が設定した保険金額(当然のことながら対象物件の評価額を上限とします)に応じて実損分を支払うというものであり、割合による支払いを排除した特約となります。
古い火災保険の場合、新価実損払方式となっていないことがありますので、火災保険の契約更新等の際に見直しを行うことをお勧めします。
地震との関係
現在のところ地震保険という単独の保険商品は存在せず、火災保険の特約として地震保険が付随するという形式になっています。
この地震保険に加入していない場合、火災が発生し損害を被ったとしても、地震によって火災が発生した場合には火災保険による保険金支給を受けることができません。地震への備え及び地震が発生した場合のリカバリーという観点からは、地震保険も加入することが望ましいといえます。なお、法令上、地震保険は居住用財産を対象としていますが、各保険会社は地震により事業用財産が被害を被った場合の対応を行う保険商品を販売しています。各保険会社によって対象範囲や保険額、免責内容など相違がありますので、比較しながら加入することが重要です。
(3)各種損害保険
以下では、執筆者が相談を受けたことが多い3つの事例について簡単な解説を行います。
ところで、上記(2)で解説した火災保険にも当てはまる事項なのですが、自動車保険以外の損害保険では、いわゆる示談代行(保険会社が加害者に代わって被害者との示談交渉を行うサービス)が付いていません。したがった、被害者との交渉はあくまでも保険契約者である会社自らが行う必要があることを押さえておく必要があります。また関連して、示談解決するに際しては、事前に保険会社に示談額・支払額が適正か照会し、保険会社の了解を得ておく必要があります。万一、保険会社に無断で示談解決した場合、保険金が支給されないこともありますので注意が必要です(事前に保険会社の了解が必要であることは保険約款に必ず書いてあります)。
情報漏洩保険
情報漏洩に対する世間からの厳しい非難等を目の当たりにし、情報漏洩対策が重要な経営課題になっている昨今ですが、残念ながらいくらセキュリティ対策を講じても情報漏洩は起こってしまうというのが現状です。そこで、情報漏洩は不可避的に生じることを前提に情報漏洩保険に加入する会社が多くなりつつあるとされています。
この情報漏洩保険ですが、各保険会社によって商品設計がバラバラであり、法務視点で指摘すると、次のような点に注意する必要があります。
- 補償範囲はどこまで及ぶか(情報漏洩被害者への見舞金等に要した費用を含むのか、謝罪広告・会見等に要する費用を含むのか、コールセンター委託費用を含むのか、原因調査費用を含むのか、被害拡大防止のための対策費用を含むのか、風評被害等の信用低下に対する損害分を含むのか等)
- 補償額は妥当か(顧客へのお見舞金について1名当たりの単価が低すぎないか等)
- 免責事由はどういったものがあるのか(従業員による情報持出しを免責事由にしていないか等)
生産物賠償責任保険(PL保険)
近時は“ジャパンブランド”と称して、国内で生産された製造物が海外に輸出され、販売されることが多くなってきていますが、一般的な生産物賠償責任保険の場合、国内で発生した事故のみ対応し、海外で発生した事故については補償外となっています。海外での販売を念頭に置いている場合、特約を付す等して補償範囲を見直す必要があります。
次に、補償対象範囲について要確認事項となります。特に、多くの生産物賠償責任保険の場合、生産物(製造物)に起因して発生した損害及び被害者への初期対応費用を補償対象としているのですが、事例によっては一番大きな費用負担となるリコール費用については原則補償対象外となっています。リコール費用を補償対象とする場合は特約が必要となることにご注意ください。
なお、生産物賠償責任保険は非常にややこしく、保険を販売する代理店もあまり内容を理解ができないというのが執筆者個人の感想です。会社としては、製造物に関する事故を想定した上で、当該事故を補償対象とする損害保険に加入することを希望して保険相談を持ち掛けるのですが、約款上の構成として免責事由があちこちに定められている関係上、加入してから実は補償対象外だったことが発覚するといった事例が実際にあったりします。場合によっては代理店ではなく、保険会社の担当者を呼び出した上できちんと保険設計を行った方が良いかもしれません。
物流保険
荷主が物流事業者に依頼して商品等を運送してもらう場合、物流事業者が定める運送約款に従って依頼することとなります。ただ、運送約款をきちんと読んで内容を理解している荷主は極少数にとどまるのが実情です。
さて、この運送約款について何が問題なのかというと、例えば、運送中に自然災害による事故が発生し商品が損壊等した場合、物流事業者は責任を負わないと定められていることが通常です。また、物流事業者の責任により事故が発生し商品等が損壊した場合であっても、損害賠償額の上限が定められていることが通常です。
運送約款の内容を変更してまで物流事業者と運送契約を締結することは稀であることを踏まえると、上記のような問題をクリアーするためには、荷主において対策を講じるほかありません。そこで、いわゆるオールリスク対応型保険に加入することで対処することが考えられますが、実はオールリスクと称しながらも、よくよく約款等を確認する一定事由による免責(保険会社が保険金を支給しないこと)が定められています。保険商品の名前だけで判断せず、補償の範囲はどこまで及ぶのかよくよく確認の上で保険に加入する必要があります。
4.生命保険
会社で加入する生命保険については、専ら節税対策で加入するといった会社も多いかもしれません。しかし、執筆者が受ける相談事例として、保険会社の担当者が説明したような節税効果が生じなかったというものが少なからず存在しますので、担当者の説明を鵜呑みにせず、最低でも顧問税理士に相談し、本当に節税効果が得られるのか確証を得た上で加入することをお勧めします。
ところで、横道にそれますが、債権回収の場面において、生命保険がターゲットになりやすいという点は債権者・債務者双方の立場であっても押さえておきたい知識となります。あまり知られていないのですが、生命保険について解約返戻金がある場合、債権者は解約返戻金を差し押さえた上で、それを現金化するために生命保険契約それ自体を解約することが可能となっています。したがって、債権者の立場であれば生命保険の有無は調査対象となること、債務者の立場であれば生命保険は安心して置いてくことができない、ということを理解していただければと思います。
以下では、生命保険の中でも、現場実務で問題となりやすいものを2つあげておきます。
(1)団体生命保険
団体生命保険とは、会社等の団体が保険契約者となり、当該団体に所属する従業員や役員等を被保険者として契約する生命保険のことをいいます。なお、受取人は会社等の団体になっていることが多いと思われます。
さて、この団体保険がどういった点で問題となったかというと、被保険者である従業員や役員等が知らない間に生命保険が掛けられ、当該従業員や役員等が死亡した場合に会社等の団体が生命保険を受給する一方で、死亡した従業員や役員等の遺族は何も受けることができないという倫理的な点です。
この点、死亡した従業員や役員等の遺族が生命保険会社に対して、直接保険金請求ができないことは既に最高裁判所の判決で決着がついています。このため、死亡した従業員や役員等の遺族が、生命保険により金銭を得た会社等の団体に対し、クレームその他請求を行ってくるといったトラブルが発生します。もちろん、理屈の上では、社内規程上の死亡退職金及び弔慰金等の定めがあればそれに従って支払えば済みますし、そもそも死亡退職金及び弔慰金等の規定が存在しないのであれば支払い義務さえ生じません。とはいえ、本件のような場合、倫理的な面では正直褒められた対応ではないことは確かですので、何らかの対応が望まれます(なお、生命保険会社もこういったトラブルを踏まえ、団体生命保険については色々と工夫しトラブル回避となる商品設計にしているようです)。
(2)事業承継
事業承継対策として生命保険を用いる場合、次の2通りのパターンがあります。
- 社長個人が生命保険に加入し、受取人を後継者とすることで、死亡保険金を納税費用に充当する、相続対策(後継者に自社株、後継者以外の相続人に代償金を分配する場合の資金とする)として用いる方法。
- 会社が生命保険に加入し、被保険者を社長、受取人を会社とすることで、後継者が自社株を取得しても相続税が支払えない場合に会社が自社株の買取りを行い、その買取代金を死亡保険金に充当することで、相続税対策を行う方法。なお、生命保険に加入することで生じる支払保険料を経費計上することで株価対策を行ったり、生命保険を途中で解約することで得られる解約返戻金を先代社長の退職慰労金に充当するといった用いられ方もあります。
注意点ですが、社長個人が生命保険に加入する場合、後継者が社長と親族・血族関係にあるのかが重要となります。なぜなら、多くの生命保険会社では、受取人について近親関係を要求しているからです。したがって、いわゆる従業員承継の場合は、生命保険を利用した事業承継対策を用いることが難しいこと、理解する必要があります。
一方、会社が生命保険に加入する場合、死亡する時期によっては会社が自社株の買取をできなかったり(財源規制の問題など)、解約返戻金が少額にとどまっていたりする(一定期間を経過しない限り解約返戻金が予定額に満たない等)といった、不確定要素が付きまとうという点です。人の死をコントロールすることはおよそ不可能である以上、加入に際しては慎重な判断が必要となります。
<2022年2月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
|
|






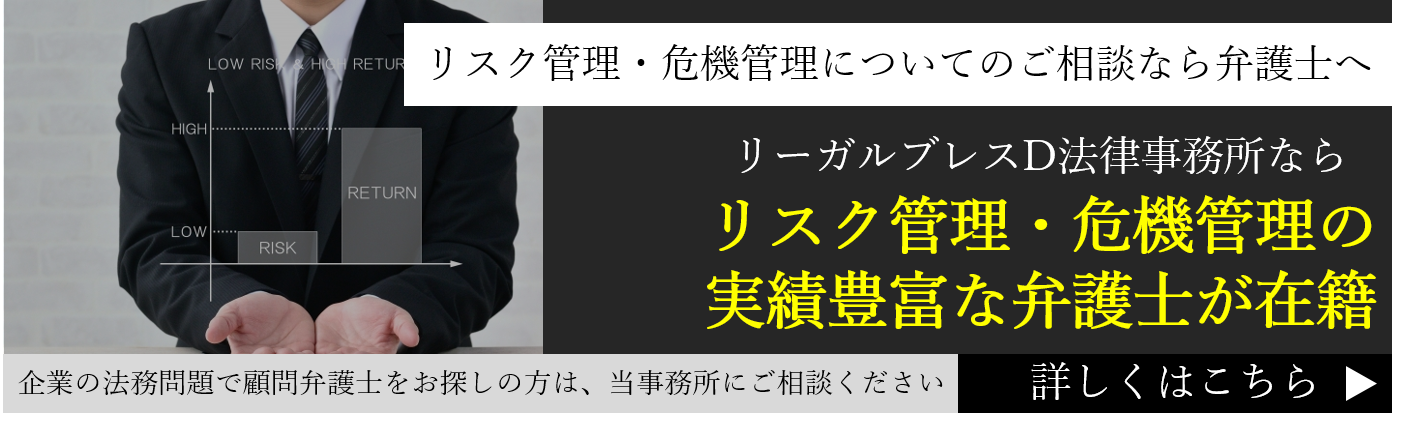

 弁護士 湯原伸一
弁護士 湯原伸一





































