【ご相談内容】
下請法が適用される取引の場合、下請事業者は親事業者に対して、どういった事項を要請できるのでしょうか。
【回答】
下請法は、下請事業者を保護するための法律ですので、下請事業者は様々な法的保護を受けることになります。具体的には次の通りです。
- 下請代金の支払を60日以内に行うよう要請ができること
- 下請事業者に対して、契約内容を明らかにする書面(3条書面)を交付するよう要請できること
- 親事業者が禁止行為を行ってきた場合、親事業者に対してはもちろん、行政機関を通じて改善を要請できること
具体的にどのように活用していくのか、【解説】にて説明します。
【解説】
1.支払期日について
「下請代金の支払期日を60日以内に行うこと」とは、文字通り、支払いサイトを60日以内にしなければ下請法違反になるということです。
この60日の起算点ですが、下請事業者が親事業者に納品(給付又は役務提供)した日から起算するとされています。つまり、単なる引渡し日が起算点とされており、検収完了日ではないこと要注意です。したがって、例えば、支払いサイトとして「検収完了日が属する月の翌月末日」と約定していた場合において、3月20日の納品、4月1日に検収完了、5月末に支払いとしてしまうと、下請法違反となってしまいます。ここは取引実務でよく間違えるところですので注意が必要です。
以上のことから、下請業者としては、下請法を根拠に支払いサイトを60日以内に設定するよう要請することで、キャッシュフローの安定化を図ることが可能となります。
なお、下請法が定める60日以内に下請代金を支払わなかった場合、年利14.6%の遅延損害金の支払うことが法律上明記されていますので、この点を指摘しながら交渉するのも一案です。
2.書面交付義務について
「下請事業者に対する書面交付義務が生じること」ですが、イメージとしては親事業者が下請事業者に対し、発注内容を書面にて交付するがこと義務付けられていると考えればよいかと思います。
日本の取引現場を見ていると、往々にして口頭で受発注のやり取りがされています。たしかに、民法及び商法の原則からすれば、口頭でも契約が成立したと法的には考えることができます。ただ、何らかの取引上のトラブルが生じた場合、口頭でのやり取りは後で確認することができませんので、いわゆる「言った言わない論争」になりがちで、どういった契約内容だったのか客観的に確認することができません(極端な場合、そもそも発注などしていない!といったトラブルさえあります)。こうなると、受注側である下請事業者は、下請代金をスムーズに回収することができませんので、こういった「言った言わない論争」を防止することを目的として、親事業者は下請事業者に対して書面(発注書など)を交付することが義務づけられています。
さて、この書面ですが、下請法第3条に根拠を有することから、通称「3条書面」と呼ばれています。この3条書面に記載するべき事項ですが、次の通りです。
- (1)親事業者及び下請事業者の名称(番号,記号等による記載も可)
- (2)製造委託,修理委託,情報成果物作成委託又は役務提供委託をした日
- (3)下請事業者の給付の内容(委託の内容が分かるよう,明確に記載する。)
- (4)下請事業者の給付を受領する期日(役務提供委託の場合は,役務が提供される期日又は期間)
- (5)下請事業者の給付を受領する場所
- (6)下請事業者の給付の内容について検査をする場合は,検査を完了する期日
- (7)下請代金の額(具体的な金額を記載する必要があるが,算定方法による記載も可)
- (8)下請代金の支払期日
- (9)手形を交付する場合は,手形の金額(支払比率でも可)及び手形の満期
- (10)一括決済方式で支払う場合は,金融機関名,貸付け又は支払可能額,親事業者が下請代金債権相当額又は下請代金債務相当額を金融機関へ支払う期日
- (11)電子記録債権で支払う場合は,電子記録債権の額及び電子記録債権の満期日
- (12)原材料等を有償支給する場合は,品名,数量,対価,引渡しの期日,決済期日,決済方法
この3条書面は取引を依頼した場合、直ちに交付する義務があります。
したがって、下請事業者としては、下請法第3条を引用しながら書面の発行要請を行うことで、発注内容の明確化と証拠化を図ることが可能となります。
3.親事業者による禁止行為
下請法が適用される取引の場合、下請事業者は親事業者に対し、下請法第4条に定める11類型に該当する行為を行わないよう要請することができます。そして、親事業者が当該行為を止めない場合、公正取引員会(実際には各地方によって公正取引委員会が委託している行政機関)に対し申告することで、行政を通じて当該行為を止めるよう圧力をかけることが可能となっています。
以下では下請法に定めている順番とは異なり、一般的な取引の時系列を念頭に置きながら、禁止行為について解説を行います。
(1)交渉段階で問題となり得る行為類型
買いたたき(第4条第1項第5号)
おそらくは「買いたたき」が問題となってくる事例は、既に下請事業者と親事業者との間で何らかの取引実績があり、今後新たに発生する個別取引にかかる単価等につき、一方的に見直し(減額)を要求された、という事例が多いのではないかと思われます。しかし、下請法上は、下請事業者と親事業者が既に取引を開始していることを前提にしていませんので、理屈の上では全くの新規取引の場合でも適用がありえます。したがって、交渉段階で該当しうる下請法上の禁止行為として整理しています。
さて、現場実務でよくご相談を受ける内容として、下請法上の親事業者が、下請事業者に対し、社会情勢に応じて(例えば円相場の変動など)、今後の取引につき代金減額交渉の申入れを行えば直ちに下請法違反になるのかという点です。
この点についてですが、まず代金の減額交渉を行うことは取引上当然あり得ることであり、これについてまで下請法が規制を及ぼしているわけではありません。したがって、原則的には問題なく、下請事業者としても直ちに下請法違反と主張できるわけではないこと注意が必要です。しかし、減額を要求する側(親事業者、例えば製造メーカー)の力が強く、部品業者(下請事業者)が否応なく従わざるを得ないという力関係の歪みがあるのであれば、下請法違反の疑いは生じるものと言わざるを得ません。
結局のところ、代金減額交渉が行われるのは世の常であるというところがありますので、下請法が禁止する「買いたたき」の該当性判断は形式的にはできません。協議の状況、通常対価との乖離状況、対価の内容、原材料の価格動向など様々な要因を検証した上で判断する必要があります。下請事業者としても、減額されることで、どういった経営上の支障が生じるのか具体的な数字を示しつつ、それでもなお減額を迫られ拒絶することが困難だったという一連の流れを示すことができないことには、なかなか「買いたたき」を主張しづらいところがあることに留意するべきです。
(2)取引実行中に問題となり得る行為類型
購入・利用強制(第4条第1項第6号)
特段の理由もないのに、親事業者が指定する物やサービスについて、下請事業者に強制購入させることが禁止されます。例えば、親事業者の取引先が販売している商品について、下請事業者に対し、協力要請と称して購入目標額を設定するといったものが該当しえます。
ところで、製造委託などで多いのですが、下請事業者が制作し親事業者に納品する製造物の品質維持のため、親事業者が原材料や治具・工具を指定し、有償で下請事業者に供給するという場合があります。この場合も一見すると購入強制に該当しそうなのですが、製造物の品質維持という正当な理由があるため、下請法違反にはなりません。ただ、製造物の品質維持目的があるとはいえ、例えば、下請事業者が部材等を自らの取引先より仕入れており、特段品質上の問題が過去発生していないにもかかわらず、今後は親事業者が指定する仕入先より部材を購入するよう指示することは、たとえ仕入値が安くなるといった下請事業者に有利となる事情があったとしても、下請法違反となりえます。
下請事業者としては、親事業者より特定の物・サービスの購入・利用を要請された場合、必要性はどこにあるのかを問い質しつつ、それによって下請事業者に生じるメリットとデメリットの比較、親事業者以外の第三者との関係で生じうる懸念とその回避策を検証しながら、受け入れるべきかを判断する必要があります。そして、納得がいかない場合、下請法違反の可能性を指摘しつつも、いきなり親事業者の要請を断るのではなく、他の代替策を含めた交渉ができないのか試みつつ、落としどころを探るといった対応が求められるものと考えらえます。
不当な経済上の利益を提供要請(第4条第2項第3号)
例えば、親事業者が下請事業者に対し、決算対策協力金や協賛金の支払いを求めること、従業員の派遣要請を行うことなど、下請事業者にとって何らのメリットが無いにもかかわらず、一方的に下請事業者に対して経済上の負担を要求することが禁止されています。
ただし、逆に下請事業者にとってメリットがある場合、例えば協賛金を負担することで、親事業者による販促行為が活発化することで販売実数が増加し、結果的には親事業者との取引拡大が確実に見込まれる場合(つまり協賛金の負担以上の利益を下請事業者が享受することが確実である場合)、あるいは従業員を派遣することで、販売ノウハウや現場対応の経験等を下請事業者が得ることができ、下請事業者自らの業務遂行の改善につながるといった場合には、「不当」とは言えない以上、下請法違反とはなりません。
下請事業者にとってメリットが生じるか否かは、下請事業者の考え方次第といったところもあるのですが、例えば、従業員の派遣要請に応じて販売経験を積んだところで、もともと親事業者との契約では、親事業者の取引先に対する直接営業は禁止されている等の制約がある場合、果たして下請事業者にとってメリットが生じているといえるのかは疑問があるものと言わざるを得ません(下請事業者がもともと別事業として、親事業者の取扱い業務とは関係のない販売事業を行っていたというのであれば、まだ検討の余地があるかもしれませんが、これとて果たして下請事業者にとって直ちにメリットがあるといえるのかは相当疑問があると思われます)。
いずれにせよ、下請事業者にとってメリットがないと本音では思っている場合、まずは親事業者に対して、要請を受けることで下請事業者にとってどういったメリットがあるのか具体的な説明を受けること、それでもなお納得がいかない場合は下請法違反を指摘しつつ、親事業者の要請をやんわり断るとった対応が求められるかもしれません。
以上が「不当な経済上の利益を提供要請」に関する典型的な事例なのですが、最近は知的財産権の譲渡に関係して、この条項が問題となり得ることが多くなってきているようです。例えば、従前から下請事業者が保有している知的財産権を用いて商品製造等を行っている場合において、当該商品の納入に際して知的財産権も一緒に譲渡するよう親事業者が要求する、しかし知的財産権の譲渡対価は考慮されていないといった事例です。特にプログラム等の情報成果物制作取引では、この問題が起きやすいので、下請事業者として注意を払う必要があります。すなわち、知的財産権の譲渡ではなくライセンスを付与する形式にて対処できないか、譲渡対象となる知的財産権の絞り込みを図ることができないか、といった視点が下請事業者には求められます。
(3)個別業務の遂行段階
受領拒否(第4条第1項第1号)
例えば、下請事業者が契約に基づいて製造物等を納入しようとした際、親事業者の都合(例:在庫がだぶついている)により、製造物等の受入れを親事業者が拒否すること、これが典型的な受領拒否と呼ばれるものであり、下請法上禁止されている行為類型となります。なお、製造物等に明らかに外観上の不具合がある場合など下請事業者に責任がある場合、親事業者が受入れを拒否することは正当性がありますので、下請法上の受領拒否に該当しません。
さて、上記のような典型事例以外でも、受領拒否の問題となり得るものとして、正式発注前の事実上の生産開始依頼の事例があります。例えば、親事業者が定める販売計画に基づき、親事業者が納期と数量を下請事業者に対し内示した場合、下請事業者としては納期に間に合わせるために正式発注前に生産を開始しなければならないという場面が多く出てきます。そして、こういった下請事業者の実情を親事業者も知りつつも放置し、その後何らかの事情で販売計画が変更となったことで、親事業者が下請事業者に正式発注する数量が減少していた、といった事例などです。下請事業者としては無駄な作業をさせられたうえ、その作業に対する対価を親事業者より支払ってもらえないということが多いのですが、こういった事例の場合、受領拒否に該当する可能性が極めて高いものと考えられます(なお、内示の場合、本件事例では実質的に発注と同視できますので、書面の発行がされていないケースでは3条書面の交付義務違反も問うことが可能です)
下請事業者としては、何らかの損失補償を親事業者に要請する場合に、下請法違反を指摘しながら交渉するといった手法もあることを知っていただければと思います。
返品(第4条第1項第4号)
例えば、既に親事業者に納品済みの商品について、下請事業者に責任が無いにもかかわらず、親事業者の都合(例:商品が売れない)で、商品を下請事業者に返還するといった事例が代表的なものであり、下請法上禁止される行為類型となります。先述の「受領拒否」禁止が納入前という時間軸であるのに対し、この「返品」禁止は納入後という点で、表裏の関係に立つと考えることができます。なお、受領拒否のところでも触れましたが、当然のことながら、納品後に検査を行ったところ不具合が見つかったので下請事業者に返品することは下請法違反とはなりません。
ところで、この返品禁止の問題は、民法上の契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)の問題と重複するところがあります。そして、2020年4月1日に改正された民法では、不具合があることを知ったときから1年以内に通知すれば責任追及することが可能と、大幅な内容見直しが行われました(なお、売買の場合は商法第526条の問題となります)。したがって、民法に従う限り、不具合があることを知ったときから1年以内に通知することで返品可能と考えることが可能となるはずなのですが、下請法の運用実務としては、民法とパラレルに考えられてはいないようです。すなわち、納品後の検査に合格はしたものの、実は直ちに発見できない不具合があり、後に不具合が発覚したので下請事業者に対して返品を要求したところ、既に納品時から6カ月を経過していた場合、原則として下請法違反として取扱うとされています。
この運用実務を踏まえると、下請事業者としては、納品後6カ月を超えての返品については拒否しつつ、補修又は金銭補償(減額等)で対応するという方針にて、親事業者と交渉することになると考えられます。
不当な給付内容の変更・やり直し(第4条第2項第4号)
下請事業者に責任が無いにもかかわらず、親事業者の都合(例:途中で仕様が変更になった)で、発注の取り消しを行ったり、既に発注時に仕様に基づく業務が開始しているにもかかわらず内容の変更を命じたり、納品した商品等のやり直しを命じたりすることが禁止されます。
なお、不当な給付内容の変更・やり直しについても、改正民法(契約不適合責任)との関係を考慮する必要があるのですが(なお、売買の場合は商法第526条の問題となります)、下請法の運用実務としては、直ちに発見ができない不具合があったとしても、納品後1年を経過した場合は原則として親事業者はやり直しを命じることができないとされています(但し、親事業者が1年を超えて契約不適合責任を負担している場合は、その期間内まで延長することを下請事業者と予めと決めておけば、やり直しを命じることは可)。
下請事業者としては、親事業者との間で契約不適合責任を負担する期間をどのように取り決めているのかを確認しつつ、たとえ下請事業者の責めに帰す事由があったとしても、一定期間が経過している場合は、当然に無償でやり直しに応じなければならない訳ではないことを頭の片隅に置いておくべきです。そして、現場実情にもよるかと思いますが、事例によっては下請法違反を指摘しながら親事業者と交渉し、下請事業者の損失軽減を図るといった策を講じることも検討してよいと思われます。
(4)支払い段階
代金減額(第4条第1項第3号)
下請事業者に責任が無いにもかかわらず、親事業者の都合(例:販促目的で価格を下げて市場販売する等)で、一方的に下請代金を値引きすることを禁止するというものです。この行為類型の場合、発注時の代金に関する合意事項を無視ものであり、当たり前と言えば当たり前の禁止行為と言えるのですが、取引上の力関係によってはこういった当たり前のことさえ守られていない実態があることがあることから、あえて明文化されています。
なお、下請事業者に責任がある場合、例えば納品物に不具合があったため、不具合分に相当するものを減額することは当然問題とはなりません。しかし、不具合があった場合に一律にペナルティとして一定額を控除するといった場合、果たして不具合と減額分との間で均衡がとれているのか不明確となります。均衡がとれていない場合は、代金減額に該当するものとして下請法違反となること、下請事業者として知っておくべき知識となります。
ところで、代金減額になりうるのか微妙な問題として、ボリュームディスカウントやリベート(割戻金)の問題があります。親事業者が一方的に下請事業者に対してボリュームディスカウント等を押し付けてきた場合は、当然下請法違反の問題となってきます。また、「一定期間内に、一定数量を超えた発注を達成した」場合にボリュームディスカウントを行うという事例において、例えば、前年度の発注実績が10万個であったにもかかわらず、今年度において8万個超えればボリュームディスカウントを行うというのは、ボリュームディスカウントという名を借りた単なる代金減額にすぎませんので、下請法違反の問題が生じてきます。
下請事業者としては、前年度の実績や今後の受注見込みを考慮しつつ、ボリュームディスカウント等を実施することでコスト軽減などメリットを得られるのか十分に考慮し、納得がいかない場合は下請法が禁止する代金減額に該当すること(なお、親事業者が申し入れてきた時点によっては「買いたたき」や「不当な給付内容の変更」に該当する場合もあります)を指摘しつつ、合理的な落としどころを探る交渉を進めたいところです。
代金支払の遅延(第4条第1項第2号)
下請事業者に責任が無いにもかかわらず、親事業者の都合(例:決済資金が無い)で代金支払いを遅延するといった事例が典型ですが、やはりこの行為類型についても、発注時の支払時期に関する合意違反に該当する点で、禁止されて当然の内容と位置付けることができます。
ちなみに、支払期日の設定に関しては、上記1.で解説した通り、納入日から60日以内という下請法上のルールがあります。したがって、60日超の支払いとなった場合は、この代金支払の遅延にも該当することになります。
なお、下請事業者と親事業者との契約上、親事業者の取引先より代金回収ができない場合は、代金回収終了後支払う旨規定されていることがあります。一見すると親事業者のみの都合とも言えず、かつ下請事業者としても一旦は合意している以上、下請法違反にはならないのではないかと勘違いするかもしれませんが、こういった場合を含め、単純に代金支払いが遅延すれば下請法違反となります。つまり、下請事業者としては、一切の例外なく下請法違反を主張して代金支払いを親事業者に請求することができますので、ある程度強気の交渉ができることを知っておくと対処しやすいものと考えられます。
割引き困難な手形の交付(第4条第2項第2号)
繊維業では90日、その他業種では120日を超える手形期間を定めた手形をもって支払いに充てることは禁止されています。
最近では紙媒体による手形が決済手段として使われないケースが増えてきているものの、一方で電子手形を用いた決済手段も用いられているようになっています。本記事執筆時点では、電子手形による支払いサイトについても上記を適用するというのが運用実務ですが、将来的には変更があり得ることに注意が必要です。
下請事業者としては、正直なところ手形決済によるメリットが薄れてきている状況ですので、可能な限り現金決済の変更を要請することが望ましいものと思われます。なお、現金決済の変更する場合、時々支払いサイトが手形による支払いサイトと同様にすることを親事業者より求められることがあります。しかし、これは上記1.の支払期日を60日以内に定めることに違反することはもちろん、実際の支払いが60日を超えた場合、合意の有無を問わず上記の代金支払いの遅延に該当し、下請法違反となります。
下請事業者としてはこういった知識を正確に保有し、現金決済に際しての支払いサイトについて適切な期間を設定してもらえるよう交渉することがポイントとなります。
有償支給原材料等の早期決済(第4条第2項第1号)
有償支給原材料を用いて制作・製造する商品の決済前に、当該原材料の決裁を行うことが禁止されています。
ちなみに、有償支給材については下請事業者が親事業者に対して、現金決済を行うということは稀であり、下請代金と相殺勘定にて決済することが多いものと思われます。この相殺勘定を行うにあたって注意したいのが、民法の規律とは異なっているという点です。すなわち、合意の有無を問わず、有償支給材を用いて製造等した商品にかかる下請代金が発生するタイミング以前に下請事業者に相殺勘定する(支払を行わせる)ことは一律に下請法違反になるというのが、ここでの意味になります。
例えば、親事業者からの有償支給材が数ヶ月分まとめて引き渡され、その有償支給材を用いる前(有償支給材を用いて製造等した商品の納入前)に決済されてしまうと、下請事業者は、従前の下請け代金を満額回収することができず、たちまち資金繰りに窮するといったこともあり得ます。相殺勘定のタイミングについては親事業者も誤解が多いように思われますので、下請事業者としても、キャッシュフロー見直しの一環として今一度検証してみるのも一案です。そして、もし問題があるようであれば相殺勘定のタイミングを後ろ倒しにしてもらう等の交渉の根拠として下請法違反を指摘するといったことも念頭に置くべきです。
(5)その他
報復措置(第4条第1項第7号)
下請法違反であることを公正取引委員会等へ通報したことを理由に報復措置を取ることが禁止されています。
下請事業者が親事業者に対して下請法違反を指摘する場合、それ相応の覚悟が必要となるのですが、その点の実効性を確保するための根拠規定であり、行政機関が親事業者に対して指導を行う端緒にもなり得る条項となります。
下請事業者からの下請け法違反の指摘に対し、親事業者が不穏な動きを見せた場合、牽制する意味でこの条項の存在を親事業者に告知するといった方法で用いることが考えられます。
4.まとめ
下請法が親事業者に対して要請している事項は、過去のトラブル類型から抽出されたものであり、多くの下請け事業者にとっては経験しているトラブルと思われます。したがって、下請法は下請事業者にとっては武器であり、活用しない手はありません。
しかし、現実には親業者にとっては不都合なものとなりますので、あの手この手で下請事業者に対する嫌がらせを行ってくる場合があります。このため、下請法に関する正確な知識を下請事業者が保有することは当然のことですが、下請法をどういった時に、どういった場面で、どういった方法にて活用するのかといった実務ノウハウについては、やはり弁護士等の専門家と相談しながら対処していくことが肝要です。
執筆者個人の見解とはなりますが、下請事業者単独で親事業者に対して立ち向かっていくのは、なかなか難しいのが実情だと思います。下請事業者が交渉の窓口になる場合であっても、弁護士の支援・バックアップが常に得られる環境下で対応することが望ましいものと思われます(場合によっては、親事業者に対して弁護士が関与していることを暗示するだけでも効果があることもあります)。是非とも弁護士に相談してほしいところです。
なお、本記事ではポイントとなる事項をかいつまんでの解説に留めていますが、詳細な内容を知りたい場合は、次の資料をご参照ください。
<2021年10月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
|
|
;






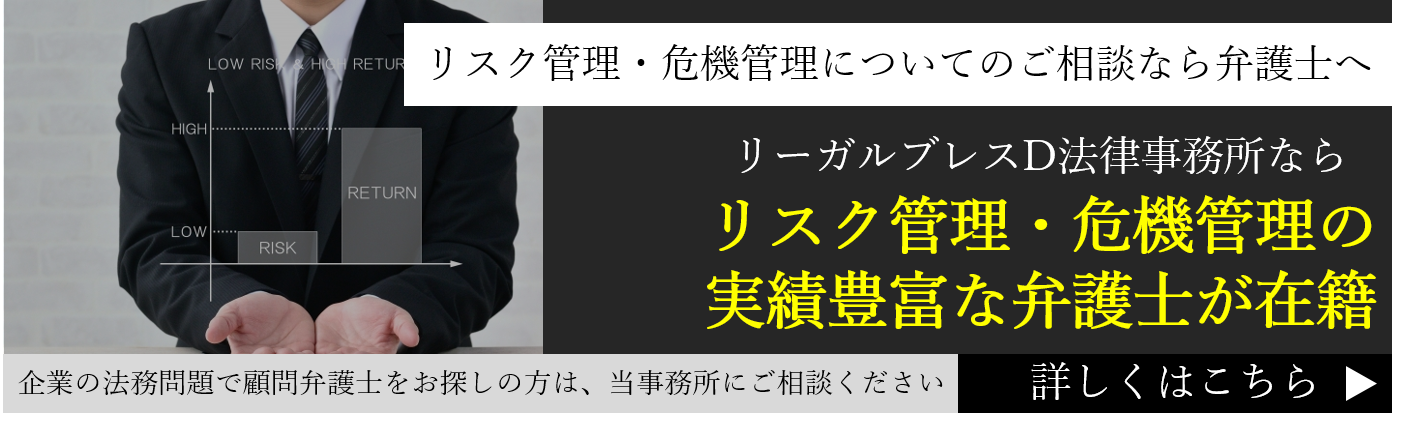

 弁護士 湯原伸一
弁護士 湯原伸一





































