Contents
【ご相談内容】
退職した従業員が残業代の未払いがあるとして支払いを要求する書面を送付してきました。当社は未払い賃金はないものと認識しているのですが、どういった点に注意して未払い残業代請求への対応を行えばよいでしょうか。
【回答】
賃金計算の基本的なやり方は、請求者が労働者であったことを前提に、「1時間当たりの単価(基礎賃金)×労働時間」となります。
したがって、労働者に該当するのか、基礎賃金の計算方法に誤りがないか、労働時間の算出方法に誤りがないかを中心に据えて検討することになります。次に、残業代として支払ったと考える手当等が法律上の要件を充足するのか、権利行使期間内で請求があったのか等の周辺部分も順次検討することとなります。
以下、具体的な手順について【解説】で説明します。
【解説】
未払い賃金(残業代など)請求が行われた場合、企業としてどういった点に着目すればよいのか、以下解説します。
1.身分・属性を確認する
(1)「労働者」に該当するのか
労働者に該当しないのであれば、労働基準法に基づく残業代発生の余地はありません。業務委託契約、請負契約といった名称にて契約を締結している者から残業代請求があった場合、労働者に該当するか否かの検討がまずは必要となります。
この点、労働者か否かの判断のポイントは「使用従属性」です。使用従属性の判断については、様々な考慮要素がありますが、大きな要素となるのは、具体的な業務指示等に対する諾否の自由、勤務時間等の拘束の有無、対価の計算方法といったものがあります。例えば、某牛丼チェーンのクルーと呼ばれる店舗業務従事者が、業務委託契約という名目で働いていたようですが、マニュアルに従って業務を行い裁量の余地が無いこと、シフトによる時間管理が行われていたこと、時間当たりで対価が支払われていたことからすると、労働基準法でいう労働者と判断されることになるかと思います。
(2)使用人兼務役員
例えば、肩書として「取締役営業部長」「取締役総務部長」といったものが使用人兼務役員に当たります。取締役として就任し登記もされているのであれば、役員であり、役員報酬である以上、労働者に該当する余地はないはずです。しかし、特にオーナー企業で親族以外の者が役員に就任した場合に多いのですが、役員に就任しても、特に業務内容は変わらず、指揮命令を受ける、時間拘束があるということもあります。
この場合は、実質は労働者として取り扱われることもありますので、単純に就任登記の有無だけで判断せず、上記(1)と同じく、労働者該当性を検討する必要があります。
(3)管理監督者(機密事項取扱者、監視労働・断続的労働)
マクドナルド店長の裁判例以降、「管理監督者」に該当する労働者は存在しないのではないかと言われているくらいですので、実際には通用しないことが多いという印象があります。一応の判断基準としては、「職務の内容、権限、責任の程度」「労働時間の裁量性、労働時間管理の程度」「待遇の内容、程度」を考慮することになります。なお、現実的な対策としては、管理監督者だから残業代が発生しない(管理監督者に該当しても深夜残業分は別途割増賃金が生じること注意)という対策を講じるよりは、待遇に応じて支給している役職手当を、後述する固定残業代に位置付けるという方がリスクヘッジになるのではないかと思います。
あと、管理監督者について定めている労働基準法41条では、機密事項取扱者、監視労働・断続的労働を行う者についても残業代が発生しない(深夜残業は別)ことが規定されています。しかし、機密事項取扱者とは経営者と一体となって行動する者と解釈されていますので、正直該当者は存在しないに等しいと思われます。また、監視労働・断続的労働については、労働基準監督署の許可が必要となりますので、これも該当者は少ないよう思います。
いずれにしましても、管理監督者の有無について検討するとして、正直勝ち目は薄いように思いますので、別の争点で戦う方が得策ではないかと考えます。
弁護士へのご相談・お問い合わせ
当サイトの記事をお読みいただいても問題が解決しない場合は
弁護士にご相談いただいた方がよい可能性がございます。
下の電話番号もしくはメールにてリーガルブレスD法律事務所までお問い合わせください。
06-4708-7988メールでのご相談
2.基礎賃金からの控除の可否について確認する
(1)手当の控除
残業代を算出するに際して、まずは基礎賃金(1時間当たりの賃金単価はいくらか)を計算する必要があります。この基礎賃金ですが、給料全額をベースにしなければならない訳ではなく、一定の手当については基礎賃金を計算するに際しては控除してもよいとされています。具体的には労働基準法37条5項、労働基準法施行規則21条に定められているのですが、現場実務で問題となるのは、「家族手当」「住宅手当」の控除の可否です。
まず、それぞれの手当ての定義ですが、
・家族手当=扶養家族数又はこれを基礎とする家族手当額を基準として算出されたもの
・住宅手当=実質的に住宅に要する費用に応じて支給されているもの
とされています。
したがって、例えば、扶養家族の有無や人数に関係なく一律に支給されている場合は、算定基礎から除外できる家族手当には該当しないことになります。また、住宅手当についても、例えば、一律支給される場合、扶養家族の有無によって金額変動させる場合(住宅以外の要素で額を決める場合)、賃貸と持家の区分にしたがって一律に支給する場合には、算定基礎から除外できる住宅手当に該当しないことになります。
(2)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与)と年俸制
賞与(ボーナス)については、は基礎賃金を算定するに際して控除してよいとされています。つまり、月額賃金のみをベースにしてよいということです。もっとも、年俸制による賃金体系の場合、控除できません。この結果、年俸制の場合は、一般的な日給月給制の賃金体系よりも基礎賃金額が増額となる傾向があります。
一昔前まで、年俸制を採用すれば残業代を支払う必要はないという間違った情報が流れていましたが、これは完全な間違いです。むしろ、年俸制の場合は、残業代の支払額が大きくなってしまうリスクがあります。
(3)基本給に残業代込
中小企業からのご相談を受ける際、社長より「採用時に、当社は残業代込で××を支払うと説明しており、従業員も納得していた。そうであるのに何故、残業代を支払わなければならないのか」と困惑・怒りの声をお聞きすることがあります。同意を得ている以上、残業代が発生する余地など無い!というお気持ちの部分は理解したいものの、同意を得た以上は一切問題が無いという訳にはいかないのが法律の世界です。特に、労働法の分野については、従業員が同意をもらっても法的には無意味(就業規則の変更が必要といった制約)ということがままあります。
さて、基本給の中に残業代が含まれているという主張ですが、現在の裁判所の考え方からすると、ほぼ通用しないと判断したほうがよさそうです。例外的に有効とされるのは、基本給のうち、具体的にどの部分が時間外手当に該当するのか明確に区分できている場合とされていますが、基本給の内訳を明示している会社は皆無に等しいのではないでしょうか。
したがって、あまり有効な判断材料にならないのが実情です。
(4)定額(固定・みなし)残業代
近時の残業代リスクを検討する上で、一番実効的であるとして注目されている方法となります。上記(3)とは異なり、基本給と別の手当を設ける、例えば、営業手当でもいいですし、もっとストレートに固定残業代という手当名称でもよいのですが、ある種の手当につき、予め残業代として充当、支払うというものです。
これについては、就業規則(賃金規程)において、ある種の手当てが時間外手当として支給されるものであることを明記しておくこと、かつ労働条件通知書・労働契約書において、ある種の手当てが何時間分の時間外手当に該当するのか記載すること、ここまでは最低限の条件として、可能であればさらに、不足が生じた場合は残業代を支払うことを明記しておくこと、給料明細上も基本給とは別に手当支給していることを明記しておけばクリアーできるのではないかと思われます。
なお、定額残業代として認められなかった場合、基礎賃金の算出に際して控除できないこと(基礎賃金が増額すること)、未払い残業代より控除できないこと、という2つのデメリットを被ります。ダブルショックなんて言われたりもしますが、定額残業代については、近時最高裁判例も出るなどして、かなり議論が煮詰まってきているので、情報のアンテナを張っておいていただく必要があります。
あと、定額残業代で不足した場合は、不足分の残業代を支払う必要があることは当然のこととして、定額残業代に含まれる残業時間まで勤務しなかった場合、返金を求めることができるのかという疑問が生じます。これについては固まった結論が無いようですが、現時点での動向を踏まえる限り、返金を求めるという対応は避けるべきではないかと執筆者個人は考えます。
3.割増率について確認する
(1)原則論
これについてはご存知の方も多いかと思いますが、2020年1月時点での法令では、
・法定労働時間を超えた残業の場合(深夜時間に該当しない)…2割5分
・深夜時間の残業の場合…2割5分
・法定労働時間を超えかつ深夜残業となった場合…5割
・法定休日に勤務した場合…3割5分
となります。
(2)中小企業の特例(60時間超え)
2010年(平成22年)4月1日以降、一定の大企業については、1ヶ月当たりの残業時間が60時間を超えた場合、60時間を超えた部分についての割増率が50%とされています。ただ、これについては「一定の大企業」にのみ適用されるにすぎません(詳しくは厚生労働省のWEB等で確認してください)。時々、労働組合が介入して残業代交渉を行っていると、知ってか知らずか、適用除外の中小企業であるにもかかわらず、60時間を超えた部分について50%割増率で計算し、残業代を請求してくる場合がありますので、要注意です。
なお、中小企業に対する適用猶予については、2023年に猶予がなくなること要注意です。
(3)法定休日と所定休日
上記(1)で、法定休日の場合は3割5分の割増率になることをご説明しました。
ところで、意外と見落としがちになっているなと思うのが、例えば土日休みの週休2日制の会社において、土日に休日出勤した場合、どちらに対しても3割5分の割増賃金を支払っている事例があるということです。労働基準法は、法定休日に対して3割5分で支払えと言っているにすぎませんので、例えば、日曜日が法定休日であれば、土曜日は単なる時間外労働に過ぎませんので、2割5分で支払えばよいという結論になります。労働基準法を上回る割増率で支払うことは自体は何ら問題はありませんが、人件費の適正化という観点からは、しっかり確認したいところではないかと思います。
なお、労働基準法上、法定休日は1週当たり1日以上定めておけばよいとされていますので、就業規則においても、法定休日については1週のうちの曜日のみを定めておけばよいのであって、わざわざ土曜日や祝祭日まで法定休日として明記する必要があるのかは、検討の余地があるのではないかと思います。
(4)法内残業
残業が発生すれば、割増賃金を支払わなければならないという意識が強いのか、意外と見落としがちなのが、
・所定労働時間を超え、法定労働時間内の残業の場合…割増率分の加算なし
という点です。
例えば、一昔前の会社であれば、所定労働時間を7.5時間とし、7.5時間を超えた部分については割増賃金を支給しているところがあります。しかし、労度基準法は8時間を超える前の0.5時間については割増賃金を支給することまでは求めていません。単に0.5時間分の賃金を支給すれば足りますので、恩恵的に割増分を支給していないか、見直してもよいかもしれません。
4.労働時間への該当性について確認する
(1)残業許可制(残業命令を出していないこと)
最近の就業規則の傾向として、「残業を行う場合は上長の許可を要する」と定めてあることが多いです。このような定め自体は何ら問題ないのですが、この定めを根拠に、会社が残業を認めたわけではない(従業員が自発的に業務しただけに過ぎない)ので、残業代を支払う必要が無いという主張が通用するかは別問題です。
例えば、残業が日常的に行われている職場環境において、いちいち上長の許可を得ることなく残業していたというのであれば、黙示に許可があったとして、会社の指揮命令下にある労務の提供=残業代が発生するという結論になりやすいと思われます。残業を許可していないことによる残業代支払い義務なしと主張するのであれば、これまでの残業について、許可制という運用が実態として伴っていたかにつき証拠固めを行う必要があります。
(2)事業場外のみなし労働
外回りの営業職の方で、現場から直帰することが多いという場合、この制度により残業代の支払い対象となる労働時間の削減(みなし労働時間を超える分については労働時間としてカウントされない)を図ることができる場合もあります。
ただ、この「事業場外のみなし労働」を用いる場合、事業場外の業務に従事したことという要件を充足する必要があることはもちろんですが、労働時間が算定しがたいことという要件も充足する必要があります。この点、最近の携帯電話やスマートフォンの発達により、いつでも上司が確認や指示ができる状況であることからして、果たして「労働時間が算定しがたい」と言えるのか微妙な情勢になってきています。したがって、携帯電話やスマホ端末等で事業場外から報告させているような場合は、事業場外のみなし労働時間に該当しない可能性がありますので、注意が必要です。
(3)裁量労働制
裁量労働制については、専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制の2種類があります。専門業務型裁量労働制については就業規則の整備、労使協定の締結、労基署への届け出という手続き要件が、企画業務型裁量労働制については労使委員会決議の書面、労基への届け出という手続き要件がそれぞれ課せられていますので、まずは手続き面がクリアーできているかがチェック事項となります。その上で、それぞれの制度が対象としている労働者に本当に該当していたのかをチェックする必要があります。
ちなみに、執筆者の経験上、裁量労働制を採用していると主張されても、そもそも論としての手続き面が整備されていないため、有効な反論となりえないことが非常に多いです。今一度、確認を行っていただければと思います。
(4)変形労働時間制
就業規則を見ていると半分以上の会社で変形労働時間制を採用する旨規定されています。
もちろん、変形労働時間制を採用すること自体は何ら問題ありませんし、上手く活用ができれば残業代抑制策になります。しかし、労働基準法が求めている要件を充足していないことがほとんどであり(典型的には一定期間あたりのカレンダーが定められていない)、有効な反論材料として使えないということが多いように感じます。
これについても、運用が法の求めるレベルに達しているか確認して頂ければと思います。
(5)手待ち時間
手待ち時間とはいわゆる指示待ち時間のことです。仕事をしていないので休憩時間に該当するのではと思われるかもしれませんが、休憩時間の定義は労働から完全に解放されている時間を意味します。したがって、指示待ち状態であれば労働から解放されておらず、指示命令があればいつでも仕事を開始できるよう準備しておくという意味での拘束時間であり労働時間としてカウントされることとなります。
なお、当然のことながら、手待ち時間ではなく休憩時間と主張できれば、その分労働時間が削減できますので、主たる争い方としては「労働から解放されていたと言えるのか」がポイントになります。
(6)週44時間の特例
これは我々弁護士でもついうっかり見落としてしまうことがあるのですが、商業(卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、駐車場業、不動産管理業、出版業(印刷部門を除く)など)、映画演劇業(映画の映写、演劇など、但し、映画製作・ビデオ製作の事業を除く)、保健衛生業(病院、診療所、保育園、老人ホーム等の社会福祉施設、浴場業(個室付き浴場業を除く)など)、及び接客・娯楽業(旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地など)のうち、常時10人未満の労働者を使用する事業主であれば、週の法定労働時間が44時間となります。
したがって、先ほど「3.割増率いて確認する」の項目で述べたように、法定労働時間を超えない残業、つまり割増賃金とはならない残業代が生じることになりますので、この点も要チェックかと思います。
5.権利不発生といえないか確認する
(1)消滅時効の援用
未払い賃金については2年の消滅時効というのが現行法です(但し、2020年4月施行の民法改正に伴い本来は5年となるところが、“当面の間”は3年の消滅時効に変更となります)。
消滅時効の援用を行えば、2年(2020年4月1日以降に発生した賃金は当面の間3年)内に発生した賃金か否かについて争点が移るはずなのですが、時々、会社が消滅時効を援用することは権利濫用であるという反論を受けることがあります。執筆者も何度かこういった反論を受けたことがあるのですが、裁判実務では、残業代請求を意図的に妨害したという事情が無いことには、こういった反論が通用するとは考えづらい状況です。単に残業代を支払わなかったという事情だけでは、消滅時効の援用が権利濫用とはならないと考えてよいかと思います。
(2)残業代請求権の放棄
前述の「2.(3)」で記載した内容とも少し関連してくるのですが、予め「残業代は請求しません」と書面を取り付けても、このような約束事は無効です。
一方、残業代が発生してから、従業員と話し合い、その結果「残業代は請求しません(放棄します)」と書面を取り交わした場合は有効です。残業代以外のメリットを提案することで、こういった書面を取り付けることになるかと思いますが、労働組合が介入してきている場合は、各従業員と個別折衝を行うこと自体、不当労働行為と言われかねませんので、慎重に対応する必要があります。
6.今後予想される方向性について確認する
(1)内容証明郵便の場合
本人名義であれ代理人(弁護士)名義であれば、内容証明郵便を利用する=相手方は本気と考えた方がよいでしょう。全く無視した場合は、高確率で次の法的手続きを取ると予想されますので、反論するべき事項があるのであれば反論するといった応答は行うべきです。
なお、よくタイムカードの開示を要求されるのですが、心情的には「開示したくない!」と思う経営者の方もいると思います。また、法律上は明確にタイムカード開示義務を定めた規定はありません。しかし、実際の裁判例をみると、明らかに残業代の支払い必要性があるにもかかわらず、タイムカードの開示を拒絶した事例について、慰謝料請求が認められた事例が存在します。
したがって、「なんで、不利な証拠を敵に渡さなければならないんだ!」と思われるかもしれませんが、法律論としては残業代の未払いがあれば支払う必要がある以上、ここは開示したほうが無難です。
(2)労働局からのあっせんの場合
まず誤解の無いよう説明しますと、あっせんについては「あっせんによる解決を受けるか否か」会社側に選択権があります。そして、仮にあっせんによる解決を拒絶したとしても、法律上の不利益や制裁はありません。
ただ、執筆者の経験上、あっせんの方が、裁判所よりも会社側の実情に沿った解決案を出してくれることが多いので、残業代の支払い義務がある場合は、参加したほうが柔軟な解決を図れるのではないかと思います。
(3)労働組合からの団体交渉申入れの場合
たとえ退職者であっても、従業員として勤務していた当時の問題ですので、団体交渉に応諾する法的義務があります。したがって、労働組合と協議しながら解決を図るほかありません。なお、団体交渉を拒否した場合、不当労働行為としてペナルティを受けることになります。
(4)裁判所から書面が来た場合
裁判所からの書面を無視した場合、会社にとって不利益な判決が一方的に出されてしまいますので、対応は必須です。
ところで、残業代に関する裁判手続きとしては、主に労働審判手続きと、通常裁判手続きの2種類に分けられます。
労働審判手続きは1回目の裁判期日に、会社の言い分と証拠をすべて出す必要がありますので、とにかく急いで準備する必要があります。
一方、通常裁判は労働審判と異なり、1回目の裁判期日ですべての主張と証拠を出す必要はありません。その意味では、少し落ち着いて対応することができます。しかし、通常裁判手続きで怖いのは、既に退職しているのであれば、残業代の支払いが完了するまでに年利14.6%という高利の遅延損害金が課せられること、会社の対応如何によっては付加金と呼ばれる、残業代以外に制裁金を課せられる場合があることが難点です。
したがって、できる限り早期の和解解決を目指すのが、出血(会社財産の一時的かつ多額な流出)を防ぐという意味では得策なのかもしれません。
<2020年3月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
|
|






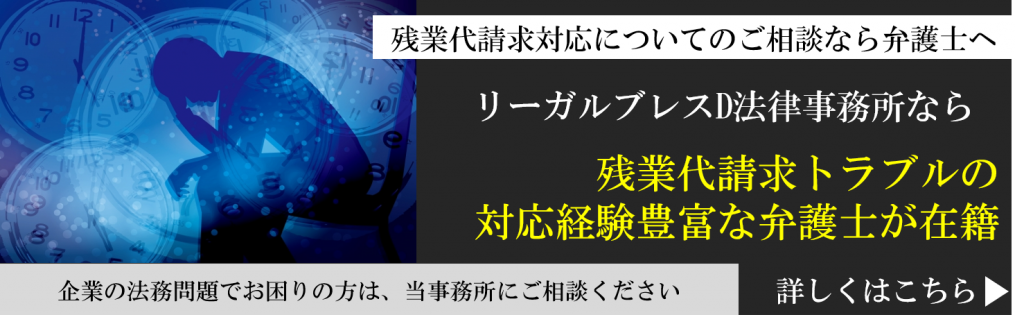

 弁護士 湯原伸一
弁護士 湯原伸一





































