Contents
【ご相談内容】
当社が債権者として、某企業に対する債権を有しているのですが、某企業は「金がない」と言ってはなかなか支払わず、当社も対処に苦慮しています。ところが、某企業と同一社長が社長を務める関連企業や社長自身は何だかお金を持っているような雰囲気です。そこで、関連企業や社長個人をターゲットにして債権回収を図ろうと考えているのですが、何か方策はあるでしょうか。
【回答】
債権回収は債務を負担する者から回収するほかなく、債務を負担していない第三者より回収することは困難です。しかし、その第三者に何らかの問題がある場合や、何らかの理由で事後的に支払いの意思表示を行ってきた場合、非常に例外的とはいえ回収対象とできる場合があります。
ここでは、第三者に問題があるパターンである、取締役等の第三者責任、法人格否認の法理、債権者代位、債権者取消権(詐害行為取消権)、第三者が事後的に支払いの意思表示を行ったパターンである(連帯)保証、併存的債務引受について、それぞれポイント事項につき解説を行います。
【解説】
1.原則
お金の支払い義務者=債務者以外の第三者は、当然のことですが債務を支払う法律上の義務はありません。したがって、当該第三者より無理やり支払わせようとして、債権者が強引な対応を取ってしまうと、かえって債権者は民事上の損害賠償責任を負担したり、刑事上の制裁を受けるなど不利益を被ることにもなりかねません。
以上のことから、債権回収を行う場合、どこまでいっても債務者に対し、債務者が保有する財産を対象として、回収手続きを進めていく必要があります。
もっとも、この原則論だけを貫くと、明らかに不合理という場合も実際の現場ではあります。そこで、非常に例外的な場面に限られますが、債務者以外の第三者より回収できる法制度がいくつか存在します。
一般化することはできない点ご留意いただきつつい、以下解説します。
弁護士へのご相談・お問い合わせ
当サイトの記事をお読みいただいても問題が解決しない場合は
弁護士にご相談いただいた方がよい可能性がございます。
下の電話番号もしくはメールにてリーガルブレスD法律事務所までお問い合わせください。
06-4708-7988メールでのご相談
2.例外的に第三者に請求できる場合
(1)取締役等の役員に対する責任追及
会社法第429条に根拠がある例外的制度となります。
この制度ですが、分解すると、
・取締役等の役員が会社との委任関係に基づき職務を遂行するに際し
・わざと(悪意)又は一般通常人ではありえないようなミス(重過失)による
・任務懈怠を起こした結果
・会社と取引関係にある者が損害を被った場合
・当該役員に対して損害賠償責任を追及することが可能
とする制度です。
したがって、本来的には、通常の取引関係を念頭に置いた債権回収のための法制度ではありません。
もっとも、過去の裁判例を見てみると、放漫経営や私的消費等により会社財産を不当に減少させ、これにより会社債権者の債権回収が困難となった場合(いわゆる間接損害型)、決済の可能性がないことを認識していながら手形を振り出し、これにより手形所持人が債権回収できなかった場合(いわゆる直接損害型)などの事例で、取締役等の役員に対する責任追及が認められています。
このため、取締役等の役員に対する責任追及制度は、実質的には債務者以外の第三者(=本件では取締役等の役員)より債権回収するための例外的手段として検討することが可能です。ただ、何をもって役員の任務懈怠とするのか、主観的事情である悪意重過失をどうやって立証するのか等、この制度を適用するためのハードルは相当高いと言わざるを得ないのが実情です。少なくとも、単なる経営判断のミスによる経営不振で支払いができないという程度であれば、当然に任務懈怠にあるとは言いづらく、この例外的制度の適用は認められないと考えられます。
いずれにせよ、この制度を用いての債権回収を検討するのであれば、弁護士等の専門家と十分に協議を行うべきです。
(2)法人格否認の法理
法人格否認の法理と称する法制度は、実は法律上の直接的な根拠規定はありません。ただ、裁判例上認められているものですので、法制度といっても間違いありません。
さて、法人格否認の法理とは、例えば、A企業という法人格は存在するものの、実質的にはオーナーの個人事業と同視できる場合(いわゆる形骸事例)や、A企業に適用される法律を回避する目的でB企業が設立されて場合(いわゆる濫用事例)など、法人格という形式を貫くことが社会的正義や公平に反する場合、その事案に限って法人の独立性を否定するという法制度です。本件の事例に当てはめた場合、前者であれば、A企業のみならず、実質的に同視されるオーナーも債務者であるとして取り扱われること、後者であれば、形式的にはA企業が債務者であっても、B企業も債務者として取り扱われることを意味します。
上記(1)との相違点ですが、上記(1)は会社の役員という第三者に対して債権回収を図る手段であるのに対し、この法人格否認の法理は会社の役員といった関係当事者を対象とするのではなく、形式的には債務者となっているA企業の実質的支配者(第三者)に対する債権回収手段として利用される法制度となります。
もっとも、法人格否認の法理は、法律上の直接的な根拠規定のない法制度ですので、非常にケースバイケースの判断になりやすく、やはり適用範囲は極めて限定されるというのが実情です。例えば、濫用事例と似て非なるものとして、企業再生の手法の1つである第二会社方式の例があります。この第二会社方式の場合、表面上は、「A企業に適用される法律を回避する目的でB企業が設立されて場合(いわゆる濫用事例)」とほぼ同視できる状態です。しかし再生手法である以上、当然に法人格否認の法理が適用されるわけではありません。結局のところ、B企業を設立した目的や動機がポイントとなるのですが、債務者側の主観的事情となる以上、債権者としてはなかなか裏付けを取りづらいところがあります。
以上のことから、法人格否認の法理についても、この制度を用いての債権回収を検討するのであれば、弁護士等の専門家と十分に協議を行う必要があります。
(3)債権者代位
上記(1)と(2)は、債権回収の対象となる第三者の行為に重大な問題があることを根拠にした法制度でした。ここで解説する債権者代位権は、第三者の行為の問題性はやや低く、支払いができない(無資力)の債務者が、自らの財産を増価させることができるにもかかわらず、権利行使を放置している場合(債権者代位権)といった、債務者側の不作為と債務者と第三者との財産の移動関係に着目した回収方法となります。具体的には、債権者代位権を用いた債権回収方法として、債務者が、第三債務者(=例えば、債務者が売主として商品を売渡した場合の買主のこと。買主は商品代金支払い義務を負担)に対して有する債権(=例えば売掛金)をいつまでたっても行使しない場合、債権者が債務者に代わってこの売掛金の回収を債務者に代わって行い、この回収金と債権者が債務者に有する債権を相殺することで、事実上の回収を実行するという方法となります。
結局のところ、債権者代位権を用いると、債権者が第三債務者という第三者より回収を行っているのと同じことになります。
ただ、本来的には、債務者が第三債務者に対して、どのタイミングで売掛金の回収を行うのかは債務者の自由のはずです。このため、債務者が無資力であるといった一定の要件を充足させない限り、債権者は債権者代位権を行使することができません。
また、2020年4月1日より施行された改正民法により、債権者が債権者代位権を行使しても、引き続き債務者は第三債務者に対して売掛金の回収を行うことが可能となりました。つまり、債権者が債務者に対して優先的に支払ってもらえるわけではないことになります。したがって、債権回収手段として債権者代位権の行使するのであれば、事前に債務者が第三債務者に対して有する売掛債権を仮差押えする(仮差押えすることによって、第三債務者は債務者に支払うことができない状態となります)といった対策も講じる必要があります。この点は、旧民法と取扱いが異なりますので注意が必要です。
(4)債権者取消権(詐害行為取消権)
債権者取消権(詐害行為取消権)を用いた債権回収とは、例えば、ただでさえ財産を持っていない債務者が、虎の子の有望な財産を第三者に不当な価格で売却した場合において、債権者がその売却を取り消すことで当該財産を債権者が第三債務者より取返し、その後当該財産と債権者が債務者に対して有する債権を相殺することで、事実上の回収を図るというものです。
債権者代位権と比較した場合、債権者代位権における第三債務者は、本来の義務を履行しただけにすぎないので影響があまりないと考えられるのに対し、債権者取消権の場合、既に実行済み(=義務履行済み)の取引を消滅させたうえで、取引実行前の状態に巻き戻すという点で第三債務者に与える影響は大きいと考えられます。このため、債権者取消権(詐害行為取消権)の場合、債権者代位権より更に厳しい要件、例えば債務者の害意及び第三債務者の悪意といった主観的事情を要件とするなど、かなり適用範囲が絞られているのが実情です。
専門的な知識はもちろん、相当綿密に準備しないことには債権者取消権(詐害行為取消権)の訴訟に耐えることが難しいため、必ず弁護士等の専門家と協議しながら行うべきです。
3.第三者が代わりに支払う旨表明している場合
債権回収の交渉を行っている最中に、債務者以外の第三者(例えば債務者が法人である場合に第三者である社長個人のこと)が代わりに支払うことを約束するという場面に出くわすことがあるかと思います。こういった場合に、本当に第三者からか債権回収することが可能なのか、可能にするためにはどういった事項に注意するべきかを以下解説します。
(1)(連帯)保証
債務者以外の第三者が代わりに支払うものとして、一番イメージしやすいのは(連帯)保証かと思われます。ただ、(連帯)保証の場合、口頭での約束のみでは成立しません。これは口頭で裏付け証拠がとりづらいからという話ではなく、(連帯)保証の場合、必ず書面による契約を行わなければならないからです。つまり、口頭での(連帯)保証契約は無効です。
支払交渉の最中に債務者以外の第三者が代わりに支払うことと約束し、それを録音化しているので、債権者としても安心…という訳にはいかないこと注意が必要です。
以下では、2020年4月1日施行の改正民法との関係での注意事項を解説します。
まず、(連帯)保証の前提となる主債務額が確定金額なのか、不確定金額(一定期間内で債務の増減が発生する)なのかを確認する必要があります。なぜならば、不確定金額の場合、根保証契約と呼ばれる類型に該当するところ、この場合、必ず保証人が負担する上限額=極度額を契約書に明記する必要があるからです。この極度額を明記しない場合、やはり保証契約は無効となってしまいますので、要注意事項となります。
次に、(連帯)保証の前提となる主債務が事業取引により発生する債務なのかを確認する必要があります。主たる債務について、事業取引により発生する債務ではない場合、改正民法による直接の影響はありませんが、事業取引により発生する債務である場合、さらに主たる債務が貸金債務であるかを確認してください。
事業取引に係る貸金債務である場合、保証契約を締結する前1ヶ月の期間内で、公証役場にいる公証人の面前で保証人候補者の意思確認を行う必要があります(但し、保証人候補者が主債務者である法人の取締役である場合など一定の場合は不要です。経営者保証の例外と呼ばれたりします)。加えて保証契約締結に際し、主債務者は保証人候補者に対し、主債務者に関する信用情報(民法465条の10第1項に定める事項)を提供する必要があります。万一違反した場合ですが、公証人の面前での意思確認を欠いた場合、保証契約は無効となります。また、信用情報の提供を行わなかった場合、保証人は後で保証契約を取り消すことができます。
一方、主債務について事業取引により発生する債務ではあるが、貸金債務ではない場合、公証人の面前での保証意思確認は不要ですが、信用情報の提供が必要となり、提供を行わなかった場合は後で保証人が保証契約を取り消すことができること、上記と同様です。
ところで、信用情報の提供ですが、法律上はあくまでも主債務者が保証人候補者に対して提供するという体裁になっています。すなわち、債権者に対して義務付けているわけではありません。ただ、信用情報の提供が行われなかった場合は保証人が後で保証契約を取り消すことができるとされていることから、債権者にとっては重大な利害関係を有することになります。したがって、債権者が主債務者に圧力をかけて、保証人候補者への信用情報の提供を行わせる必要があります。また、債権者主導の方策として、保証契約を締結する際、念のため、信用情報の提供を受けた旨の表明保証を保証人にさせるといった対策も講じたほうが無難と考えられます。
以上の通り、(連帯)保証については単に書面で契約書を締結すればよいという話ではなく、2020年4月1日施行の改正民法により、保証契約が有効となるための要件がかなり細かく設定されていることに注意が必要です。
(2)併存的債務引受
上記(1)で記載した通り、(連帯)保証については、書面での契約であることを前提に、その有効性を担保するためには様々な条件が課せられていることから、債権者にとってはかなり使いづらい制度となってしまったというのが実情です。
そこで、おそらく今後注目を浴びると考えられるのが併存的債務引受と呼ばれるものです。簡単にいうと、第三者が主債務者と同様の債務を引き受けることで、連帯債務者になるというものです。厳密には色々と異なるところがあるのですが、イメージ的には併存的債務引受を行った第三者は、保証人になったのと類似する効果が生じることになります。
債権者にとって都合が良いのは、この併存的債務引受の場合、書面での契約は不要であること、主債務の内容に応じた公証人の面前での意思確認や信用情報の提供が不要であるという点です。つまり、非常に簡易な方法で併存的債務引受を成立させることができます。
このように書くと、わざわざ保証にする必要性はなく、第三者に支払ってもらう場合は併存的債務引受にすればよいのでは、と考えらえるかもしれません。たしかに、理に適っている考え方ではあるものの、一方で懸念点としては、実質的には保証の脱法行為にならないかという点です。執筆者個人の経験にはなりますが、仮に第三者の言質を取った録音データが存在したとしても、裁判では、その発言だけを切り取って併存的債務引受の成否を判断することはありません。その発言に至るまでの前後関係を踏まえ、第三者の真意で(騙されたり、脅されたり、勘違いしていないか等)支払うと発言したのか厳密に検証の上、判断が行われることになります。
したがって、併存的債務引受についても確実性を期すのであれば書面にしておくこと、口頭で約束した場合であっても、前後の交渉過程を含めて記録化することが最低限必要になると考えられます。
<2020年12月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
|
|






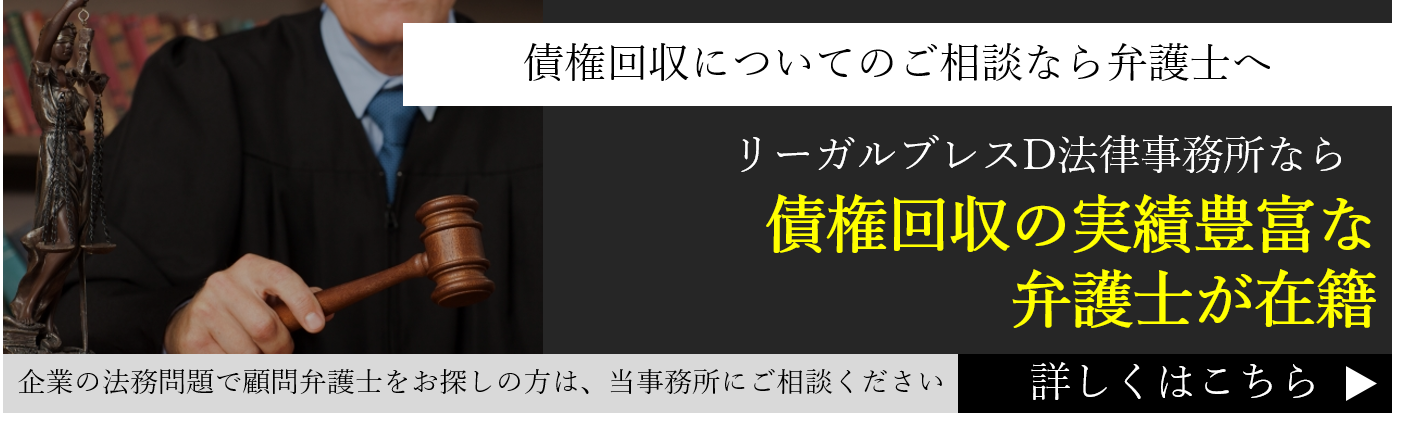

 弁護士 湯原伸一
弁護士 湯原伸一





































