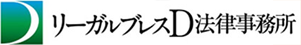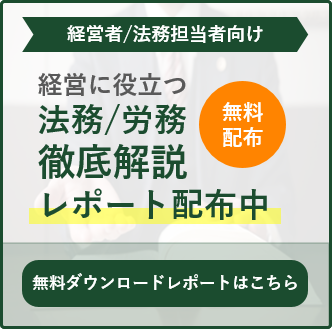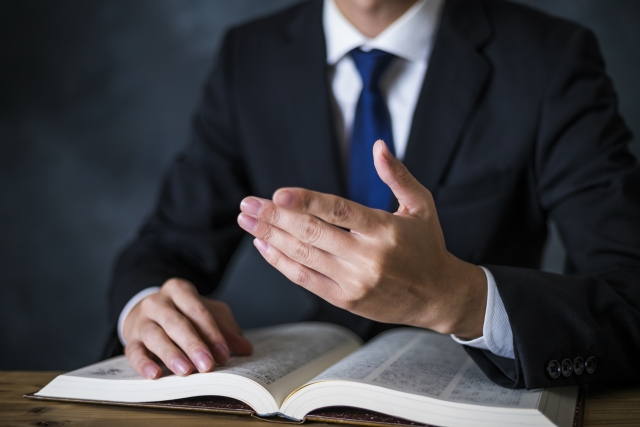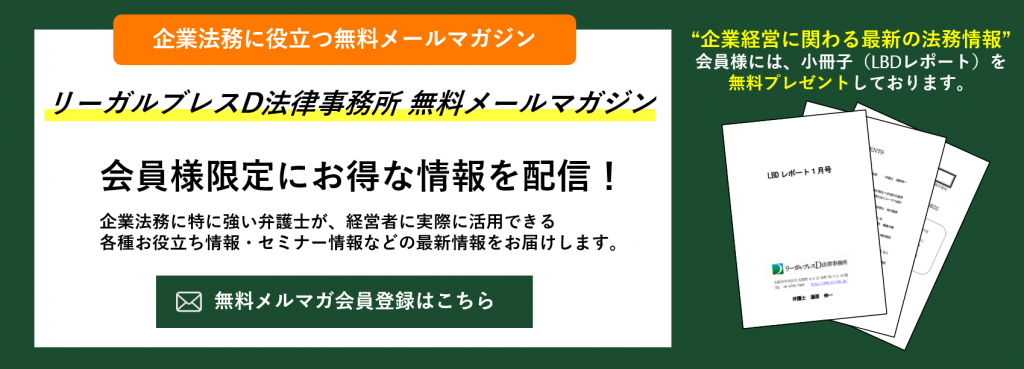 国内での取引が頭打ちになる中で、海外進出に活路を見出そうとする中小企業が多くなってきました。
国内での取引が頭打ちになる中で、海外進出に活路を見出そうとする中小企業が多くなってきました。
ただ、いきなり現地法人を立ち上げて活動することはハードルが高すぎることから、現地の事業者に商品を卸して販売してもらう方法が主流のようです。
この際に締結することになる特約店契約書(代理店契約書)につき、海外事業者であることが故の特殊性に注意を要します。
この特殊性につき簡単にまとめました。
ご相談
当社が取扱う商品を海外で販売するべく、現地の事業者に特約店になってもらうことを前提に、現地の事業者に商品を売渡すことを計画しています。
国内で用いている特約店契約書をそのまま翻訳して用いようと考えているのですが、何か注意点はありますか。
回答
いわいる代理店の取扱いについて、日本では特別な法規制が存在しないのですが、国によっては代理店法と呼ばれる特別法が存在します。
このため、国内で用いている契約内容が、その国の代理店法に違反していないかを確認する必要があります。ただ、海外法令であり調査するのが難しく、海外法令に対応できる弁護士も限られることから(場合によっては対応できる弁護士は存在しないということもあり得ます)、現実問題としては調査不十分のまま取引を開始せざるを得ないこともあるかもしれません。
その他で注意したい事項は、次の「解説」欄に記載します。
解説
実のところ考えだすとキリがないのですが、最低限押さえておきたい事項は次の6点です。
①請求額について
請求額に対し、日本法に基づく源泉徴収を行うのか、消費税は課されるのか、現地国の法律に基づく付加価値税が課されないか等の税務の取扱いについて、確認する必要があります。
なお、実費的な要素となりますが、関税の負担を誰がどのように行うのかについても取り決める必要があります。
②決済方法について
まず、決済に用いる通貨を決める必要があります(日本円、米国ドルなど)。また、為替レートについて、いつの時点を基準とするのかについても決めておく必要があります。
次に、銀行振込みによる決済を選択する場合、取引金融機関に対して海外からの送金に対応しているのかを確認する必要があります((場合によってはマネーロンダリングその他不正送金の疑いありとして、いきなり口座が凍結されることがあるため)。
③契約書の言語について
海外取引の場合、日本語と取引先の現地語の2種類の契約書が作成されることが多くあります。この場合、どちらの言語で作成された契約書が優先するのか決めておく必要があります(翻訳の誤り等で、契約内容に矛盾等が生じた場合に対処できるようにするため)。
④準拠法について
準拠法という言葉自体が聞きなれない言葉かもしれません。誤解を恐れずに端的に説明すると、契約の履行に当たり、どの国の法律が適用されるのかというのが準拠法の問題となります。例えば、現地法を準拠法として定めた場合、たとえ取引の全部又は一部が日本国内に行われたとしても、現地法に従って処理されることになります。
自社にとって有利な国の法律の適用が認められるのか、確認する必要があります。
⑤紛争解決手段について
国内取引の場合、紛争解決手段として裁判が選択されることを前提にどの場所にある裁判所を利用するのかという合意管轄に関する条項が定められることが通常です。
しかし、海外取引の場合、日本の裁判所で判決を取得しても、現地国では判決の効力が認められないという場合が多々あります。このため、仲裁手続きを紛争解決手段として選択するべきか確認する必要があります(なお、仲裁手続きを選択するに際しては、現地国が仲裁判断に従うことに表明するニューヨーク条約加盟国かの調査が必須となります)
⑥その他
日本法ではあまり意識されていませんが、現地法では「代理店」と「販売店」では明確に区別されている場合がありますので、用語例を整理統一する必要があります。
|
|





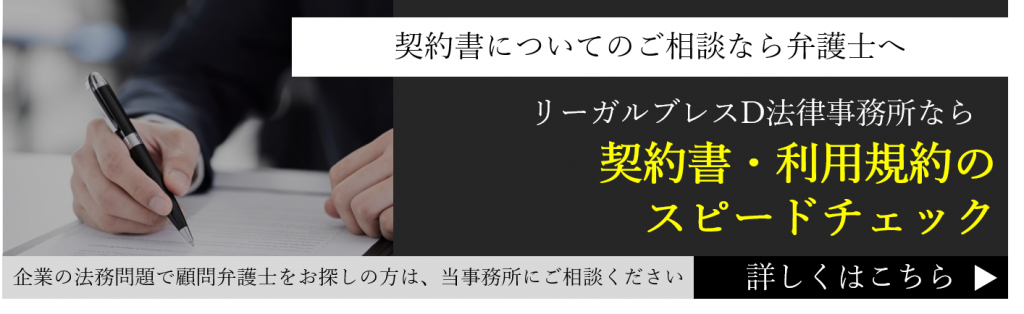
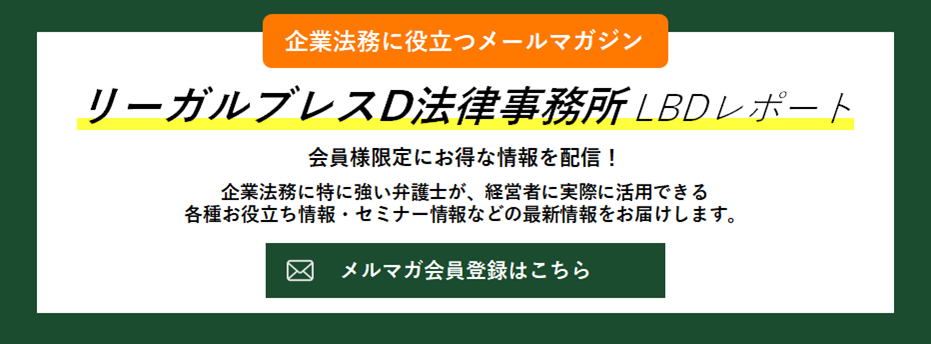
 弁護士 湯原伸一
弁護士 湯原伸一