Contents
【ご相談内容】
新型コロナにより、納期遅延や取引続行が不可能になる等の取引上の障害が多々発生したのですが、これを機に伝染病その他不可抗力による取引障害への対応マニュアルを整備しようと考えています。
まずは伝染病による取引障害が発生した場合における、法的な対処法・考え方について教えてください。
【回答】
不可抗力という用語例は契約書に定められていることが多いにもかかわらず、一方で不可抗力を前提にした紛争処理を行うことは通常ないため、何となく不可抗力について分かった気になっている…という方も多いかと思います。
実は不可抗力については、民法上の定義がありません。また、契約書を読み比べてみると、地震・水害・暴風等の自然災害のみを指している場合もあれば、テロや戦争・動乱といった人為的な異常事態を含めている場合、労働争議・物流遮断・法令改廃といった果たして不可抗力なのかと疑義のあるものまで含めている場合など、様々なパターンがあります。とはいえ、今回問題となっている伝染病・疫病については、不可抗力条項で対処するのか、また対処可能なのか検討対象になっていなかったように思われます。
そこで本記事では、法解釈論を中心としつつ、執筆者が知る限りの現場実務の工夫にも適宜触れながら解説を行います。
【解説】
1.不可抗力を原因とした取引解消の可否
(1)売主からの解除・価格改定の可否
例えば、世界的な伝染病が発生したことにより原材料の生産活動が停滞してしまった結果、売主が原材料を用いて商品製造することができず、買主への引渡しが困難となったという事例の場合、売主としては何か対策を講じたいという形で問題化します。
この点、理屈の上では、一度は売買契約を締結していること、上記事情は買主の帰責事由とは言い難いことから、売主は買主に対し、当然に何かを要求できる権利があるとは言えません。
しかし、売買契約書を締結しているのであれば、通常は不可抗力が発生した場合の対処法に関する条項が定められています。そこで、この不可抗力条項に基づいて何か対策を講じることができないかを検討することになります。ただ、従前用いられていた不可抗力条項は、風水害等の自然災害を念頭にしており、上記のような伝染病の事例に適用することが難しいことが多いように思われます。
では、不可抗力条項を用いることができない、あるいは契約書に不可抗力条項が定められていない(そもそも契約書を締結していない場合を含む)場合、売主としては何も言えないのでしょうか。
この点、解釈論とはなりますが、「事情変更の原則」と呼ばれる法理を用いることができないか検討することになります。この「事情変更の原則」ですが、要は契約締結時点では一切予測しえなかった事情が発生し、当該事情により一方当事者に看過できない著しい不利益が生じる場合、例外的に契約内容に従う義務から解放されるというものです。例えば、著しいインフレ等で対価の均衡を失することになった場合、契約内容に従った履行を行うことが経済的に著しく困難となった場合、契約内容に従って履行を受けても契約目的を達成できない場合などに適用の余地があると考えられています。
ただ、「事情変更の原則」という考え方、その考え方自体は承認されてはいるものの、少なくとも現実の裁判例を紐解く限り、この「事情変更の原則」を適用して事案の解決を図った事例は存在しないといわれています(本記事を執筆した2021年11月時点)。もちろん過去において適用事例が存在しないからと言って、今後も一切適用がないと考える必要はありませんが、「事情変更の原則」を錦の御旗として、売主が買主に対し、契約解除や価格改定を当然に要求できると考えるのは筋悪と言わざるを得ません。
ところで、現場実務ベースで考えた場合ですが、2020年4月1日施行の民法が適用される場合、契約の解除自体は相手方の帰責性を要求しないため実行可能です。しかし、買主に帰責性がない以上、買主は売主に対して損害賠償請求することは必須であり、売主としてはリスクある行動と言わざるを得ません。
正直なところ、売主において一刀両断で解決できる法的手段はないといわざるを得ないのが実情です。特に本件のような事例の場合、たしかに売主に同情するべき事情があるとはいえ、買主が非難されるいわれがないのも事実です。売主としては、平身低頭に買主にお願いベースで交渉を試みつつ、当事者間のみの交渉だけではうまく進まない場合、第三者が間に入る交渉の場を設定する(例えば民事調停など)といった方法を用いるほかないものと考えられます。当事者間のパワーバランスはもちろん、売買対象物の代替性、遅延することによる納品可能性、損失補償に対する負担の在り方等を考慮しながら交渉することになりますので、必要に応じて弁護士と相談しながら方針を決めていくことをお勧めします。
(2)買主からの契約解除の可否
上記(1)とは逆に、例えば、買主側の作業員全員が伝染病に罹患し、売主から商品の引渡しを受けることができないといった事情が発生した場合、買主としては売主に対して何らかの要望を出したいという形で問題化します。
この点、考え方としては同様に、まずは契約書が存在するのか、契約書が存在するのであれば不可抗力条項の定めはないか、不可抗力条項の定めがあるとして伝染病の場合に適用可能なのかを検討することになります。もし適用可能であれば、不可抗力条項の定めにしたがって処理すれば足ります。
一方、不可抗力条項を用いることができない場合、「事情変更の原則」を適用できるのかを検討することになりますが、上記(1)でも記載した通り、「事情変更の原則」の適用は極めてハードルが高く、これを用いて一気に解決を図ることが可能と考えるのは難しいところがあります。特に、買主が一方的に商品の受け取りを拒否した場合、法律上は受領拒否という扱いとなるため、売主から損害賠償請求を受けるなどのリスクが高まることになります。また、2020年4月1日に施行された民法に従えば、たしかに買主は売主の帰責性の有無にかかわらず、契約を解除することが可能ですが、やはり売主からの損害賠償リスクはどうしても残ります。
結局のところは、買主としては、売主に対して実情を説明したうえで、売買対象物となった商品が売主において転売可能であれば転売するよう要請し、売主の損失が少しでも減るような工夫を提案しつつ、一定の範囲で損害賠償を行うというのが現実的な対策になるものと考えられます。
なお、損害賠償の問題として対応する場合、損害賠償請求権者は、徒に損害を拡大させないよう防止する義務が課せられると考えられています。この点を考慮するのであれば、買主としては、商品受け取りが難しいと判断した場合、即座に売主に対して転売や代替販売先の提案などを行い、売主の損害拡大防止義務の履行を促した格好にするのが、後々の交渉で有利に進めやすいかもしれません。少しでも有利に交渉を進めようと考えるのであれば、早急に弁護士に相談の上、必要な対策を講じていくことが肝要です。
2.不可抗力により生じた契約違反への対応
(1)納期遅延した場合の売主の責任
例えば、売主の仕入先が伝染病の影響を受け、商品を仕入れるのに時間がかかった結果、買主に対して引渡し期限までに商品を引渡すことができなかったという事例において問題化します。
この点、契約書を締結している場合、納期遅延が生じた場合の処理方法について定めがある場合があります。また、納期遅延に関する処理方法に関する定めがない場合であっても不可抗力に関する定めで対処可能かを検討することになります。そして、これらの条項の適用可能な場合は、当該条項に従って処理することになります。
もっとも、契約書を締結していない、契約書を締結しているが納期遅延や不可抗力に関する条項が定められていない、又はこれらの条項を適用することができない場合もあり得る話です。この場合、少なくとも納期については口頭ベースを含め何らかの合意があるはずですので、形式論的には当該合意に反すること、すなわち契約違反に該当すると考えざるを得ません。したがって、買主から契約解除を主張されても、売主は原則的に文句を言えない立場となります(但し、厳密には民法第541条以下の該当性を検討する必要があります)。
しかし、売主が損害賠償義務を負うかは別問題です。なぜなら、納期に間に合わなかったこと、すなわち履行遅滞となったことにつき売主の帰責性が問われるからです。ちなみに、上記事例のような伝染病の場合、売主に帰責性が一切ないと言い切れるかというと正直なところ微妙と言わざるを得ません。なぜなら、理屈の上では、代替の仕入先を見つけて仕入れることが可能であった、原因の如何を問わず商品供給が滞らないよう在庫を確保するべきであった等々の、売主において履行遅滞にならいよう事前に防止策を講じることができたのではないかという指摘が必ず出てくるからです。
現場実務ベースでは、売主としては、納期遅延であることは事実である以上、その点は素直に謝罪しつつ、納品可能な時期を示したうえで買主に待ってもらうよう交渉するのが穏当ではないかと考えられます。なお、最近、BCP(事業継続計画)に絡めて、買主においても、売主以外の商品供給ルートを構築するべきであって、その点を怠っていた以上、売主に対して全額損害賠償請求を行うことが不当であると考える方もいるようです。今後の議論状況にもよるかと思いますが、現時点(本記事執筆は2021年11月)では、やはり責任転嫁の理屈と言わざるを得ず、法律論として売主の免責事由にならないことはもちろん、よほどの特殊性がない限り過失相殺事由として考慮されることもないのではないかと執筆者個人は考えます。トラブルをこれ以上拡大させないためにはどういった方策を講じるべきかという視点で、弁護士からアドバイスをもらうことも検討して良いのではないでしょうか。
(2)納期遅延による買主の対応(受取り拒否・解除)
納期遅延が発生した場合、契約書に定めがあるのであれば、それに従って対処することになります。では、契約書に定めがない、定めがあっても適用ができない場合はどうするのかになりますが、買主の選択肢としては、①受領を拒否する(契約を解除する)、②納品されるまで待った上で、納期遅延により生じた損害の清算を図る、という2つが考えらえます。
まず、①については、民法第541条以下に従って契約解除の手続きを行う必要があります。2020年4月1日施行の民法が適用される場合、売主の帰責事由は不要ですが、原則として催告(=納期を遅延しているので、××までに納品するよう連絡を行うこと)が必要であることに注意が必要です。
(参考)
第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
第542条 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
①債務の全部の履行が不能であるとき。
②債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
③債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
④契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑤前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
2 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
①債務の一部の履行が不能であるとき。
②債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
次に②ですが、繰り返し解説している通り、相手方の帰責性が必要となります。民法が改正されたことで、やや誤解されている方もいるのですが、解除が認められたから当然に損害賠償請求ができるというわけではないことに注意が必要です。(2020年3月31日以前の旧民法では、解除する場合も相手方の帰責性が要求されていました。このため、旧民法が適用される事例の場合、解除可能=損害賠償可能と考えることがむしろ正解でした)。
なお、買主視点で検討した場合、実際に損害賠償請求となると、具体的な損害額をどのように立証するのか、実は非常に悩ましい問題となることがあります(いわゆる迷惑料なる損害賠償請求は法的には認められません)。かなり緻密に検討する必要があることから、是非とも弁護士に相談してほしい事項となります。
(参考)
第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
①債務の履行が不能であるとき。
②債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
③債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
(3)危険負担
例えば、制作物供給契約において、売主が制作物の製造を完了させ、買主に引渡すために物流事業者に制作物を預けたものの、伝染病の発生で物流がストップし、そのストップ期間中に物流事業者の責任ではない事情で制作物が滅失又は毀損した場合、どういった対処をすればよいのかといった形で問題化します(制作物=生もの・食料品などをイメージすれば分かりやすいかと思います)。
まず、危険負担の処理についても、契約書を締結しているのであれば、契約書に定めてある事項に従って処理することになります(ちなみに、2020年4月1日施行の民法に伴い、あえて危険負担という考え方を用いず、契約関係からの離脱=解除に統一してルール化している契約書も一部存在します。その場合は、危険負担ではなく、解除に関する定めを検討するべきです。なお、現行民法の趣旨からすると、危険負担に関する条項はあえて設ける必要はなく、解除ルールに統一化する方が適切ではないかと執筆者は考えますが、執筆者が知る限り、現場実務では危険負担に関する条項を今でも定めることがむしろ多いように思われます)。
契約書を締結していない、契約書を締結しているが危険負担に関する定めがない場合(定めがあっても適用ができない場合を含む)、民法の定めに従って処理することになります。この点、現行民法では「引渡し」を基準としてリスク分担を定めています。上記事例の場合、買主への引渡し未了となりますので、買主は代金支払い義務を負わないという結論になります(危険負担の問題は、契約対象物が滅失又は毀損した場合の、それに対応する債務=契約対象物に対する代金支払い義務はどうなるのかというリスク分担を規律するにすぎません。したがって、危険負担の問題と契約解除の可否や再度の商品供給の有無は理論上別問題となります)。
なお、現場実務としては、危険負担という観点から支払い義務なしという結論を出したとことで、商品の調達はどうするのか、損害が発生した場合はどうするのか等の別の問題への対応が必須となります。これらを総合的に検討するに際し、弁護士と相談するのも一案かもしれません。
(参考)
第536条 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
(4)売買取引(制作物供給を含む)以外の取引における危険負担
上記(3)で記載した、商取引における売買であれば、かなり明確な形で結論が出るのですが、売買以外の取引では、契約上の履行ができない場合における、対価の支払いがどうなるのかという問題は新型コロナウイルスの発生により色々と問題が生じました。ここでは執筆者が特に悩ましいと感じたものを簡単に解説しておきます。
◆賃貸借契約における賃料支払い義務
危険負担という用語例を当てはめてよいのかという点はさておき、例えばモール等に入居している店舗経営者に対し、モール運営者や大家等の賃貸人の意向で店舗営業を中止するよう指示された場合、休業期間中の賃料支払い義務が生じるのかという問題があります。
賃貸借契約書にこういった場合の処理方法について定めがあるのであれば、それに従うことになりますが、たいていの賃貸借契約書ではこういった事態を想定した定めを行っていないため、契約書だけでは問題解決を図ることができません。
この点、2020年4月1日施行の民法第611条第1項では、「賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される」と定められていることから、賃料の減額可能(=休業期間中の賃料支払い義務なし)という考え方も可能ではないかと思われます。もっとも、現場実務では、現行民法の適用のない賃貸借契約が大半であったところ(2020年3月31日以前に賃貸借契約を締結している事例が大半であるという意味です)、現行民法のような「その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合」という定めが旧民法にはないため、形式的な文言解釈からすると賃料支払い義務を免れることは難しいと考えることも可能です。この点については明確な結論が出ていないように思われます。
なお、実際には解釈論で解決を図るのではなく、売上が無くなること、経営余力がないこと(窮状)を丁寧に説明しながら、賃料減免交渉を行うということが主流だったように思われます。この場合、どのような説明を行うのか、文書作成を含めて弁護士が関与することが多かったのではないでしょうか。
◆役務提供契約における対価の支払い義務
例えば、スポーツジムが新型コロナの影響を受け休業した場合における月額利用料はどうなるのか、イベントが新型コロナの影響を受け中止した場合における前払いチケット費用は返還してもらえるのか、といった形で問題化しました。
この種の取引の場合、不特定多数の顧客を取り扱うため約款を定めていることが多いこと、取引当事者に消費者が含まれていること、といった特殊性を考慮する必要があります。
まず、約款についてですが、不可抗力の場合、事業者は返金義務を負わない(利用者は支払い義務を負う)という定めがされていることが多いように思われます。この条項について、定型約款に該当することを前提にした民法第548条の2第2項に違反しないか(相手方の利益を一方的に害する内容については合意対象外と定められています)、違反しないとして、伝染病の場合に不可抗力に該当するのか、いわゆる自粛要請についても不可抗力に該当するのかという点を検討する必要があります。
次に、利用者に消費者が含まれている場合、上記の不可抗力免責条項について、消費者契約法第10条に違反しないかについても別途検討する必要があります(民法第548条の2第2項と消費者契約法第10条は対象範囲が異なります)。
実際のところは、法律論よりも風評被害を含む社会的な関心動向を踏まえて、事業方針の対処方針が異なっていたように思われます。弁護士は、事業担当者において理論的な説明を行うことができるようサポートする(想定問答集の作成など)といった関与が多かったように思われます。
(参考)
民法第548条の2
(第1項省略)
2 前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。
消費者契約法第10条
消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
◆派遣契約における派遣料支払い義務
新型コロナ下で執筆者個人として、かなりご相談の多かった類型となります。パターン的には、①派遣従業員が罹患した場合、②派遣従業員が濃厚接触者認定を受けた場合、③派遣従業員に感染の疑いが生じた場合、④派遣先における従業員に罹患等があった場合に分類しつつ、それぞれにおいて派遣従業員の就労を拒否した場合の派遣料支払い義務と整理することができます。
そして、派遣先からすれば、安全配慮義務という観点から職場環境を整備しているところ、特に①や②のパターンの場合、派遣従業員を自社(派遣先)に受け入れるわけにはいかず就労を拒否する正当性ありと判断したにもかかわらず、派遣料の支払い請求が来たというのは納得がいかないところかと思います。
この問題は、派遣契約書において、派遣料の支払いを免れる場合が制限列挙されており、その条項に従って原則的には処理されることに原因があるものと考えられます。したがって、派遣先としては、新たに派遣契約を締結する場合は、上記①から④の事態が発生した場合、派遣料支払い義務はどうなるのかという視点も入れながら契約書チェックを行い、必要に応じて条項修正協議を行う必要があります。なお、①②は派遣料支払い義務なし、④については派遣料支払い義務あり、③については別途協議(検査結果が確定するまでの間は代替要員を派遣する等)というところで、落しどころを探ることが多かったように思います。
なお、上記問題(特に①②の場合)について、派遣会社が強硬に派遣料の支払い請求を行ってきた場合は、弁護士が交渉窓口となって支払いを拒絶するといった関与が多かったように思います。一方で、新たに派遣契約を締結する場合、上記のような問題が頻発したことを踏まえ、条項修正や契約交渉について、弁護士が関与することが多かったように思われます。
3.不可抗力により金銭支払いができなかった場合
例えば、売主より商品を受け取った買主が、契約に従い商品売買代金を支払うべく送金手続きを行おうとしたところ、伝染病により金融機関の業務が停止となり、支払い手続きを行いたくてもできなかったという場合に問題化します(上記のような事例よりも、金融機関のシステム障害により送金手続きが完了しないといった事例のほうが分かりやすいかもしれません)。
この点については、民法上明確なルールが定められており、たとえ不可抗力であったとしても、支払期限までに支払いが行えなかった以上、債務者(本件では買主)は遅延責任を負う旨定められています(民法第419条第3項)。
現場実務の対応としては、例えば売主に電話等して事情を説明し、支払意思さえ示していれば、通常は売主も遅延損害金の支払い等の責任追及までは行ってこないものと思われます。
<2021年11月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
|
|






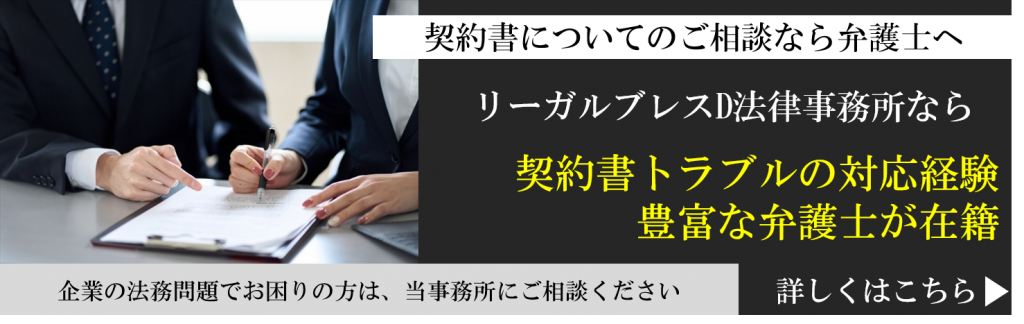

 弁護士 湯原伸一
弁護士 湯原伸一





































