Contents
【ご相談内容】
新型コロナ等の影響もあり、今後の事業展開に期待ができないことから、思い切って廃業しようと考えています。廃業するに際してどういった手法があるのかを教えてください。
また、廃業に関連し、連帯保証人になっている私自身(社長)が今後の生活のために必要な財産を残す方法はないのかについても教えてください。
【回答】
廃業することによって、これまで事業に関与してきた利害関係人との関係をどのように清算するのかが重大なポイントとなります。特に、負債や何らかの支払い義務がある場合、これらの支払い問題を避けて通ることはできません。
手っ取り早く支払い義務を免れたいというのであれば、自己破産申立を行い、免責を得るという方法になります。ただ、自己破産申立の場合、経営者の手元に残すことが可能な総財産は99万円以下となることから、住居等は手放さざるを得ず、当面の生活はかなり苦しくなると予想されます。
こういった問題を回避するために、会社・法人に対しては廃業支援型の特定調停の活用、保証人である社長等の経営者に対しては経営者保証に関するガイドラインの適用といった、裁判外での整理手続きが近年整備されてきています。これらの手続きを利用するためには一定の要件を充足する必要がありますが、利用可能な場合は、自己破産するよりも手元に残すことが可能な財産を増やすことができます。
以下では、会社・法人における廃業・清算に関する方法論と、保証人である社長等の経営者における政務整理手続きに分けて解説します。
【解説】
1.廃業する方法について
経済活動としての廃業を行うのであれば、事業を中止することで実現可能です。ただ、昨日まで通常の事業活動を行っていたのであれば、銀行、仕入先や家主等への未払い費用をどうするのか、売掛金の回収はどうするのか、勤務している従業員への対応をどうすればよいのか、賃借していた物件の明渡しはどうすればよいのか、社長個人の連帯保証はどうなるのか等々の事業活動に伴い生じた関係を清算する必要があります。また、廃業を決断した社長個人は、明日からの生活費をどのように得るのかも考える必要があります。
さて、会社・法人の廃業を検討する場合、まずは、金銭支払いについて、債権者に何らかのお願い(債務免除等)を行う必要性があるのか確認する必要があります。例えば、資金を潤沢に有しており、債務の支払いを問題なく行えるというのであれば、通常の清算手続きを取れば済みます。
一方、資金が十分ではなく、債務免除等の債権者との交渉が必要な場合、次に検討するべき事項として、金融機関以外の債権者(例えば、公租公課、賃金、賃料、商取引上の買掛等)の支払いが可能なだけの資金があるかを確認することになります。もし金融機関以外の債権者への支払い可能な資金であれば準備できるというのであれば、私的整理(金融機関に一定程度の債務免除を打診し協議を通じた清算手続き)を模索することになります。
金融機関以外の債権者の支払いが困難、又は金融機関以外の債権者の支払いが可能であっても金融機関より債務免除の了解を得られそうもない場合は、法的清算手続きである破産を検討することになります(反対する金融機関がごく少数である場合は多数決原理を用いた特別清算も検討可能)。
次に、社長等の経営者(本記事内では会社・法人の連帯保証人であることを前提とします)については、通常の清算手続きの場合は債務全額の支払いが可能である以上、特に対処することはありません。しかし、通常の清算手続き以外の方法を選択せざるを得ない場合、経営者個人については今後の生活や再起更生を図るべく、原則的には「経営者保証に関するガイドラン」に従って協議による清算手続きができないか検討することになります。ただ、このガイドラインに定める要件を充足しない場合は、経営者個人も破産手続きを選択せざるを得ないことになります。
以上が概要となりますが、それぞれの方法に関するポイントを以下では解説します。
弁護士へのご相談・お問い合わせ
当サイトの記事をお読みいただいても問題が解決しない場合は
弁護士にご相談いただいた方がよい可能性がございます。
下の電話番号もしくはメールにてリーガルブレスD法律事務所までお問い合わせください。
06-4708-7988メールでのご相談
2.会社・法人の処理
(1)全額の支払いが可能な場合は通常清算
上記1.でも記載しましたが、廃業を決断した時点が会社・法人が抱えている債務全額について、会社・法人が保有する財産(連帯保証人が保有する財産も支払いに充当するのであればその分も加算)をもって支払いに充てることが可能な場合(なお、一部債権者との間で債務免除の合意をすることで支払い可能となる場合も含みます)、会社法第475条以下に定める清算手続きを行えば、法的に廃業を完了させることができます。
なお、執筆者が知る限り、中小企業における通常の清算手続きであれば、顧問税理士等が一連の手続きについて関与・アドバイス等を行ってくれることが多く、実際に弁護士が関与することは少ないようです。
(2)私的整理(裁判外交渉)を行うのであれば、廃業支援型の特定調停
廃業を決断した時点が会社・法人が抱えている債務全額について、会社・法人が保有する財産(連帯保証人が保有する財産も支払いに充当するのであればその分も加算)をもって支払いに充てることが困難な場合、通常清算手続きをとることは不可能です。
この場合、方法論としては、一部の債権者と債務免除等の交渉可能であれば、債務免除の合意を行いつつ整理を図り、最終的に通常清算又は特別清算手続きを行うことを検討することになります。なお、債権者との交渉が困難である場合は、後述する(3)の自己破産申立てを行うほかありません。
さて、タイトルにある私的整理(裁判外交渉)による廃業支援型の特定調停とは、一部の債権者(=債務免除の交渉対象となる債権者)を金融機関に限定した上で行う整理手続きとなります。ちなみに、特定調停手続きは正確には裁判所が関与する手続きとなります。しかし、ここで記載する廃業支援型の特定調停とは、支払い方法や債務免除については特定調停手続の前段階、すなわち裁判所が関与する前に債権者と協議し合意することが前提になっている手続きであって、合意書の取り交わしのみを裁判所で行うというイメージです。したがって、裁判外での交渉が中心となることから私的整理として位置付けています。
この廃業支援型の特定調停手続きを利用する場合、まずは押さえておく必要があるポイントとして以下の3点があります。
①金融機関に対する債務以外、すなわち公租公課(税金や社会保険料など)、労働債権(賃金や退職金など)、商取引債権(買掛金や賃料など)について全額支払いが可能なだけの資産を有していること
②私的整理を行ってもなお金融機関にとって経済的合理性があること
③すべての金融機関の同意が得られる見込みがあること
廃業支援型の特定調停手続きを利用するに先立ち、まずは上記3点を検討する必要があります。そして、いずれか1つでも満たさないというのであれば、この手続きを利用することは諦め、他の廃業手法(原則的には自己破産)を検討することになります。
ところで、①の要件からすると、債務超過となり一定期間経過していた場合、通常は充足することは不可能です。したがって、早期の廃業決断(傷が浅いうちと言えばよいでしょうか…)を前提になっていると言わざるを得ません。資金繰りに窮し、新たな融資も受けられないといった末期状態でこの手続きを利用することは、正直不可能であることを理解する必要があります。
次に②の要件ですが、「現時点において清算した場合における主たる債務の弁済計画案に基づく回収見込額と保証債務の弁済計画案に基づく回収見込額の合計額」の方が、「過去の営業成績等を参考としつつ、清算手続きが遅延した場合の将来時点(最大3年程度)における主たる債務及び保証債務の回収見込額の合計金額」よりも多くなる場合、経済的合理性ありと判断されることになります。誤解を恐れず端的に説明すれば、金融機関から見て、将来的な破産手続きで配当をもらうよりも、廃業支援型の特定調停手続きを現時点で実行した場合における弁済案の方が多く支払ってもらえる場合、経済的合理性ありと判断されることになります。
なお、この経済的合理性のうち特に将来の回収見込額を検討するにあたっては、弁護士のみならず公認会計士や税理士の協力が必要不可欠になるため、これらの専門家への委託費用を考慮する必要があります。また、現時点での弁製計画案を策定する際に費目に現れない潜在的な支払い(典型的には債務免除益による課税)も考慮する必要があります。
さらに③の要件については、債務者が廃業支援型特定調停手続きを利用する旨宣言したところで、金融機関が同意を強制されることはありません。最終的には日ごろからの金融機関との付き合い方といった信頼関係の問題(正確な決算書を作成し開示しているのか、事業計画について日頃から説明しているのか)になるケースも多いと言われていることを考慮する必要があります。
上記①~③を含む一定の要件を充足し、金融機関との合意が得られた段階で特定調停の申立てを裁判所に行うことになります。そして裁判所にて合意の取り交わしを行い、会社・法人は金融機関に弁済を行いつつ、最終的には通常清算(場合によっては特別清算)手続きを通じて会社・法人を消滅させ、法的な廃業を完了させることになります。
(3)法的整理を行うのであれば自己破産
債務への支払いに充てる財産が不十分であり、上記(2)に記載した廃業支援型の特定調停手続きも利用ができないとなると、法人・会社については自己破産による清算手続きを行うほかありません。
ただ、ある意味矛盾するかもしれないのですが、自己破産手続きを行う場合、弁護士への依頼費用や裁判所に納める費用等を考慮すると、最低でも80万円前後の現金は残しておかないと自己破産申立ての手続き自体を進めることが難しいのではないかというのが、執筆者個人の現場感覚となります。
なお、上記(2)に記載した廃業支援型の特定調停手続きを検討するに当たり、特定の金融機関のみが反対し、大多数の債権者(この場合は金融機関のみならず、金融機関以外の債権者も含めて検討する必要があります)との間では合意ができるという場合、廃業支援型の特定調停手続きではなく、あえて特別清算手続きを利用するという方法も考えられます(債権者集会において、出席議決権者の過半数の同意と議決権総額の2/3以上の同意を得られることが確実な場合)。ただ、かなり限定的な話になるので、あまり一般化できる手続きではないように執筆者個人は考えます。
3.社長等の経営者(保証人)の処理
廃業により、会社・法人は最終的に消滅するので将来的なことを考慮する必要がない一方で、会社・法人の保証人になっている社長等の経営者は今後も生活を続けていく必要があります。したがって、債務の整理を図りつつ、如何にして経済的再起更生を図るのかが重要な課題となってきます。
(1)経営者保証に関するガイドラインに基づく協議
会社・法人が廃業するためにどのような方法を使うかに関わらず、経営者保証に関するガイドランを利用することは可能です(会社・法人が破産申立てを行った場合、保証人である社長等の経営者も当然に破産申立を行う義務はありません)。そして、この経営者保証に関するガイドラインを利用することの最大の目的は、破産手続きで自由財産(=破産しても、経営者の手元に残しておくことができる財産のこと)として認められる99万円を超えて、経営者の手元に財産を残すことができるという点です。
ただ、経営者保証に関するガイドランの適用を受けるためには、やはりそれ相応の要件を充足する必要があります。
その中でも上記2.(2)でも記載した「経済的合理性」がやはり問題となってきます。同じような話になってしまうのですが、金融機関等の保証債権者にとって「現時点において清算した場合における主たる債務の回収見込額及び保証債務の弁済計画に基づく回収見込額の合計額」の方が、「過去の営業成績等を参考としつつ、清算手続きが遅延した場合の将来時点(将来見通しが合理的に推計できる期間として最大3年程度の想定)における主たる債務及び保証債務の回収見込額の合計金額」より多い支払額となる場合、経済的合理性ありと判断されることになります。
なお、裁判外(任意)での整理手続きとなりますので、当然のことながら、全ての金融機関等の保証債権者の同意が必要となります。
さて、経営者保証に関するガイドラインのメリットは、債務整理手続きを行った際、経営者の手元に残すことが可能な財産が破産手続きの場合より多くなる点にあると解説しました。具体的にどの程度多くなるかというと、上記の経済的合理性の検討より導かれる「回収見込額の増加額」が上限となります。結局のところ、この上限額の範囲内で金融機関等の保証債権者と協議を行い、同意を取り付ける必要があるということになります。
全ての金融機関等の保証債権者からの同意が得られる見込みとなった段階で、特定調停手続きの申し立てを行い、裁判所で合意の取り交わしを行うこと、上記2.(2)と同様となります。
(2)自己破産
上記(1)で記載した経営者保証に関するガイドラインの適用が難しい場合、保証人である社長等の経営者も自己破産の申立てを行うしか選択肢がありません。
この場合、経営者の手元に残すことができる財産=自由財産は99万円以下となりますが、現預金、生命保険の解約返戻金相当額、自動車や不動産の評価額等の全ての財産の合計額が99万円の範囲内にとどまる必要があります。99万円を超える場合、超過する財産については原則的に手元に残すことができない点に注意が必要です。
ところで、破産申立て費用を少しでも削りたいためか、時々、会社・法人の清算処理は特に行わず、経営者個人のみ破産申立を行いたいと希望される方がいます。しかし、少なくとも執筆者が弁護士活動を行っている関西地区の裁判所では、このような取り扱いは認めていません(執筆者が知る限り、東京およびその周辺地域も同様の取扱いです)。経営者個人が自己破産申立てを行う場合、必ず会社・法人も破産等の清算手続きを行う必要があることを理解する必要があります。
なお、会社・法人に属する一事業をどうしても存続させたいというのであれば、当該事業に関するM&Aを実行する、第二会社方式による事業再生を図るといった別の手法も併せて検討する必要があります。
<2020年12月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
|
|





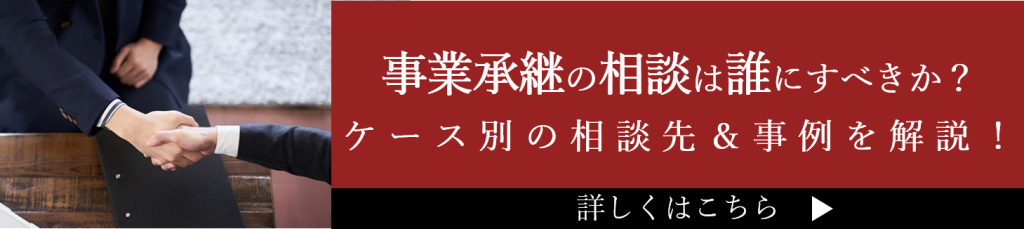


 弁護士 湯原伸一
弁護士 湯原伸一




































