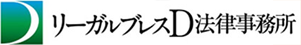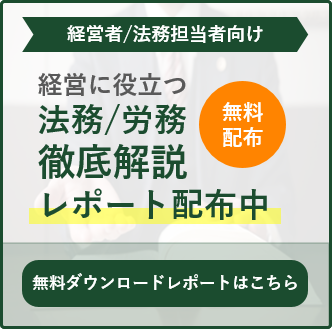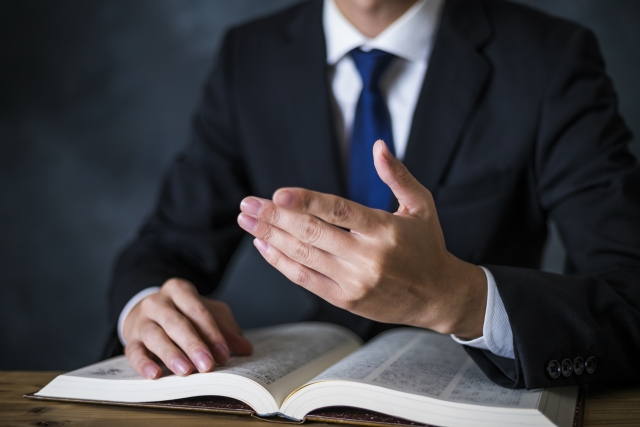「いつまで使えるか」ではなく「いつまでにやめるか」。紙の手形は事実上の終了局面に入りました。
混乱を避けるための手順と、今後の対応につきポイントをまとめます。
ご相談
手形が使えなくなると聞き及びました。
具体的な内容や今後の対応について教えてください。
結論
「紙」の手形については、多くの金融機関が2026年10月1日以降に振出した手形を受け付けないとしています。
このため、当座預金からの支払いができなくなりますので、2026年10月1日以降に振出した紙の手形については、事実上決済ができなくなります。
ちなみに、2026年9月末までに振出された紙の手形の取扱いについて、多くの金融機関では2027年3月末まで取立受付を行いますが、2027年4月1日以降は取立受付を行わないようです。このため、2027年4月1日以降で保有したままの紙の手形については、事実上支払いう受けられないことになります。
なお、上記は「紙」の手形についてであり、「でんさい」は引き続き利用可能です。
解説
現場実務で押さえておくべきポイントは、
- ①「2026年9月末」で何が終了するのか
- ②「2027年3月末」で何が終了するのか
になります。
今後の対応について、(1)現在手形を振出して決済している事業者、(2)手形を受領して支払いを受けている事業者に分けて、簡単に整理すると次の通りです。
(1)現在手形を振出して決済している事業者
今やるべきこと
- 新規発行をやめる(2027年4月以降は交換所で決済できなくなるため、これ以上の手形発行はリスク)
- 契約条項の見直し(取引基本契約や注文書の「支払方法:手形」を「振込or電子記録債権(でんさい)」に切替)
- 社内規程改定(与信・稟議ルールを変更し、紙手形を前提とした決済スキームを廃止)
2026年内に目指したいゴール
- ・主要取引先との間で「手形廃止」を通知、合意。
- ・銀行との間で「でんさい」利用契約、ネット振込システム導入を完了。
2027年3月末までに完了
- 未決済の手形を整理し、2027年4月以降に満期を迎える手形を残さない。
- 仕入先との支払はすべて振込かでんさいに移行。
(2)現在手形を受領して支払いを受けている事業者
いまやるべきこと
- 受取停止を宣言(新規の取引で手形条件を拒否し、振込またはでんさいに変更するよう取引先へ依頼)
- 既存手形の確認(手元にある受取手形の満期一覧を作成し、2027年4月以降に満期を迎えるものを早めに相談)
2026年内に目指したいゴール
- 主要取引先との協議を終え、今後は手形を受け取らない体制にする。
- 受取債権の管理方法を「でんさい」または「振込消込」へ移行。
2027年3月末までに完了
- 受取済み手形をゼロにし、残存リスクをなくす。
- 手形割引、担保などに依存していた資金繰りを「でんさい割引」や「ファクタリング」「短期融資」で代替。
|
|





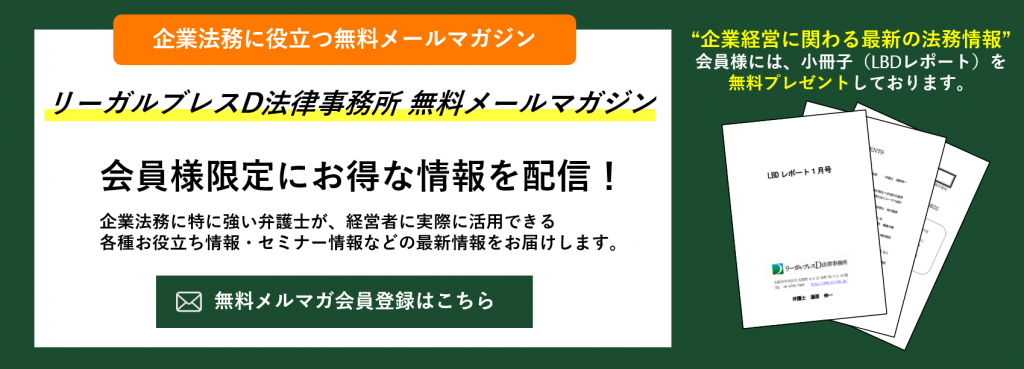
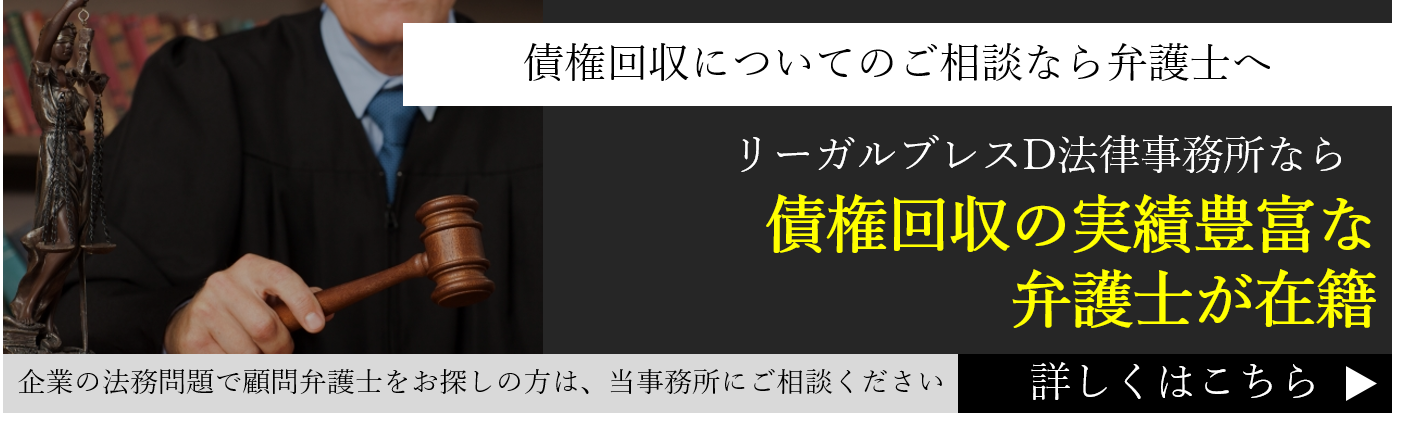
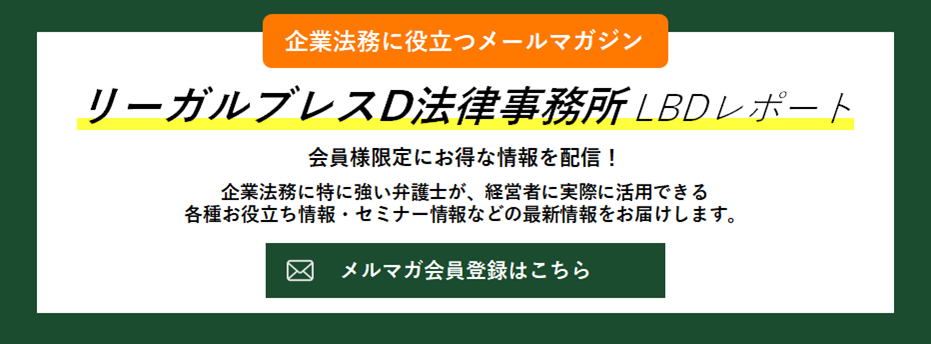
 弁護士 湯原伸一
弁護士 湯原伸一