Contents
【ご相談内容】
最近の印鑑廃止の流れを受けて、業務に関係する書類への押印は極力省略することにしています。もっとも、取引先と締結する契約書についてまで押印を省略するのは問題があるように考えていますが、法的にはどのように考えればよいのでしょうか。
【回答】
コロナ騒動を契機とした在宅勤務・テレワークが徐々に普及する中で、書類へ押印を行うという従来の慣行を見直す動きが生じてきています。
ここでは契約を締結するに際して、「契約書に押印することの意義」に絞って解説を行います。
結論だけを記載しますと、次の通りです。
・押印がなくても、契約は有効に成立するのが原則であること
・そもそも契約書という書面が無くても、理論上契約は成立すること
・押印が重要視されるのは、従来の慣行以外に、民事訴訟手続きの中で有利に取り扱われる点にあること(いわゆる「二段の推定」)
・最近普及しつつあるプラットフォーム提供事業者を通じた電子契約については、二段の推定が及ぶと断定するに至っていないこと
【解説】
1.押印は契約成立のための有効要件ではないこと
「署名押印がない契約書は無効である」と考える方が一定数いらっしゃいます。しかし、2つの意味で誤解があるようです。
まず1つ目として、契約書を作成する場合、法律上は署名を行えば十分であり、押印は原則不要です(例外的に押印が必要になるものの代表例として、第三者が事業用融資の保証人になる場合の保証契約などがあります)。法律では押印を原則不要としているにもかかわらず、署名押印が必要となったのかは諸説ありますが、一言でまとめてしまうと日本独自の慣習といえばよいのかもしれません。いずれにしましても、法律上、契約書を作成する場合に、原則押印を求めているわけではないことがポイントです。
次に2つ目として、契約が成立するためには、そもそも契約書という書面は原則不要です。この点を指摘すると驚かれる方が多いのですが、法律上は原則口頭でも契約は成立すると定められています(例外の1つとして保証契約は必ず書面で行う必要があります)。したがって、口頭でも契約が成立する以上、印鑑・ハンコが出てくる余地がないことになります。
以上のことから、法律の原則論としては、契約成立の有効要件として押印が条件となっているわけではないと考えてください。
では、なぜ契約書作成の必要性が言われるのでしょうか。
これは、契約=合意内容を証拠として残すためです。
上記でも記載しましたが、契約は口頭でも原則成立します。ただ、口頭での契約の場合、後で言った言わない論争が起こりがちです。たとえば金銭授受があった場合、一方はお金を貸したと主張し、他方はお金をもらった(贈与を受けた)と主張していたとします。どちらの言い分が正しいかを判断するためには、金銭授受を行った当時、どういったやり取り・合意があったのかを探求することになります。しかし、録音でもしていればともかく、金銭授受当時の口頭でのやりとりを後で再現することは不可能です。このため、双方の言い分が異なる場合、証拠がないことからどちらの言い分が正しいか判断が付かないことになります。ところが、当時のやり取り及び合意事項を契約書に残していた場合、その内容を確認すれば貸付なのか贈与なのか明確になります。つまり、契約書は自らの言い分を裏付けるための材料となるわけです。このような証拠を確保することを目的として、契約書の作成が求められることになります。
次に、なぜ押印の必要性が言われるのでしょうか。
これは押印があったほうが、万一の民事裁判において有利に扱われるからです。次の2.ではその点について解説を行います。
弁護士へのご相談・お問い合わせ
当サイトの記事をお読みいただいても問題が解決しない場合は
弁護士にご相談いただいた方がよい可能性がございます。
下の電話番号もしくはメールにてリーガルブレスD法律事務所までお問い合わせください。
06-4708-7988メールでのご相談
2.なぜ押印が重要視されているのか
この疑問に対して端的に回答する場合、「押印した契約書であれば二段の推定が働くからです」となります。
おそらく「二段の推定」という言葉は耳慣れないかと思います。法曹界の業界用語と言ってもよいかもしれませんが、次のようなことを意味します。
①ハンコ・印鑑が押されたことによって生じた印影が契約書に残っている。
↓
(一般的にハンコ・印鑑は重要な物であり、ハンコ・印鑑の名義人しか用いない)
↓
契約書にハンコ・印鑑を押した者は、印影にある名義人であると推定される。
②契約書のハンコ・印鑑を押した者は、印影にある名義人である。
↓
(一般的にハンコ・印鑑を押すのは、契約書の内容を確認し納得したからである)
↓
契約書が有効に成立したことについて、印影の名義人は承認していると推定される。
(※このことを法曹界では「文書成立の真正」と呼んだりします)
なんだか探偵小説の推論プロセスのようなものに思われるかもしれませんが、上記①②で記載したように、押印が行われたことによる2段階の推定を経て、一定の結論が導かれる状況になります。これを「二段の推定」と呼んでいます。
要は、ハンコ・印鑑が押されていた契約書が存在した場合、印影の名義人は「このような契約書は見たことがない。一切知らない!」という主張が原則通用しないと考えればわかりやすいかもしれません。
押印には、民事裁判上このような特殊効果が認められているため、非常に重視されていると考えられます。
ただ、特殊効果が認められているとはいえ、しょせんは「推定」にすぎません。したがって、上記①については、例えば、ハンコ・印鑑が無断で持ち出され第三者が勝手に押印したという事実があるのであれば、推定は覆されることになります。また、上記②についても、例えば、白紙の書面に押印した後で、名義人の関知しない内容が書面に記載されたという事実があるのであれば、やはり推定が覆されることになります。
また、二段の推定という特殊効果を得られなければ、文書成立の真正が絶対に認められないというわけではありません。例えば、契約書を取り交わす前に当事者双方が電子メールで複数回やり取りを行っており、契約書に記載されている内容で合意したことが電子メールより明らかであるといった事情がある場合には、たとえ押印後の契約書に後で書き加えられたとしても、契約書の成立が認められる場合もありうるところです。
たしかに、二段の推定が適用されるほうが、契約書に記載されている内容通りの履行を請求する側にとっては、民事裁判を有利に進めることができます。ただ、二段の推定のみで契約書の成立の真正が決まるわけではありません。契約書に記載されている内容通りの履行を請求する側にとって、立証の程度が軽減されるといった限定的なものにすぎないことに注意が必要です。
3.電子メールのやり取りのみで証拠十分と言えるか
上記でも記載した通り、契約書に押印することは、一部例外を除き契約成立の有効要件ではありません。そうであれば、あえて契約書を作成しなくてもよいのではないか、という発想が出てきてもおかしくありません。
そこで、今では当たり前になった、電子メールを用いて契約締結を行うことができないかといった質問を受けたりします。
結論から申し上げると、理屈上は可能です。また、口頭で合意した場合と異なり、合意内容が後で再現可能であることから、口頭での契約よりもむしろ望ましいと言えるかもしれません。
しかし、電子メールによる契約の場合、重大な落とし穴があるのも事実です。
特に考えられるのが、電子メールのやり取りを行っている当事者が、本当に電子メールアカウント上に記載のある名義人といえるのか、という点です。外部の人間が不正にアクセスして電子メールのアカウントを乗っ取り、なりすましてメールの送受信を行っているという事例ももちろん想定されます。あるいは端末上のメーラー(電子メールクライアント。例えばOutlook等)について、名義人以外に複数人が共有して利用しており、名義人以外の第三者が形式的に名義人を名乗って電子メールのやり取りを行っていた場合なども想定されます。つまり、電子メールアカウント上の名義人と同一と言えるのか、実際にやり取りを行っていた者が名義人より権限を得て行っていたのか、という点について、電子メールのみから裏付けることが難しいという問題がどうしても残ります。当然のことながら、電子メールアカウント上の名義人の表示については、二段の推定のような特殊効果は発生しません。
以上のような問題点をクリアーするためには、電子メールのやり取りを行っている者は電子メールアカウント上の名義人であること、又は当該名義人より許可を得ていることの裏付け証拠を事前に確保しておく必要があります。色々なやり方は考えられますが、確実な証拠を残そうとすればするほど、それなら書面上の契約書を作成し、署名押印したほうが手っ取り早い…ということになりがちなので、悩ましいところがあります。
4.電子契約はどこまで活用可能か
電子契約については、従前より、コストの削減が可能となること(印紙代の削減、紙媒体の印刷・郵送・保管費用の削減など)、労力の削減が可能となること(紙媒体の印刷や発送、保管などの作業がなくなることによる業務改善など)等のメリットがあると言われてきましたが、新たなツールの導入等が必要となるため、あまり普及してきませんでした。ところが、 2020年3月以降のコロナ騒動を受け、押印不要とする電子契約について俄かに注目が集まっています。
ここで、電子契約について説明する前に概念整理をします。
まず、上記3.で記載した電子メールのやり取りを通じた契約の成立は、いわば便宜的な事実上の対応策に留まります。したがって、ここで解説しようとする法律上の電子契約ではありません。また、最近ではタッチペンでパネル上に署名することで契約の成立の証とする方法がとられることがありますが、この方法も法律上の電子契約ではありません。
さて、本題に戻ります。電子契約については、「電子署名及び認証業務に関する法律」による法律を前提に検討する必要があります。そして、同法の最大のポイントとして、法定要件を満たした認証局に登録した本人名義の電子署名について、同法に従って契約書に使用した場合、ハンコ・印鑑を押印した場合と同様の効果を認められること、すなわち二段の推定の適用があることが重要です。
ただ、この電子契約について、現在国内で普及しつつあるのは、プラットフォーム事業者が、プラットフォーム事業者名義の電子署名を発行する形態のものです。本記事を執筆している現在(2020年10月1日)の状況で指摘すると、プラットフォーム事業者名義の電子署名では「電子署名及び認証業務に関する法律」に基づく二段の推定は及ばないというのが行政の解釈のようです(つまり、本人名義の電子署名のみ二段の推定を認めるという取扱いのようです)。
もっとも、この点については見直し作業が進められていますので、動向を確認する必要があります。なお、非常に専門的なことを申し上げますと、2020年7月17日に公表された「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A」は、同法第2条に定める電子署名該当性について行政の解釈を示したものにすぎません。上記で記述している電子署名と二段の推定については、同法第3条の問題となります。この点は誤解が多いようですのでご注意ください。
電子契約がどこまで普及するかは、プラットフォーム提供事業者が発行するプラットフォーム提供事業者名義の電子署名により二段の推定が適用されるのかがポイントのように思われます。もっとも、仮に二段の推定が適用されるという行政解釈の変更が行われたとしても、今度はプラットフォーム提供事業者の信用性、特にプラットフォーム提供事業者が倒産等した場合に電子契約の確認はどうやって行うのか等の問題が生じることになります。こういった問題点があることを踏まえると、全面的に電子契約に移行させるというのは時期尚早といえるかもしれません。例えば、重要な契約については引き続き書面で行い、継続的な契約に基づく日常取引については電子契約を利用するといった使い分けを検討するのも一案かもしれません。
<2020年10月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
|
|






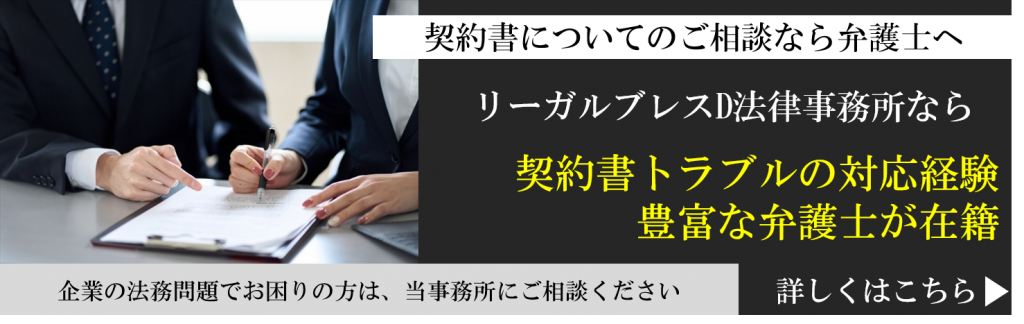

 弁護士 湯原伸一
弁護士 湯原伸一




































