Contents
【ご相談内容】
当社は非上場の株式譲渡制限がある中小企業です。経営には全く関与していない社長の親族が一部株式を保有していたところ、その親族が亡くなった旨の報告がありました。これから遺産分割等の協議を行うそうなのですが、当社は親族が保有していた株式について、どのように取り扱えばよいのでしょうか。
【回答】
相続人が株式を保有し続けることについて異論なしと会社が判断する場合、株式の帰属に関する遺産分割協議を待って、最終的な株主を確定させ、取扱うことになります。
一方、相続人が株式を保有することに問題ありと会社が判断する場合、会社は相続人より当該株式を何らかの手段を用いて買取る必要が生じます。原則的な手段としては任意の買取り交渉になりますが、例外的に定款の定めに基づく強制売渡し、相続人が第三者に株式譲渡を行うことを希望した場合を利用した会社等への買取請求といった手法を用いることもあります。
なお、会社が相続人より株式を買取る場合、自己株式の取得になりますので、自己株式取得に関する独自の法規制も意識する必要があります。
以下では、ポイント別に分けて解説を行います。
【解説】
1.株式会社と合同会社・合名会社・合資会社との違い
株式会社の株主が死亡した場合、当該株主が保有していた株式は相続の対象となります。ただし、遺産分割前の段階での相続対象株式の取扱いは、他の相続財産と異なり特殊です。この点については2.以下で解説します。
ちなみに、合同会社、合名会社及び合資会社の場合、社員が死亡することは法定退社事由となります(会社法第607条第1項第3号)。したがって、当該社員が保有する社員権は相続の対象とならないのが原則的取扱いです。ただし、2点注意点があります。
1つ目は、定款で相続人が承継する旨定めた場合、社員が死亡しても法定退社事由とはなりません(会社法第608条第1項)。したがって、この定款の定めがある場合、例外的に社員権を相続対象として取扱うことになります。
2つ目は、定款に定めがない場合、社員権は相続対象とはならないものの、退社に基づく持分払戻請求権は相続対象となるという点です。なお、持分払戻請求権は債権である以上、相続人の法定相続分に従い当然分割になるのではと考えるかもしれません。しかし、古い審判例によると当然分割扱いとはならないようです。
弁護士へのご相談・お問い合わせ
当サイトの記事をお読みいただいても問題が解決しない場合は
弁護士にご相談いただいた方がよい可能性がございます。
下の電話番号もしくはメールにてリーガルブレスD法律事務所までお問い合わせください。
06-4708-7988メールでのご相談
2.株式は法定相続分通りに当然帰属するのか?
相続人が複数名存在する場合、相続対象となった株式は誰にどのように帰属するのか。
例えば相続対象となった株式が100株あり、相続人が配偶者と子供2名という事例であれば、遺産分割を経ずともと法定相続分に従い配偶者に50株(1/2)、子供は各25株ずつ(1/4)に当然に分割されると考えるかもしれません。
しかし、これは間違いです。現行法の解釈としては、遺産分割協議によって株式の帰属を決めない限り分割されることはありません。
遺産分割協議がまとまらない段階で、株式に関する権利関係は法定相続分通りで準共有することになり、上記例でいえば、配偶者が1/2、子供は各1/4の割合で共有します。ただし、あくまでも「準共有」であって、相続人に単独帰属するわけではありません。1人の子供が1/4の割合を共有しているから、1/4相当分の議決権を行使する、あるいは配当の1/4を先に支払え等の具体的要求を行えるわけではないこと、注意が必要です。
3.遺産分割前に株主権を行使するには?
上記2.で記載した通り、遺産分割前の段階では、相続対象となる株式が確定的に相続人に帰属することにはなりません。したがって、各相続人が単独で株主権を行使することは不可能です。
株主権を行使したい場合、相続人間で協議を行い、権利行使者1名を選任の上、会社に通知した上で権利行使を行う必要があります(会社法第106条)。この協議の方法ですが、法定相続分の多数決によって決めることが可能と解釈されています。したがって、上記例でいえば、基本的には1/2の割合を有する配偶者の意向により多数決の結果が生じることになりますが、子供2名が協力しあった場合、配偶者1/2・子供たち1/2となり多数決とはなりません。人数割りで多数決が決まるわけではないことに注意が必要です。
4.相続人に対して株式買取交渉を行うことは可能か?
会社としては、被相続人とはある程度の信頼関係を構築していたものの、相続人とは付き合いもなく株主になられては困る、といった事態が生じることもあります。この場合、会社は相続人(遺産分割前であれば相続人全員、遺産分割後であれば株式を保有する相続人)に対して、任意に株式の買取りを申出ることになります。
もっとも、あくまでも任意の買取り申出となるため、相続人が売渡すことを了承しない限り、手続きを進めようがありません。
また、相続人が売却すること自体は異論がなくても、価格の点で協議がまとまらないということもあり得ます。ちなみに、時々勘違いされている方がいるのですが、裁判所が株式の売却価格を決めるという会社法上の手続きは、法律が定める一定の事由(例えば後述するような譲渡制限会社における株主が第三者に株式を譲渡する旨申出てきた場合や相続人に対して定款の定めに基づく売渡請求を行う場合などに限定されています)に該当しない限り、当該手続きを利用することが不可であることに注意が必要です。
さて、会社と相続人との間で株式売買に関する協議が整った場合、これで一気に買取手続きを実行できるかというと、そうではありません。この場合、会社による自己株式取得となりますので、会社法上のルールを守る必要があります。具体的には次の2点です。
①手続き
・買取手続き実行前に株主総会での特別決議を経ること(会社法第156条、309条2項2号)。
※なお、特定の株主(相続人)より買取る場合であっても、他の株主はこれに乗じた買取請求不可(会社法162条)
②財源規制
・買取金額は会社の分配可能額内に収まること(会社法第461条第1項第2号)
なお、上記②に定める財源規制に違反しても、株式の売買契約自体の効力は失われないとする見解もあるようですが、定説はないようです。したがって、保守的に売買契約の効力に及ぼす可能性があることを念頭に、財源規制違反とならないか事前に検討しておく必要があります。ちなみに、上記①に定める手続きを守っていない場合は株式の売買契約は効力が失われると考えられています。
ところで、実務的によくあるご相談として、会社が相続人より株式を買取ろうとしても上記②の財源規制に抵触するというパターンです。ただ、どうしても株式を買取りたいので、傀儡の第三者(会社の意向に従う第三者)を立てて、当該第三者と相続人との間で売買契約を結んでしまうという方法を検討することがあります。
一見すると、自己株式取得のようには見えないのですが、例えば当該第三者は買取資金を有しておらず、会社が当該第三者に買取資金相当額を拠出しているといった場合、会社法が定める自己株式取得規制の潜脱行為と言わざるを得ません。したがって、第三者を立てる場合、買取資金の出所について十分に検証しないことには、後で会社法違反により株式売買契約の効力に疑義が生じてしまいかねないこと注意が必要です。なお、自己株式取得に関する規制以外にも、第三者に買い取らせる場合、形式的には譲渡制限会社における株式譲渡に該当しますので、譲渡承認に関する手続き(株主総会決議等)が必要となることも注意が必要です。
5.相続人より株式を強制取得することは可能か?
上記4.で記載した通り、相続人が株主となり続けることが会社にとって問題ありと判断する場合、買取り交渉を行うことが原則です。ただ、会社法はこの原則に対する例外を設けています。それは、定款に定めることで、株式を取得した相続人に対し、会社に対して売渡すよう請求することができるというものです(会社法第174条)。
なお、この定款の定めですが、相続発生時に定められていることが絶対必要とされていません。すなわち、相続発生後に定款変更手続きを行うことで、売渡し請求することも可能とされています。したがって、任意の買取り交渉で解決ができない場合、事後的に定款変更を行って、相続人より強制的に株式の買取りを行うという方針を立てることも可能となります。ただ、相続人が有する株式の持分割合が高い場合、この定款があることで、逆に相続人が現経営陣の保有する株式を売渡すよう請求することも可能となります。このため、定款変更がかえって仇とならないか、株式の持分割合を考慮した上で定款変更を行うのか判断する必要があることに注意が必要です。
さて、定款に基づく売渡し請求を行う場合、次の事項に注意する必要があります。
①株主総会の特別決議を行うこと(会社法第175条、第309条第2項第3号)
②相続があったことを会社が知った日から1年以内に請求すること(会社法第176条)
③価格協議の有無を問わず、価格が決まらない場合は売渡し請求の日から20日以内に裁判所に売買価格決定の申立てを行う必要があること(会社法177条)
④自己株式取得における財源規制に違反しないこと(会社法第461条第1項第5号)
簡単にポイントを解説します。
上記①については、売渡し請求の対象となった人物は、その保有する全ての株式について議決権を行使することができないこと要注意です。よくある勘違いとして、売渡し請求の対象となる相続人がもともと保有していた株式と、相続により取得した株式のうち、後者の株式のみ議決権行使不可と認識している方がいるのですが、間違いです。この場合、もともと保有していた株式も含めて議決権行使不可となります。
上記②については、相続人の遺産分割協議が紛糾し、相続の対象となった株式について確定的な帰属者が決まらない状況が1年を超えても続きそうという場合もあります。この場合、会社としては、相続人全員を対象として売渡し請求を行う必要があります。遺産分割協議終了してから売渡し請求すればよいと誤解しないよう注意する必要があります。
上記③については、売渡し請求を行ってから20日という極めて短期間内に裁判所に申立てる必要があります。この期間内に裁判所への申立てが行われなかった場合、売渡し請求は効力を失うことになりますので要注意です(会社法第177条第5項)。現場実務としては、価格協議と並行しながら裁判所への申立をいつでも行えるように準備しておくこと、場合によっては価格協議を行うことなく、いきなり裁判所への申立を行うといった方法も検討する必要があります。
上記④については、売渡し請求により会社と相続人との間で売買契約が成立する(売買価格が定益)時点を基準として、分配可能額の範囲内に収める必要があります。売渡し請求から売買契約成立時点まで少し期間が空くことがありますので(特に裁判を通じて価格決定を行う場合)、分配可能額が維持できるよう財務対策が必要となります。なお、分配可能額を超える自己株式取得を行った場合、株式売買自体が無効となるリスクも存在すること、上記4.で記載した通りです。
6.相続人が第三者への株式譲渡を希望してきた場合の対処は?
会社が相続人より何らかの手法を用いて買取りを検討していたところ、相続人が先手を打って第三者に株式を譲渡したいと申出てくる場合があります。当然のことながら、当該第三者が会社にとって都合の良い人物であれば、株式譲渡を認めればよいだけです。しかし、相続人がそのまま保有するのも嫌だが、当該第三者が保有するのも嫌という場合は往々にしてあり得ます。この場合、株式の譲渡制限があることを根拠に、会社が株式を買い取ることができないかを検討することになります。
手続き(スケジュール)の概要としては次の通りです。
①株主又は株式取得者が会社に対して譲渡承認の請求を行う(会社法第136条~第138条)
②譲渡を承認しない旨の決定を会社が行った場合、①の請求より2週間以内に株主等に通知する(会社法第139条、第145条第1号)
③-A 会社が買取る場合は②の通知より40日以内に、会社が買取る旨の通知と供託を行う(会社法第141条、第145条第2号)
③-B 会社が指定する者が買取る場合は②の通知より10日以内に、当該指定者が買い取る旨の通知と供託を行う(会社法第142条、第145条第2号)
④価格協議の有無を問わず、価格が決まらない場合は③の通知より20日以内に裁判所に売買価格決定の申立てを行う必要があること(会社法144条第2項)
実務的に厄介なのは、それぞれの手続きを実施するに際して、様々な日数制限が混在していることです。特に③については、会社が買取る場合は40日、会社が指定する者が買取る場合は10日と大きな相違があること要注意です。最悪のパターンではあるのですが、決して珍しくない事例として、期限内に株式譲渡不承認通知を行ったまではよかったものの、そこから既に10日経過しており、会社が指定する者への買取りを請求できず、さりとて会社は自己株式取得の規制(財源規制)により取得不可、この結果、株式譲渡を承認せざるを得ないというものがあります。株式譲渡を不承認としたいのであれば、同時に誰がどうやって買い取るか、買取資金を捻出できるのか等まで検討を進めないことには、時間的に難しい問題が生じることに注意が必要です。
7.株券発行会社と株式譲渡
上記4.~6.に記載した手続き等を通じて、会社(又は会社の息がかかった第三者)が相続人より株式を取得することになった場合、最後の砦(?)として株券の問題があります。
会社法が制定された平成18年以降に設立された会社であれば、あまり問題ならないのですが、会社法が制定される以前(旧商法)に設立された会社の場合、株券を発行する会社となっていることが多いのが実情です。しかし、実際の中小企業の現場では株券が発行されている事例は少ないと言われています。ところが、法律上、株式譲渡を行う場合、株券を譲受人に交付する必要があります(会社法第128条第1項)。
そこで、株券発行会社であるにもかかわらず、株券を発行していない場合、次のような対策を講じた上で、売買取引を完結させる必要があります。
・株券を改めて相続人に発行した上で、当該株券を売買取引で用いて交付する
・株券不発行会社に変更する(定款変更手続きが必要)
なお、被相続人が保有していた株式について、会社から直接発行されたものではなく、実は第三者から譲受けて保有していたという場合、理屈の上では、当該第三者と被相続人との株式譲渡の有効性が問題となりえます。これはケースバイケースによって判断するほかないのですが、株式譲渡の有効性を争う者が見当たらない場合、この問題点は見て見ぬふりをして処理することもあったりします。ただ、素人判断は危ういところがありますので、やはり弁護士等の専門家に見解をもらった上で処理することが無難です。
<2021年3月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
|
|





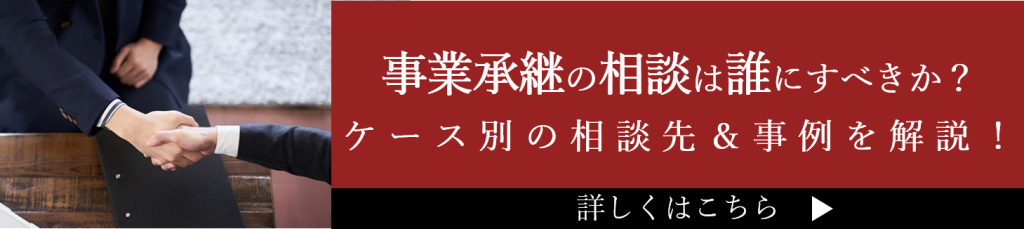


 弁護士 湯原伸一
弁護士 湯原伸一




































