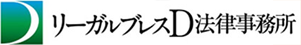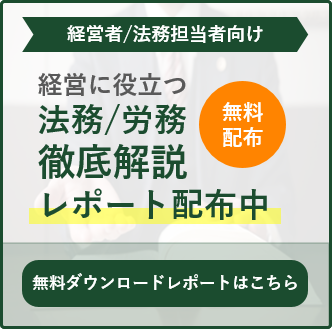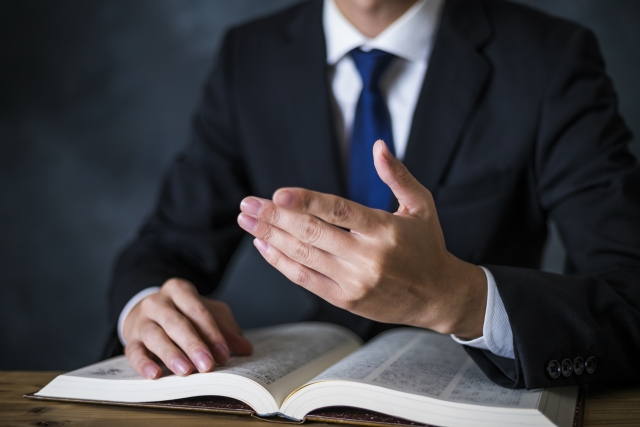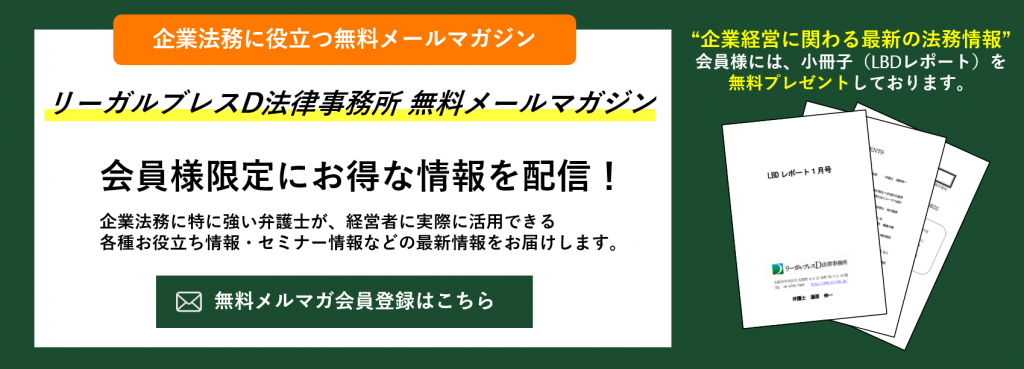
社内不正の相談が増える中で、窃盗以外に社員や役員が起こし得る行為として、詐欺、横領、背任を取り上げ、その備えや対応のポイントを整理しました。
①起きやすい原因、②予防法、③発覚後の対応に分類して端的に解説していますので、短時間で知りたい方委にはお勧めの記事となっています。
ご相談
少し前に某銀行の行員が、顧客より預かっていた物を盗んだとして逮捕された事例が注目を浴びたが、窃盗以外に自社の役員や社員が起こしうる犯罪にはどういったものがあるのか。
予防策や発生した場合の事後対応についても教えて欲しい。
結論
自社の役員や社員が起こす犯罪には様々なものがありますが、会社が直接的な損害を受ける犯罪類型として、詐欺、横領、背任の3つがあります。
言葉は聞いたことがある方も多いと思いますが、どういった場合に犯罪となり得るのか正確に理解できていないことも多いようです。以下でポイントを整理します。
解説
会社が直接的な損害を受ける犯罪行為には、主に以下の3つがあります。
①詐欺(刑法第246条)
詐欺とは、人を欺いて財産を取得する行為です。
例えば、従業員が架空の取引を装って会社に請求を行い、不正に支払いを受けるケースなどが該当します。
多くの場合、適切な監査を行っていなかった、社内の承認プロセスが甘く一人で不正を実行できたことが原因となります。
②横領(刑法第252条)
横領とは、会社から預かった財産を不正に自分のものにする行為です。
例えば、経理担当者が会社の口座から私的に資金を引き出すケースが典型例です。
多くの場合、経費申請者と承認者が同一であるためチェック機能が働かない、小さな額を定期的に横領することで発覚しづらいといったことが原因となります。
③背任(刑法第247条)
背任とは、会社の利益を損なう行為を意図的に行い、会社に損害を与える行為です。
例えば、役員が会社の資産を低価格で自分の関係する会社に売却するケースなどが該当します。
多くの場合、役員の権限が強く内部チェックが機能しない、「業務上の必要」を吟味せず漫然と放置したことが原因となります。
上記のような犯罪行為に対する予防策として、例えば次のようなものが挙げられます。
- 経理や財務の分業化(1人に権限を集中させないようにすることなど)
- 監査体制の強化(社内監査・外部監査を定期的に実施することなど)
- 電子承認システムの導入(経費や支払いのチェックを厳格化することなど)
- コンプライアンス研修の実施(役員や従業向けに「不正行為が発覚した場合のリスク」を理解させること、内部通報制度(ホットライン)を整備することなど)
なお、言い古されたことにはなりますが、不正を防ぐには、単なるルール作りだけでなく、実際にルールが機能するかどうかを定期的に検証することが不可欠です。
犯罪行為が明るみとなった場合、次のような対応を行うのが一般的です。
- 事実関係の調査(内部監査や外部の専門家(弁護士・会計士)を活用し、証拠を確保する)
- 社内処分の決定(就業規則に基づき懲戒処分を行う)
- 刑事告訴
- 民事訴訟(損害賠償請求を行い、不正に取得された財産を回収する)
もっとも、適切な証拠が収集できないこと、刑事告訴はなかなか受付けてもらえないこと、刑事告訴と民事責任の追及を同時並行で行うことは事実上の制約があるといった壁もあったりします。
何らかの対応を行う場合、早い段階から弁護士に相談し、足元をすくわれないよう準備をすることをお勧めします。
|
|





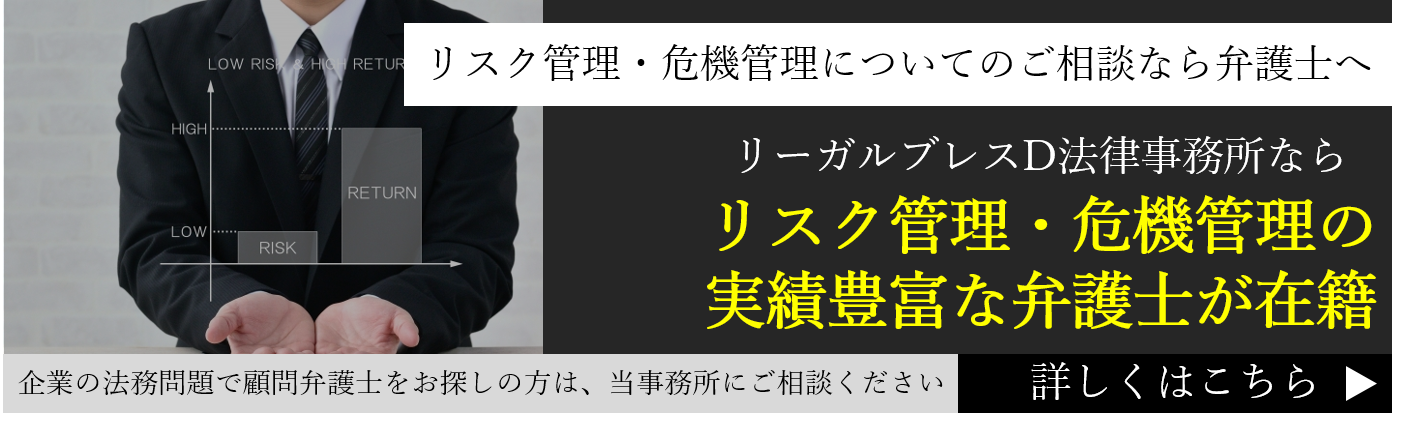
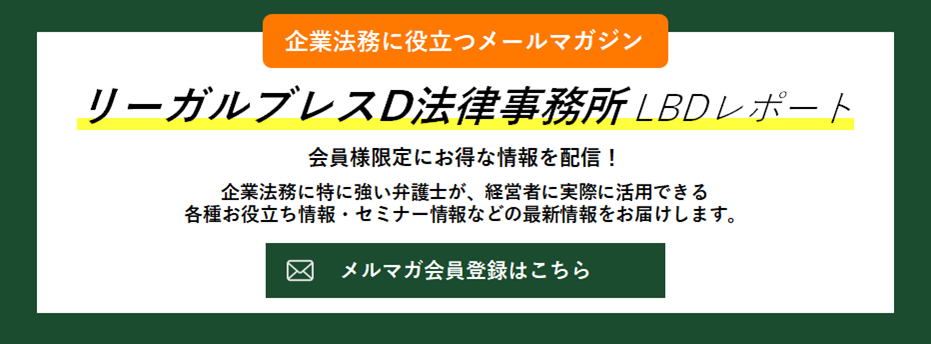
 弁護士 湯原伸一
弁護士 湯原伸一