Contents
【ご相談内容】
勤務継続中の労働者との間で労使トラブルが発生し、協議の結果、当社が当該労働者に対して一定の解決金を支払うことで、トラブルを終息させることになりました。
解決金を支払うこと自体は当社も納得しているのですが、当社の顧問税理士より、税務処理(源泉徴収)をどうするのか確認するよう要請を受けています。
解決金の支払いに伴う源泉徴収義務の取扱いについて、教えてください。
【回答】
執筆者のような弁護士を含め、何らかのトラブルを解決するために金銭支払いを行う場合、対価名目について厳密に検討することなく、安易に「解決金」としてしまうことが多いように思われます。
たしかに、損害賠償金よりも解決金という名目の方が、事業者にとっては抵抗が幾分弱まるといった心理的な事情があったりします。また、法務のみの視点からすると、あまり対価名目について拘る必要はないというのが実情です。しかし、解決金と言いつつも、例えば、実質的には賃金支払いの性質を帯びる場合、税務上は給与所得として取扱う必要があるため、結果的に事業者には源泉徴収義務が発生します。これを失念して額面通り支払った場合、後で源泉徴収分を労働者より回収しなければならないという面倒が生じる、回収手続きを行ったものの労働者が無資力で回収ができず事業者の自己負担とせざるを得ない、といった不利益を事業者が被ることがあります。
そこで本記事では、解決金と現象徴収義務の関係を押さえつつ、合意書等にどのように反映させればよいのかその対処法を含め、以下解説を行います。
【解説】
1.未払い賃金(残業代)・退職金と解決金
(1)税法上の原則的な考え方
未払いとなっていた賃金を「解決金」名目で支払うにすぎない以上、税務上は給与所得として取り扱われることになります。同様に退職金を「解決金」名目にて支払う場合は、退職所得として取り扱われることになります。
したがって、事業者は、名目上解決金として支払うとしても、実質的には賃金・退職金である以上、源泉徴収義務があります。
ところで、源泉徴収義務があるにもかかわらず、事業者が源泉徴収を行わなかった場合、税務署は事業者に対して、源泉徴収分の納税を行うよう処分してきます。本来、労働者が負担するべき税金である以上、税務署は労働者に対して直接請求するべきであると反論したくなる事業者もいるかもしれません。しかし、事業者に源泉徴収義務とその納付義務が課せられている以上、当該反論は通用しません。それどころか、事業者が納付を怠った場合、刑事罰が科せられるほか、退職所得にかかる優遇税率(いわゆる退職所得申告書の提出による優遇税率の適用)が適用されないなど、不利益を被ることになります。
以上のことから、事業者は、労働者に対して解決金名目で金銭の支払いを行う場合、源泉徴収義務の有無について検討する必要があります。
(2)対処法
では、事業者が源泉徴収義務のことを検討することなく、解決金として定められた名目額をそのまま支払った場合、どう対処すればよいのでしょうか。
端的には、事業者は労働者に対し、源泉徴収分につき求償を行えばよいという結論になります。
しかし、労使トラブルとなり、時間をかけて協議した結果、解決金名目で金銭支払いを行う場合、合意書を締結することが一般的です。そして、その合意書の中には清算条項(「甲及び乙は、本書に定めるほか何らの債権債務がないことを確認する」といった条項のことです。あえて言うのであれば、当事者双方は、合意書に書いてあること以外は、今後は何も文句を言うな!と考えればよいかと思います)を定めるのが当然とされています。たしかに、清算条項を入れることで、支払を余儀なくされる事業者にとっては、労働者よりこれ以上の支払要求を受けなくて済むという点でメリットの大きい条項であり、必ず定めるべき条項となります。しかし、源泉徴収義務を失念し、名目額をそのまま支払ってしまった場合、事業者が労働者に対して源泉徴収分につき求償を行いたくても、労働者から清算条項を盾に拒絶されるリスクが発生します。労働者の言い分も不当と断定する訳にもいかないため、結果的に事業者は、源泉徴収相当額について自らの財布で税務署に納付するほかありません。
この点を意識するのであれば、やや不細工な条項とはなりますが、次のような条項を定めるほかありません。
(例)
事業者と労働者は、本合意書に定めるほか、何らの債権債務がないことを確認する。但し、本合意書に基づき事業者が労働者に対して支払った金銭について、後日、事業者が税務当局より源泉徴収税の納付を求められた場合、労働者は事業者による当該納付分の求償に応じるものとする。
ただ、執筆者個人の経験では、上記のような清算条項を定めた合意書を用いたことがありません。また、執筆者が知る限り、上記のような条項を用いている他社事例を見たが事ないのが実情です。労使紛争となった場合、最終的には労働者の手元に残るお金がいくらなのかが重要な解決基準となる以上、こういった手元に残るお金について変動が生じることを明記することについては、労働者側の強い抵抗が予想されるからです。
したがって、あまり現実的な対策ではないように思います。
では、事業者において他に対処法は無いのでしょうか。
一番単純なのは、合意書において源泉徴収後の残額を確定させたうえで、その残額を明記し支払うことを合意書に定めるということです。例えば、次のような条項です。
(例)
事業者は労働者に対し、解決金として448,950円(但し、500,000円より源泉徴収を行った残額)を支払うものとする。
【注】ここでは源泉徴収分のみ考慮していますが、実際には社会保険料の本人負担分控除等も検討する必要があります。
非常に単純明快なのですが、しかし労使紛争を解決するための交渉上、50万円で交渉がある程度まとまり、合意書作成の段階となって上記のような条項を事業者が労働者に提示した場合、やはり労働者の手元に残る金額が目減りしているものとして、最後の最後でトラブルになったりします。交渉段階から、源泉徴収が必要である(なお、実務的には源泉徴収以外に社会保険料控除等も想定する必要があります)ことを示しながら、協議を行わないと、思わぬところで協議が行き詰ってしまうことに注意が必要です。
上記以外では、おそらく現場実務では一番多いパターンとなるのは、源泉徴収分について会社が自己負担することを覚悟の上、特に何も定めないという方法です。
(例)
事業者は労働者に対し、解決金として500,000円を支払うものとする。
なお、上記の亜種と言えばよいでしょうか、源泉徴収後の残額であることを明記するといった方法もあるかもしれません。
(例)
事業者は労働者に対し、解決金として500,000円(但し、源泉徴収後の残額)を支払うものとする。
どのような方法を採用するかは、労使紛争の深刻度や原因、解決に至るまでのスピードや協議状況などにもよるかと思いますが、源泉徴収の取扱いについては、往々にして検討対象外ということが多いので、事業者としては注意が必要です。
(3)裁判手続きの場合の注意点
労使紛争が交渉では解決できなかった場合、裁判手続きにて解決が図られることになります。労使紛争の多くの場合、和解にて解決することが多いのですが、この裁判上の和解手続きの際、裁判官は源泉徴収について一切考慮せず、名目額=実支払額としての解決を図ろうとするのが通常です。事業者において源泉徴収義務に留意する場合、最初から源泉徴収後の残額を支払うことで和解する必要があります。
ちなみに、源泉徴収義務を考慮することなく、事業者が労働者に対し、裁判上の和解にて解決を図った場合、いざ支払いという段階になって、裁判上の和解手続きにて取り決めた金額(和解調書と呼ばれる裁判所発行の書類に支払い金額が明記されています)より勝手に源泉徴収し、その残額を支払った場合、残念ながら和解内容通りの支払とはなりません。下手をすれば、その控除額((源泉徴収分として控除した額)について強制執行手続き、例えば事業者の取引銀行口座や売掛金への差押えが行われることにもつながりかねません。この場合、面倒でもいったん名目額を全額支払った上で、後で(税務上の取扱いにつき勘違いがあったとして)源泉徴収分につき求償を行うか(但し、清算条項に注意)、最終的には事業者の自己負担にて処理するといった対応が必要となります。
次に、裁判上の和解手続きでも解決できなかった場合、判決という形で労使紛争は終結することになります。この判決にて支払いを命じられる場合、判決書に記載されている金額は源泉徴収義務を考慮しない金額となっています。判決に従って支払いを行う場合、事業者は予め源泉徴収分を控除し、その残額を支払うという対応が必要となります。
判決の場合と裁判上の和解とで対応が異なることになりますが、和解の場合、事前に源泉徴収分の取扱いについて事業者は検討する余地があり、源泉徴収義務があることを踏まえて支払金額を合意した以上、後で源泉徴収義務を失念していたと主張するのは不当であるので、名目額通りの支払いを要求されるものと考えられます。一方、判決の場合は、事業者の源泉徴収義務を裁判所が一切考慮しない以上、事後的に事業者において対処する必要がある、という点で対処法に差異があるものと考えられます。
なお、強制執行手続きとなった場合、源泉徴収分を考慮されることなく、いったんは労働者が名目額全額を回収することになります。事業者は労働者に対し、事後的に源泉徴収分を求償するほかないと考えられます。
2.パワハラと解決金
(1)税法上の原則的な考え方
被害者である労働者が事業者に対し、パワハラやセクハラ等に基づき請求するのは損害賠償となり、この損害賠償金を受領する労働者は非課税所得して取扱うことになります。したがって、事業者がこれを「解決金」名目で支払うことは、損害賠償金を支払ったことに他なりませんので、源泉徴収義務なしというのが税務上の結論となります。
(2)対処法
上記(1)で記載した通り、源泉徴収義務がない以上、合意書に特別な条項を定める必要性はありません。ただし、事業者として、源泉徴収義務を負わない金銭支払いであることを明確にしたいと考えるのであれば、解決金による支払いではなく、損害賠償金名目での支払いとした方が無難です。また、損害賠償金の発生原因について簡単に触れておくことも一案となります。例えば、次のような条項です。
(例)
事業者は労働者に対し、本合意書を締結するまでに生じたパワーハラスメントに対する一切の損害賠償として、金100万円の支払い義務があることを認める。
なお、損害賠償金としての支払であれば源泉徴収義務がないことは明らかなのですが、例えば税務調査が入った場合、税務当局は「本当に損害賠償金として支払ったのか」という疑いをかけてくる場合があるようです(実際に執筆者が関与した労使紛争事例でも、後日の税務調査の際、支払の経緯等に関する意見書を作成し、税務当局に提出したことがあります)。したがって、合意書の条項に明記するだけでは不十分であり、なぜ支払うことになったのかに関する記録を残すことが重要となります。特に、解決金名目での支払の場合、文面上からは損害賠償金の支払なのか明らかとはならないことが多いため、金銭支払い理由の証拠を残しておかないことには、税務当局と新たなバトルが勃発しかねないため要注意です。
3.合意退職と解決金
(1)税法上の原則的な考え方
合意退職に伴い、事業者が労働者に対して解決金名目で何らかの金銭支払いを行う場合、場合分けをして検討する必要があります。
- ・希望退職や退職勧奨による退職金の上乗せとして解決金を支払う場合
…退職所得扱いとなり、源泉徴収義務が生じるものと考えられます。 - ・労使トラブル(不当解雇を除く)の解決策として、合意退職する代わりに解決金を支払う場合
…解決金の内、①労使トラブルに基づく金銭支払い、②合意退職に伴う金銭支払い、に分類した上で、①についてはトラブルの原因 に応じて検討する(例えば、未払い賃金であれば給与所得扱いとして源泉徴収義務あり、ハラスメント等の損害賠償金であれば非課税扱いで源泉徴収義務なし)、後者については退職所得扱いとして源泉徴収義務が生じるものと考えられます。 - ・不当解雇を理由とする紛争解決策として、合意退職する代わりに解決金を支払う場合
…解決金の内、①いわゆるバックペイ分(解雇された日から解決に至るまでの賃金相当額)、②合意退職に伴う金銭支払い、に分類した上で、①については給与所得扱い、②については退職所得扱いとして、それぞれ源泉徴収義務が生じるものと考えられます。
ちなみに、上記事例のうち、後半2つの事例については、必ずしも退職金として支給しているわけではない(特に退職金制度を設けていない場合)と認識している事業者も多いかと思います。しかし、税務当局の基本的な考え方は、退職したことを原因として支払われる一時金である以上、退職所得であるという形式的なものと言われています。
また、後半の2つの事例については、解決金の内訳が分類できることを前提に記載しましたが、実際の現場実務の観点からすると、厳密に内訳を検討することなく、総額としていくら支払って紛争解決を図るのかという観点で検討を進めることが通常です。このため、解決金について、具体的な金額をもって内訳を説明することが困難なことの方が多いのですが、この場合、税務当局は全額を退職所得として取扱い、源泉徴収の負担を求めてくる傾向があるとされています。
したがって、合意退職に伴う解決金支払いの際、事業者は、原則的には源泉徴収義務の問題を避けて通ることができないと認識しておいた方がよいのかもしれません。
(2)対処法
上記(1)である程度解説しましたが、合意退職に伴う解決金支払いの場合、各事由に基づき発生した様々な金銭が包含されていることがあります。この場合、(a)解決金の内訳を明示することで税務処理を行う、(b)解決金という言葉を用いず、対価名目を明らかにした上で税務処理を行う、(c)解決金全額を退職所得扱いとみなして税務処理を行う、のいずれかを選択することが考えられます。具体的な条項例としては次のようなものが考えられます。
((a)の場合の例)
事業者は労働者に対し、両者間における紛争の一切の解決金として金1,846,850円(但し、未払い賃金150万円より源泉徴収分を控除した1,346,850円、及び合意退職に伴う退職金として50万円の合計額)を支払うものとする。
【注】ここでは源泉徴収分のみ考慮していますが、実際には社会保険料の本人負担分控除等も検討する必要があります。
((b)の場合の例)
・事業者は労働者に対し、未払い賃金が150万円あることを認め、これについて源泉徴収及び社会保険料等の法令上必要な控除を行った残額を支払うものとする。
・事業者は労働者に対し、合意退職に伴う退職金として50万円を支払うものとする。
((c)の場合の例)
・事業者は労働者に対し、解決金として1,795,800円(但し、額面200万円より源泉徴収分を控除した残額)を支払うものとする。
なお、税務上の疑義を払拭するのであれば、(a)のような形式ではなく、(b)のような支払い名目・対価ごとに分けたほうが無難と考えられます。また、内訳を区分することができない場合は、(c)のような形式にした方が事業者としては分かりやすいかもしれません。
もっとも、労使紛争による交渉を行う際、源泉徴収義務に留意しながら交渉ができるとは限りませんし、むしろ留意することができない方が多いかと思われます。したがって、(d)源泉徴収分について労働者から回収することを諦め、事業者が自己負担する、といったことも念頭に置かなければならないかもしれません。
4.まとめ
労使紛争において解決金を支払う場合の注意点について、ポイントをまとめると次の通りです。
(1)解決金に賃金と損害賠償金の両方が含まれている場合
上記3.に記載した通りです。
なお、賃金と損害賠償金について明確に分類できる場合、賃金支払い条項と損害賠償金支払い条項は別々に定めた上で、賃金に対する源泉徴収義務をどのように処理するのか労働者と交渉しつつ、合意書に定めることが望ましいと考えられます。
(2)裁判手続きの場合
上記1.(3)で記載した通りですが、特に次の3点が重要となります。
- ・和解にせよ判決にせよ、源泉徴収義務を考慮した金額を裁判官が考慮することは無いこと
- ・源泉徴収分について後で求償することを考えているのであれば、清算条項に注意すること
- ・強制執行手続きにより回収された場合、別途労働者に対して源泉徴収分の回収手続きを行う必要があること(税務当局に対し、労働者より源泉徴収分を回収するべきであると主張しても認められないこと)
(3)労働組合が介入した場合
上記1.から3.では触れなかったのですが、労働組合が介入した場合の注意点についても簡単に解説しておきます。
まず1つ目として、解決金を受け取る権利者は労働者であるものの、支払先が労働組合宛となっている場合です。この場合、支払った金銭の内、いくばくかは労働組合が控除することになるのが通常ですが、労働者が実際に受領する金銭をベースにするのではなく、支払った金額をベースに検討する必要があります。そして、支払った金銭の実質的な対価内容に応じて源泉徴収義務の有無を検討しつつ、対処する必要があることはこれまでの解説通りです。
次に2つ目として、解決金を受け取る権利者が労働組合となる場合です。労働組合との固有の紛争を解決するために要する費用と考えられるため、源泉徴収不要と考えられますが、結局のところは実質的な対価内容如何によって結論が変わることになります。
<2021年12月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
|
|

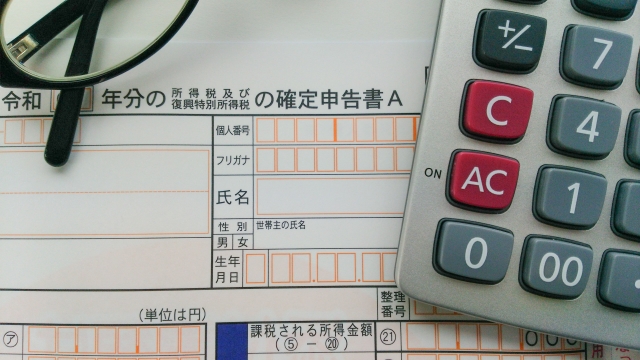






 弁護士 湯原伸一
弁護士 湯原伸一





































